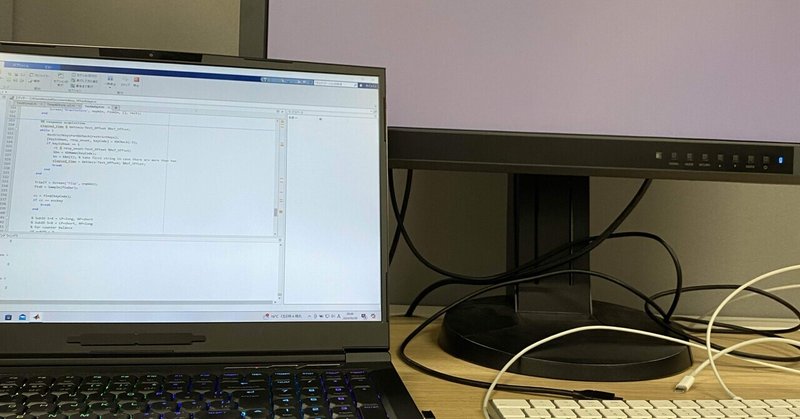
イヤイヤ機
研究室という空間はおそらく、中で何が行われているのかわからない部屋ランキング第1位だと思う。
ちなみに個人的第2位は視聴覚室である。
きっと何をしているのかわからない人が多いだろうし、誰にも見られる事なく淡々と作業をしているだけでは僕も寂しい。
と言うことで、僕が先週まで取り組んでいたことの一部を少し書いてみる。
研究室で行う作業は基本的には個人で黙々と手を動かすのみなので、1日を通して挨拶以外に一言も発さず帰ることもある。
じゃあ何をそんなに1人でやっているのかというと、ざっくり言えばプログラミングだ。
僕は大学で認知心理学ゼミに所属していて、認知心理学とは簡単にまとめると「ヒトの見え方・聴こえ方・感じ方」を研究する。
だから、実験対象は多くの場合は人だ(動物実験もある)。
そして実験では参加してくれる人に、光を見せたり音を聞かせたり、あるいは触覚で感じ取れる何か(振動や触圧など)を与える。
そういう、光とか音とか何かしらを全部まとめて「実験刺激」と呼ぶのだが、実験は1人だけに対して行うわけではなく、通常数人〜数十人を対象に行う。
そのすべての人に対して0.1秒のズレもなく、狙った時間に同じ長さの実験刺激を与える必要があるため、実験手順をミスなく完遂するなどという所業は、到底人間にできるものではない。
そこで、機械にやってもらう必要がある。
僕がプログラムしているコードは、そういった光や音を「このタイミングでこれだけの長さ出してね」と指示するためのものだ。
で、このプログラミングで動いてくれる機械(PC・ソフトウェア)なのだが、良い意味でも悪い意味でも、ソースコードに書かれていることに従順である。
つまり、コードが間違っていたとしても、こちらの意図を汲み取ってくれるなどという事はあり得ない。
機械に「筆者の気持ちを読み取りなさい」の類の問題は解けないのだ。
見ていて面白いくらいに、本当にぶっ飛んだ挙動を見せる。
だから基本的には「書く→動かしてみる→ぶっ飛ぶ」のサイクルをひたすら回していって、最終的にようやく狙い通りの挙動を見せてくれるのだ。
先週は、GW明けということもあり僕の挙動も冴えていなかったせいか、PCが怖いくらいに言うことを聞いてくれなかった。
ある日の事。
本来であれば「3種類の画面が2秒ごとの間隔を開けながら順番に出てくる」という画面提示を行なってほしかったのだが、そこの部分だけ3倍速になったのかと思うような速さで処理が行われてしまっていた。
自分なりにおかしいと思うところを探し、書き換え、試し、そしてまだおかしい。
この作業を、数時間にわたって繰り返した。
だが目の前のPCは、おもちゃを買ってもらえないとわかった途端、イオンのフロアでブレイクダンスを始める3歳児くらい言うことを聞いてくれない。
ただ3歳児に比べてタチが悪いのが、本人は至って真面目に「言われたことを完璧にやってます!」という顔をしてくるところだ。
自分のコードの欠陥を棚に上げて、PCにあたりそうになる。
思い切って研究室のPI(主任研究員:研究室の代表みたいな人)に相談して、一緒にコードを見直してもらった。
かれこれ数十分ほど、機械の動作の不具合とコードを見比べてから、その人は言った。
「あ、ここ[](パラメーターを入れる括弧)が抜けてるね」
たった2文字。
たった2文字抜けただけで、思うように動いてくれなくなっていたのだ。
僕には目の前にいるPIの先生が、救世主のように見えた。
感謝を伝えると、「プログラミングだとよくある事だよ」と返された。
ますます救世主に見えた。
再び頭を下げてから、僕は目の前のPCをシャットダウンした。
さっきまでイヤだイヤだと反抗し続けていたPCは、疲れ切って眠りに落ちたかのように静かになった。
まだまだ、骨の折れる作業が続きそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
