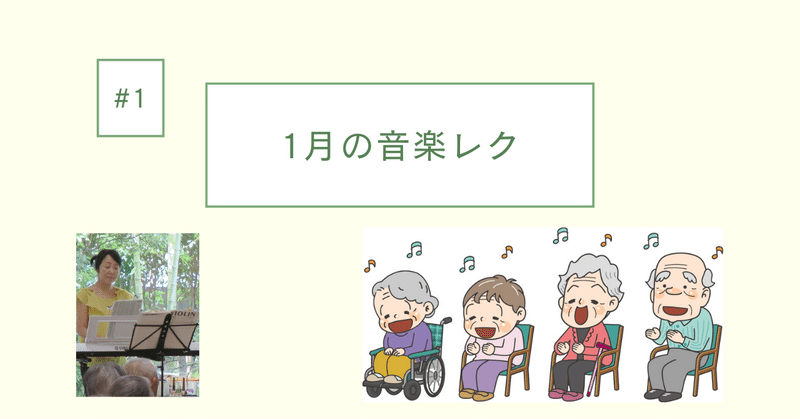
1月の音楽レク【お正月と八重の桜】
お正月に関係する歌と、今年の大河ドラマ「八重の桜」にちなんだ歌を選んでみました。
そして、お正月アイテムを使って、懐かしい遊びを話しあいました。
参加者のみなさんの笑顔があふれ、たくさんの発言を引き出すことができました。

「福笑い」は粘着テープ付き磁石を顔のパーツに貼って、白板を使って職員の方にアイマスクをしていただき、福笑いの一部始終をみんなで見て楽しみました。
「もっと右」とか「あら~変な顔になっちゃったね」とか「うまいうまい」など思わず発言が飛び出し、笑顔があふれ楽しいひと時になりました。

「いろはかるた」は、いろいろなやり方があると思いますが、私はトランプのようにして1枚引き、出た絵札を見せて、読みを答えてもらいました。
私の知らないような読みをスラスラと答える人がいたり、誰かが間違えてもみんなが考えて正解を導きだしたりと、いい活動になりました。

「けん玉」も私がやって見せると、「持ち方が違う」と正しい持ち方を教えてくれる人がいました。
その他、凧、百人一首、双六、羽つきなどもいいですね。
一月一日
千家尊福作詞 上真行作曲 明治26年
たこの歌
作詞作曲者不詳
お正月の遊びの歌ですね。
凧上げについてお聞きすると
「昔は今みたいに電柱が無かったからね~」
「上手く上げるまでが大変なんだよ」
「走ったなあ」
「女は羽つきだね」
などの発言がありました。
箱根八里
鳥居忱作詞 滝廉太郎作曲 明治34年
お正月の2日、3日に行われるのが「箱根駅伝」。
それにちなんで選曲しました。
歌詞に漢字がたくさんあります。
ふりがなをふって読みやすくしましょう。
この歌詞を読むだけでも相当頭を使いますね。
意味についても皆で話しあいましょう。
「箱根八里は馬でも越すが、越すに越せない大井川」
男はつらいよ
星野哲郎作詞 山本直純作曲 渥美清歌 昭和46年
お正月映画といえばかつては「男はつらいよ」でした。
「私生まれも育ちも葛飾柴又です・・」という寅さんの台詞も読んでみましょう。
映画には物売りの口上もいろいろ出てきます。
調べて紹介するのもいいですね。
会津磐梯山
福島県民謡
「おはら庄助さんなんで身上つぶした・・・」という台詞も入れましょう。
民謡は高齢者はたいがい好きですし、盛り上がります。
伴奏が無くても手拍子で十分歌えます。
一緒に大きな声で歌いましょう。
大河ドラマ「八重の桜」のヒロイン「新島八重」は会津の出身です。
白虎隊
島田馨也作詞 古賀政夫作曲 藤山一郎歌 昭和12年
「新島八重」は戊辰戦争の時、鉄砲を担いで男と一緒に戦いました。
白虎隊はこの頃に作られた少年兵団。
会津の町が燃えているのを見て鶴ヶ城が落城したと思い、飯盛山で自害しました。
忘れている人が多いと思いますので、歌ってみて反応を見ましょう。
徐々に思い出します。
レク担当(音楽療法士)ひとりの現場なら伴奏は無くても、歌える人が前で歌詞を指したほうが参加者は歌いやすいでしょう。
荒城の月
土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲 明治34年
「新島八重」が籠城していた鶴ヶ城から降伏する際に詠んだ歌があります。
「明日の夜は いずくの誰か ながむらん 馴れしみ空に 残す月影」
この歌をヒントに土井晩翠は《荒城の月》の歌詞を作ったという説があります。
確かに2番の歌詞は9月に落城した鶴ヶ城を霜が降りる頃に月が見下ろしているようにもとれますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
