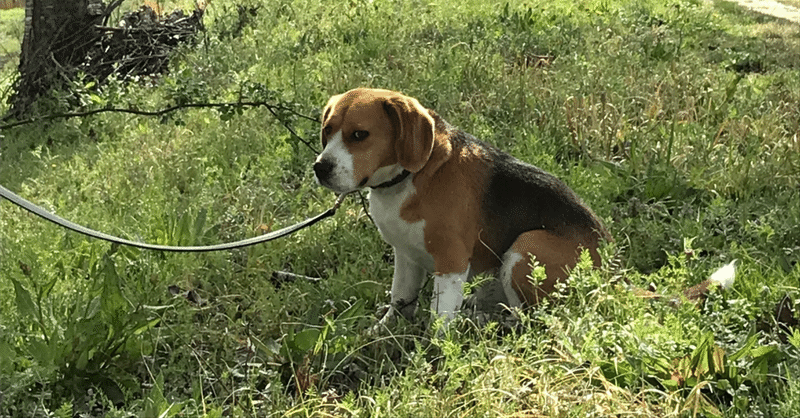
「正しさ」について
ぼくは人から迷惑をかけられないためには、今すぐ世界じゅうを一コペイカに売り飛ばしたって平気だ。世界が破滅するのと、このぼくが茶を飲めないのと、どっちが一大事かと思う? その答、――世界は破滅しても、ぼくはいつでも茶を飲まなくちゃいけないんだ。
堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である。
注意:本のネタバレを含むことがありますご了承ください。
「正しさ」の圧力
時折「正しさ」に押しつぶされそうになることがある。常に正しい判断、正しい言動を周りから求められているような気がする…。そんな中で心が摩耗してしまう。そして、時たま「正しさに耐えられる強い心を持て」と言われることもある。が、中々難しい。耐えられる強い心を持てば生きやすくなるのかもしてない。はたして、耐えることは果たして良いことなのだろうか。
特にコロナ禍を経た日本社会は正しさへの圧力が強くなっているように思う。正しい者と正しくない者は明確に分断されるようになり、正しい者は正しくない者を大きな声で糾弾し、裁く。そんな光景をよく目にした。
そんな中、ぼくは逃げるように病気を理由に仕事もあまりしなくなった。政治にも関心がなくなり、選挙にも行かなくなった。ただ今は、子供とあそび、同じ本を何度も読み、たまに近く山へ散歩に行く、なんとなくそんな風に過ごしていた。
オンラインの読書会や書くこともその中から始めていった。ぼくが参加している読書会は、同じように精神的に疲れてしまっている人が多かった。その方々との対話の中で、この人たちとの出会いは偶然だけれども、同じように悩んでいる人がこの場で出会ったことは、なにか見えないものに導かれた必然的なつながりのように思えた。その人たちは何かに疲れてその場に集まったように見えた。それはやっぱり、「正しさ」なのかなと思ってしまう。
この文章は「正しさ」に疲れてしまった人が、「正しさ」以外で語る言葉はないか模索していく文章である。
子供の立場になって
最初読んだときはよくわからなかったが、ただその中に書かれてあった言葉が印象的で、ふとした時に「ああ、あの言葉はこういうことを言いたかったのかな」と反芻する、そんな本がある。ぼくにとって加藤典洋の『敗戦後論』がそれにあたる。
その本の中に書かれた言葉は、「正しさ」に違和感を覚えた時、疲れてしまった時によく思い出す。
『敗戦後論』の主張はわかりづらい。ただ無教養なぼくなりの解釈を話すと、人が正しくないこと、誤ってしまうことを含みながら、どう話すか、そしてどうもう一度人々がつながることができるか、ということが書かれた本だと思っている。
すこし内容を話すと、日本人は第二次世界大戦で敗戦した後、敗戦したことを受け入れずにいたので、本当の意味で反省することがなかった。そのためジキル博士とハイド氏のように人格分裂(ねじれ)を生んでしまった。その象徴として、保守派は自国の死者を哀悼し、革新派は他国の―アジアの―死者を哀願する。
どうして、反省することがないと人格分裂を生むのか。例えば、仕事をしていると自分は全然悪くないと思っていても、場を収めるために謝らないといけない機会は多い。そうなると「表面的に反省してる自分」と「心の中で反省していない自分」と分裂してしまう。いわゆる本音と建前の関係である。
その分裂してしまった人格をどう統合していくかが一つのテーマとして書かれる。
そんな『敗戦後論』は雑誌掲載以来、様々な批判にさらされた。それに対して加藤は「その批判はまったくもって正しい」という。しかし加藤自身は「正しい立場」で話すより、「誤ってしまう立場」で話すことを選ぶ。(注1)
文学は、誤りうる状態に置かれた正しさのほうが、局外的な、安全な心理の状態におかれた、そういう正しさよりも深いという。深いとは何か。それは、人の苦しさの深度に耐えるということである。文学は、誤りうることの中に無限をみる。
加藤は右、左のイデオロギーの対立(分裂)を統合するために「誤ってしまう立場」で語ったのだ。それは、思想というゲームの中で一人だけルールを理解せず、自分の深いところで「こうだ」と思ったことを実行していく立場であった。「右とか左とかそんなのどーでもいいよ」という、なにもわかっていない子供と同じような立場といってもいい。(注2)
このことについて思い出すのは、フィリップ・K・ディックの『ヴァリス』という小説である。
この小説は、大量の情報が整理されずに語られており、また、どこまでが現実でどこまでが狂った妄想なのか判別のつかないような、内容になっている。友人の自殺をきっかけに主人公は狂い始め、その狂った部分を主人公の名前とは別の名前をつけ、その部分について記述し始める。つまり、不幸をきっかけにして「書いている自分」と「書かれた自分」に人格分裂してしまう。そのことに主人公は苦悩し、その狂った部分は主人公から離れ奇妙な神学思想を作り上げ、世界・宇宙の成り立ちを記述し始める。しかし、後半部で「救世主たる子供」と出会い、なぜか急に人格が統合される。
この意味をどう考えるか。
ぼくも2歳になる子供がいるのでよくわかるが、子供の前では社会的立場や自分が抱いている正義、イデオロギーは通用しない。ぼくが話した言葉の返答が全く予想と違うものが返ってきたりする。子供はあらゆるルールが通用しない。『ヴァリス』でいえば別人格が作り上げた神学思想は子供の前では通じない。
それゆえに、深い部分で人格は統合されるのだ。ルールに則るためにどうしても人は、ルールに合わせて人格を作ってしまう。子供との対話は、その人格を無効化し、0から出発する。それゆえ人格統合されるのだ。
加藤は政治の人格分裂を統合するため、子供のような「誤ってしまう立場」をとる。そのために、政治ではなく文学の言葉持ち出す。大岡昇平、太宰治、サリンジャー、ハンナ・アーレントを引きながら、「誤ってしまう立場」についてと、その立場で語ることの困難さについて語る。
『敗戦後論』を読むたびに思うのは、ぼくたちにはもしかしたら文学の言葉が足りていないのではと思ってしまう。
「正しさ」への欲望
もう一人、最近「読んだ当初、よくわからなかったけど、こういうことをしたかったのかな?」と考える人がいる。村上春樹だ。
前述の加藤典洋は村上春樹について数多くの批評文を残している。ぼくはその批評文をほとんど読んだことがないが、村上春樹も人が誤ってしまうことについて、自分も誤っていしまうという立場から、ゆっくり一歩ずつ―時には後退しながら―筆を進めている作家のように思える。村上春樹が書いたものは読みやすいが、なかなかわかりづらいものが多いのも、そういった理由であるような気がする。
「完璧な文章なんて存在しない、完璧な絶望が存在しないようにね。」
村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』の冒頭では、完璧な文章ー正しい文章を書くことの困難さが示されている。しかし負ってしまった傷と向き合うため文章を書き始める、それは「自己療養のささやかな試みに過ぎない」。そこで語られた言葉は物語であった。
村上春樹は物語という虚構を使用して書くことが、正しさに少しでも抗うための手段であったように思う。
村上春樹以外のほとんどの作家の本を読むと、物語でありながら、どこかで、現実とのつながりがあるように考えてしまうが、初期の村上春樹の作品を読むと丁寧に現実を避けるように腐心して書いているように思う。
例えば、『風の歌を聴け』の「ぼく」はデレク・ハートフィールドという作家に影響をうけたと語る。この作家はアメリカのロストジェネレーションの作家でヘミングウェイ、フィッツジェラルドと同時期に活動していたことが示されており、あとがきにもデレク・ハートフィールへの謝辞が書かれた上、最後にご丁寧に「村上春樹」と作者の名前まで書かれている。このようにデレク・ハートフィールドは実在しているかのように書かれているが、この作家は実在しない虚構の作家である。そしてその作家に影響を受けた「ぼく=村上春樹」は虚構の存在として、現実と切断される。
何故この作家は現実へ繋がることを切断するのであろうか。それは「ぼく」が自由に羽ばたくためには、「正しさ」への枷を外す必要があった。そこで虚構としての「ぼく」を語ることが選択されるのだ。
そんな村上春樹の転換点となる作品が『ねじまき鳥クロニクル』である。
村上春樹は河合隼雄との対談で、『ねじまき鳥クロニクル』が上梓された1995年前後に、自身の中で「デタッチメント」から「コミットメント」へと転回があったことが語られる。「デタッチメント」とは「かかわりのなさ」を表す。初期の村上春樹の小説に出てくる人たちは、名前がなく、どこの土地なのかもあいまいで、歴史も希薄でる。名前、土地、歴史はたとえば国を運営していく上で極めて重要な要素であるが、それらが希薄であるというのは共同体から切断した虚構の「ぼく」を確立する。いわゆる「ひきこもり」の状態になるということである。しかし、そこから「コミットメント」ー「かかわりあうこと」を目指していく。そこのターニング・ポイントに位置するのが、『ねじまき鳥クロニクル』である。
この『ねじまき鳥クロニクル』の主題は歴史である。
この小説の主人公、岡田トオルは現実で負ってしまった「傷」から、井戸に入り、そこから歴史や世界といった現実と再びつながっていくという話である。この設定からわかる通り、村上春樹の「コミットメント」は単純に外へ出て政治や社会とつながるという話ではなく、初期にあった、「ひきこもるがゆえに自由である」という価値観を保持しながら、現実といかにつながることができるのか、模索していく過程であった。
なぜ「デタッチメント」から「コミットメント」への転回があったんだろう。ぼくはたぶん、村上春樹はひきこもること、虚構の「ぼく」だけでは生きてはいけないということに気づいたのではないかと思う。人はどこかでつながりを求めてしまう。村上春樹のこの転回は「正しさ」への欲望とぼくは解釈する。
インターネットの検索機能の発展や最近のAIブームなどを見ていると、どうも人類は「正しさ」に対してひどく弱いようだ。『ねじまき鳥クロニクル』ではこの人類の欲望を利用しコントロールする存在、綿谷ノボルという人物が悪として出てくる。綿谷ノボルはテレビなどのメディアを使用し持ち前の喋りのうまさで影響力を増していく。そこに、主人公はなにか違和感を覚えるのだ。
主人公は綿谷ノボルを信じている大衆のように安直に正しさに接続するのではなく、井戸に潜り、歴史(ノモンハン事件)と接続され「悪」について考える。
ただ、この試みは最終的には破綻してしまう。
主人公は「悪」である綿谷ノボルの殺害を実行する。しかしそれは主人公の夢でしかなく。現実の綿谷ノボルの殺害は主人公の妻、クミコが担うことになる。(注3)
なぜ現実ではなく、夢でしか殺害できなかったのか。村上春樹は「正しさ」への欲望を理解しつつ、「正しさ」への接続しようとすると回避してた結果、夢=虚構という自由の空間で「悪」の殺害をした。このふるまいは読む人によっては、撤退しているように思えてしまう。しかし、書き手として「正しさ」へは安直に接続しないことが倫理として機能する。『ねじまき鳥クロニクル』は「正しさ」への欲望をどう考えるか、示唆してくれる。
「間違っている可能性があること」の困難さ
加藤典洋、村上春樹を読みながら、いかに「正しさ」に対抗していくか考えた。
正しいこと、正義を追求することは素晴らしいことだ。苦しんでいる人のために社会や制度の枠組みを変える、その人のために活動するという流れは途絶えさせてはいけない。
ただ、ぼく自身は「正しいこと」と「間違っている可能性があること」だったら、「間違っている可能性があること」に寄り添っていきたい。
「正しいこと」はいつも強い。それに比べ「間違っている可能性があること」ははっきりいって、弱い。同じ土俵に立った場合いつも負けてしまう。
「正しいことは」前に進むことであり「間違っている可能性があること」は撤退することもあるのかもしれない。
それでも、それが困難さを含んでいても、「間違っている可能性があること」に寄り添う。ぼくはそこに自由を感じるからだ。
正しいことを土台としている学問とは違い、文学は、正しいことの手がかりがないこと、間違ってしまう立場の中に真をみる。その立場では、自分の深い部分での判断が頼りになる。そこで人は無限、自由に触れることができる。
と考えていたが、書いていくうちに一つの困難に出くわした。「人は「間違っている可能性があること」には耐えられず、「正しさ」への欲望に抗えないのでは」という壁だ。
ぼくたちは弱い、どうしても「正しさ」という強さを必要としまう。もしかしたらぼくは、人の「正しさ」を必要としてしまう弱さに寄り添うべきなのでは、と考えるようになった。しかし、それは「正しさ」に回帰することになってはいけない。ぼくの、人の弱さを理解しながら、それでも「間違っている可能性があること」に寄り添うにはどうすればよいか?
この文章には結論はないので、ここで打ち切らせてもらう。結論を出すことは、ぼくの中でこれだという「正しさ」を決めるようなものだ。この「正しさ」に抗うために無理に結論づけない。
注釈
注1:『敗戦後論』には「敗戦後論」「戦後後論」「語り口の問題」と三篇の論考で成り立っている。まず最初に「敗戦後論」が雑誌掲載され、右からも左からも激しい批判にさらされた。その後、その批判に応えるため「戦後後論」「語り口の問題」という論考が編まれた。批判者の中で代表的なものは哲学者の高橋哲哉という人の批判がある。詳しい批判の内容は「高橋哲哉【戦死者の哀悼をめぐって】」か「加藤典洋氏と高橋哲哉氏の「論争」」を読んでほしいが、すこしここでも述べさせてもらう。
加藤は日本人が謝罪するにはまず、人格分裂の統合以外にないと考え、そのため国民主体の構築として、侵略戦争に駆り出されて無意味に死んでしまった自国の兵士たちをまず深い哀悼を捧げることが必要と主張する。対して高橋は、それでは自国の死者への閉じられた哀悼共同体、自国の兵士の死者への閉じられた感謝の共同体として日本の「国民主体」を作り出し、結局は日本の戦争責任を曖昧にすることにつながると考え、汚辱の記憶を保持し、それに恥じ入り続けることが必要と主張する。
「語り口の問題」で高橋の批判に応答する。加藤は高橋の主張に対しては「まったくもって正しい」というが、その主張には「鳥肌が立つ」ような違和感を生じると言う。なぜ加藤は違和感を感じるのか。ぼくは「日本人は戦争加害者だ!反省しろ!恥じろ!」といわれても、正直「うるせーよ」としか思わない。それで反省や恥を出したとしても、言われたからやっただけの表面的なものにしかならない。反省や恥は外部から強要されるものではなく、自分がしてしまったことの罪を意識することで、内部から湧き出てどうしようもないものである。
注2:加藤のここでの立場は、複雑なものを含んでおり、「子供と同じような立場」という簡単な言葉では説明できない。「子供」という言葉を使うと、汚れをしらない純粋無垢の状態をイメージされるが、『敗戦後論』の内田樹の解説にもあるように、むしろ純粋無垢なのは批判者である高橋哲哉の主張であり、加藤の主張は自国の死者の「汚れ」をどう引き受けるかも含んでいる。この加藤の主張は、ぼくたちが加害者にも被害者にもなりえる世界でどう言葉を紡ぐか考えるうえで重要な視点であるので、また別の機会にゆだねたい。この文章の論点である「正しさ」にどう対抗できるかという視点において、加藤はノンモラルの声「右とか左とかそんなのどーでもいいよ」を重要視している。ぼくはこの声は「子供と同じような立場」と考えているため、ここではその言葉を採用した。
注3:綿谷ノボルの殺害を妻クミコが担うというのは、男性が自己目的を達成するために女性を傷つけるという性的搾取の構造である。この構造は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
