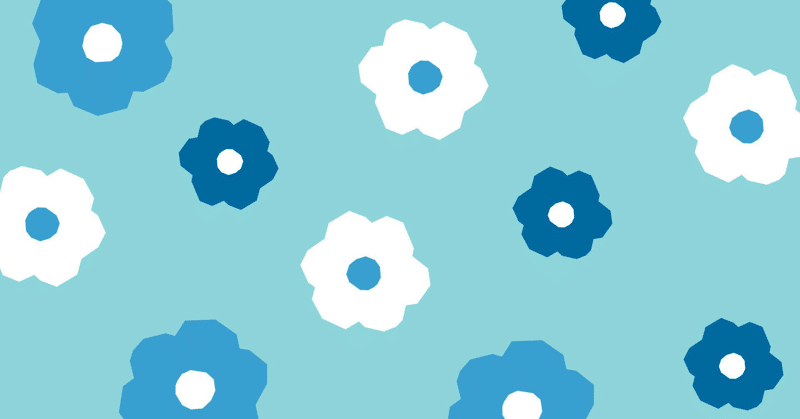
彼女たち、わたしたち、あたらしい家族①
1
松村さんはいつも淡いパステルカラーの手編みのセーターを羽織っていて、しゃんと伸びた背筋を庇うようふんわりと纏う姿は、いかにも上品な印象を与えた。
「フランスの毛糸で編んだの」
自作の羽織りを褒められると、いつも必ずそう返答した。
「だからちょっと、いいでしょ?」
ウフフ、と照れながら笑う。90歳を超えても決してだらりと椅子に腰掛けたりせず、遥かに歳下の職員たちにも丁寧に受け応えするので、こちらも妙にしゃんとしてしまう。
そのパステルカラーのセーターも、松村さんが亡くなった翌日には、無機質な90Lゴミ袋に詰められ、やがて捨てられた。何も残さなくいいと言った息子の意向だった。松村さんの一人息子は大手企業の幹部だったとの噂だった。妻は亡くなり子はなく、仕事に行くような身なりで毎日松村さんの顔を見に来ては職員とひと言ふた言話し、じゃあよろしくお願いしますと頭を下げて足音もたてずにいなくなる人だった。最後の日も表情を変えずに部屋から出てきた息子は、いつも以上に頭を下げて、ありがとうございました、と言った。そして翌日、私たち現場職員には不釣り合いな高価な菓子折りを持ってきた。
松村さんの身体が横たわる部屋はいちばん低い温度に設定され、部屋の前を通るたびに換気のために少しだけ開けられた隙間から冷気が足元をかすめた。どういうわけか業者が手配できずに刻々と変化していく松村さんの身体を、大切なもののような、気味の悪いような気持ちで、日に何人かが、たびたび確認しに行くのだった。
「猫がいるのよ」
換気のために少しだけ開けたベランダの窓の下半分にダンボールを当てながら施設長の林が言った。
「もしこの部屋に入られてしまったらと思うと」そう言って自分の身体をシャカシャカ撫でてぶるっと震える仕草をして、またテキパキとダンボールを貼った。
「さすがにそれはないと思いますけど」
介護主任の田中は冷静に返す。
「都会の猫は、そこまでお腹空かせてないよ」
林が躍起になる。
「わからないでしょ。朝起きて顔が半分なくなってたりしたら、私たち、次の日から無職よ。」
なにやってんの?と男性職員たちがぼやきながら見に来た。まだ業者来ないの?おかしくない?ほら、松村さん、紫色になってるし。
「なに、あんたたち金目のものなんかなにもないわよ。いくらお金持ちのお嬢様でも最後はなにもないのよ。人間わからないもんね」
「あれ、CDも捨てちゃうの?これは残しておこうよ」
そうして男性職員のひとりが1枚のCDを別にした。宝塚歌劇団と書いてある。
「他のみんなも、好きかもしれないし」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
