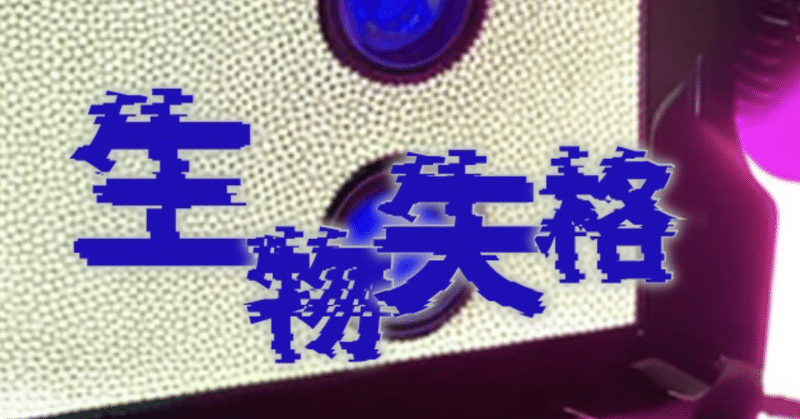
小説『生物失格』 3章、封切る身。(Post-Preface 3)
Post-Preface 3:捕捉。
***
「――お前の報告はよく分かったぜ、『破壊屋』」
報告を電話で受けた男の返答には、明るさと怪訝さが混じっていた。
彼はカラオケボックスに座っていた。画面の向こうでは女性司会が楽しげに売れっ子アーティストにインタビューをする様子が、話の邪魔とばかりに無音にされたまま流れている。
その足元には干からびたミイラが2体。元々は若いカップルだったものだ。来るであろう幸福も苦痛も将来も併せて、残りの寿命を全て男に吸われた末路であった。
「で、『破壊屋』。質問なんだが――お前が死城のクソガキを見つけたのは良い。非常に良い事だ。だが、破壊衝動を抱えたお前が死城のガキを破壊せず、更にはその恋人まで見逃したのは何故か聴きてえんだ」
返答次第ではお前も殺す。
言外にそう含ませた男が足で乾燥した死骸を小突いていると、電話口から返答があった。
『一言で言えば、まだ破壊するには早いと気付いたからだ』
その答えは自信に満ち溢れていた。
「ソイツはどういうことだ?」
殆ど興味本位で尋ねる男に『破壊屋』は答える。
『俺は大事なことを学んで心打たれたんだよ、『根源』――大切なモノを壊した方が、人はよりよく壊れるってな。言わば、壁を破壊する時に予めヒビを入れとく様なモンだ。そして、その方が壊れ方は派手で爽快。ちまちまと壁を削る様に崩すよりは、一気に崩壊させた方が気持ち良いだろ?』
「……それが、俺の質問にどう繋がる?」
男は何となく察しがついたが、敢えて尋ねた。質問者はあくまでも自分である。会話の主導権をこの『破壊屋』に握らせる訳にはいかない。
『死城の少年は、あからさまにあの恋人に依存している。病的と言っても良いレベルでな――それこそ、世界を犠牲にしても良いと思ってるんじゃねえのか?』
「……」
男は、思わず足元のミイラの頭を踏み砕いた。
世界を犠牲にしても良い。
それは奇しくも、死城の末裔が嫌い、男が憎悪する他の死城の人間達と同じ思考回路であった。
『であれば、少女を壊してから少年を壊す。これが最も心地良い。しかし、あの時ではダメだった。舞台があまりにも悪い。悪過ぎる。もっと相応しい状況で相応しい時に少年をぶち壊したい。つまり、少女を破壊した上で、少年を破壊したい。だからあの時は見逃したんだ――後で心置きなく壊せる様にな』
「……よーく分かったぜ」
男はその返答を聞いて頭を抱えた。
コイツを招き入れたのは、やはり間違いだったか?
ダークウェブに流したあの招集文。
《その身に『死城』の呪いを受けし人間共。完膚なきまでの復讐の時だ。心当たる者の連絡を待つ。》
当の連絡をくれた者は、全部で5人。1人は今電話している『破壊屋』。1人は『術師』。残り3人1組が『瞰隊』。
その時、あくまで死城を殺すのは自分だ、お前らにはその為の用意をしてもらいたい、と宣言した。4人は直ぐに了解した。『術師』は殺す気はなくただ苦しめたいだけであり、『瞰隊』は金さえ貰えれば忠実に守ると約束し、契約書まで渡してきたからだ――ご丁寧に2通1組を作成してまで。
しかし残る『破壊屋』は別だった。宣言には一時了解したものの、暫くして覆す様な発言をした。「破壊する欲を満たしたい。死城を壊して快感を味わってみたい」と。
無論ここで切り捨てても良かったが、破壊の為ならば用意周到に動き、さらにはそれを実現する行動力もある。野放しにする方が危険だった。だから、無駄かもしれないと思いつつも何度か「死城の末裔を殺すのは俺だ」と言い聞かせつつ繋ぎ止めてきたに過ぎない。
やはり無駄だったか――と推測が確信に変わったその時だった。
「お待たせしましたー」
がちゃりとカラオケボックスの扉が開く。オレンジジュースとコーラのグラスを盆に載せた店員が入って来た。
「オレンジジュー……ス?」
店員は見た。見てしまった。だから言葉が続かなかった。
2名の客が入っている筈の部屋に、怪しげな男が1人。そしてその足元に、客数と同じ数のミイラが転がっているのを。
店員はネットニュースで知っていた――とある交番で警官が1人、ミイラになって死んでいるのが発見されたという事件を。
「……っ、ぅ」
叫ぼうとした。だが遅かった。男は店員の髪の毛を掴んで強制的に部屋の中へ連れ、ドアを閉める。オレンジジュースとコーラが空を舞い、干からびたカップルミイラの体を湿らせた。
「あ、あなた、一体……っ!!」
「見られちまったんなら仕方ねえな」
店員の髪の毛をそのまま掴み続ける。すると店員の人生が強制的に進む。青年の顔立ちは壮年の面立ちに変化し、皴が深くなり、老化していく。10秒程で人生の終わりまで駆け抜けた店員は、そのまま床に頽れた。店員の死亡を確認した男はソファに座り直し、何事もなかったかのように通話に戻る。
「……すまねえな、邪魔が入った」
『別に構やしねえよ』
その言葉を聞きつつ、男は先の『破壊屋』からの報告を思い返し、「あー」と嘆息する。
「あのピエロ……折角の同志だと思ったんだけどな。呪いを自覚しながらそれを呪うのではなく受け入れて生きていたんじゃあどうしようもねえ。そんなモン、死城と何も変わらないからな。コードネームまで決めていたんだが、もう必要ないか」
『殺しとくか?』
「必要ねえよ」
どうせ暫く出てこられねえんだから、と男は気を取り直した。いつまでも小さな失敗を引き摺る余裕は、彼には存在しない。
「『破壊屋』。お前にはこれから別の仕事を頼みたい」
『破壊か!』
明らかに電話口の声が明るくなる。子供の様なはしゃぎ方に男は忠告を交えて告げる。
「ああ、そうだ。死城本体以外ならば思う存分破壊しろ。破壊して破壊して、破壊した後も破壊しろ。この俺が死城本体以外ならば許す」
だが、と続ける。
「ただ闇雲に破壊しても駄目だ。死城家を相手にする時の大原則は教えたよな。『「死城」を相手にするのなら、念には念を入れて懇切丁寧に用意周到にしなくてはならない』。だからこそ、効果的に効率的に破壊をする必要がある。勿論、その破壊に容赦は要らねえ」
だから、と男は指定する。
死城を相手にする為の第一歩として。
『破壊屋』に一歩譲歩して、少女の『破壊』を促すべく。
「手始めに、学校でも破壊してみるか?」
その瞬間、電話口の声が笑った。期待と愉悦が混じった、豪快な笑い声だった。その返答に満足したのか、男は命ずる。
「決まりだな。じゃあ頼んだぜ、『破壊屋』」
あくまであのクソガキだけは殺すなよ、他は何をしても構わない――そう言ってから通話を切り、スマートフォンを破壊した。元々このカップルのモノだから壊しても問題は無い。通話履歴が残らぬ様、丹念に粉々にした。
カラオケボックスを出る。通りがかりの部屋では、何も知らない一般人が呑気に流行りの曲や各々の好きな曲を歌っていた。殆どがカップルであった。
「……」
男は舌打ちする。しても何も変わらないと分かっていても、自然に舌打ちが出てしまう。
苛立たしさを隠さずに歩くスピードを速める。この時間は客が少なく暇なので、大体の店員が店の裏で時間を潰しているのを知っていた男は、誰にも見られることなく退店した。
「さあて、と」
言いながら、空を見上げる。雨でも降りそうな曇天だった。
「じわじわと確実に、喉元に食らいついてやる――覚悟しろよ、死城の唯一の生き残り」
お前を殺さないと、浮かばれない奴がいるんでな。
数秒灰色の雲を見上げた後、再び前へと向き直り、雑踏の中へと消えて行く。
***
ミイラのカップルと店員は数時間後に発見され、また新聞を賑わすこととなった。何せ、交番に続いて2件目だ。
連続ミイラ化事件として巷間を駆け巡るその事件は、また忽ち記者と読者に消費されていく。
誰も、その裏にある闇に辿り着くこともなく。
Chapter 3 "Who (will) Kill Me?" is the SALTY END.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
