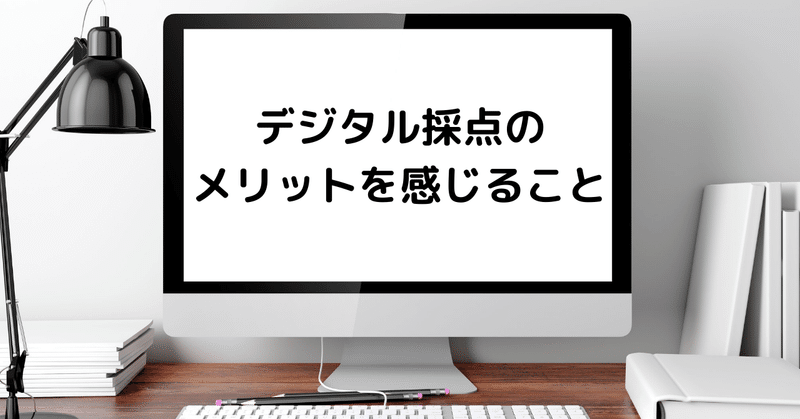
デジタル採点のメリットを感じること
このような記事を読みました。
勤務校でもデジタル採点を導入して約1年が経ちますが、使いこなせるようになってくると、「教員の業務軽減」という点では確かに大きな効果を感じます。
「採点や集計が本当に楽になった。土、日曜日が採点業務でつぶれることがなくなった」。岐阜北高(岐阜市則武)で現代文や古文を担当する教諭は自動採点の効果を実感する。1クラス当たり5時間ほど掛かっていた採点業務は、システムの導入でおよそ2時間半まで抑えられているという。「教職員で連携しやすく、ミスも起こりにくい。問題ごとにクラス全体の正答数を算出できるので、より重点的に生徒に指導しやすくなった」とメリットを語る。
教科が同じと言うこともありますが、本当にこのコメントの通り、採点時間がかなり減ります。
しかし、実はデジタル採点のメリットはそれだけではないのです。
実際にデジタル採点を使うことでどのようなメリットを感じているかを少し紹介します。
記号問題の採点の自動化
デジタル採点の最大のメリットは、AIの画像認識のおかげで記号問題はほぼ自動で採点が出来てしまう点です。答案をスキャンしてソフトに読み込みをさせると、瞬時に何十枚、何百枚あろうと、採点が終了してしまいます。この爽快感と感動が一番インパクトがアリした。
ただし、AIの画像認識なので100%正確に行える訳ではありません。おそらく、使ったことがない人が想像する数倍以上の精度で、乱筆な解答も判別してくれますが、逆に人間の目からすると謎に感じられる認識ミスも起こります。そのため、そういう採点ミスが無いかは、最終的にはきちんと人間が確認しなければいけません。
とはいえ、ほとんどミスは起こりませんし、ミスがあってもボタン一つで簡単に修正できるので、「答案をめくる→採点する→得点を書く→答案をめくる→……」と延々とやっていた作業に比べると、かかる時間は雲泥の差です。
採点ミスの激減
デジタル採点を利用することで、採点ミスの頻度が激減しました。
というのも、上で書いたとおり、デジタル採点を使うことで記号問題の採点は瞬時に終わるため、手で採点しているよりも明らかに負担が減っており、ミスをしにくくなっています。
また、採点ミスで比較的多くやってしまいがちなことが、合計点の計算ミスなのですが、デジタル採点だと採点と同時に設問別の得点が記録されていき、コンピュータが自動で採点してくれるため、計算ミスが起こるこということがなくなりました。
採点ミスの修正の負担軽減
採点ミスの修正も非常にラクになりました。
今までであれば、採点ミスの指摘を受けたら答案と模範解答を見直し、合計点を見直し、成績の記録しているデータベースを書き換えて……と、色々な手間をかけていましたが、デジタル採点だと採点箇所を確認して、採点を変えるだけで対応可能になりました。
実は、採点ミスのやらかしで一番、ダメージが大きいものは「模範解答自体を間違っている」というものです。数年に一度くらいの割合でやらかすのですが……この場合は、全員の答案を回収して全員点検し直すということになります。
しかし、そのような大事故を起こした場合でも、デジタル採点ならばデータをいじるだけですぐに修正が出来ます。
本領はデータの分析と蓄積にある
ここまで紹介してきたように、デジタル採点は「採点する」という場面でも強力に業務をサポートしてくれます。
しかし、個人的に約1年デジタル採点を使ってきて感じていることは、手間の削減以上に、生徒の答案データを蓄積できることにあるように感じています。
デジタル採点だと、答案を生徒にも返却しますが、スキャンデータは教員の手元に残るので、採点結果を見直しながら授業づくりを考えることも出来ます。
また、採点後のデータ分析も強力です。これまでは自分でやろうとしなければ出来なかったことが、採点と同時に終わっているということが多いです。たとえば、私の勤務校で採用しているソフトだと、次のような機能があります。
生徒個票作成
結果一覧(度数分布、平均点、標準偏差など)作成
設問別正答率一覧作成
採点結果別答案一覧表示
少し詳しく紹介します。
生徒個票作成
生徒の得点、クラス、学年の平均点、偏差値などの表示をしてくれるのはもちろん、設問ごとに生徒の回答(記号のみ)や得点(記述のみ)および、正答・配点・正答率などを記載した個票を自動で作成してくれます。
配点と正答を記載できるのが地味に便利です。模範解答を配布して、採点ミスがないかを確認してもらう時の速度が確実に上がっていますし、生徒自身が復習を行うときに、どこから手をつけたら良いか分かりやすいです。
結果一覧
採点結果を教師用資料として一覧にまとめる機能も付いています。度数分布や「正答率の高い問題」「正答率の高い問題の一覧」などを示してくれるだけではなく、「設問の見直しが必要なもの」(生徒の得点と正答率が上手く相関していないもの)なども指摘してくれる機能があります。
設問別正答率一覧作成
この機能に非常にデジタル採点のメリットを強く感じます。
デジタル採点で採点をしていくと、設問ごとに正答率が自動的に集計されます。手で採点している時には、採点が終わった後に百枚近い答案の、それぞれの問題の正解、不正解を打ち込んでいく……という途方もない手間をかけていたことが、採点と同時に終了になっているのは非常にありがたいです。
設問別正答率が分かると、作問が適切だったのかどうか、授業の内容が身についているのか、授業の狙いが達成されているのか、ということを確認することが出来ます。
きちんと授業についても客観的な数値でPDCAを回そう!と思うときに、この設問ごとに正答率を出してくれる機能はありがたいところです。自分の手作業でやるの本当に辛かったところです。
採点結果別答案一覧
これは記述問題の答案のまとめとしての機能です。
たとえば、10点をつけた答案の一覧、9点をつけた答案の一覧……と言った具合に、同じ得点をつけた解答を一覧にまとめて出力してくれる機能です。
国語科の採点で一番議論になるのが記述の部分点ですが、この機能を使うと、採点にブレがないかをしっかりと確認できます。
担当者同士のブレがないかということの確認はもちろん、生徒に対して得点別の答案例を示すことで、採点基準の説明も可能です。
これは手作業でやるとなると、答案のコピーを取るなど大がかりなことになるので……おそらく不可能に近いと感じます。
大切なのは試行錯誤
デジタル採点を利用して感じることとしては、採点の手間とデータの集計の手間が小さくなったことで、他のことに色々と工夫が出来るということです。
これまでは考査の次の日に100枚返却しないといけない……なんてこともあり、とても分析までたどり着かないということもあったことを思うと、採点を終えるのと同時に、分析と採点済み答案の蓄積ができるということに、圧倒的なメリットを感じます。
また、過重労働気味であるので、業務量の削減ということの意味は大いにあるのですが、ただ、採点の手間を減らすことで浮いた時間をもっと授業づくりや単純な採点よりも時間のかかる評価に充てられるように感じています。
例えば、来年からは観点別評価が高校でも始まります。観点別評価を実質化するためには、パフォーマンス評価も重要になると思っています。
定期考査の採点を圧縮することで、浮いた時間を質的に丁寧に見取るべきことに時間をかけられたらいいなと思います。
ただ、そう考えていくと、定期考査の在り方自体も、今のままでなくてもよいかもしれませんね。
有料のものを使うのが難しい場合は…
デジタル採点の導入にはかなりの額のお金がかかります。
そのため、「これはいいぞ!」と思ってもなかなかすぐには導入が難しい場合が多いと思います。
そのような場合、以下の有名なソフトがあります。
昔からあった「採点斬り」というデジタル採点ソフトをパワーアップさせて、フリーソフトとして共有してくれています。
さすがに有料のソフトほどの高機能ぶりではありませんが、デジタル採点を利用することで、採点と同時に得点集計が済むことのメリットなどを感じることができると思います。
個人情報の保護など、学内のルールに気をつけつつ、試しに確認テストなどで使ってみると、よさが確認できるのではないでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
