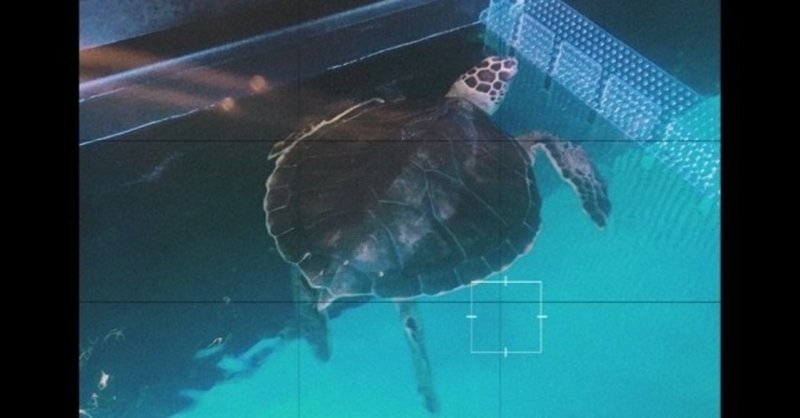
わたしのおじいちゃん
おじいちゃんが死んでしまう!
わたしのなかでは、その話題で持ちきりだった。わたしのこころが新聞紙になったとしたら、輝かしくも、憎たらしい一面を飾るのは「おじいちゃん、危篤」という表題だろう。ああ、わたしの大切なおじいちゃんが、しんでしまうかもしれない! わたしの心模様は大荒れだった。大荒れ過ぎて、逆に、お母さんと妹たちには平生通りに見えたかもしれない。
わたしのおじいちゃんは、よくわたしたちをドライブに連れて行ってくれた。ひかりの海が観えない土地で育ったわたしたちは、おじいちゃんに穏やかな海を教えてもらった。今思えば、長いドライブは心身ともに負担が大きいだろうに、たくさん連れて行ってくれたのは、やっぱり、おじいちゃんのやさしさだったのだと思う。おじいちゃんは、わたしたち姉妹を、あいしてくださったのだろう。あいして、くださったのだ。
おじいちゃんに連れられて向かったおおきな海を観るたびに、「うみはひろいな おおきいなあ」という歌を姉妹で合唱することが恒例行事だった。そう、我らがいとおしきわらべうたを知ったのも、その恒例行事からだった。おじいちゃんの車のなかには、わらべうたが流れていた。わらべにも、座敷童子にも親しくないわたしたち平成の子どもたちは、もう、物心が付く前、そのくらいのはじまりこそは首を傾げていたかもしれないが、いまでは、もう、あたたかく、潮のかおりがするわらべうたは、暗唱できる。これも、おじいちゃんのお蔭だ。おじいちゃんのお蔭で、わたしたちは、皆んなとおんなじように、日本の子どもたちになれたのだ。
それから、――もう、伝わっているかもしれないが、わたしのおじいちゃんは、わたしたち姉妹にやさしかった。お母さんが怒鳴っても、おじいちゃんが頭を撫でてくれる。わたしたちは、おじいちゃんのやさしさが、だいすきだった。
いま、わたしは、願っている。
神さまでもなく、仏さまでもなく、わたしたちの思い出に、乞うように願っている。殺風景な病室を思い出しながら、「おじいちゃんが、しあわせな夢を観ていますように。」と、希っている。これは、祈りだ。錆びた十字を抱きながら、せめて、最早動かない記憶のなかからとくべつうつくしいものが、わたしたちの、わたしたちのだいすきなおじいちゃんを、慈しみますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
