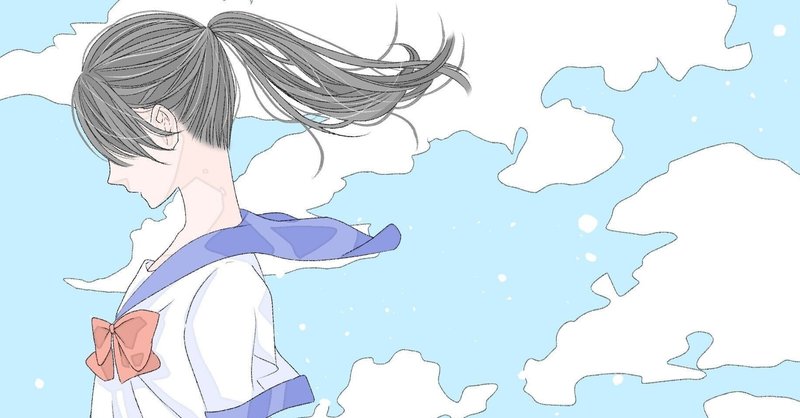
日々の雑感 day61【秋の気配を聴いて】
台風が通り過ぎていった8月10日のこと。
30度を超える気温でアイスを食べながら、17歳の女の子は
「最近、なんか秋っぽくなってきてませんか?」
と言った。アイスを食べながら僕が
「午後になるとより思う。山から秋の気配が降りてくるような感じ」
と答えると、彼女は「そうですよね!!」と、とても嬉しそうに答えて、あらためてその空気を感じるようにちょっと顔を傾けたのだった。
☆感性と感覚と
誰だって鈍感だなんて言われたくない。
だから、彼女のように自然との関係性を積み上げて、自然の変化の感知に優れた生命体は否定されやすい。西暦を見ろ、気温を見ろと、感性のセンサーを失った鈍感な大人達は、彼女の感性、つまり個性を悪気なく否定し、鈍感な人になるように彼女を引っ張って行く。そして、
「私の感性は間違ってるんだ」
「この感覚は勘違いなんだ」
と相手が自分を間違っていると認めるまで追い込んでいく。
その結果、こうした優れた感覚と感性を持つ個性ある生命体が凡庸に染まっていき、私達集団は未来で彼ら、彼女らが生み出すはずだったクリエイティヴな何か、イノベーティヴな何かを失っていく。
そのことをずっと繰り返してしまい、この国は何かを生み出すことがとても難しい国になってしまった。
実のところ、江戸時代に制定された二十四節気七十二侯では、8月7日頃から「立秋・涼風至」にあたる。人本来が持つ感覚に近づけば、彼女や僕が感じている秋の涼風を同じように見る事が出来るかもしれない。それもまた事実の一つ。
その意味でも、今、南アルプスの山小屋で働くあの女性は、こうした自分自身の感覚を、それは必死に守り続けてきたのではないだろうか。そう思うこともしばしばある。
☆誠実さと聴く関係
自分は当たり前で、普通に出来ていると思う。思いたい。そのマインドセットは他人にこうした感覚が備わっている可能性を怖れ、その存在に嫉妬し、相手を否定するような言動を選択してしまいがちだ。
相手を尊重し、相手の話を「聴く」という基本の世界は本当に奥深い。
出来ているようで、出来ていない。ゆえにそれを良く知る出来ている人ほど「出来る」とは言わない。だから年齢差や国籍や性別で相手を差別する事がないように自らを律する事もしやすくなる。誰からでも「聴く」ことが自らの発見や学びになることが習慣にすらなっているからだ。
こうした話をすると、否定されたと感じる人もいる。
また、相手の話に嘘でも肯定したり、それっぽく同調すればいいと考える人も多い。
そんな虚飾は相手側にとってよりひどい反応でしかなく、話をするに値しない人と認識されてしまうだろう。
知っている、知らない、わかる、わからない。そんな正解不正解だけの世界では苦しくなるばかりだ。こうした感覚の世界に絶対の基準や二項対立で測ろうとする方が無理。
真ん中が大事。それが「中庸」という言葉の本質にもあるだろう。
なので、もし同じように応じられる感覚が自分になかったとしても、人は対話によって分かり合う事が出来る。相手の感覚を尊重し、その感覚に興味(好奇心)をもって「聴く」ことが出来る。
「僕にはわからなかったな。どんな時に秋を感じたの?」
と相手を知ろうとする姿勢、態度を持っていれば、こんな「聴き方」も可能だろうる。そして、相手が見たもの、聴いたもの、感じたものを共有してもらうことで、自分にもその世界が感じられるようになっていく。
そうすれば、その学びから自分自身も本来あった感覚や感性を取り戻していく事が出来るし、大人が小さな子供から学ぶ事や思い出させてもらうことも数多く生まれてくる。
☆さて自分自身はどうだろう
今日から読み始めるのが「LISTEN」という本。
この2年くらい一緒にお仕事をさせて頂いている (株)YELLの取締役・篠田真貴子さん(前職のほぼ日の方が有名かもですが)が監訳された本で、この日を待っていた感もある。が、読む前から既にぶった切られたコーチやカウンセラー達がSNSで悲鳴をあげているようで、ある意味ワクチンより怖いという気持ちもちょっとある。
でも、そんな斬られ方をするのもといいかと寝る前の読書本に入れていく予定。安眠出来ないくらい斬られるようなら、読む時間を変えるかもしれないけど(笑)
後日レビューもしていきますが、対話、傾聴の本質に触れたい方、一緒にいかがでしょう。おススメです!
ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。
