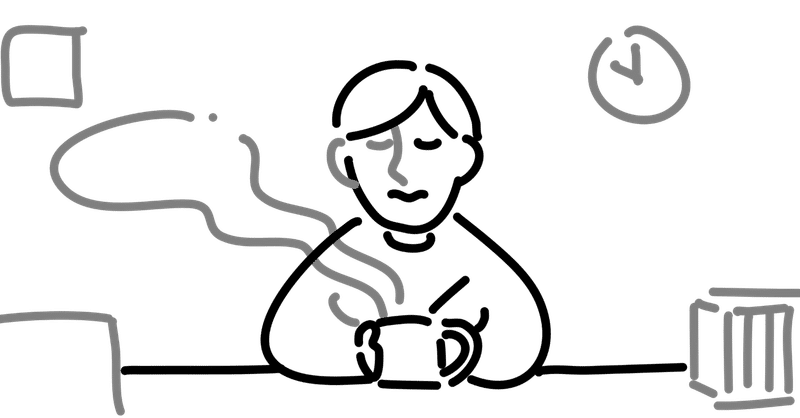
コーチング Note【プロコーチ向けLogic・感情と向き合う①】
前回は
【僕の流派では、よくメタファー(例え)として、ポジティヴとネガティヴをブレーキとアクセルに例えます。車がブレーキだけでは進めないし、アクセルだけでは停まれない(大事故)。そんな車と同じように、自分の中のポジ(アクセル)もネガ(ブレーキ)も心に必要な存在。だから、それをしっかりハンドルしてコントロールするドライバーとしての自分自身こそが大事】
とお伝えしました。当然、
ではどうしたらいいのか? コーチとしてどう関わっていくのか?
ということが気になります。そんな問い合わせも頂きましたので、今回からここの部分を解説していきましょう。ただし、あくまでも守破離の原則を忘れないようにしてください。最終的に「離」の段階。自分自身としての最適化に至る構築や研鑽を繰り返していくこと。それが出来なければ、どんなに数多く「守」(マニュアル、方法)を集めても意味がありません。集めたものを組み合わせる「破」によってオリジナルにしていき、意識しなくても出来る身につくレベルへと向上させていく。その為の「守」ですから。
まずその確認を内に確認して、進めていくとしましょう。
☆形容詞を名詞化せよ
まずはイメージを作るためにこんな資料にも目を通してみましょう。
【幸福度と生産性の相関関係を中心にした研究では、両者の間には正の相関関係が確認されてきました。参考に、図1のように、OECD諸国の幸福度と1時間あたりの労働生産性の関係をプロットしてみると、正の相関関係が確認できます。図の中で、赤点にあたるのが日本で、日本はOECD諸国の中では、幸福度も生産性も低い位置にあります】

マインドフルネスの回でも触れましたが、人として「良い状態」。幸せだと認識できている状態であれば人は創造的になり、より生産的に働ける状態になっていることがこの図からも理解できます。
「経済は民の気持ち!」とも呼ばれますが、人々がご機嫌であること、気持ち良い状態であることが、良い経済にとっても不可欠なことであり、初手であるとも言えるでしょう。
ですので、私達コーチは、この図を構成する個々人。クライアント一人一人がご機嫌である為にどのようなリソースや条件や状況や環境が必要なのか。個別化されたそれぞれの条件や構成を見出していくために「観察」と「探索」。そして、その「言語化」に秀でていなければいけないということになるわけです。
コーチングに際してクライアントから出てくる言葉の多くは、ふわっとしたイメージで抽象的なものが多いでしょう。そして、コーチ側では意図せずにクライアントの発した形容詞を自分勝手な理解で「わかったふり」をしていることがよく見受けられます。
これ、本当に惜しい、残念な瞬間です。よい傾聴で引き出せた「素材」をそのままにしてしまっています。この「素材」を調理するように、問いで具体化し、クライアントが理解できる「名詞」へと変えていき、
「そうそう。この料理が食べたかったんだよ」
と感じるかのような納得、腹落ちした状態の自己認識をクライアントに作れるか。ここでコーチングのこの先が一気に変わってくるのです。
☆ネガティヴ感情のメッセージとは?
そのうえで、よいコーチの関わりとして、ネガティヴな感情を否定しないことはいうまでもありません。むしろ、コーチとしてクライアントのネガティヴ感情と向き合えないことで、成長出来ていないコーチも少なくないように思います。
例えば、コーチが未来や幸せに関する質問ばかりの態度をとってしまっていると、クライアントからは「そんな理想的な人間ではない」といった感情や反応も生まれるでしょう。
あるいは生産性をあげるという大義名分でクライアントに「我慢」「忍耐」という感情を生みだす習慣化を強いるような人もいます。が、これはもはや「コーチ」と呼ぶに値しません。目先の改善という成果を伝えればクライアントの会社から報酬はもらえる「理由」にはなるでしょうが、クライアント自身はその時からずっと内に対立する感情を抱えることになり、長期的には会社の生産性を下げることにすらなってしまうからです。
これらは「型」や「我流」から脱却できていないケースに起こりがち。「守」のままでは不十分・というわけです。
一方で、クライアントのネガティヴな感情は向き合ってみると様々な情報、リソースにあふれていることがプロコーチは数多く体験していることと思います。
ここから先は
¥ 300
ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。
