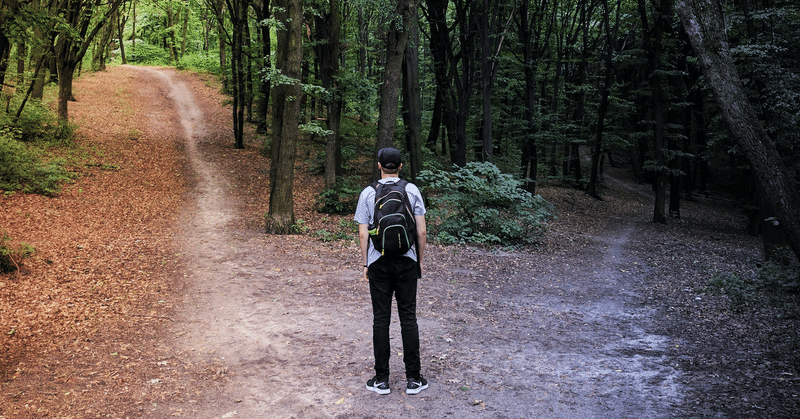
意思決定論1/2
最近触れる機会の多い、意思決定というテーマについて、気になったことをノートしていきます。AIに関する考察を含め、初学者なので詳しい方からするとだいぶ的外れな見解が含まれていると思いますが、あくまで私的な見解としてご覧いただければ幸いです。
AIによって人間の意思決定の精度は高まるのか?
恋愛のように、人間も経験を積めば積むほど、意思決定の精度は高まると言われている。なぜなら時間の経過と共に経験値が増えて、判断材料が増えるからだ。しかし、この短い人生においては、十分な経験をした段階ですでに、歳を取り過ぎてしまっているということがしばしば起こる。それならば、人々の行動パターンを機械学習を通じて AI に学ばせて、誰でも合理的な意思決定が行えるようにするのはどうか?そうすれば、あなたはその都度、最良の意思決定がタイムリーに行えるかもしれない。つまり、意思決定を下す際に、自分が十分な経験を積んでいなくても、それまでの人々の経験を基に、科学的に最も合理的な意思決定をAIがアシストすることで下せるのである。
1 人でも多くの人々を効率的に幸せ(それが本当の幸せかはここでは別として)にする手法として、この手段はとても合理的に聞こえる。しかし、この点に関し、敢えて苦言を呈するのであれば、AI の機械学習的な判断を人間の意思決定に適応することで、結果的に「望めば手に入るものしか望めない人間」になってしまうのではないか、という懸念を私は抱いている(*1)。
(*1)村上春樹著「騎士団⻑殺し」の中で、IT 企業の経営者として成功し、莫大な富を手に入れた免色(メ ンシキ)という人物が、50 代になり、自分の人生を振り返った時に、以下のような発言をしていることに インスピレーションを受けて借用。P.269「あなたには望んでも手に入らないものを望むだけの力がありま す。でも私はこの人生において、望めば手に入るものしか望むことができなかった。」
AI 開発に対する批判的見解
初学者であるので、あえて批判的に AI(機械学習)開発の論点を取り上げてみたい。 意思決定が「合理的」であったか否かを判断するのが、同じく AI なのか、人間なのか、人間だとして、どの立場から判断するのか、それによって意思決定の評価は全く異なる。例えば、飼い犬のポチにとってより合理的な選択を、飼い主がポチの生涯に渡って行ったとする。飼い主は常に最善と思われる選択を合理的に行ってきたので、きちんと責任を果たしたつもりでいる。しかし、果たしてそれは、ポチにとっては合理的な生き方であったのだろうか?自分の運命を決めてきた意思決定が合理的であったと知ることな く、一生を終えた場合、それはポチの人生にとってどんな意味があったのだろうか。
「意思決定」という言葉はビジネスシーンでもよく聞く。しかし「意思決定とは何か?」について、その正体をきちんと語れる人間は多くはないと感じる。政治でも経済でもスポーツでも、勝敗がはっきりするゲームとして考えるのであれば、正しい「意思決定」はあるのかもしれないが、それは「誰」にとって「正しい」と言えるのか?有権者、政治家、株主、経営者、選手、監督、、、ゲームでも様々なプレーヤーが存在する。果たして「誰」にとって最善の意思決定をすることが大事なのか、考えを巡らせる日々は続く。
もし興味を少しでも抱いてくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ2/2やその他も記事もご参照ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
