Teddy Bear Hunt と野花摘みーコロナショックから写真文化を考える
今日もおもしろいニュースをみた。ニュージーランドではじまって世界に広がっているらしいのだけれど、家の出窓なんかの外から見えるところにクマのぬいぐるみをおいておいて、それをコロナの影響で散歩程度の外出しかできなくなったこどもたちが見つける「テディーベア・ハント」という遊びがはやっているらしい。
ためしにインスタで調べてみると、素敵な写真がたくさん上がっている。

同時に、すぐにわたしの記憶と繋がった写真集がある。ジョエル・マイエロウィッツ(Joel Meyerowitz)の『Wild Flowers(野の花)』という、わたしのお気に入りの写真集だ。

マイエロウィッツといえば、1960年代後半に、それまでアートフォトの分野ではマイナーだったカラー写真によって作品を制作しはじめたひとたち(「ニューカラー」と呼ばれるくくりで評価されたりもする)のひとりである。彼らの作品は、自分たちの身の回りの事物を主なテーマにしていて、マイエロウィッツの初期作も、アメリカの日常でありながらどこか神秘的な力が宿っていて、水辺をテーマにした作品集『Cape Light』(1978)は、ホックニーの絵画に相通じる静謐な美をたたえている。
今日紹介したい『野の花』は1983年に出版されたもので、大学生の時に初めて見て度肝を抜かれた。そのへんに生えているタンポポやヒナゲシを撮っているのではない。出窓に飾られた花、街角の外壁に描かれた花の絵、街をゆく人の花柄のシャツなどの「野花」が収められているのだ。
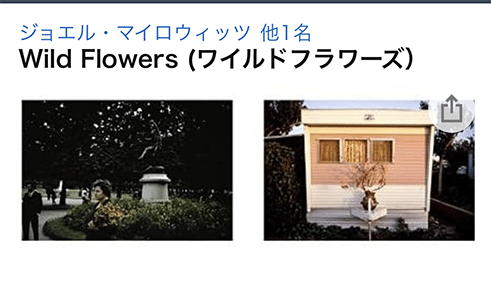

コレクションというのは古代からつづく人間の根源的嗜好のひとつだ。集めるものはなんでもよいけれど、あつまったことに意味がある。タレントのみうらじゅんは新聞折り込みの分譲マンションの広告をあつめたら、東京を網羅する空撮写真の地図ができたと言っている。これが、コレクションのおもしろさ。
コレクションと写真は1850年代なかばに結びつき、人々のあいだでは名刺サイズの人物写真、長じて美術作品の複製写真をコレクションが大流行した。1861年にイギリスのアルバート公が亡くなったとき、妻のヴィクトリア女王の名刺判写真は一週間で7万枚も売れたという。時を同じくして、海をわたったアメリカでリンカーンが大統領選のために自分の写真を全土で配って大成功したというのも、この流行と無関係ではないのではとわたしは思っている。
マイエロウィッツに戻ると、写真家の仕事というのは、えてして「写真をコレクションする」ではなく「写真でコレクションする」という側面があろう。「なにをコレクションするか」はコンセプトということになるが、写真で野花摘みをするという発想はとても斬新で繊細なものに思える。
「#teddybearhunt」も、結果として似たような発想になっている。だが、それを一堂にまとめる場は写真集ではなく、インスタグラムというプラットフォームになっているし、「ハンター」たちは一人でなく世界中にいる。みんなでつくるテディーベア・コレクションが、コロナを克服しようという世界中のひとびとの旗印になればいいなと思う。蛇足だが、マイエロウィッツも「Wild bear」をハントしてくれたら素敵だなと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
