村上仁一写真集『地下鉄日記』ーやみくろが跋扈する地下道をめぐって
地下鉄にはそれとなく、ジャック・ケルアックの気配が漂う。
新刊・村上仁一写真集『地下鉄日記』によせた森山大道の文章冒頭のエピグラフである。
地下鉄は不思議と、いや、ある意味で必然的に不安と結びつく。例えば1900年パリ万博にあわせて開通した地下鉄はドアが内側から開けるすべなく閉められ、車両間の移動が不可能だった。それゆえ、強盗や犯罪に端を発する死の恐怖についての証言が多く残されている。
19世紀から20世紀初頭の鉄道車両自体、だいたいが同じ構造になっていたが、やはりその恐怖を過度にあおるのは風景のない、無機質な暗闇の中を走っているからだろう。パリ、ローマ、ニューヨーク・・・欧米の大都市では、つい10年くらいまで落書きだらけの車両が走り、窓はすすけて薄汚れ、よっぱらいや薬物中毒者が駅にうろついていた。わたしがパリに暮らしていた2010年ころでさえ、早朝や終電近い電車内ではドラッグをやっている輩がいたほどである。
東京の地下鉄はそれにくらべれば遥かに安全な交通手段である。車両は綺麗だし、ホームや車内では泥酔している人くらいはいても、タバコを吸う人がいたり、恐喝が横行しているというわけでもない。それでもなお、不安はシミのように張り付いている。
今回、村上の『地下鉄日記』は2バージョンの表紙で制作されている。わたしが選んだのは右のほう(収載作品のサンプル画像はリンク内にあり)。
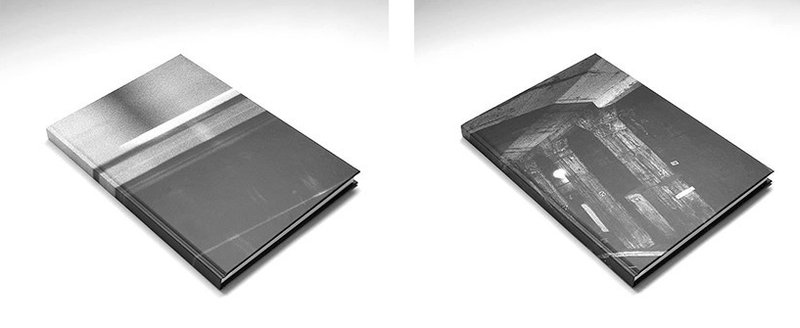
なぜかといえば、それがすぐにある物語を思いだしたからだ。ちょっと長いけど引用してみよう。
「出口?」「ここから地上に出る出口です」「時間がかかるし、やみくろの巣のそばを通ることになるがかまわんですかな?」「かまいません。こうなると怖いものなんてもうあまりありませんからね」「よろしい」と博士は言った。「ここの岩山を降りて水面に出ます。〔……〕向う岸の壁の水面の少し上あたりに小さな穴が開いておるです。そこをつたっていけば下水道に出ます。その下水道がまっすぐに地下鉄の軌道に通じておるです」「地下鉄?」「はい、そうです。地下鉄銀座線の外苑前と青山一丁目のちょうどまん中あたりですな」「どうして地下鉄なんかに通じているんですか?」「やみくろたちは地下鉄の軌道を支配しておるからです。昼間はとにかく、夜になると奴らは地下鉄の構内を我がもの顔に跋扈しておるです。東京の地下鉄工事がやみくろたちの活動範囲を飛躍的に拡げたというわけです。なにしろ奴らのために通路を作ってやったわけですからな。彼らはときどき保線工を襲って食ったりもするですよ」「どうしてそれが明るみに出ないんですか?」「そんなことを発表したらえらいことになるからです。そんなことが世間に知れていったい誰が地下鉄に勤めますか? もちろん当局はそのことを知っておって、壁を厚くして穴をふさいだり、電灯を明るくして警備しておるですが、それしきのことでやみくろたちがふせげるというものではない。奴らは一晩で壁を破り、電気のケーブルを食いちぎるのです」(村上春樹『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』新潮社、1985年)
地下鉄の光が届かないところには「やみくろ」がいる。なるほど、たしかに地下鉄の線路わきには、むかし汚いスニーカーが片っぽだけ打ち捨てられたりしていたものだ。なんとなく、そんな情景とハードボイルド・ワンダーランドの描写がつながっていく。そういえば、村上春樹はデビュー作でも少し違和感をおぼえる書き方で地下鉄に触れている。
(「僕」が関係をもった)二人目の相手は地下鉄の新宿駅であったヒッピーの女の子だった。彼女は16歳で一文無しで寝る場所もなく、おまけに乳房さえ殆んどなかったが、頭の良さそうな綺麗な目をしていた。それは新宿で最も激しいデモが吹き荒れた夜で、電車もバスも何もかもが完全に止まっていた。「そんな所でウロウロしてるとパクられるぜ。」と僕は彼女に言った。彼女は閉鎖された改札の中にうずくまって、ゴミ箱から拾ってきたスポーツ新聞を読んでいた。(村上春樹『風の歌を聴け』講談社、1979年)
大江戸線も都営新宿線もまだない。そこは丸の内線の改札である。なんで国鉄の改札ではいけなかったのか。これは春樹のこだわりであるように思える。
丸ノ内線とて東京メトロではない。帝都高速度交通営団(通称・営団地下鉄)である。この写真集の中には、営団時代の地下鉄の風景も含まれている。営団が東京メトロになった時期を調べたら、2004年と意外に最近でちょっと驚いた。いうまでもなく、営団地下鉄にかかわるわたしたちの不穏な感情のシミを考えるとき、1995年の地下鉄サリン事件の記憶を避けては通れない。むしろ、30代後半以上の世代はどうしても地下鉄をその記憶と無意識に結びつけずにはいられないのではないだろうか。
この写真集にはサリン事件関係の写真はないし、撮られ始めたのは事件より4年あとの1999年のことである。にもかかわらず、ぼくはあの大きな記憶のシミを意識してしまう。そして、それが引き金になって同時代の数々の凶悪犯罪の記憶が圧縮されて蘇ってくる。いまにして思えば、90年代半ばから後半はかなり特殊な時代だったように思える。
村上仁一が嗅ぎとった、体感した、そんな先の見えない不穏な時代感情がその発端にあるように思えてならない。村上は次のようにいう。
目の前にはいつも不安があった。それは、現実生活の不安というよりはもっと漠然としたもので、自分が生きてのうのうと暮らしていることへの深い憤りのような、何もかもが突然気に食わなくなるといった、脈絡もなく押し寄せてくる不穏な感情だった。いつからか私は、そんな浮き沈みのある自分の精神状態に向けてシャッターを切るようになっていった。(村上仁一『地下鉄日記』序文より)
村上は、1999年当時を写真学生として送っている。時代はあたかも就職氷河期でもあった。繁華街の電話ボックスは一面テレクラの手のひら大のチラシで埋められていた。御茶ノ水駅近くの歩道橋の支柱には終戦55年云々と書かれたビラが貼られ、近くには「テロ・ゲリラに注意」と書かれた立て看板さえ立っていた。20世紀最後とはそんな時代だった。
でも、ぼくは、村上の感情の源泉を時代のせいにしたいわけではない。ましてや、多感な20歳前後の誰にでもあることと片付けたくもない(20年にわたって撮り続けられたものなので、最近撮られたものも収録されている)。「脈絡もなく押し寄せてくる不穏な感情」。そしてそれを表象する手段としての地下鉄。村上春樹にとってもそうではなかったか。不安に飲み込まれそうなヒッピーの少女がいるのは、国鉄の改札ではダメだったのだ。
『地下街の人』『オン・ザ・ロード』『孤独な旅人』。この代表作の書名だけ見ても、森山が「地下鉄にはそれとなく、ジャック・ケルアックの気配が漂う」と言いたくなるのが十分にわかる。『オン・ザ・ロード』はヒッピーのバイブルである。村上春樹が地下鉄の新宿駅で出会ったのも、くしくも「地下街の人」、あるいは「オン・ザ・ロード」のヒッピーの少女だった。
森山が「どことなく」というように、村上の写真とケルアックはどことなく結びつくし、どことなく結びつかない。だが、『オン・ザ・ロード』には20年前の村上に重なるように思える一節がある。
おばは、彼がぼくに迷惑をかけることになるよ、と警告してくれたが、ぼくには新しい呼び声が聞こえ、新しい地平線が見えた。ぼくは若さでそれを信じることができた。〔……〕ぼくは若い作家だから飛び立ちたかったのだ。(ジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』1953年)
この場合、「おば」や「彼」はだれでもいい。村上に有形無形に不安を与え、警告してくるなにものかたちに置き換えられる。1985年当時36歳の村上春樹も似たことを感じたのかもしれない。「やみくろ」は彼らの(もちろん、わたしたちの、でもある)まわりにそれとなく跋扈する社会の虚像なのだ。
自分の感情に向き合った20年。村上春樹が時代の「不穏な感情」を地下鉄にトレースすることで物語を紡いだなら、村上仁一はそれを地下鉄にぶつけて砕けたガラスのように解体し、その破片から再構築していく。ふたたびかたちづくられる時代の記録と村上の感情。ぼくは、それが「不穏な感情」の解体と再生ではなく、ケルアックがいうように「新しい地平線」を見るための村上仁一の感情世界の歴史ではないかと思う。
きっと村上は、「時間がかかるし、やみくろの巣のそばを通る」地下道を抜けた先に新しい地平線が見えるのだと思っていたはずだ。いや、現に見たのだろう。なぜならば、村上の感情と綾になった時代の記憶も、時代の希望も、ここにはぎっしりと詰まっているのだから。
村上が「浮き沈みのある自分の精神状態に向けてシャッターを切るようになっていった」1999年に流行した曲、the brilliant greenの「そのスピードで」の歌詞を思い出したーー「鏡を叩き割るのに 心の鈍らぬそのうちに 悲しい声を この声を投げつけ進む ひたすらに息をして 光のスピードで 気まぐれに星を目指して」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
