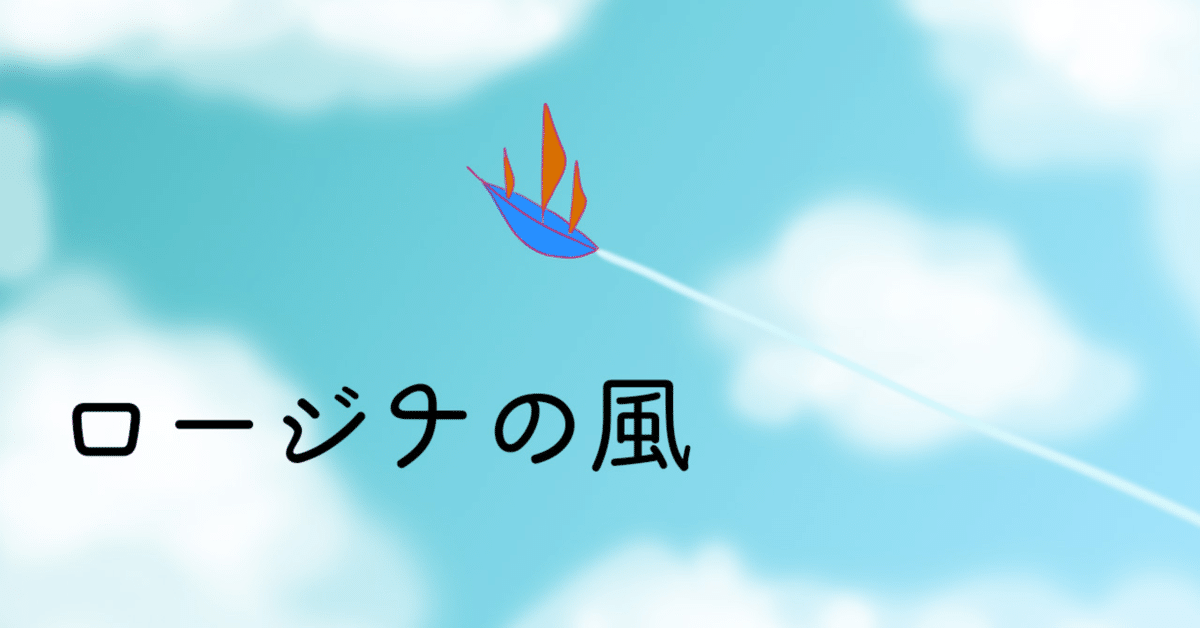
ロージナの風:武装行儀見習いアリアズナの冒険 #206
第十三章 終幕:14
もしケイコばあちゃんの情報統制が上手くいってればだよ。
噂話にすら上るはずのなかった今回のインデックス・索引者案件だった。
いわゆるアリアズナマターは、当事者をそっちのけにして、どうやら知る人ぞ知る大物に成り上がっていたようだった。
「私もうかつだった。
失敗を繰り返すつもりは更々なかったわ。
操り糸はしっかり持っていたはずなんだけどね。
現役を外れて、音羽村であなたと姉妹のように暮らしている内に、私もヤキが回ったのかしらって。
少し落ち込んだわ」
『何が姉妹だよ』
わたしは泣き過ぎて腫れぼったくなっている涙目を、それでも精一杯細めて無言の突っ込みを入れた。
ケイコばあちゃんは、わたしの情けない半眼なぞ平気の平左で先を続けた。
「情報が洩れたことが明らかになってすぐ穴は塞いだのだけれど。
本当に人の口に戸は立てられないわねぇ。
分かってはいたの。
それでも前回つながりで
どうしても秘密を知る人間が多くなってしまったわ。
私的には、慚愧に耐えぬってやつ?
じわじわと噂話が広がって各地の権力層の間で、索引者っていう存在が都市伝説みたいな独り歩きを始めちゃったのよ」
そうした経緯に危惧を覚えたか。
何らかの利権の匂いを嗅ぎ取ったか。
やがて桜楓会と名乗るおたっしゃクラブ内のインナーサークルまでがしゃしゃり出てくる。
そうして二度目は捨て置けぬと前口上を述べて、あたしんち関係のごたごたに介入してきたんだと。
・・・桜楓会ってさ。
アレックスさんとシャーロットさんの口の端に上っていたカルトのことだよね。
「桜楓会って・・・胡散臭そうなカルト・・・集団って、おばあちゃんが会長・・・なんでしょ?
シャーロット・・・さんがそう言って・・・たよ?」
「あら、もう知ってたの。
カルト集団と言うのはご挨拶ね。
まあね。
アンにしてみれば、当たらずと言えども遠からずか。
私だって最初は『この際、ぶっ潰してやりましょ』って思っていたのだけれどもね。
それはそれで利用価値がありそうだったので、考え直してマルっと乗っ取ったの」
ケイコばあちゃんはこともなげにサラッとおっしゃった。
わたしはあんぐり口を開け鼻水が垂れるのもそのままに、ケイコばあちゃんの顔を穴が開く程見つめてしまったよ。
この場にタケちゃんが居なくてホントに良かった。
だらだらと鼻水を垂らしながらの泣きっ面で、ヒックヒックしゃくりあげながら、おまけにポカン顔だなんて。
そんなの乙女が人目に晒してよい相貌じゃない。
「桜・・・楓会?・・・何なの・・・それ」
新たなグループの登場でわたしはこの星の大人たちのサークル活動好きに、せぐりあげながらほとほと呆れ返ったことだった。
「桜楓会と言うおたっしゃクラブ内の特殊部会については、私も昔から気なっていたの。
少し調べたことがあったのだけれどね。
前回の時は音無しの構えで、私の邪魔になるようなサークルじゃ無さそうだったの。
他にもやることが山積みでね。
毒にも薬にもならないなら『まっ。いっか!』って思って、そのまま放置していたの」
実のところ、わたしの家族を含め姉の一件に関係したおたっしゃクラブの人間は、けっこう沢山いた。
だけどその人達と桜楓会の間には、この時まで繋がりどころか接点もなかったらしい。
あちらこちらに張り巡らせた情報網の網元として、権謀術数と情報操作にその才能と情熱を傾けるケイコばあちゃんだった。
そのケイコばあちゃんにして、桜楓会と言うインナーサークルの実態を把握できていなかったのだ。
ケイコばあちゃんは『放置してた』とか事も無げに言ったけれど、実は良く分からなかったと言うことだろうね。
本気で調べなかったからなんて言い訳は悔し紛れの感じ?
だけどインテリジェンスマスターのケイコばあちゃんがその程度だったとなると、桜楓会の存在はかなりディープな内緒ごとだったのだろう。
おたっしゃクラブ内の選ばれし力持ちの間でも、桜楓会あたりの事情については秘中の秘だったということだ。
そもそも桜楓会とはなんぞや?
「まあね。
とんでもない所から、索引者とか検索者なんて言葉が聞こえてくるようになったからね。
これは何かあるってピンときたわ。
実際お会いしてみれば、寝惚けたような爺婆なの。
そんな爺婆が桜楓会の代紋を引っ提げて、いきなり偉そうに押し出してきたのだから、それってどうよ?
おまけに桜楓会の爺婆は上流階級だなんて自称して、私にマウントまで取ってくる始末よ。
笑っちゃった」
ケイコばあちゃんは呆れちゃうわよねと口角を上げた。
「アリアズナマターに美味しい利権の種でもあると思ったのかしら?
巨視的に見れば、当たらずといえども遠からずなんだけどー。
この私相手に良くもまあ戯けた大呆けかましてくれたものよ。
一枚噛ませろって、ホントもう煩くてね。
放置してたのはまずかったかも。
なんて、改めて思ったの」
ケイコばあちゃんは、頭の周りを飛ぶハエでも追うような仕草をして見せた。
「例えて言えば、桜楓会はおたっしゃクラブの理念的核心に相当する寄合ね。
有力ブランチからスカウトされた極少数のお年寄りで構成される委員会のようなものと言ったら良いかしら。
こっちはおたっしゃクラブの理念に従って事を運んでるのだから、黙ってお金だけ出してれば良かったのに、って。
今になっても思うわ」
ケイコばあちゃんはやれやれと小さな溜息をついて、首を左右に傾げながら男の子みたいにぐるぐると右の肩を回した。
ケイコばあちゃんは桜楓会のお年寄り達に何かしたに違いない。
ぞわっと背筋が寒くなったもの。
「大災厄のおかげでロージナからはライブラリーも多次元リンクも失われてしまったの。
ロージナは新たな知識を生み出すどころか科学文明を維持することすら難しくなったわ。
アンも知る通り、ロージナのしょぼすぎる千年紀はそうして大災厄と共に始まったの」
ケイコばあちゃんによる桜楓会についての講釈は、ロージナ千年史の基本の基から始まった。
「おばあちゃん・・・と・・・ふたりきりの時・・・もわたしはアンなの?」
頭はかなりはっきりしていたけれど、わたしのしゃくり泣きはまだ収まっていなかった。
「あたりまえでしょ。
上手の手から水が漏れるって例えを知らないの?
わたしは完全な人間ではないわ。
だからね。
少しでも間違える可能性は減らしたいの。
あなたの命が掛かっているのだもの」
正直、孫娘をこんな目に遇わせておいてどの口がそれを言うと思った。
けれども、ケイコばあちゃんの緑色の瞳は真っ直ぐで澄んでいた。
わたしは自分の中のケイコばあちゃんに対する評価を一時保留にした。
「話を元に戻すわね。
子供でも知っている大災厄と名打たれたロージナのカタストルフでは、ご先祖様達の身に実に様々な災難が降り掛かったわ。
中でも群を抜いた最大最悪の厄介事は多次元リンクの消失ね。
多次元リンクの消失は、同時にライブラリーへのアクセス遮断を引き起こしたの。
そのことは多次元リンクに制御された社会インフラや、実生活を支える各種システムが完全に停止することも意味した。
ロージナ市民が享受する満ち足りた衣食住と安全安心快適な日常は、瞬時に壊滅的打撃を被ったと言うこと」
それでもロージナという辺境にある星にとって、本当の意味で深刻だったのは知財の喪失だったと、ケイコばあちゃんは続けた。
地球から持ち込んで代々引き継ぐとともに、僅かながらも新知見を付け加え、文字通り手塩に掛けて育てて来た人類が人類たる証。
文明という名の知恵と知識と創造の集積。
それをまるごと失ったのは想像以上に深刻な事態だった。
ライブラリーがあまねく全ての情報を、一元的に統括管理するシステム故の惨事だった。
「みんなもうあまり考えなくなっているけれども、本来ロージナは地球を母星とする植民星なの。
大災厄の時ははまだ植民星としての本格的経営は始まっていなかったわ。
まんまロージナは開発途上だった。
独立して生計を営んでいた訳じゃなかったからね。
大災厄当初は地球や近隣の植民星からの救援や支援を、当然のこととして期待し当て込んでいたのよ。
多次元リンクは星間通信ともプラットフォームを共有してたからね。
データ通信の遮断は非常に分かり易い、ロージナに異変アリの信号だったはずだから」
それにも関わらず、待てど暮らせど他の人類社会から差し向けられる、御用聞きはおろかお見舞いすら皆無だったのだ。
自分達は見捨てられたのか、ロージナ以外の人類世界にも同時多発的に何か壊滅的異変が生じたのか。
ただ事ならぬ何事かが、銀河に広がった人類の版図に起きている。
ご先祖様達はそう推測して見たものの、まるでロージナだけ仲間外れの様な状態で、いたずらに年月だけが過ぎて行った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
