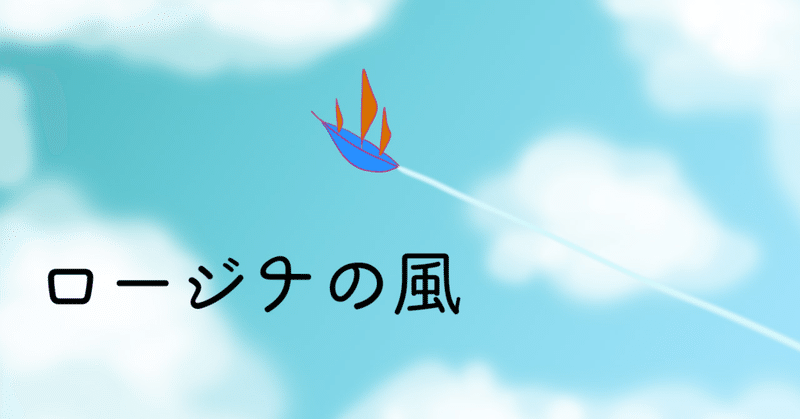
ロージナの風:武装行儀見習いアリアズナの冒険 #204
第十三章 終幕:12
「お嬢さん。
良く頑張りましたね。
残念なことに、あなたの並外れた命がけの冒険譚が、歴史の本に載ることは無いでしょう。
けれども、あなたの勇気と立派な振舞は、志ある者達の間で、未来永劫語り継がれていくことでしょう。
まずは皆を代表してありがとうを言わせて下さい」
柔らかな笑みを浮かべた老ポストマンは、振り上げた拳の持って行き場を失い、呆然と立ち尽くすわたしに向かって、深々とこうべを垂れた。
老ポストマンの誠実は疑いようもなく、わたしはさっきとは別の意味で言葉を失った。
彼はしばらくそうして腰を折ったままだった。
やがて面を上げると、慈愛としか表現のしようがない眼差しをわたしに向けて、頭の上に大きな手を置いた。
それはいつかと同じ。
ごつごつした、けれども暖かくて優しい手だった。
「少し落ち着いたら大事な話があります。
あなたもきっと驚きますよ」
そう言い残して心優しい隻腕の老ポストマンは、アレックスさんとハイテンションで盛り上がる色ボケケイコばあちゃんの下へ、ゆっくり歩いて行った。
老ポストマンの瞳と掌は、まるで魔法の様にわたしの荒ぶる魂を鎮めた。
正直言わせてもらえば、タケちゃんを前にした時みたいなトキめきなんかまったくなかったけどね。
J・Dに感じた類の包み込むような思いやりの気配が、すっかりやさぐれてしまったわたしにはとても心地よかった。
どうせまたろくでもない悪巧みの相談でもしていたのだろう。
ケイコばあちゃんが、わたしの前に再び姿を現したのは、その夜もだいぶ更けての事だった。
第一折半直の三点鐘が鳴るころ船室に夕食が運ばれてきた。
シャーロットさんと二人で世間話をしながら食事をして、デザートのフルーツブナを楽しんでいると、まず彼女にお呼びが掛かった。
第二折半直の一点鐘が鳴る前だから、午後の六時を少し回ったころだったろうか。
スキッパーもソルベーグ号で勤務するシリウスちゃんの所へ遊びに行ってしまった。
シリウスちゃんはスキッパーと同じ歴戦の甲板犬。
クールでチャーミングなドーベルマンの女の子だ。
そりゃ、しょぼくれちまったわたしの相手をしているくらいなら、可愛子ちゃんとお近付きになる方が楽しいだろうよ。
わたしはスキッパーにも置き去りにされ、船室にひとりぼっちのまま取り残された。
仕方ないのでわたしはケイコばあちゃんから渡されたマニュアル。
分厚いアンブックスに目を通して時間を潰した。
アンの人となりはほぼアリアズナと同じで、妙な造り込みの必要は無さそうだった。
経歴と生育環境がアリアズナと似た様な設定になっているのも助かった。
どうやって仕込みをしたのか分から無いが、目立ち易い人間関係も、名前を入れ替えればまんまアリアズナの人生とそっくりだった。
驚いたことに、ディアナに相当する幼馴染の女子まで用意されていた。
深読みをすると中々に興味深いアンブックスだったが、花摘みタイムで集中が切れると嫌気がさした。
何だかこの世の全てが虚しくなった。
手遊びに遺書なんぞをしたためてもみた。
やがてあまりの退屈に痺れが切れた。
こうなったら、メインマストによじ登って、当てつけに身投げでもしてやろうかと思った頃。
初夜直の八点鐘が鳴った。
当直の交代を見計ったかのように、いきなりケイコばあちゃんが部屋に入って来た。
鐘の音からトータルすると、わたしは都合六時間弱ひとりで捨て置かれたことになる。
「おばあちゃんには命懸けの苦労を強いた孫娘に対する、思いやりや気遣いってものが無いわけ?」
別に悲しくはなかったが顎が震えて涙が自然と出た。
ここまでは作戦通り。
怒りが届かないのなら、ここは泣き落としが有効かもしれないと考えたのだ。
何時間もひとりぼっちで過ごしていたので、作戦立案に使う時間はたっぷりあった。
・・・あんなケイコばあちゃんでこんなわたしだけれどもね。
いざケイコばあちゃんとふたりきりに成ったら懐かしいやら腹立たしいやら。
そしてちょっぴり甘えたい気持ちやらが混ぜこぜのカクテルになって胸に溢れちまった。
気が付けば、わたしの現身は彼女の胸で泣きじゃくっていた。
とんだ醜態だった。
人の目が無い場だったので、これはわたし的には計算外で突発した感情の爆発だった。
そうとしか説明のしようがない。
わたしは当初。
あくまで計算づくの泣き落とし作戦で、ケイコばあちゃんから情報を引き出そうと思っていたんだよ?
泣きじゃくりながら、わたしはケイコばあちゃんを責め続けていたらしい。
そこのところはよく覚えて居ない。
何年ぶりだろうか。
おばあちゃんはよしよしと言いながら、泣き喚くわたしを抱きしめ続けてくれた。
高ぶった感情が治まってから、ケイコばあちゃんに紅茶を入れてもらった。
久しぶりに飲むおばあちゃんの紅茶を・・・。
遺憾ながら楽しみつつ、筋道立てて語られる事の次第にわたしはおとなしく耳を傾けた。
隠されている事実や出来事も多いのだろうなと言う印象だったが、教えられたことに嘘はなかったと信じたい。
話半分と突き放して俯瞰して見ても、色々な疑問の内七割くらいは解き明かされた勘定になる。
ケイコばあちゃんの話しが終わった時、わたしは腫れぼったい目が鬱陶しいなと思いつつも、まだ鼻を垂らしながら時折ひっくひっくとしゃくり上げていた。
意地も矜持もあったものではなかったが・・・。
計画通り、泣き落とし作戦は成功したのだろうな。
ここは勝ち鬨を上げるべきところだったので、心の中で無理矢理ガッツポーズを取ってみた。そんなわたしの子供っぽい負けん気に気付いたのかな。
愛し気?な眼差しをわたしに向けていたケイコばあちゃんの瞳が、今にも笑い出しそうな色に変わった。
彼女のなんでもお見通しといった毎度お馴染みの上から目線が、この時ばかりはえらく癪に障った。
『おあいにく様。
白くて素敵なワンピースの胸元を、涙と涎と鼻水で台無しにしてやったので相打ちだよーん!』
わたしの中の人が心の内側に向かって大声で悪態を吐き高笑いした。
だがしかし、ケイコばあちゃんから聞かされた事実は重かった。
パラダイムシフトとはこのことを言うのだろう。
ケイコばあちゃんの話しを聞く前のわたしと聞いた後のわたしは、まったくの別人になってしまった。
アリアズナとアン以上にね。
わたしはまったりのほほんと生きる道を永遠に閉ざされた。
そのことだけはよーく、分かった。
ケイコばあちゃんの話しは実に奇怪至極だった。
彼女がお茶を入れてくれた時、わたしは声涙あわせくだると言う状態をさすがに脱してはいたものの、鼻水は垂れているし子供の様なせぐりあげも続いていた。
けれども熱いお茶を啜り彼女の語り口に集中する内。
わたしはいっそ荒唐無稽とさえ思えるロージナの珍談的歴史秘話に、次第に深く引き込まれていく自分を止める事が出来なかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
