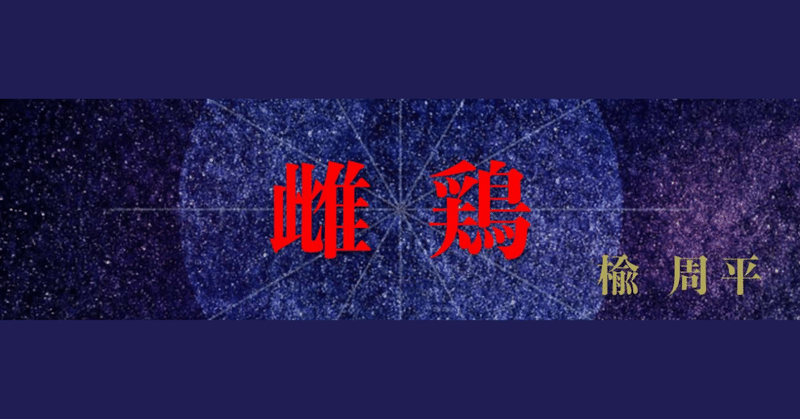
雌鶏 第四章 2/楡 周平
3
「坂道を転げ落ちるように」とは、凋落(ちょうらく)の速さを比喩する言葉だが、逆の場合にも言えるのだと清彦(きよひこ)は思った。
手形金融に続いて清彦が始めた主婦金融は、予想を超える大商いとなった。
まずは、尼崎(あまがさき)の大手製鉄会社の社宅の郵便受けに「担保不要、審査ナシ、電話一本で即融資」と謳(うた)った広告チラシを入れたところ、ちょうど夏の賞与を翌々月に控えていたこともあったのだろう。半月も経(た)たぬうちに、融資を申し込む電話が引きも切らずとなった。
この成功から学んだことは多々あって、その第一は、貸付金を直接自宅に届けることにしたのが大きい。
一庶民にとって借金に対する抵抗感は根強いものがある。まして街金からともなれば尚更(なおさら)だし、事務所に出入りする姿は絶対に他人に見られたくはないに決まっている。
しかし、電話一本で街金が金を届けてくれるとなれば話は違ってくる。しかも、北原(きたはら)は金の届け役に背広を着用させて、さもセールスマンの類が訪問してきたように装うことにしたのだ。
第二に、夫が大企業に勤務する主婦に対象を絞ったことである。
これは全ての商売にいえることなのだが、街金稼業において、最も難しいのが代金の回収である。
取り立ての手段はいくつもあれど、主婦が相手では従来のやり方は通用しない。
なぜなら、一度でも「街金から金を借りるのは危険だ。怖い目に遭う」と認知されれば、悪評は瞬く間に広がり、客が寄り付かなくなってしまうのは明白だからだ。
その点、この主婦金融では、悪評が立つのを恐れるという点では、客もまた同じなのだ。
街金からカネを借りた。返済が滞って、トラブルになった。
そんな評判が立とうものなら、亭主の出世にも響くだろうし、家庭が崩壊しかねない。
つまり、守らなければならないものが大きければ大きいほど、返済は期日通り、確実に履行される。与信審査も、返済が遅れた貸付金の回収の手間も一切不要。最小限の人員で、高い収益を生むことになったのだ。
同時に、確実に返済がなされることによって、トラブルが一切発生しなくなったことで、利用者の間に、淀(よど)興業に対する安心感と信頼感が生じたのが大きい。
そう、確実に返済できる相手を対象に、かつ、短期間の融資に絞れば、一件当たりの融資額が大きくなくとも、チリも積もれば何とやら。結果的に、大きな商売になることを、清彦は学んだのだ。
尼崎での成功に意を強くした清彦は、勢いのまま事業を拡大させた。
神戸、大阪、広島、名古屋と、支店を置き、その度に従業員を増やした。
そして、昭和三十四年。
いよいよ東京に進出という段になって、望外の朗報がもたらされた。
オリンピックの東京開催が決定したのである。
日本初、いや東洋初のスポーツの祭典にして、間違いなく経済の起爆剤となる国家的大事業である。
各種目の競技場、世界各国から集まる選手の宿泊施設、首都高速をはじめとする都市整備、果ては先端技術の粋を集めた新幹線と、建設計画は目白押し。用地買収から始めなければならない案件も多々ある上に、開催日が決定している以上、一日たりとも遅れは許されない。
建設業界が特需に沸くのは当然のことだとしても、問題は建設資材や労働力の確保である。国家の威信がかかっているだけに、政財界はもちろん、国民も協力を惜しまないだろうが、特需とは一定期間に需要が集中することを意味する。
資材や機材、労働力の争奪戦が始まれば、確保の決め手は金になる。しかも、遅延は絶対に許されないのだから、金に糸目をつけてはいられない。
かくして、建設業界は大いに潤うことになったのだったが、下請け、孫請けへの支払いは、相変わらず手形である。
期日が来れば確実に支払われるとはいえ、人件費の支払いは待ったなしだ。手形の決済日までの資金繰りに、頭を痛める中小企業が続出するに違いないと考えた清彦は、東京で開始する予定だった主婦金融を一旦取り止め、手形金融に力を注ぐことにした。
これが、読み通り大成功。しかも、このオリンピック特需は、昭和三十四年の東京開催決定から、昭和三十九年までの五年間もの長きに亘(わた)って続いたのだ。
この間手形金融によって齎(もたら)された利益によって、淀興業はもはや街金とは呼べないほどの資金力を持つ、街金融としては日本一の大会社に成長を遂げるに至ったのだった。
「とうとう東京に城が建ったな……」
昭和四十一年の初出社は、新宿に建設した本社ビルで迎えることになった。
新宿駅の直近、青梅(おうめ)街道に面した新社屋は地下二階、地上七階建て。全面ガラス張りの外観と相まって、周囲のビル群の中にあっても一際目立つ威容である。
その最上階にある社長室で、窓際に立った清彦は、背後に控える北原に言った。
「ほんま、あっという間ですわ……。必死に駆け抜けてきたこともありますけど、社長が尼崎に出てきて、二十年も経っとらへんのですからねえ。あの頃を思うと、正直、夢の中にいるようですわ……」
主婦金融を大成功に導いた北原は、今では専務取締役の重責にある。
最低限の教育しか受けていない我が身を思ってか、北原の言葉には実感が籠っている。
「でもな、城は建ったには違いないが、満足してはいないよ。この景色を見ろよ」
清彦は窓の外に目を向けたまま、顎をしゃくった。「どこを見ても、ビルまたビル。この程度の成功者は、世の中にごまんといるってことの証だ。遥(はる)かに高い場所から、見下ろせる城を建てるくらいになって、はじめて成功者と言えるんだ」
「さすがですわ」
北原は、すっかり感じ入ったような口ぶりで合いの手を入れるのだったが、調子を合わせているように感ずるのは気のせいではあるまい。
「人の一生なんて短いもんだ」
そこで清彦は言った。「二十年も経たないうちにとお前は言ったが、それだけ早く時はすぎるものなんだ。高みから見下ろせる城を建てるにしたって、同じ時間をかけるわけにはいかないんだよ」
清彦の言葉が厳しくなったのを察したのだろう。
北原は、
「はい……」
と短く漏らし、口を噤(つぐ)んでしまう。
「この本社ビルを東京に建てるに当たって、社名から興業を取り、『ヨド』にした理由を、まだ話していなかったな」
「はい……」
新築した東京本社の屋上には、青地に白抜きの文字で『ヨド』とだけ記した大きな看板を掲げた。
淀興業は、万事が清彦の命令一下で動く会社である。社名変更も清彦が独断で決めたことで、異を唱えるどころか、説明を求める者すらいなかった。しかし、今日は新社屋、新社名で迎えた門出の日である。
「実は、今日の年頭の訓示で話すつもりだったんだが、主婦金融の対象を拡大しようと思ってね」
「拡大するって、どういうことです? 主婦金融は、各地でも利用者が根づいて――」
主婦金融成功の立役者だけに、北原が疑問に思うのも無理はない。
「主婦に限定したのを、月給取りなら誰でも手軽に借りられるようにすることで、客を増やし、貸付高を増大させるのさ」
「そしたら、ただの金貸し、どこにでもある街金になってしまいませんか?」
タメ口の、しかも関西弁が出てしまう辺りからも、北原が清彦の考えを理解しかねているのは明らかだ。
そこで、清彦は問うた。
「お前は、ただの街金になってしまうと言うが、本当にそう思っているのか?」
「そ、それは……」
「短期間の間に、これほど多くの主婦が、うちから金を借りるようになったのはなぜだと思う?」
「それは、対象を旦那が一流企業に勤めている主婦に限定したからです。返済が滞れば、周りに金を借りたことがバレてしまう。ややこしいことになれば、亭主の出世にも響きかねないと思うので、きっちり返済してきたからです。結果的に、それがうちは怖い業者やないという安心感を与えるようになったからやと――」
「つまり、街金でも、ウチは怖い業者ではないという評価が、利用者の間に出来上がっているわけだ」
「まあ、そういうことになりますね……」
「なあ、北原……」
清彦は、振り返り様に呼びかけた。「どんな商売にも言えることだが、最も大切で、かつ最も難しいのは信頼を得ることなんだ。街金は怖いというイメージが世の中に定着している中で、ウチはその信頼を得ているんだぜ。それでも、ただの街金なのか?」
自虐的とも思える言葉が北原の口を衝(つ)いて出るのも、分からないではない。
過去とは歴史であり、決して消すことができないもの。中でも出自や学歴は、その最たるものだ。
尼崎の一街金に過ぎなかった淀興業の社員であったなら分相応。己の出自や学歴も、気になることもなかっただろうし、むしろ勲章、時に武器にもなっただろう。
ところが、今や日本一の街金会社の専務となったのだ。
おそらく北原は、その現実に戸惑い、己の過去に引け目を感じているのだろう。
「いや、そうではないのですが……」
北原は視線を落とし、口籠るのだったが、すぐに目を上げると、「なんや、怖あなるんです。だって、そうやないですか。アマの街金で使いっ走りをやっとったワシがですよ。今や、日本一の街金の専務やなんて、下駄を履くまで分からんのが人生やとはいいますけど、我が身にこんな幸運が訪れるなんて……」
果たして、清彦の推察を裏づけるような言葉を口にする。
「そんな人間は、歴史を紐解(ひもと)けばいくらでもいるじゃないか」
清彦は鼻で笑った。「秀吉は信長の草履取りから天下人になったんだぜ。今をときめく、幸之助さんだって、最初は電気屋の親父だ。運に恵まれ過ぎて怖いなんて言ってたら、天下が取れるかよ。第一、先のことなんて誰にも分かりゃしねえんだ。それとも、日本一の街金の専務は荷が重いとでも言うのか?」
実のところ、北原には新たにやって欲しい仕事があったのだが、どう切り出していいものか、考えあぐねていたところだった。
これ幸いとばかりに、清彦は問うた。
「いや、そういうわけではないのですけど……」
再び目を伏せる北原に向かって、
「後先が逆になってしまったが、年頭の訓示の後で、お前に話があったんだ」
清彦はすかさず言った。
「話といいますと?」
「主婦限定から、月給取りなら誰にでも金を貸すとなると、問題になるのは資金だ。客が増えても、貸す金がないんじゃ商売にならないからな」
「確かに……」
「銀行は街金に金を貸さない。ならば、どうやって原資を確保するかだ」
もちろん、清彦に策があるからこそなのは、北原も百も承知だ。
北原は、黙って清彦の次の言葉を待っている。
清彦は続けた。
「そこで、別会社を作ろうと考えてな」
「別会社……ですか?」
「そう、資金を集めるための会社だ」
「そこで何をやるんですか?」
「金の匂いのするところに集まってくるのは、どんなヤツらだよ」
真っ当な答えを期待していないことは明らかだ。
「そら、ヤクザとか、タチの悪い連中ですわ。金が欲しゅうて、懲役覚悟で極道やってるんですもん、儲(もう)かると見れば、一枚噛(か)もうと目の色変えて寄ってきますわ」
「東京に進出して以来、その手のヤツらが、手を替え品を替え、俺にいろんな話を持ちかけてきてな」
「どないな話を?」
「そりゃあ、いろいろとな……」
清彦は、苦笑混じりにこたえたのだったが、すぐに真顔になると話を続けた。
「中でも、俺が惹かれた話が二つあってな。一つは、純粋な出資。もう一つは手形なんだ」
「出資ですか?」
「要は、ウチに元手を貸すってことさ。ヤクザが絡んでいる街金から金を借りるには、相当な覚悟がいるが、ウチには主婦金融で得た信頼がある。第一、怖い先から借りるのは、よほど金に困ったヤツだ。取り立てに手間もかかれば、焦げつくこともあるだろうさ。だったら、多少利子は低くとも、ウチに出資したほうが得ってもんだろ?」
「なるほど……。ヤクザが出した金でも、客はヨドからの借金ですからね。そら安心して借りますやろな」
「その出資を新会社を通して、ウチに回そうと考えているんだ」
北原は、怪訝(けげん)な表情になると、
「ちょっ……ちょっと待ってください。新会社は、どないな商売をしますのん? ヤクザから預かった金をそのままヨドに回すいうなら、ただの又貸しやないですか」
少しばかり慌てた口調で言う。
「手形だよ。ヤクザが持ち込む手形を担保に、ヤツらに金を貸すのさ」
「ヤクザ相手の手形金融ですか?」
北原は、目を剥(む)いて絶句する。
「金に敏(さと)いという点では、ヤクザはピカイチだ。その一方で、金に困ってにっちもさっも行かないでいる会社は世の中にごまんとある。苦し紛れに手形を担保に、ヤクザから借金する経営者は後を絶たないんだよ」
「そやし、ウチとこの手形金融が繁盛しとんのやないですか」
この辺が、北原の知恵の回り具合の限界だ。
清彦は、ため息をつきたくなるのをすんでのところで堪(こら)え、説明を始めた。
「ウチは二枚の手形を預かるが、一枚は確実に決済される会社が振り出したものであるのが条件だ。つまり繋(つな)ぎ融資の意味合いが強いのだが、ヤクザは持ち込んだ会社のものであろうと、他社のものであろうと、一枚でも金を貸す。それも額面から、相当割り引いてだ。だから、今すぐ金を工面できないと会社は倒産。後のことなど考える余裕もないヤツらが、縋(すが)る思いでやってくるんだ」
「そらそうでしょうけど、相手が倒産したら終(しま)いやないですか」
「ヤクザだぞ?」
清彦は思わず失笑した。「倒産したからって、済ますような連中かよ」
「そら、そうでしょうけど……」
「あの手この手で、回収しにかかるってのは、お前もよく知っているだろ?」
「それは、まあ……」
「その点、ウチは全く違う。主婦金融で、金を借りても怖いことにはならないって評判が定着したのを機に、月給取りが気軽に利用できる街金になろうってんだぜ? 手形金融だろうと、ヤクザまがいの取り立てなんかできるかよ」
「なるほどねえ……、社長の考えが分かってきたような気がしますわ」
北原は、さも感じ入ったような口ぶりで言う。
清彦は、その考えとやらを言ってみろとばかりに、軽く顎をしゃくった。
「要は、汚れ仕事はヤクザに任せる。ウチは、ヤクザが持ち込んできた手形を担保に金を融通しただけに過ぎない、一金融業者の体裁を整えようちゅうわけですね」
「その通りだ」
清彦は顔の前に人差し指を突き立てニヤリと笑い、話を続けた。
「面白いのはな、ヤクザが手形と引き換えに金を貸すのは、世間に名の通った会社が結構あるってことなんだ」
「えっ? そんな会社がなんでまた。名の通った会社なら、銀行から借りることかて――」
「この会社で、俺のやることに逆らえる社員がいるか?」
「いや、そら社長の会社でっさかい……」
「大会社といっても様々でな。旧財閥系のような由緒正しい会社は別として、オーナー会社や同族会社ともなると、ウチと同じで、社長の鶴の一声で、万事が通る会社があるんだよ」
街金一筋でやってきた北原が、会社経営に通じているわけもなく、目をぱちくりさせながら話に聞き入るばかりだ。
清彦は続けた。
「中でも一代で会社を急成長させたオーナー経営者は、事業の拡張に貪欲だ。二代目、三代目もまた同じでな。先々代、先代に勝る業績を挙げようと、闇雲に事業を拡張しようとするヤツがいるんだよ。ところが、思惑通りに運ばないのが商売ってもんだ」
「独断で始めた事業なら、なおさらですわな」
北原は、ようやく合点がいったらしく、大きく頷(うなず)く。
「なまじ資金力がある分だけ、突っ込む金額が大きくなるのがこの手の経営者の常でな」
清彦はニヤリと笑った。「なにしろ、己の威信がかかっているんだ。何がなんでも成功させねばと、どんどん金を注(つ)ぎ込むんだ」
「名のある会社の手形なら、取引先も安心して受け取るやろうし、振り出すほうにしたって、支払いは二ヶ月、三ヶ月先ですからね。当面必要な資金を回すには、手形ほど便利なもんはないですからね」
「規模の大小に拘(かかわ)らず、事業で最も難しいのは損切りだ。当たり前だよな。中止、撤退は己の失敗を認めることになるんだ。だから引くに引けなくなって、事業の継続を図り手形を乱発し始める。こうなると、金なんかいくらあったって足りやしねえ。それこそ、乾いた砂に水を撒(ま)くように、金は消えていくだけになるのさ」
「それで、いよいよヤクザのところに、自社の手形を持ち込むことになるわけですね」
「直接持ち込んでくることもあれば、事業の成り行きに不安を覚えた中小の取引先が持ち込んでくることもあるらしい。そりゃそうだよな。裏書きすれば、金として通用するんだし、落ちるかどうか分からない手形なんか時限爆弾を抱えているようなもんだからな。多少損が出ようが、金に替えてもらえるならば、ヤクザだろうが構わないって連中もいるだろうさ」
「不渡りになっても名のある会社なら、回収する方法はなんぼでもありますからね、なんせ、ヤクザはその手のプロでっさかい……」
北原も口元に不敵な笑みを浮かべ、目をぎらつかせる。
「そこで問題になるのが貸付の原資だ。ヤクザだって無尽蔵に金を持っているわけじゃない。ヤツらだって持てる資金を、いかにして効率よく回転できるかで儲けの額が違ってくる。手元の金には常に余裕があるに越したことはないんだ」
清彦は、いよいよ新会社を立ち上げる狙いを続けて話し始めた。
「そこで、新会社では、ヤクザが持ち込んできた手形を担保に、額面通りの金額を貸し付けることにする」
「えっ?」
北原は、俄(にわか)には清彦の狙いが理解できないらしく、またしても目をぱちくりさせる。
「裏書きされていようが、いまいが、ヤクザに持ち込まれた手形を担保に満額融資する金貸しはいやしない。ヤクザだってそうさ。自分たちのところに持ち込まれる手形はワケありに決まってる。だから、満額融資なんて絶対にしない。相当額を割り引いた上で、融資に応ずるんだ」
北原は、ますます清彦の狙いが分からないとばかりに、小首を傾(かし)げるだけだ。
そこで、清彦は言った。
「利子を先払いするんだよ」
「利子の先払い?」
「投資への見返りとしてね」
清彦は一言でこたえ、話を続けた。
「ヤクザは手形の額面を割り引いた上で、持ち込んだ相手に金を貸す。ウチが額面通りの金を貸せば、差額分はヤクザの儲けとなる。ここまではいいな」
「はい……」
「ただ担保といっても形式上のことで、振り出し先が飛んだ時には、融資を受けた金額をヤクザが新会社に返済し、手形を引き取ることにするんだ」
「それやったら、貸付金は戻ってはきますが、ヤクザが儲けるだけやないですか。いや、ヤクザかて、手形が不渡になれば――」
「だから、さっき説明したろ?」
清彦は、北原の言葉を途中で遮った。「担保に取った手形が不渡りになったら、ウチはどうやって回収すんだよ。取れなくなったところから、取ってくるのがヤクザだろうが。ウチがヤツらのような手荒な手段を取れるのか? これから、月給取りに広く使ってもらえる街金になろうってのに、ヨドは怖い会社だって評判が立ったら終いじゃねえか」
「はい……」
清彦の鋭い一喝に、北原は俯(うつむ)いて短く返すのがやっととなる。
「これはな、手元の資金を確保するためにやるんだ。ヤクザだって手元の金に余裕があれば、手形金融を拡大できる。ウチだって同じさ。事業を拡大しようってのに、肝心の元手がなけりゃ、貸そうにも貸せねえだろ?」
「なるほど、元手がいらん商売なんて、あらしませんからね。元手をどんだけ上回る儲けを上げるかが商売ですもんね」
ようやく合点がいったようで、北原は顔を上げ眉を開く。
「それともう一つ狙いがあってな」
清彦は言った。
「もう一つとは?」
北原は喉仏を上下させながら問うてきた。
「政治だよ」
「政治?」
「金の匂いに敏感なのは、ヤクザばかりじゃない。政治家もまた同じでね。政治は数だが、数を確保するためには金が要るんだ」
清彦は、そこでしっかと北原の視線を捉えると話を続けた。
「要は権力とは金の力なんだよ。だから、金に窮すればヤクザだろうが、街金だろうが関係ない。縋る思いで、金策に走るようになるのは、事業に行き詰まった経営者と同じなんだ。そして、金主と借主、どちらが強い立場に立つかは言うまでもない。つまり、ヨドの事業が成長を続ければ、黙っていても政治家が近づいてくる。それは――」
「社長が権力を握るということですね」
続く言葉を先回りした北原の喉仏が、またしても上下する。
清彦はニヤリと笑って見せると、腕時計に目をやった。
時刻は、午前八時二十分になろうとしている。
ヨドの始業時刻は、午前九時だが、今日は年頭の訓示があるので、八時三十分に大会議室に準管理職以上の社員が集まることになっていた。
「時間だ。そろそろ行こうか」
清彦は北原を促すと、先に立ってドアに向かって歩き始めた。
4
昭和四十一年五月。
鬼頭(きとう)がこの世を去った。
脳梗塞の発作に見舞われたのが四年前。後遺症として右半身に麻痺(まひ)が残った鬼頭は、以来床に就く日が多くなった。
しかし、病魔は確実に鬼頭の老体を蝕(むしば)んでいく。
一年ほど経った頃、二度目の発作で重い言語障害を起こしてからは病状が急速に悪化。思考能力を完全に失い、遂に終焉(しゅうえん)の時を迎えたのだった。
青山葬儀場で行われた葬儀には、政財界の重鎮たちが列席したのだったが、鬼頭の死を悼むというより、彼に代わる権力者を披露する場となった。
それは誰でもない。鴨上(かもうえ)、そして貴美子(きみこ)である。
権力者が、権力者たり得るのも健康であればこそ。衰える兆しがあれば、潮が引くように人は離れていくのを熟知していた鬼頭は、最初の発作に見舞われた時点から、己の病状について厳重な緘口令(かんこうれい)を敷いた。
以来、鴨上が窓口となって請願の一切を取り仕切るようになった。
一方、的占を繰り返す貴美子への依存度は増すばかり。しかも、鴨上を通さずして、卦(け)を立ててもらうことはできないのである。かくして、鴨上、貴美子への権力移譲は、鬼頭の死を待たずして、完全に済んでいたのだった。
「策士、策に溺(おぼ)れるとは、まさに先生のことだな」
鴨上が、そう漏らしたのは、鬼頭の葬儀が終わって、ひと月ほど経った貴美子の自宅でのことだった。
「それ、どういうことです?」
貴美子が訊(たず)ねると、鴨上は嘲るように口元を歪(ゆが)める。
「八卦に目をつけたところまではさすがだが、結果的に池田山を訪れるご重鎮方の関心を、先生よりも君に向けてしまうことになったんだ。でなけりゃ、四年もの間、一切表に出てこなくなったら、いい加減、先生の身に何か起きたんじゃないかと勘づくだろうに、最期まで誰も気づかなかったんだぜ?」
「元々、会う、会わないは先生の意向次第だったこともあったんじゃないかしら。お願い事をしたくても、会ってもらえない人のほうが多かったんだし、要件を先生に代わって聞くのが秘書の役目の一つじゃない。鴨上さんに話をすれば、先生に伝わるはずだって思い込みもあったんじゃないかしら……」
「確かに、それは言えているんだよな」
鴨上は、含み笑いを浮かべる。「これだけ長く側に仕えていれば、先生がどう判断するか、どう動くかは、判断を仰ぐまでもないからね。実際、先生が倒れる前も、事後報告で済ました案件も多かったからね。そうとも知らず、池田山を訪ねる連中は、願いが叶(かな)ったのは、全て先生の力添えのお陰と信じ込んでいたけど、そんなことはない。先生が直接動くのは、余程大きな案件か、無下にできない人間だけだったのさ」
つまり、各界の重鎮であっても、鬼頭の中では松竹梅に位づけがなされていたということだが、所詮鴨上は秘書である。鬼頭亡き後、彼が権力を継承することができたのには、もちろん理由がある。
鬼頭が二度目の発作に見舞われ、思考能力がすっかり低下し、回復は絶望的と医師に告げられた鴨上は、
「アメリカには、ロビイストという人間たちがいるそうでな」
突然、貴美子の元を訪ねて来るや、そう切り出したのだ。
「ロビイスト?」
初めて聞く言葉に問い返すと、
「まあ、早い話、口利き屋だ」
鴨上は瞳に不穏な光を宿し、低い声でこたえる。「業界、会社に有利な法案、政策を通すよう、政党や議員に働きかけるのを職業にしているやつらがいるのさ」
「先生がやっていることと、同じじゃありませんか」
「そう、その通りだ」
鴨上は、至極当然のように言い、「ただ、先生の存在は知る者ぞ知る。表には決して出ないが、ロビイストは違う。社会に認知されているというんだな」
意味ありげな笑いを浮かべる。
「それで?」
鴨上が、唐突になぜこんな話題を口にしたのか真意が読めず、貴美子は先を促した。
「事務所を開設しようと思ってね」
「事務所?」
「口利きの窓口になる事務所をね」
「ちょっと待って」
さすがにこれには驚き、貴美子は思わず鴨上を制した。「事務所なんか開いてどうするの? 知る人ぞ知る存在だったから、先生の力に縋ろうと池田山詣でをする人たちが後を絶たなかったわけで、そんなもの開いたら――」
「何が変わる?」
鴨上は、貴美子の言葉が終わらぬうちに問うてきた。
そう言われると、こたえに詰まってしまう。
言葉に窮した貴美子に向かって、鴨上は言う。
「窓口の場所が、池田山から事務所に変わるだけで、やることは何も変わらんだろ? ただ一つ、常駐するのは私で、先生には一切会えないという一点を除いてね……」
それでも鴨上の狙いが読めない。
「まだ、分からないかね」
そんな貴美子の内心を見透かしたように、鴨上はニヤリと笑う。「先生が倒れたことは、まだ誰にも知られてはいない。既に請願、相談事の全てが私の判断、差配で行われていることも誰一人として気がついてはいないんだ。さて、そうなると問題は先生が亡くなった時だ」
「占いが的中するのも、先生に指示されたままを告げればこそ。いきなり訪ねて来られたら、ただの八卦おきになってしまいますからね」
「だから、事務所を開くのさ」
鴨上は、ここからが核心だと言わんばかりに声を潜める。「当面の間、事務所の会長は先生、私が副会長となって、相談や請願を受けつける。そこから先は、今までと同じで、内容によって君に卦を立ててもらうよう勧めることにするのさ」
鴨上の狙いがようやく読めてきた。
「鴨上さんを通さなければ、私に会えないとなれば、先生が亡くなった後も、事務所に行かざるを得ないというわけね」
そうは言ったものの、すぐに新たな疑問が脳裏に浮かぶ。
「でも、先生の力って、政財界に広く、深く、浸透した人脈と、なによりも莫大(ばくだい)な資金があってのことでしょう? 特に政界人は先生の資金目当ての人が――」
鴨上は、貴美子の視線を上目遣いで捉えると、「そこだ」と言わんばかりに顔の前に人差し指を突きたて、
「先生の財産を事務所に移すんだよ」
ぎらりと瞳を光らせる。
「先生の財産を?」
鴨上は頷く。
「先生は莫大な金を持っているが、大半は裏で回る金。つまり決して表には出ない金だ」
「でしょうね。私の見料だって、領収書なんか要求する人はいませんからね。まして、池田山を訪ねる方々は、他人には知られてならないことをお願いに上がるんですもの、尚更でしょうね」
「もちろん、銀行に預けるわけにはいかない。だから、蓄えた金は池田山の地下にある金庫に保管しているんだ」
「地下? 池田山のお屋敷には地下室があるんですか?」
まるで映画の世界のような話だが、考えてみると莫大な金を手にするまでの鬼頭の人生そのものが、常人では想像もつかぬものだったのだ。
鴨上は言う。
「そこには、大きな金庫がずらりと並んでいてね。しかも中に保管されているのは、大半が金融債権なんだ」
「金融債権?」
「ああ……。それも無記名のね……」
それがいかなるものなのか、貴美子には皆目見当がつかない。
小首を傾げた貴美子に、
「まあ、細かい説明は置くとして、金融債権ってのは金融機関に持ち込めば、現金に変えられる。しかも無記名だから、誰が購入したものだろうと、持ち込んだ人間に支払われるんだ」
鴨上は短く説明する。
「まさか、その金融債権を事務所に移そうと?」
鴨上の目論見が完全に読めてきた。
果たして貴美子の言葉に、
「その、まさかさ」
鴨上は平然と答え、続けた。
「金庫の施錠を解くダイヤルナンバーを知る者は、先生と私の二人だけ。帳簿への記載は私の担当だ。まあ、それだけ信頼されていたわけだが、もう先生は終わりだ。亡くなると同時に、先生が手にしていた力がなくなってしまうのは、あまりにも惜しいからね」
「金庫の番号を教えるほど信頼していた先生を裏切るわけ?」
言い分には理解できる部分もあるのだが、どう言い繕っても、裏切り行為以外の何ものでもない。
ところがである。
貴美子は鴨上が発した次の言葉を聞いて、耳を疑った。
「先生が私を信頼していた? そんなことは全くないね」
「だって、鴨上さんは金庫番だったんでしょう? 全幅の信頼を置いてなければ――」
「君、鵜飼靖子(うかいやすこ)が何のために、ここに送り込まれたと思う?」
「えっ……」
突然、靖子の名前が出たことに貴美子は戸惑い、短く漏らした。
「君の動きを監視するためさ。もちろん、私のこともね……」
「だって、靖子さんは――」
「彼女は、聴力に問題なんか抱えちゃいないよ。聴こえないふりをしていただけなんだ」
「まさか、そんな……」
驚愕(きょうがく)のあまり、言葉が続かない。
そんな貴美子に、鴨上は続ける。
「先生は、猜疑心(さいぎしん)の塊でね。まあ、無理もないさ。戦中に莫大な富を手にしたのも、軍部の重鎮や兵站(へいたん)の納入業者、果ては政治家に至るまで、先生が物資を横流しするのを黙認して懐を肥やしたやつがそれだけいたってことだからね。それに、戦争は人の本性を剥き出しにするものだ。己の命がかかれば、平気で人を殺せる。そんな様を、目の当たりにしたんだもの、そりゃあ人なんか信じることはできなくなるさ」
「でも、鴨上さんは別だったんじゃないの? でなければ、金庫の番号なんか――」
教えはしないでしょう、と続けようとした貴美子を遮って鴨上は言う。
「正直言って、私もそう思っていたさ。靖子の聴力に、何ら問題はないと知るまではね……」
「それ、いつ気がついたんですか?」
「先生が最初の脳梗塞を発症する少し前だ。その頃から、先生の体に予兆めいたものが起きていたのかもしれないな。ここでの君と客の会話の内容を、私が報告してもいないのに、先生が口を滑らせたことがあったんだ」
見立ての内容は事前に書面で提出するのが決まりだが、そこは占いの場である。流れの中で、別の相談事を持ちかけられたり、私的な悩みを打ち明けられることがよくある。それが本人が抱えている健康状態や、家族の問題であったりすればしめたもの。直(ただ)ちに貴美子から鴨上へ、そして鬼頭へと報告されることになるのだ。
「この家に常駐するのは、私と靖子さんだけですものね。あなたが報告しなければ、先生が知っているわけがありませんものね」
「先生は、信頼できるのはお前だけだ。自分亡き後は、お前がこの力を継承することになると事あるごとに言っていたんだが、嘘(うそ)っぱちだったのさ」
そういえば、二度目の発作が起きた直後に、鬼頭の介護にあたらせると言って、靖子は池田山に居を移した。
「じゃあ、靖子さんを池田山に移したのは、先生のお世話をするためだけではなかったのね」
「病に臥(ふ)したことは、絶対知られてはならないからね。先生の周囲は内輪の人間で固めなければならなかったこともあるが、それでもどこから漏れるか分からないのが秘密というものだ。だから靖子を監視役として置くことにしたんだ」
「監視役? 靖子さんは、そんな役目を受け入れたの?」
「大金を前にして転ばぬ人間がいるものかね。靖子もその例に漏れず、あっさり引き受けたよ。第一、聴覚障害を装っていたのがバレてしまったんだもの、断ることなんかできるもんかね」
ついに呵々(かか)と笑い声を上げる鴨上に向かって、
「さっき、金庫の中のものを移したと言ったけど、不正に蓄財したとはいえ、先生の個人財産じゃない。相続人がいるでしょうに大丈夫なの?」
鴨上は不穏な光を瞳に宿し、
「先生に家族がいたのは、前に話したことがあったよな」
唐突に問うてきた。
「ええ……。先生が満州に出かけている間に、空襲で奥様とお子さんを亡くしたと……」
「あれも、先生が作ったでまかせなんだ。過去は、ほとんど話さないが、長く傍に仕えていると、ポツリポツリと漏らすことがあってね。それを総合すると――」
そう前置し、鴨上が語った鬼頭の過去を纏(まと)めると、こういうことになる。
信州の田舎の農家の長男で、学歴は尋常小学校卒。広い畑を持っていたこともあって、人手が欲しかったのだろう。十八歳で嫁を娶(めと)り、程なくして長男が誕生した。
しかし、幼い頃から野心家であったらしく、その後家族、故郷を捨てて出奔。上京した後、右翼の政治結社に入った。
鴨上は言う。
「よほど水があったんだろうな。そこから先は、快進撃の始まりさ。なんせ、政治結社ってのはヤクザまがいの一面があるからね。政界、財界だって彼らの存在は無視できない。そこに大戦が起こったんだ」
「奥様や、お子さんは、そのままに?」
「離縁したんだよ。戦争が始まる大分前にね」
「じゃあ、捨てたの?」
「力を持つにつれ、女房が邪魔になったんだろうな」
鴨上は平然と言う。「当たり前じゃないか。学もない。閨閥(けいばつ)もない。政財界の重鎮たちを動かせる地位を目指すなら、何の役に立たないどころか、邪魔になるだけだ」
清彦が自分を捨てた理由を聞かされたようで、貴美子は胸に刺されたような痛みを覚えた。
「先生には相続人がいないんだよ。だから、先生の言葉を信じたのさ」
そんな貴美子の内心を知る由もない鴨上は続ける。
「ところが、長年仕えた私でさえ、先生は信用していなかった……。でもね、失望したと言うより、感心したね。どうやって、これほどの権力を手にすることができたのか。その理由がはっきり分かったし、己の甘さを思い知らされもしたね」
「お金や権力は、あの世へは持って行けないのに、先生は自分の死後、どうするつもりなのかしら……」
鴨上は口角を吊(つ)り上げ、不気味な笑みを浮かべる。
「そんなことはどうでもいい。とにかく、鬼頭清次郎(せいじろう)がこの世を去るのは時間の問題だ。彼の財産の大半は、私がいただく。それすなわち、彼が持っていた権力を、私が継承するということだ」
先の言葉からして、鴨上が鬼頭の生き様を踏襲するのを決めたことは明らかだ。
つまり、貴美子にも信を置かぬと宣言したに等しい。
あれから三年。
鬼頭が持っていた権力の移譲は、鴨上の思惑通りに進んだ。
国会議事堂に程近い平河町(ひらかわちょう)のマンションの一室に開設した事務所には、鬼頭の力に縋ろうと、連日政財界の重鎮たちが訪れるようになった。
人間は、目に見える存在よりも、目に見えぬ力の存在に畏敬の念を抱き、そして恐れる。
神仏を崇拝し、願をかけるのはその表れなのだが、一切表に出なくなったことが、彼らの間に鬼頭の存在を神格化する効果を生んだ。
貴美子についても同じことが言える。
的占を繰り返す貴美子は、不思議な霊力を持った預言者となった。そして、二人に通ずる唯一の人間が鴨上であったのだ。
この四年、鬼頭が病の床にあったことは、葬儀の場で初めて明かされた。
鬼頭の元を訪ねた重鎮たちの中には、鴨上にしてやられたと思った人間も多々いたであろうが、表立った行動に出る者は、誰一人として現れなかった。
なぜなら、すでに鬼頭が持っていた権力は、この間に鴨上の手に落ちていたことに気がついたからだ。
「いよいよ我々二人の時代の始まりだな」
果たして鴨上は言うのだったが、あの日、鴨上が発した言葉を貴美子は今もはっきりと覚えている。
鬼頭が自分に信を置いていなかったことに、失望よりも感心を覚えたと言った。どうやって、これほどの権力を手にすることができたのか。その理由がはっきり分かった。己の甘さを思い知らされたと言ったことを……。
こいつは、清彦と同類だ。
己が野望、己が利益のためなら、人を裏切り、捨て去ることを躊躇(ためら)わぬ人間だ。
それが、「我々二人の時代の始まりだな」だと?
猛烈な不快感、嫌悪感が込み上げ、罵声を浴びせたくなるのを堪え、
「本当に……」
貴美子は静かに頷きながら、微笑んでみせた。
(次回に続く)
プロフィール
楡 周平(にれ・しゅうへい)
1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
