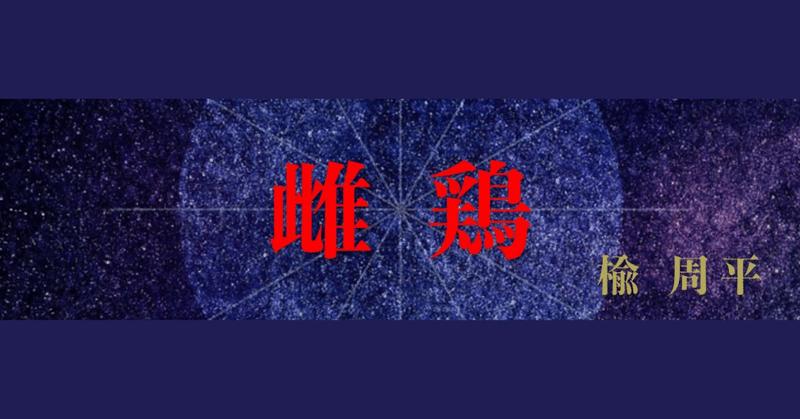
雌鶏 第五章 2/楡 周平
3
応接室に入ってきた男の姿を見て、鴨上(かもうえ)はギョッとした。
暴漢に硫酸を浴びせられ、深手を負ったことは聞いていた。
しかし、その痕跡の生々しさは想像以上だ。
頭髪が抜け落ちた部分を隠すために鬘(かつら)を着用しているのだろうが、素材の質感や光沢が不自然で、違和感を覚えること甚だしい。右側の顔面に残るケロイド状に引き攣(つ)った皮膚。目にも損傷を受けたのか、濃いサングラスをかけており、それがまた外見の異様さに拍車をかける。
「お初にお目にかかります。ヨドの森沢(もりさわ)でございます」
一礼し、差し出してきた名刺を受け取った鴨上は、
「鴨上です。今日は、呼びつけてすまなかったね」
と鷹揚(おうよう)にこたえ、目前のソファーに座るよう促した。
テーブルの上に置いた名刺には、『株式会社ヨド 代表取締役社長 森沢繁雄(しげお)』とある。
「先生のお名前は、以前から存じ上げておりました。お目にかかれて光栄でございます」
繁雄は改めて頭を下げると、正面から鴨上の顔を見詰めてきた。
感情は目に表れるものだが、サングラスのせいで表情が分からない。
そこに異様な容貌が加わると、不気味さが先に立ち、どうもいつもと勝手が違う。
それでも鴨上は、
「事件のことは知っていたが、大変な災難に遭われたものだね。怪我(けが)のほうは大分いいのかね?」
案ずるような口ぶりで問うた。
「もう半年になりますので、医者通いは一応終わりました……。ただ、見ての通り痕跡が残りましたし、視力も低下致しまして……。サングラスを着用させていただくことをお許しいただきたいと思います」
隠すところからして、目にも痕跡が残ってしまったのだろう。
鴨上は怪我の話を切り上げて話題を転ずることにした。
「それで、犯人は捕まったのかね?」
「いいえ……」
「半年も経(た)って、まだ捕まらんのか」
「阿漕(あこぎ)な商売をしているつもりは毛頭ないのですが、どこで恨みを買っているか分からないのが金貸しですので……」
「金貸しねえ……」
鴨上はふっと笑った。「君は、ただの金貸しとは違うだろ? 今やヨドは日本一のサラ金会社じゃないか」
「規模が大きくなればなるほどトラブルも多くなりますから、恨みを買う確率も高くなるわけです。客のメインはサラリーマンや主婦ですし、支店網は全国の主要都市を網羅しております。恨みを買う要因といえば、真っ先に浮かぶのは取り立てですが、返済が遅延している利用者は少なくありませんから対象者、地域共に広すぎて、警察も的を絞れずにいるようでして……」
内心では煮えたぎるような怒りを覚えているだろうに、本心が全く読めないのはやはり目の表情が一切窺(うかが)い知れないからだ。
「随分達観したような物言いじゃないか」
鴨上は薄く笑った。「災難に遭うのも覚悟の上だ。金貸し稼業には、それを上回る魅力があると言っているように聞こえるが?」
「どんな事業でも成功に代償はつきものです。サラ金は担保なしで金を貸すのですから、事前に交わした約束事。つまり契約は確実に履行していただかなければなりません。とはいえ、期日がきても返済できない人は必ず出てきますので――」
「急場を凌(しの)げた感謝の念が、一転恨みに変わるというわけか」
先回りした鴨上に、繁雄は肩を竦(すく)めて同意する。
「取り立ての方法は様々ですが、ウチには専門の部署がありまして、彼らにはもれなく回収のノルマが課されております。成績は人事考課に反映され、賞与、昇級に大きく影響しますから皆必死ですし、そもそも相手の懐具合や事情を汲(く)んでいたのでは、金貸しは成り立ちませんので……」
繁雄の言い分は絶対的に正しい。
サラ金は慈善事業にあらず。借り手の懐具合や事情を一々忖度(そんたく)していたのでは、金貸し稼業は成り立たない。その点は銀行も同じで、返済が滞れば容赦なく担保を取る。要は返済が現金をもってなされるのか、担保をもってなされるのかが違うだけなのだ。
そしてヨドのような大手サラ金と銀行の共通点はもう一つある。
それは、いずれも取り立て役がサラリーマンであることだ。
考えてみれば、法に触れでもしない限り、いや、時に法を犯してでもサラリーマンほど組織の命を忠実に履行する人種はいない。なにしろ与えられた任務を確実にこなすか、目標を達成できるか否かに組織人としての将来がかかっているのだ。
当然、中には血も涙もない行為に走る輩(やから)も少なからず出てくるわけで、それが会社、ひいては経営者への恨みに変わったとしても不思議ではない。
「今回の事件は、日本一のサラ金にのし上がった代償だというわけか」
鴨上が言うと、
「命を取られたわけではありませんのでね。醜い容貌になってしまいましたが、嫁入り前の娘でもなし。そもそも、サラ金には裏稼業というイメージが世間に根付いているのは事実です。表に顔を晒(さら)す機会も滅多にありませんから、果たして代償と言えるかどうか……。まあ、この程度で済むのなら、御の字と言ったところでしょうか」
含み笑いを浮かべる繁雄だったが、やはり本心を語っているのか、強がっているのか、判断がつかない。
「実は今日来てもらったのは、君に訊(たず)ねたいことがあってね」
そこで鴨上は、いよいよ本題を切り出すことにした。
繁雄も察していたのだろう。表情一つ変えることなく、静かに頷(うなず)いた。
「君が最終的に目指しているのは、ヨドを日本一のサラ金会社に育て上げ、さらに事業を大きくすることかね?」
「それはどういう意味でしょう?」
「一介のサラ金会社のオーナー社長で終わるつもりなのか。他に野心があるのかと訊(き)いているんだ」
繁雄はすぐには言葉を返してこなかった。
微動だにせず、サングラスの下から鴨上を凝視し、こたえに考えを巡らしているようだった。
「人間、財をなせば、次に欲しくなるのが地位、名声、そして権力だ」
鴨上は先に口を開いた。「今の話を聞く限り、君は地位、名声には然程(さほど)興味を覚えてはいないようだが、権力はどうなのかね?」
「政財界に隠然たる力をお持ちの先生が、なぜそのようなことをお訊ねに?」
当然の疑問というものだ。
権力者は、己が唯一無二の存在であり続けたいと願うのが常だからだ。
「権力は金があってはじめて手にできるもの。そして、金の多寡で権力者の序列ができあがるものだ。その点から言えば、君は既に権力者の一人になる条件を満たしていることになるのだが、その力をより大きなものとし、影響力を持つ人間になりたいとは思わんのかね?」
繁雄は思案を巡らすように、暫(しば)し沈黙すると、
「確かに多方面から、相談を受けることは多くなりましたが――」
「もっぱら金の相談だろ? それも本業とは別の……」
「はい……」
頷く繁雄に鴨上は言った。
「融通してやれば貸しになる。つまり、相手の上に立つことになるわけだ。それが権力になるんだよ」
「おっしゃることはよく分かります。しかし、サラ金のオーナーに金の相談を持ち掛けるからには、やはり相手にもそれなりのワケがありまして……」
「そりゃそうだろうな」
改めて説明を受けるまでもない。
実のところヨドを知ったのは、つい最近のことだ。
「サラ金業界で、瞬く間に日本一になった会社がある」と、財界人の一人が酒の席で話題にしたのがきっかけだった。
聞けば「手形融資」から始まって、主婦金融、サラ金と事業の領域を広げ、あっという間に全国に支店を持つほどの成長を遂げたのだと言う。
手形金融の仕組みを聞いた時にはなるほどと思ったし、主婦金融とはうまいところに目をつけたものだと感心したのだったが、万事において日本一の座に上り詰めるのは容易なことではない。しかも破竹の勢いで、短期間のうちにヨドをここまでの地位に成長させた経営手腕には尋常ならざるものがある。
もっとも金に纏(まつ)わる事業は綺麗事(きれいごと)では済まない。それもサラ金となればなおさらのことで、タチの悪い輩との関わりは避けられない。
手形金融はその最たるもので、ヤクザにとってもシノギの一つであるだけに、その手の連中とのつき合いもいまだあるのに違いないと鴨上は睨(にら)んでいた。
「表裏一体という言葉があるが」
鴨上は続けた。
「権力はまさにそれでね。表と裏が一体になって、初めて強大な力となるんだ」
「それはどういうことでしょう」
「例えば政治だ」
鴨上は即座にこたえた。「政界は単に政治を司る場ではない。権力を巡って争う場でもある。権力をモノにするためには金がいる。それも表には出せない金がね。要は裏金が必要なんだよ」
まだ話には先があると思っているのだろう。
繁雄は黙って話に聞き入っている。
鴨上は続けた。
「もちろん、発覚すれば政治生命を失うことになりかねない。だからあの手この手、違法、合法のグレーゾーンをついて金を掻(か)き集めることになる。国会は立法府、法律を決める場だ。そして法は権力そのものでもあるわけだ」
「つまり、法を決める権限を持つ議員、それも有力者に貸しを作れば、権力そのものを手にできるとおっしゃるのですね」
繁雄は鴨上の言葉を先回りする。
なかなかどうして、頭の回転が速い。
鴨上は感心しながら、
「その通りだ」
繁雄の見解を肯定した。
「金を目当てに擦り寄ってくる連中は、一旦つき合いができると簡単には離れない。タチの悪い連中は特にそうだ。君にも心当たりがあるだろ?」
「ええ、それはまあ……」
「議員と言っても様々だが、与党の有力者、有望株ともなると力を持つのは事実だ。警察を動かすことぐらいは朝飯前だ。国家権力が後ろ盾になれば、タチの悪い連中だってつき合い方を変えざるを得ないだろうし、何よりも君の今後の事業にも必ず役に立つはずだ」
「役に立つ……とは?」
「サラ金業界だって競争が激しいんだろ?」
「もちろんです。日本一のサラ金会社になったとはいえ、あくまでも現時点でのこと。競争は終わりなき戦いですので、いつトップの座を追われても不思議ではないと、心しております」
「ならば訊くが、君は目指される存在になった自覚はあるのかね?」
繁雄はハッとしたように、僅かに身を起こす。
鴨上は続けた。
「競合する大手他社の目標は、ヨドを追い抜き日本一のサラ金の座に就くことだろうが、街金は違う。目指せ森沢のはずなんだ。中には悪辣な手段を講じることも辞さず、がむしゃらに金儲(かねもう)けに邁進(まいしん)するヤツも多々出てくるだろう。いや、大手にしたって従業員はもれなくサラリーマンだ。そして債権の回収にはノルマが課されている以上、血も涙もない手段も辞さずってことになるんじゃないのかね」
繁雄は黙って話に聞き入っている。
何を言わんとしているか察したのだ。
それでも鴨上は、話を続けた。
「となれば、今回のように感謝の念が恨みに変わり、報復に走る輩が出てくることもあるだろうし、強引な取り立てが社会問題になるかもしれんよな」
「おっしゃる通りですね……」
繁雄は素直に同意する。「正直なところ債権の取り立てに関しては、回収実績を数字で見ているだけで、現場でどんなことが行われているかまでは把握しておりません。今回の件にしても、警察は、襲撃したのがヤクザなら、こんな手段はまず取らない。個人の犯行ではないかと見立てているようでして……」
「借金の強引な取り立ては、マスコミの格好のネタだ。まして自殺者でも出てみろ。街金だろうが大手のサラ金だろうが関係ない。業界を一纏めにして批判報道の嵐がくるだろうさ。問題は政治の場に持ち込まれ――」
「法によって、何らかの規制がかかる。だから国会議員に貸しを作っておいて損はないとおっしゃるのですね」
またしても先回りした繁雄だったが、
「しかし先生、議員と言っても様々です。先に先生がおっしゃったように、野党の平代議士を味方につけても役に立つとは思えませんし、与党にしても力を持つ議員でなければ――」
「もちろん」
今度は鴨上が一言で遮った。「もっとも、力があるだけでは駄目だ。将来性があり、長く現職を続けられる議員を味方につけることだね」
「では、先生に心当たりがおありなんですね」
サングラスの下の目が、緩んだように感ずるのは気のせいではあるまい。
「だから、来てもらったんだよ」
鴨上はニヤリと笑って見せると、「面白い男がいるんだ」
そう前置きし、いよいよ本題を切り出した。
4
「要件は鴨上先生から伺っております」
ヨドの本社ビル。最上階の社長室に小早川(こばやかわ)が現れたのは、鴨上と会ってからひと月ほど経った頃だった。
型通りの挨拶を終え、部屋の中央に置かれたソファーに腰を下ろしたところで、繁雄は早々に話に入った。
「で、いかほどご用意したらよろしいのでしょうか」
恵んでやるわけじゃなし、貸した金を何に使うかは借り手の自由だ。
唐突に、それもあまりにも率直に切り出されて、面食らってしまったのだろう。
小早川は、「えっ」というように目を見開くと、
「四千万円ほど用立てていただければと……」
「分かりました……」
繁雄は素気なく言い、座ったばかりのソファーから立ち上がった。そして、執務机の上に置かれたインターフォンのボタンを押すと、
「四千万だ。すぐに持ってきてくれ」
秘書に向かって命じた。
入室から五分も経っていない。
あっさりと話がついてしまったことに拍子抜けしたとみえて、小早川はキョトンとした表情で繁雄を見上げるばかりだったが、席に戻った繁雄に、
「あの……、条件は……」
法外な利子を課せられるのではないかと不安になったのか、掠(かす)れた声で問うてきた。
「条件? そんなものはありませんよ」
繁雄は、またしても素気なくこたえた。「用途は鴨上先生から聞いておりますが、借金の使い道は借り手の自由。期限までに返済していただければいいだけの話です」
「しかし、利子が――」
「鴨上先生から、直々に面倒を見てやってくれと頼まれたのですから、本業と一緒にするわけにはいかんでしょう。ですから四千万、無利子でお貸ししますよ」
「ほ、本当ですか? お言葉に甘えてよろしいのでしょうか?」
「ただし、借金は借金です。ある時払いの催促なしとはいきませんよ。返済期限は守っていただきます」
繁雄は含み笑いを浮かべたのだったが、鴨上と会った時と同様、鬘にサングラス、しかも顔の右半分にはケロイド状に引き攣れた火傷の跡が生々しく残っている。
社長室に通され、繁雄の顔を目にした瞬間、小早川は顔を強張らせ立ち止まってしまったほどだった。
同じ笑いでも、人相や容貌によって見る者の印象は大きく変わる。さぞや不気味に思えたのだろう。小早川は慌てて視線を逸(そ)らし、「はっ……」と短く漏らすと下を向いた。
ノックの直後にドアが開き、秘書が入ってきたのはその時だった。
「ご用意いたしました……」
繁雄に歩み寄った秘書が、一枚の封筒を差し出してくる。
それを受け取った繁雄は、中から四枚の紙片を取り出し、テーブルの上に広げた。
「では先生。これにご署名下さい」
いずれも額面一千万円の手形である。
中小企業の経営者には馴染(なじ)みのものだが、大企業では手形の現物を目にするのは、営業職か財務部の社員ぐらいのもの。政治家ともなると、まず皆無といっていいはずだ。
「これは、小切手?」
果たして小早川は、怪訝(けげん)そうに問うてくる。
「手形です」
「手形?」
「裏にご署名を……」
「裏に署名すれば、どうなるのです?」
「この場で四千万。現金を用意いたします」
やはり手形を見るのがはじめてならば、仕組みを理解していないのは明らかだ。
小早川は困惑した様子で押し黙る。
「つまり、こういうことです」
繁雄は説明を始めた。「この四枚は、融資の担保としてヨドが預かっている手形です。先生は、手形の仕組みをご存知ないようですね」
「恥ずかしながら、さっぱり……」
「手形は商取引で発生した代金の支払を保証するものでしてね。現金化できるまでに期間がありますが、金券と考えていただければ分かりやすいかもしれません。ですから、担保として通用するのですが、譲渡することもできましてね。手形に裏書きをすると、今度はその人間、あるいは会社に支払い義務が生じることになる。早い話が連帯保証人になるわけなんです」
「ということは――」
「つまり、万が一振り出し人が倒産して手形が不渡りとなった場合、代わって裏書きをした人間、会社に支払い義務が生じることになるのです」
小早川が仕組みを理解したのかどうかは分からぬが、いずれにしても金を融通してもらいにきたのに変わりはない。
「要は、借用書の代わりというわけですね」
果たして、小早川は言い、背広の内ポケットから万年筆を取り出した。
「衆議院議員 小早川宗治(むねはる)とご署名ください」
小早川は繁雄に指示されるまま、四枚の手形の裏に名前を書き込む。
署名が終わったところで、繁雄は再び席を立つと、インターフォンに向かって、
「金を持ってきてくれ」
と秘書に命じた。
繁雄が席に戻る間にノックの音が響きドアが開くと、紙袋を手にした秘書が現れた。
いとも簡単に大金が出てきたことに驚いたのか、小早川は目を丸くして喉仏を上下させる。
繁雄はソファーに腰を下ろし、秘書が差し出す紙袋を受け取ると、テーブルの上に置き、無言のまま小早川の方へ差し出した。そして短く言った。
「どうぞ、お改めください……」
頷いたのか、頭を下げたのかは分からない。
小早川は小さく頭を縦に動かすと、紙袋の中から帯封で巻かれた札束を取り出し、テーブルの上に積み上げはじめる。
一段五束、上に八段の札束を積み終えたところで、
「四千万、確かに……」
小早川は低い声で言い、上目遣いに繁雄を見る。
繁雄は小早川の視線を捉えたまま、
「しかし先生、その程度の金で目的は遂げられるのですか?」
口元を緩ませながら訊ねた。
「えっ?」
「政治の世界のことは皆目分かりませんが、今先生が所属していらっしゃるグループを派閥内でトップにするための資金に充てるんでしょう? 何にどう使うのか、考えはおありなのでしょうが、それにしては額が少ないように思うのですが?」
「そりゃあ、十分とはいえませんが、この程度と言われましても……」
「先生……」
繁雄は表情を消し、硬い声で語りかけた。「先生は派閥内に波風を立てようとする、戦(いくさ)を始めようとしているのですよね」
「ええ……」
「戦は勝つか負けるか二つに一つ。そして勝たなければ意味がない。負ければ一切合切を失ってしまうものですよ」
「承知しております……」
小早川は苦しげに同意する。
「先生、戦で最も重要なのは何だと思います?」
繁雄はこたえを待つことなく続けた。
「兵站(へいたん)、中でも最も重要なのは弾ですよ。戦は戦略が正しくても、指揮官、兵の士気が高くても、それだけでは勝つことはできません。兵站を確保し、敵に勝る弾を送り続けたほうが勝つんです。先の戦争で日本が負けた最大の要因はそこなんです。中途半端な準備で戦を仕掛けたら、命を取られて終わりますよ」
「もちろん弾。つまり資金は多いに越したことはないのは重々承知しております。正直申し上げて、四千万でいいのかと問われれば、あるに越したことはないとおこたえするしか――」
「足りないのなら、出して差し上げますよ」
繁雄は小早川の言葉を遮った。「先生だって、政治生命を賭けて戦に臨もうとしているのでしょうし、鴨上先生直々に面倒を見てやってくれとおっしゃってきたのは、先生を支援したいことの表れだと私は解釈しておりますので」
「心強い御言葉ですが、ではどれほどお貸しいただけますか?」
「いくらでも……」
「いくらでもって……」
話がうますぎるとでも思ったのか、小早川の目が繁雄の魂胆を探るかのように鋭くなった。
「ただし、先生に勝てる確信があればですよ」
繁雄は念を押した。「政治に金がかかるのは重々承知。綺麗事では済まない世界ということも……。ですがね、私は金貸しです。元本に利子をつけて返してもらってはじめて成り立つ商売をしているのです。それを無利子でお貸しするのは、勝るとも劣らない見返りを期待してのことなんです」
「承知しております」
「はっきり申し上げますが、戦に負けた政治家はそのまま議員でいられてもその他大勢の一人。役立たずも同然なんです。金を貸すのも今回限り。返済していただくと同時に縁も切れてしまうことになるのですが、本当に勝てるのでしょうね」
「勝てます」
意外にも小早川は自信満々の体で断言する。
「随分自信がおありのようですが、その根拠は?」
「実は考えを改めまして……」
小早川は口元に不敵な笑みを宿す。
「考えを改めた?」
「鴨上先生からどこまで聞いておられるかは分かりませんが、実は当初の方針を改めまして、菱倉グループから出ることにしたのです」
話が違う。
政界のことに興味はないが、鴨上からは「大河派内で三番目の勢力を誇る菱倉グループの中堅議員で小早川というのがいる。次回の選挙で菱倉グループを大河派内で最大勢力にすべく、資金集めに奔走しているのだが力になってやってほしい」と依頼されたのだ。
そんな気配を察したのだろう。小早川は言う。
「実は先生の勧めで、とある霊能者に卦(け)を立ててもらったのです」
「霊能者って、占い師のことですか?」
「占い師には違いありませんが、恐ろしいほどよく当たると、政財界では知る人ぞ知る、伝説的な女性でしてね。ただ、誰でも観てもらえるわけではありませんで、少なくとも初回は鴨上先生を介さないことには会ってももらえない。伝説的な存在でして……」
また占いか……。
クメが改名を懇願した理由が占い師の見立てであったことを思い出し、繁雄はため息をつきたくなるのをすんでのところで堪(こら)えた。
学もない、まともに職に就いたこともない、高齢のクメが占いを信ずるのはまだ分かる。大きな災難に遭った婿の将来を案ずるあまり、占い師の奨(すす)めで改名を持ちかけた気持ちも理解できる。
だから改名程度でクメが安心するのならと、申し出を受け入れたのだったが、小早川は違う。
俗人の集団とはいえ、仮にも衆議院議員。それも与党の中堅議員だ。国政を託された選良が占いを信じ、己の信念をいとも簡単に変えるなんてあり得ないと思った。しかも、見立ててもらうよう勧めたのが鴨上だというのだから呆(あき)れるしかない。
「それで、先生にご紹介いただきまして、今回の件を見立ててもらったのです」
ところが小早川は、興奮しているのか声に力を込める。「そうしたら、つく相手を間違えていると断言されましてね。その理由を訊ねたところ、今まで党を率いてきた派閥の長の引退と同時に、勢力図が激変する。盤石と思われていた最大派閥内で不協和音が生じ、城を支えてきた石垣が崩壊する。その時、派閥を率いるのは今の二番手だと……」
本気で言っているのか。
ヨドの社員がこんなことを口にしようものなら、一喝して解雇するところだが、仮にも国会議員となるとそうもいかない。
ならば、四千万円を貸し付けたことを後悔したかと言えば、そうではなかった。
小早川に裏書きさせた手形は、落ちればよし。不渡りになる恐れがあるものばかりで、その際には支払い義務を負うのは小早川だからだ。しかも、担保としてもう一枚、こちらは確実に換金できる手形を担保として押さえてあるのだから、ヨドが損害を被ることはないのだ。
話にはまだ先があるのだろうと、繁雄は小さく顎をしゃくった。
「それで、私探ってみたのです」
果たして小早川は続ける。
「そうしたら、最大派閥を率いる大河先生の資金源は、同族経営の企業集団なのですが、先生の後継者を巡って揉(も)めていることが分かりまして……」
「同族経営というなら、血縁者はいずれ役員、社長に就任するのでしょう? 国会議員になるより、企業の役員、社長のほうがよほど魅力的だと思いますが?」
「経営者の判断次第で傾きかねない危険性を常に孕(はら)んでいるのが会社というものです。当代に複数の子供がいれば、後継者争いにも発展しかねませんからね。例えば長男よりも、次男、あるいは三男が優秀だからって、経営を任せることにしたら、そりゃあ揉めますよ。まして娘に優秀な婿養子をとって、後継者に据えるとなったら、直系が黙っているわけないじゃないですか」
その点は小早川の言う通りだ。
ヨドが急成長を遂げ、日本一のサラ金会社になったのは、森沢には子供がミツ一人しかなく、繁雄を婿養子に迎え入れ経営の一切を任せてくれたからだ。もし、息子が一人でもいたならば、後を継がせたとしても、いまだ一介の街金であったかもしれないし、少なくとも今のヨドがなかったのは間違いない。
「しかし大河だっけ、一族が経営する会社がどれほどあるのかは知りませんが、同族経営の会社には、トップを支える優秀な番頭がいて、間違いがないよう目を光らせているものじゃないですか。もちろん、兄弟間で後継者を争って不協和音が生ずる話はよく聞きますが、だからといって国会議員の座を巡って争いになるとは、ちょっと考えられないのですが……」
「国会議員は誰でもなれるものではありませんが、重責を担えるかどうかは別として、大河一族のように盤石な資金源、支持基盤を持っていれば、なってしまえば何とかなるんです」
ところが、小早川はあっさりと言う。「参議院の全国区は別ですが、衆議院の選挙区では地元に確固たる支持基盤を持つかどうかで当落が決まります。そりゃそうですよ。選挙区選出の議員は地元のしがらみを引き摺(ず)っていますのでね。しがらみとは主に選挙区内の後援会の有力者のことですが、彼らにしたって現職議員の身内に後を継いでもらえれば、一から関係を築く必要がありませんし、それに――」
何かを言いかけた小早川だったが、苦笑を浮かべ口を噤(つぐ)む。
「それに?」
「担ぐ方だって、神輿(みこし)は軽いに越したことはありませんのでね。お国のためというより、まずは地元のため。選挙区の支援者は県議、市議、町議が中心になって纏(まと)めていますから、なまじ優秀で天下国家を論じられても理解できませんからね」
「と言うことは、大河一族は議員職を一昔前の口減らしみたいな感覚で捉えているように聞こえますが? 家督を継ぐのは長男だ。次男以下は家を出ろというのと同じじゃないですか」
「そんなもんですよ」
小早川は、またしてもあっさりと肯定する。「国会議員が家業化しつつあるのは紛れもない事実ですからね。私も三代目ですから偉そうなことは言えませんが、だからこそ痛感するのです。大志なき人間は、国政の場から去れと……」
大志を抱いているにもかかわらず、占い師の見立てでかくもあっさり宗旨替えをしてしまうのだから、まさに「どの口が言う」というやつだ。
しかし、「神輿は軽いに越したことはない」のは、繁雄にとっても言えることでもあるし、小早川は当選三回。派閥内の第三勢力とはいえ、菱倉グループの選対委員に任命されるところからして、有望株の一人と見做(みな)されているのは間違いあるまい。
「では、派閥内第二勢力に乗り換えれば、大志を遂げることができると先生はおっしゃるのですね」
「ええ……」
大志がいかなるものかは鴨上から既に聞かされている。問題は、実現するか否かである。
「その根拠は?」
「第二勢力を率いる興梠(こうろぎ)先生から、菱倉グループの議員を引き連れて合流すれば、人数次第で優遇すると確約をいただきまして……」
「本人が、直接そう言ったのですか?」
「正確には、興梠派のナンバーツーの江沢(えざわ)先生を通じてです。さすがに興梠先生本人とお会いすると、人目につきますので……」
「で、先生の誘いに乗る議員に目処(めど)はついているのですか?」
「今現在確定しているのは十二人です。いずれも私が主宰しております派内のグループを越えた中堅、若手議員の勉強会のメンバーで、増えることはあっても減ることはありません」
小早川は確信の籠った声で言う。
繁雄は黙って頷くと、先を話すよう目で促した。
「会が終われば酒席を共にするのが常でして、酔いが回れば口も軽くなる、思わず本音を漏らすようにもなるわけです。そこで、大河派に属していることに漠とした不安を抱いている議員が少なからずいることが分かったのです」
政治家が抱く不安といえば、第一に次回の選挙で勝てるか、議員で居続けられるかだろう。
そこで繁雄は訊ねた。
「大河先生の資金基盤は盤石。与野党合わせても唯一無二と言っていいと聞きます。餅代、氷代だって滞りなく配られているだろうし、選挙の際には相応の金が用立てられるのでは?」
「見返りを求めずして金を配る人間はいませんよ。そのことは、社長が一番ご存じのはずですが?」
「確かに……」
これは一本取られた。
繁雄は苦笑いを浮かべた。
「政治家が、もれなく独自の支援団体、要は資金基盤を確保しようと必死な理由はそこにあるんです。親分の世話になっている限りは、ずっと子分のままですのでね。議員で居続けるだけが目的ならば割り切ることもできるでしょうが、若手、中堅はまだまだ野心がありますのでね。大河先生が引退なさっても、資金基盤をご子息が継ぐのですから体制は変わらない。今度は若様に仕えることになるのです」
なるほど、若様ときたか……。
政治家が家業化する傾向は代替わりする度に顕著になる一方だ。それも確たる支持、資金基盤を持つ者ばかりなのだから小早川の言は的を射たものには違いない。
「子分だって、親分を選びますのでね」
小早川は続ける。
「しかも興梠先生は、大河先生に先生のご子息を将来の首相候補に育てることと引き換えに、派閥を禅譲してもらうことを持ちかけたのです。ご子息が海のものとも、山のものとも分からぬうちにですよ」
小早川だって三代に渡る世襲代議士だ。違いは確たる資金基盤を持つか否かの一点だけ。要は、持たざる者の僻(ひが)みでしかないのだが、世襲議員の割合が増す一方なのだから、小早川と同じ思いを抱く議員は少なくないだろう。
「すると先生は、大河先生の後継者を巡って一族の結束は崩壊する。その機に乗じて若手、中堅のリーダーとしての地位を確立しようと考えているわけですね」
「その通りです」
もちろん、占い通りの展開になればだが、当たると信じている人間に何を言ったところで通じはしまい。
そこで、繁雄は続けて言った。
「しかしですね、子分だって親を選ぶとおっしゃいましたが、親分だって子分を選べるんですよ」
唐突過ぎて繁雄の言葉の意味するところが俄(にわか)には理解できなかったのだろう。
小早川は小首を傾(かし)げる。
「菱倉先生から興梠先生への鞍替(くらが)えは、よく言えば機を見るに敏、悪く言えば裏切り行為。謀反と見る向きもあるでしょう。そんな行為を働いた人間が新しい派閥で徴用されますかね?」
「兜(かぶと)首を取って馳(は)せ参じれば大功労者でしょう。しかも謀反には大きなリスクが伴います。失敗すればそれこそ返り討ちになって命を取られて終わりですからね」
つまり、小早川は今回の決断に、己の政治生命を賭けていると言いたいらしい。
その意気はよしだが、それも目論見通りに事が運べばの話である。
「では、菱倉先生の首を取れると確信しているのですね」
繁雄が念を押すと、
「もちろんです」
小早川は自信満々の体でこたえる。
「その根拠は?」
「引退しても大河先生の影響力がなくなるわけではありませんが、現職と元職とではやはり歴然とした違いがあります。興梠先生が大河グループを吸収すれば、単独で最大派閥を率いることになるのです。だからこそ、菱倉先生も自派の勢力拡大に必死なのですが、私が十人以上もの議員を引き連れて、興梠先生に鞍替えすれば勝負は決したも同然です。なにしろ、政治家は機を見るに敏ですからね。残る三つの勢力の中から、一つでも興梠先生に合流するところが出てくれば、他の二グループも後に続く」
「つまり、君は派閥内勢力図の再編の鍵を握っているというわけか?」
「そう考えていただいても、よろしいかと……」
「たった、四千万の金で?」
「足りなければ、用立ててくださるとおっしゃったではありませんか」
確かに……。
繁雄にとって四千万円はどうということもない額だ。それにくれてやったわけじゃなし。足りないと言うのなら、担保に取った手形に新たに裏書きさせればいいだけのこと。支払い義務を小早川が負うことになるのだから、後は野となれ山となれ。損失を被るわけでもない。
それに、小早川には「ある時払いの催促なしではない」と言ったものの、実のところ繁雄は返済が滞ったとしてもかまわないと思っていた。債権者と債務者のどちらが強い立場かは言うまでもないことだし、完済できない限り縁を断ち切ることができないのが借金だ。結果的に小早川は債務者、つまり繁雄の言いなりになるしかないからだ。
まして政治家にとって、発覚すれば最大の痛手になるのが金に纏わるスキャンダルである。目論見通り興梠グループに合流。その功績をもって重用されるようになれば、地位への執着は高まるばかりになるだろう。
そして権力とは金の力である以上、地位が高くなるにつれ資金需要は増すばかり。借金は残り続け、まず完済できない。いや、完済させてはならないのだ。なぜならば、元本はそのまま、延々と利子だけを払い続ける客が街金にとって最も好都合なのと同様に、常に繁雄が優位に立つことができるからだ。
小早川を使って何をさせるのか、今のところ特に案はないが、政治家を手駒の一つとして持っていて損はない。まして彼が順調に出世し、党の重鎮、あるいは閣僚になればなおさらだ。
「用立てますよ。いくらでも……」
繁雄は小早川の視線をサングラス越しにしっかりと捉え、「ただし、条件があります」
と告げた。
「条件とは?」
「資金の調達は他に求めないでいただきたい。つまり、私からのみにしていただきたいのです」
小早川の顔が一瞬曇った。
警戒しているのだ。
果たして小早川は言う。
「それは、なぜです?」
「長いこと金貸しをやっているとよく分かるんですが、金策に奔走する人間は、こちらで摘み、あちらで摘みと、借金する相手の懐具合に合わせて、借金を重ねるものでしてね。行き詰まると今度は返済のための金策と、遅延する言い訳に奔走するようになるんです」
小早川は神妙な顔つきで話に聞き入っている。
繁雄は続けた。
「大志なき人間は去れとおっしゃるからには、先生には大志がおありになるのでしょう。ならば、金策に時間と労力を費やすべきではありません。借金を返済するための金策、遅延の言い訳のためにだなんてなおさらですよ。借金は一本化すべきなんです。言い訳だって、都合一度で済むんですから」
小早川への影響力を高めるための方便なのだが、金貸しを生業とする者からのアドバイスなのもまた事実である。
それだけに、小早川もこたえに迷っている様子だったが、やがて口を開くと、
「しかし、そこまで社長に甘えていいものか……」
苦しげにこたえる。
「返済する自信がおありなんでしょう? 返してしまえば貸し借りなし。それが借金ってものですよ。利子を取らないでお貸しするのは鴨上先生に頼まれたからであって、借りができるのは私にではありません。鴨上先生にです」
繁雄の言葉にようやく納得したのか、あるいは、これで金策に完全に目処がついたことに安堵(あんど)したのか、小早川は自らを納得させるかのように頷くと、
「分かりました。社長のご厚意に甘えさせていただくことにいたします」
きっぱりと断言した。
(次回に続く)
プロフィール
楡 周平(にれ・しゅうへい)
1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
