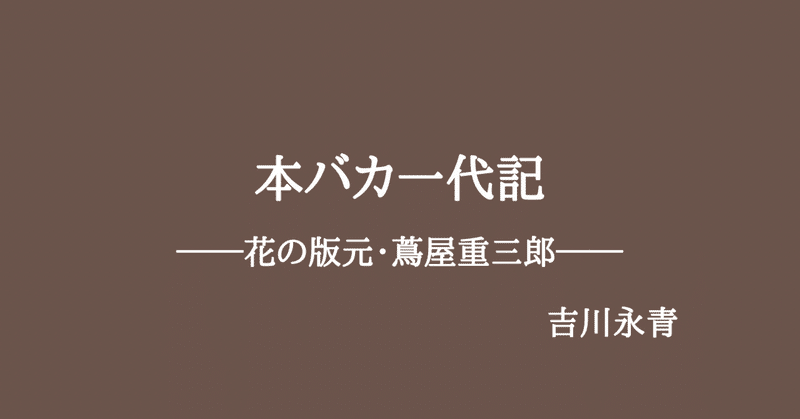
本バカ一代記 ――花の版元・蔦屋重三郎―― 第五話(中)
*
西村屋から聞いた話は全てが真実であった。
明くる日、鱗形屋孫兵衛は奉行所に召し捕られた。取り調べが進められ、沙汰が下ったのは二ヵ月の後である。
裁きの場で、鱗形屋は申し開きをした。盗品だとは知らずに質屋を紹介したのだ、と。
この申し開きは一面で容れられた。だが、全てが認められた訳ではない。
質屋を紹介したことで、結果として盗みに加担した格好になってしまっている。しかも謝礼が多額に過ぎ、これを以て怪しむべきところだったはず。然るに届け出でさえしないとは不届き至極、相応の責めは免れぬところなり――下された罰は、十里四方の江戸所払いであった。
半月ほどが過ぎて七月を迎え、蔦屋版の吉原細見だけが売り出された頃、鱗形屋孫兵衛は江戸を去ることになった。
その日、重三郎は鱗形屋に出向いた。見世が閉め切られていたことから、出立は裏口からだと知れた。
「旦那」
別人のようにやつれた姿に声をかける。鱗形屋は少し驚いた顔であった。
「こりゃ蔦屋さん。どうしたんだい」
「せめて見送りくらいは、って思いまして」
「そうかい。ありがたいね」
返された小さな笑みは、自嘲の笑みなのかも知れない。それを見ると、何と声をかけて良いのか分からなくなる。
少しの沈黙が重たかったか、次に口を開いたのは鱗形屋の方であった。
「迷惑をかけたね。あたしのせいで、あんたは何人も絵師を引き剥がされちまった」
「そんなこと……いえ。はい」
そんなことはない、とは言えなかった。
戯作者や絵師の作は、概ね決まった版元から売り出される。そういう取り決めがある訳ではないが、他の版元と仕事をするのは不義理に当たると考えられているからだ。今回の一件では、北尾重政から紹介された絵師のうち、幾人もの優れた若手を西村屋に奪われる格好になってしまった。
「でも手前には、北尾先生や勝川春章先生とのご縁もありますから」
北尾や春章ほど名のある絵師に限っては、二つ、三つの版元から売り出している場合もある。その人たちとの繋がりがあれば大丈夫だと返すと、しかし、鱗形屋はゆっくり首を横に振った。
「あと幾年、北尾さんや春章さんが一番でいられる?」
世には次々に新しい絵師が生まれ、異なる画風で人々の目を塗り替えてゆく。これから版元となる重三郎にとっては、北尾たちに続く若手との繋がりの方が大事なはずだ。鱗形屋の眼差しがそう語っていた。
「仰るとおりです。でも、そのまた次に出て来る絵師さんを探せばいいんですよ」
精一杯の強がりに、鱗形屋は柔らかい笑みで「そうかい」と頷いた。
「初めて会った日に言ってたっけね。俺は世の中を動かす側だ……って。あんたが新しい絵師を担いで、世の中を動かせるかどうか。楽しみに見させてもらうよ」
「ええ。必ず」
そう返して、また少し間が空く。重三郎には、ひとつ問うておきたいことがあった。一方の鱗形屋も、何かを話そうか話すまいか迷っている顔である。
「なあ蔦屋さん。あたしら、互いに同じことを考えてんじゃないかね」
寄越される笑みの中、目だけが凄腕の版元に戻っている。どうにも決まりが悪く、重三郎は苦笑を浮かべた。
「参りましたね。多分、そうです」
ひとつ頷き、踏ん切りを付けて切り出した。
「実はね、西村屋さんが言ってたんですよ。自分と旦那は血の繫がりがあるだけだって。どうしてそんなこと言うんでしょう。こんな大ごとなのに、あんまり冷たいじゃあないですか」
鱗形屋は「はは」と笑った。またも自嘲の匂いがした。
「やっぱり、そこだったか。まあ……身内の恥を晒すことにゃあなるが、あんたに迷惑をかけた大本の話だからね。聞かせとくよ」
そして大きく溜息をつき、しみじみと二度頷いた。
「あたしには二人の子がいる。上の子が孫太郎で、下の子が孫次郎だ」
「孫次郎さんが、二代目・与八の西村屋さんですね」
「そう。あれは、できのいい子だった」
幼い頃から、まさに一を聞いて十を知るという利発さだった。対して兄の孫太郎は、父の贔屓目で見ても盆暗と言うしかないと嘆いている。
「歳を重ねるほど、二人の力はますます開いちまった。ただ……孫次郎は妾腹なんだよ」
それを鱗形屋の後継ぎとすれば、兄の孫太郎は肩身の狭い思いをするだろう。父としてはどちらも自身の子であって、等しくかわいい。片方が冷や飯食いの憂き目を見ることは避けたかったのだと言って、またひとつ溜息をついた。
「そこで西村屋さ。あそこの先代にゃあ子がなかったから、孫次郎を養子に取ってくれないかって頼んだ」
できの良い方を養子にと言われて、先代・与八は大いに喜んだらしい。そして孫次郎は西村屋を継ぎ、二代目・与八となった。
「けど孫次郎にゃあ、それが面白くなかったんだろう」
盆暗の兄が家を継ぎ、兄より優れた自分がなぜ放り出されるのか。自分は疎まれている。嫌われている。父にとって厄介者なのだ。孫次郎――二代目・西村屋与八はそう思い、恨みを募らせたのではないかと、鱗形屋は言う。
「まあ、そう思って当然だろうね。何しろ妾の子さ。手許に置くと女房がうるさいもんで、見世から離れた長屋に住まわせてたんだ。生まれてから、ずっとね」
「そうですか。だから」
血の繫がった親子だろうと言いかけた時、西村屋は「商売に関わりのない話」と言って、けんもほろろに斬って捨てた。あの時の、恨みがましい眼差しの訳が知れた。
鱗形屋は「だけどさ」と苦笑した。
「それにしたって、ちょっと……やり過ぎだよなあ?」
「え? 何がです」
「今回のことさ。でき過ぎた話だって思わないかい」
用人の主君が、なくなった家宝を探すのは当然である。だが家宝である以上、まず外には持ち出さない品であるはずだ。
「だったら屋敷の中をくまなく探す。それでも見付からなけりゃ、盗まれたって考える。そんな時にゃ、奉行所に話して下手人探しを頼むもんさ。ところが」
「あ!」
重三郎の目が丸くなる。この話について、西村屋が何と言っていたかを思い出した。
「質種になってんのを、ものの十日で突き止めたって。早すぎる」
「つまり、そういうことなんだよ」
質入れした用人は、その後すぐに暇乞いをしている。これを下手人として疑うまでは頷ける話だろう。しかしだ。奉行所の手も借りず、しかもたった十日で質入れの事実まで突き止めたというのは、明らかにおかしい。
「旦那が質屋を紹介したって、知ってる奴がいた。そいつが?」
「だと思う。三年前の正月だったかな。あの用人を質屋に連れてったのが……実は、手代の徳兵衛なんだよ」
「徳兵衛って。ええと……。誰でしたっけ?」
鱗形屋は「ぶは」と噴き出した。
「まあ覚えてなくて当然さ。あんたにとっちゃあ、一度っきり聞いただけの名だろうからね。盗版の時の、あの手代だよ」
そして続ける。盗版の罪を着せられて所払いとなり、徳兵衛の胸には遺恨があったのだろう。そこで西村屋与八に目を付け、文のひとつも送って過日の一件を教えたのではないか。父を恨んでいるなら陥れてやれ、と。
「いや……それ、証はあるんですか?」
「証も何も、お白州に呼ばれた証人が当の徳兵衛なんだ。まず間違いない」
徳兵衛は言った。所払いの身ゆえ、とある人を通じて質種の一件を報せてもらったのだと。
「その『とある人』ってのが西村屋さんだって?」
「お奉行様は、そこは明かせねえって仰せだった」
質種にされた家宝は見付かっているのだから、鱗形屋を裁くに当たり、密告した者の名を明かす必要はないと言われた。すぐに、ぴん、と来たそうだ。これは孫次郎だと。
「きっと徳兵衛の奴は、ずいぶん前から孫次郎……与八に渡りを付けてたんだろう。与八は与八で頃合を測ってたんだと思う」
「いや、おかしいでしょう! おかしいですよ。実の子が父親を」
止めようもなく声が大きくなる。鱗形屋はそこに向け、大きく首を横に振った。
「蔦屋さんは真っ正直な人だから、そう思うんだよ」
実の両親と引き離されながらも、重三郎は養父・利兵衛を父と慕っている。常に前を向いている。そういう人間に、恨みを拗らせた者の心が分かるのか――。
「与八はさ、小さい頃から寂しい気持ちを抱えて育ったんだ。親父に認められたいって、それだけ思いながらね。だから、必死で親父の姿を見てきたんだろう」
その父は、時に後ろ暗い手も使って見世を大きくしてきた。見世と奉公人を守りたい一心だった。だが、そういう胸の内は誰にも明かさずにきた。
「だから、あいつは親父のやり様しか知らない。滅多に顔も合わせねえんじゃ、そうなるしかないよな。その末に性根が曲がっちまった。あたしのせいだよ」
違う、と言うつもりはない。しかし、大きく首を横に振って返した。
「それでも気に入らねえ話です。手前が言うのも何ですがね、旦那には版元の才覚ってのがあるじゃないですか。西村屋さんは旦那のそういうとこ、しっかり受け継いでんだ」
ずっと芽が出ずにきた礒田湖龍斎の絵を見て、少し画風を変えれば本物になると言った。その言葉どおり、重三郎の案を加えて売り出した『雛形若菜初模様』は当たっている。
「そんな力があるんだから、旦那を恨むんなら商売で勝ちゃいいでしょう。なのに」
鱗形屋は「はは」と嬉しそうに笑った。
「あんたは、そういう人さ。あたしが『こうありたい』って思って、なれなかったような人なんだよ。だからこそ、あんたを見込んだ。与八はそれも気に食わなかったんだろう。だったら蔦重も潰してやれって、思ったんじゃないかな」
ぞくりと、背に冷たいものが走った。
今の自分はまだ小物である。まともに考えれば、蔦屋重三郎を潰して西村屋が得られるものはないと言えよう。
だが違う。そういうことでは、ないのだ。
西村屋が鱗形屋を陥れたのは、父と兄への恨みを晴らすためだった。しかし、それだけでは足りない。蔦屋重三郎――実の子を差し置いて父に認められた男を潰してこそ、復讐は全きものとなる。自分の心が満足する。それが西村屋与八の胸中ではなかったか。
「ねえ旦那。その。与八……あの人、だから手前に?」
わなわなと震え始めた重三郎を見て、鱗形屋はやる瀬なさそうに小さく頷いた。
「さっき、与八は頃合を測ってたって言ったろう? あんたに勢いが付いたとこで叩いてやりゃあ、親父と兄貴と併せて一石三鳥だって考えたんじゃねえかな」
重三郎には北尾重政の伝手があり、多くの絵師との交わりがある。それを引き剥がしてやれ。北尾の次に一線で働ける者を奪ってしまえば、丸屋の株を買っても満足な商売はできまい。何もできないまま消えてしまえ――。
「あたしも昔、似たような手を使ったことがある。だから分かるんだよ」
「あ……の野郎ッ!」
嵌められた。騙されていた。怒りが脳天を突き抜けて、くらりとした。
「本当にすまない。親子の諍いに巻き込む格好になっちまった」
鱗形屋が深々と頭を垂れる。重三郎は叫ぶように「いいえ」と返し、きっぱりと首を横に振った。
「騙す奴ぁ、確かに悪い奴ですよ。でも騙された奴が悪くない、なんて話はありません。そうでしょう? だって、騙されるような馬鹿なんだから」
言い放って、ぎろりと目を剝く。
「ひとつお聞きします。旦那が所払いになったら、鱗形屋はご長男が継ぐんですよね。でも旦那は、ご長男は盆暗だって仰る。その人で巧く行くとお思いですか?」
「あんた厳しいとこ聞くね。でも、どうだろうな。見世の者が力を尽くしてくれても、孫太郎じゃあ……。あと十年もかけて、一人前に仕込んでやるつもりだったんだが」
この先の鱗形屋は泥船だと、面持ちが語っていた。
「うちが抱えてる物書きや絵描きにも、離れたく思う人は多いだろうね。義理を通そうとする人もいるだろうけど、それにしたって必ずとは言えない」
重三郎は「そうですか」と返し、勢い良く一礼した。
「でしたら。そういう人たち、手前に引き抜かせてください」
そして顔を上げ、真っすぐに相手を見る。
「まんまと騙されちまった馬鹿野郎です。でも学びました。同じ轍は踏みません」
「それで、与八の奴を殴り返すって?」
「手前のことだけじゃあないんだ。失礼ながら旦那の江戸払いは身から出た錆ですが、だからって、実の子が父親を足蹴にしていいって話にはならないでしょう。受けるべき報いってもんがある。そのために、そちらさんでお抱えの人らを使わせて欲しいんですよ」
ぐっと奥歯を嚙む。鱗形屋は「ふふ」と笑い、ゆっくりと二度頷いた。
「分かった。やってみな。うちが先細りになるのは見えてるからね。ただで潰れるより、あんたの肥やしになった方がいい」
「恩に着ます。この勝負、きっと勝ってお見せしますよ」
鱗形屋はもう一度「ふふ」と笑った。先より少し嬉しそうな笑い顔だった。
「さて。いつまでもここにいたら見世に迷惑だな。そろそろ行かないと……って、おい。そんなとこで何やってんだい」
裏口の内、鱗形屋が声をかけた先には、供を務めるのだろう小僧が――歳の頃は十二、三くらいか――突っ立っている。今の話を聞き、重三郎の激昂する姿を見たせいか、少し怯えているらしかった。
小僧がおずおず出て来ると、鱗形屋は重三郎に軽く会釈して、静かに旅立って行った。
*
明けて安永八年(一七七九)一月、それぞれの版元が新しい本を売り出した。
かつて鱗形屋の『金々先生栄華夢』から始まった黄表紙本は、今ではすっかり人気の草双紙となっていて、この正月も多くが売り出されている。しかしながら、これを仕掛けた鱗形屋からの新刊は少ない。しかも全く売れずにいた。
「おう、今帰ったよ」
一月の末、重三郎は本の貸し歩きを終えて帰った。見世番をしていたお甲が「あら」と声を寄越す。
「ずいぶん早いね。借りる子、あんまりいなかった?」
「いや、そうでもないんだが」
実際、本を借りる女郎はそれなりにいた。しかし人気の黄表紙はすぐに借り手が付いて品切れとなり、鱗形屋の本しか残っていないと知ると、皆が「なら止めておく」と言う始末なのだ。貸本まで避けられているという一事を見ても、鱗形屋の受けた傷が如何に大きいかが分かった。
貸し残しの本を片付けながら、その辺りを話す。お甲が渋い顔で「ふうん」と頷いた。
「まあでも、それなら……あんたが何も刷らなかったのは正しかったかもね」
「こんな時にゃ、死んだふりに限るよ」
今のところ洒落本くらいしか出せない身だが、鱗形屋と繋がりの深い版元が軒並み苦しんでいる折、新しく何か売り出したところで鳴かず飛ばずだったろう。強すぎる向かい風の中で無理をするより、来るべき時に備えて資金を温存するというのが重三郎の判断であった。
「ただ、それでも細見だけは売れるんだけどね。あたしが空けてる間に幾つ売れた?」
「ええと……三十三だね」
「上々だ」
細見ばかりは、他の版元には作れない。こんな時でも相応の数が捌けるのだから、ありがたい品である。そう言うと、お甲は「皮肉なもんだね」と軽く溜息をついた。
「鱗形屋さんの一件で足踏みしてんのにさ。鱗形屋さんと付き合ってたからこその細見で、飯は食えてんだから」
「違えねえや」
軽く笑う声が、どうにも乾いている。お甲の面持ちにも憂いがあった。
「この先の鱗形屋さん、どうなんのかね」
「多分、苦しいだろうね」
先代・鱗形屋孫兵衛は、後継ぎのできが悪いことを嘆いていた。見世の皆が力を尽くしても、この先は泥船だろうと。どうやらその懸念は現実になりかけている。
ならば、やはり――。
「今年の秋か」
「ん? ああ、丸屋さんの株か。ついに、あんたも版元になれるって訳だね」
重三郎は「それだよ」と頷いた。
「来年からは草双紙も売り出せる。株のことと併せて、どうやらその支度を始めなきゃいけねえらしい」
「え? 何で『らしい』なんだよ。支度は始めなきゃなんないだろ?」
お甲の怪訝な眼差しに、苦笑交じりに頷いた。
確かに支度は始めなければならない。だが、それを言った訳ではないのだ。
こんな始末になったとは言え、鱗形屋には恩がある。その見世がこの体たらくでは、江戸を去った先代・孫兵衛に言ったとおり、戯作者や絵師を引き剥がさねばならない。
「先代の旦那には『やってみな』って言われたんだけどね」
「何だい。まさか今さら尻込みしてんの?」
「そんな訳ないだろ。ただ、先代にゃあ目をかけてもらってたからね。やっぱり、申し訳ないって気持ちにはなる。人の心ってもんさ」
しみじみと語る。お甲も少しばかり神妙な顔であった。が、すぐに目元を引き締めて「馬鹿だねえ」と鼻息を抜く。
「あんたのそういうとこ、あたしは好きだよ。恐らく先代の孫兵衛さんもね」
そしてお甲は、重三郎の背を平手でパンと張った。
「だったら、あんたが巧くやって名を上げんのが恩返しってもんさ」
「分かってるよ。ありがとうな」
良い女房だ。重三郎はまたひとつ苦笑を浮かべ、自らの頬を両の掌で挟むように強く張った。
「さあて。西村屋の野郎、目にもの見せてやるぜ」
以後の重三郎は、暇を見ては鱗形屋が抱えている戯作者を訪ね歩いた。すると、やはり鱗形屋の先々を危うく思い、離れたく思っている者たちの多いことが分かった。
それらと話し合いを続ける一方、何が何でも外せない戯作者があった。朋誠堂喜三二である。
五月も半ばを迎えた頃、重三郎は喜三二を招き、養父の営む尾張屋で宴を催した。
「――てな訳でね。かねてお約束してましたとおり、是非とも喜三二先生に書いていただきたいんですよ」
喜三二は盃を嘗め、軽く息をついて「やれやれ」と笑った。
「やっと頼んでくれたか。待ちくたびれたぞ」
「え? そりゃ、どういう?」
「実は、鶴屋からも熱心に誘われているんだ」
それは鱗形屋と西村屋に次ぐ大版元であった。
「もっとも重さんのとこで書くのは、ずっと前からの約束だったろう。だから、きちんと頼んでくれるのを待って、鶴屋への返答は先延ばしにしていたんだ」
「そりゃ、すみませんでした。でも喜三二先生くらいになると、他で書いたって文句を付けられやしないでしょ? 鶴屋さんのお話だって、受けて良かったんじゃありません?」
喜三二は「いや」と頭を振った。ことはそう単純でもないのだ、と。
「鶴屋からは、他では書かない約束で頼むと言われておった。鱗形屋がああいうことになったのなら、この機に西村屋もまとめて追い抜いてやれと考えておるのだろう」
「あららら……喜三二先生ほどのお人を囲い込もうなんて。鱗形屋さんでやってた時だって、他でも書いてたってのに」
「それだけ鱗形屋の一件は大きいんだよ」
江戸一番の大版元が躓いて、二番手の西村屋を抜けば一番になれるのである。鶴屋がそういう野心を抱いたとて、なるほど不思議はない。
「まあ、わしは重さんが声をかけてくれると思っていたから、ずっと返答していなかったのだがな。鶴屋に誘われたら、他の物書きは靡いてしまうと思うぞ。その辺りは大丈夫なのか?」
懸念の色に向け、重三郎は「もちろん」と胸を張った。
「ねえ先生。手前は、ただ本を売り出しゃあ良し、とは思ってないんですよ」
「おお?」
「前に書いてもらった洒落本があるでしょう。あれだって、洒落本ってだけで見下されてるのを変えてやるのが大事だった訳ですよ」
「うん。確かにそう言ってたな。世の中を動かしてやるって」
重三郎は「そうです」と大きく頷いた。
「今、黄表紙は大人気じゃないですか。出してやりゃ、誰が書いたのだって結構な数が売れるんですよ。でも、手前はそれじゃ駄目だって思います。鱗形屋の先代が言ってたこと、洒落本の時にお話ししたじゃないですか」
それは、世の中には字を読んで中身を読まない者が多い、という言葉である。
「そういう人らが多いんなら、売れるのは今のうちだけです。他に何か面白そうなものが出て来たら、本そのものから離れて行っちまいますよ」
「それは困るな」
「だから手前は、黄表紙って形を育てんのと一緒に、読む人にも育ってもらわないといけないって思うんです」
本に書かれていることは、確かに読んで面白い。だが、それだけで終わるものではないはずなのだ。読んだ側が物語を噛み砕き、自分の中で膨らませて、幾重にも楽しむことができる。
「鱗形屋の先代が言ってんのは、そういう楽しみ方ができる人は少ないってことでしょう?」
「なるほど。当を得ておるな」
重三郎は身を乗り出して、真剣そのものの眼差しを向けた。
「だったら、売り出す値打ちがあるのは、書かれたこと以上に楽しめる本なんですよ。手前はそういう本物を世に送り出して、誠のある商売で成り上がりたいんだ」
ずっと前からそう言ってきた。本の商いで勝負したいという思いの根源と言っても良い。この思いが丸屋を動かし、株を譲ってもらえることになったのだ。
「本当にいいものが正しく売れる世の中であって欲しい。だから、本当にいいものを書ける人にしか興味はありません。そういう人には、もう唾を付けてます」
喜三二は「あはは」と楽しげに笑った。
「わしも、そういう物書きと認めてくれるのかね。ありがたい話だ。他には誰を?」
「王子風車先生と、大田南畝先生です」
二人のうち、大田南畝は国学と漢学に通じ、多くの随筆を手掛けてきた高名な才人である。その名を聞いて、喜三二は目を細めた。
「なるほど。いい人に目を付けたな」
「でしょう? きっと黄表紙を大きく育ててくれるはずですよ」
この日、朋誠堂喜三二は蔦屋耕書堂で黄表紙を書くことを正式に約束した。鶴屋の「他では書かないでくれ」が満たされなくなった以上、そちらの誘いは断ることになった。
〈次回に続く〉
【プロフィール】
吉川 永青(よしかわ・ながはる)
1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
