
バーチャル坐禅会「お経ってなに?」
こんにちは!
今月のバーチャル坐禅会のテーマは「お経ってなに?」
法事やお寺でのお勤めなどで、お経を聞くことはありますが、
「よくわかんないこと唱えてるし、あれって何なの?」って思いますよね。
今回はお経についてお話させていただきました。
お経ってなんなの?

お経は簡単に言えば
お釈迦さまや仏教の教えが書かれている書物です。
なんでお経があるのかというと、教えを後世に残していくためです。
お釈迦さまが実際に生きていた時代や、お亡くなりなってすぐはお釈迦さまの教えは口伝で伝えられていました。
伝言ゲームみたいな感じです。伝えるのが下手な人がいると上手く伝わらないやつです。
それじゃ困るっていうことで弟子たちが集まり、教えの内容を書物にまとめました。それがお経の始まりです。
お経っていろいろある

実際同じお釈迦さまの教えでも人によっていろんな受け止め方があります。なので、伝言ゲームでいろんな解釈がうまれ、たくさんのお経が生れました。それもまた仏教です。
お経の内容は置いといて、書かれている形式で大きく3つのパターンにわけられます。
梵字
漢訳
日本語訳
①梵字
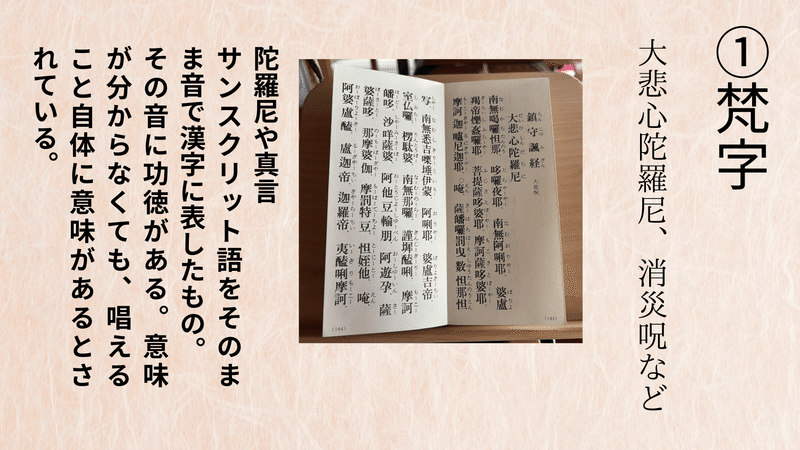
陀羅尼や真言とも言います。
サンスクリット語をそのままの音で漢字に表したものです。(音訳)
曹洞宗(自分たちの宗派)では『大悲心陀羅尼』や『消災呪』などです。
呪文みたいで、聞いた感じが一番よくわかんないものになります。
その音自体に功徳があると言われており、意味が分からなくても唱えること自体に意味があるとされています。
②漢訳

梵字のお経を意味で訳し、漢字(中国語)で訳したものになります。
ちょっと読み方は違いますが、中華系のお寺でも同じテキストを使っています。
『般若心経』や『観音経』などです。
レ点を付けたり、書き下し文にするなどして、漢文の知識があれば何とか意味をつかむこともできます。
③日本語訳

漢訳のお経を日本語にしたものや、日本のお坊さんが書いたものになります。
『修証義』や『参同契』になります。
古文っぽかったり、専門用語が多かったりしますが、じっくり読めば理解することができます。
誰のために、お経を読んでるの?
答えは「自分のため」です。
お経には今を生きる私たちへのヒントがいっぱい書かれています。

仏教は悟りの宗教です。仏になる。(成仏)修行によって悟りを得ることが仏教徒最大の目的です。
お釈迦さまの教えを学べたら悟れるかも。。。
お経を読むと功徳があります。
この世界でお経を読むと、拍手がもらえたり、紙吹雪が舞いますが、
正直功徳ゲットしてる時などで、積極的にそういうことをしていただけると
お坊さんは嬉しいです。
じゃあ、「なんで法事などで亡くなった人のためにお経を読んでるの?」って思いますよね。
実はお経の最後に「回向」というパートがあります。
この回向は「このお経による功徳は〇〇の為に~」みたいな感じで、今のお勤めが誰のためだったかということを読み上げる部分になります。
功徳ってマイルみたいなものです。ためるといいことあります。
そして、その「功徳マイル」は便利なことに転送も可能なんです。(しかも、転送しても自分のマイルは減らない!!)
法事は追善供養ともいいますが、その回向でご先祖さまに「功徳マイル」を転送しています。
法事のお経ではざっくりいうと、こんなことをしています。
お経にはきちんとした意味があることを知りました。
— ぽんでぎ (@pondegi_000) May 20, 2024
ためになった~#cluster #バーチャル坐禅会 pic.twitter.com/sdNgFZB3WM
お経の例をもっと丁寧に解説したかったのですが、またのご縁と機会に。
— 桃山れんか (@renkataoshan) May 20, 2024
ちなみに八万四千とはざっくり言うと「たくさん」という意味です。
#バーチャル坐禅会 pic.twitter.com/eVAPVGcB1w
知ってるようで意外と知らない話が結構あるものですねぇ。
— チャーリー@Cabin1365 (@Yuan1365) May 20, 2024
アカデミックで楽しい。😎👍
#バーチャル坐禅会 pic.twitter.com/MXTVLD5jMp
バーチャル坐禅会 https://t.co/ioGMWRzjQX #バーチャル坐禅会 #cluster pic.twitter.com/TASZiNjRPq
— MoMo (@sabinekomomo153) May 20, 2024
昨夜は座禅会に参加したので、それっぽい画像を作らせてみた。
— チャーリー@Cabin1365 (@Yuan1365) May 20, 2024
ふわっと坐禅ぽくなったかな?🧘
本当は目を閉じたかったんですが、うまくできませんでした。😅
#バーチャル坐禅会#avalab pic.twitter.com/Df6axLYGQ0
そーめん #cluster #バーチャル坐禅会https://t.co/A9SHVjrg9b pic.twitter.com/uuRfisxtGD
— カタコッテ・マスネン (@ccmasunen) May 20, 2024
#cluster #バーチャル坐禅会https://t.co/439NlZ7gdW pic.twitter.com/d1CxKUsS5b
— ようせい (@spfairy2015) May 20, 2024
#cluster #バーチャル坐禅会https://t.co/A9SHVjrg9b pic.twitter.com/BCTiwn2jVu
— カタコッテ・マスネン (@ccmasunen) May 20, 2024
#cluster #バーチャル坐禅会https://t.co/gmegNveEX0
— meh(めー) (@meh_1365) May 20, 2024
知らないことがいっぱいあるなあって見てるよ🍃 pic.twitter.com/Hx4GSm6L3j
バーチャル坐禅会 https://t.co/OdKScWR2Q6 #バーチャル坐禅会 #cluster
— 桃山れんか (@renkataoshan) May 20, 2024
本日の講話「お経って何?」このあと二回目の坐禅です。 pic.twitter.com/Ccsvgzt1Fs
坐禅会始まっております~^^ #cluster #バーチャル坐禅会https://t.co/T0b3YAFmYz pic.twitter.com/YgnGi5cSTr
— メタカントン (@meta_kanton) May 20, 2024
次回のバーチャル坐禅会は「お経って何?」
— 桃山れんか (@renkataoshan) May 19, 2024
5/20 20:45開場 バーチャル寺大縁寺にてhttps://t.co/OdKScWR2Q6 #バーチャル坐禅会 #cluster
曹洞宗 MASASHI お坊さんによるお話と坐禅会(只管打坐)です。自分のありのままに立ち返る時間です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
