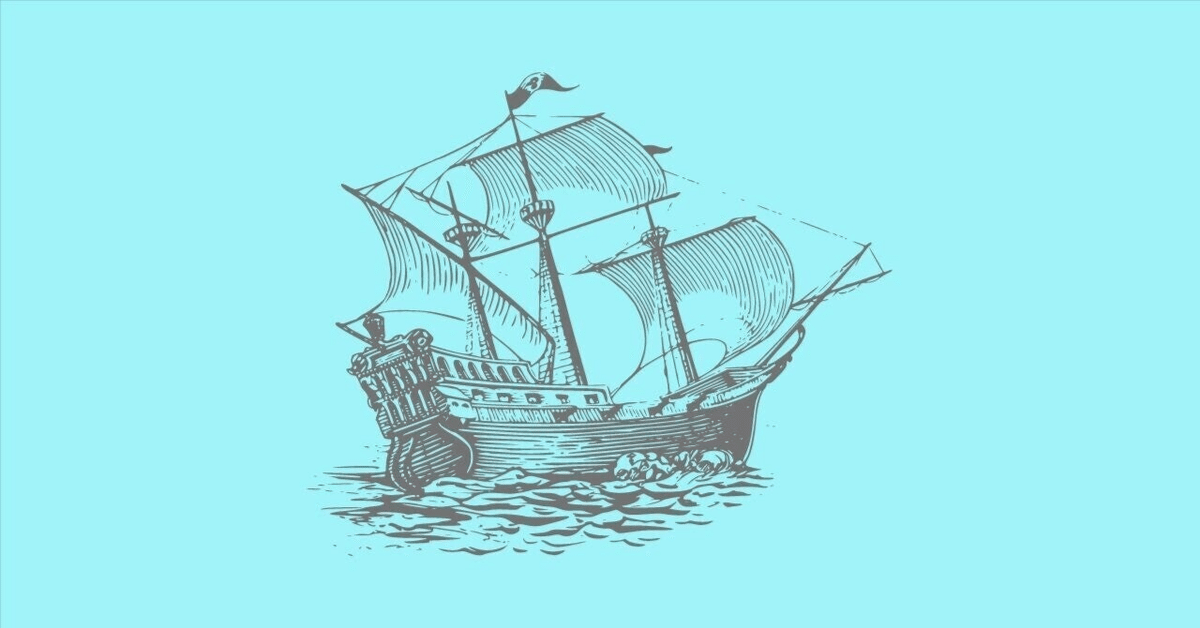
今は漕ぎ出でな
にきた津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
額田王
60年代の高度成長期の成功物語を背景に、それ以降も日本の学校教育はいわゆる<学力信仰>にあぐらをかき、護送船団方式(みんなで渡れば怖くない)でやりすごしてきた。Japan as Number One 1979と持ち上げられ、その惰性(慣性)は今日まで及んでいる。
これに最初に警鐘を鳴らしたのが臨教審1987だった。
当時はまだ保守と革新、右と左の対立軸が生きていたので、自由主義だ、市場主義だといった通り一遍の批判が聞かれた。臨教審のメンバーは旧対立軸を含みながら、このままでは日本の護送船団は遅かれ早かれ沈むほかはないだろう、という危機感を共有していた。かれらの共通項は「多様性」diversityだった。
今日、多様性は社会を考える上で最も重要なキーワードのひとつである。
臨教審1987を受けて、初等教育においてかろうじて実現したのは「生活科」の導入だった。社会科理科の守旧派を抑え込んでのすれすれの導入だった。それまで学力は、学ぶ人の外に、客観的に存在する知識をどれだけ習得し記憶するかだった。生活科の学力は、子どもが活動や体験の中で発見し子どもの中で生成してくる知である。一教科とはいえ学力観の180度の転換を意味した。風穴が開いた。しかし、ほかの教科は旧のまま温存、護送船団方式は続いた。
21世紀初頭に登場したのが「総合的な学習の時間」である。英訳は「period for integrated study」=「統合された学習の時間」。統合するのは学習者一人一人であり、現実の社会や自然に意図的に関与し相互交渉する中で、学習主体自身が生成する知である。知識を注入される対象から、知を統合する主体へと、学習観の180度の転換を意味した。
こちらも守旧派によるマスメディアを総動員した猛烈な排斥キャンペーンにより、「確かな学力」なる旧学力信仰むき出しの復古主義に席巻され、総合の時間数は削減に至った。さらに2010年代になると突如政治的介入により道徳の教科化、外国語や外国語活動の導入が矢継ぎ早に決まり、混乱と混沌の中、旧学力信仰がいびつな形で蔓延し今に至っている。
この動きに対峙するように、汎用的資質という、教科を超えた新しい学力モデルが令和学習指導要領(とくに総則)に挿入された。私見によれば、臨教審1987で実現できなかった多様性の基底となるような、あるいは多様性の核となるような部分の新しい学力の提言である。
臨教審1987が提言されたころは、日本丸という護送船団はまだ沈んではいなかった。このままいくと沈みかけていくのは時間の問題だと察知した人たちが警鐘を鳴らしたのだった。「失われた30年」は、日本経済の沈みゆく現実を各種データで裏付け命名した言葉である。だが、学校教育も、やはり「失われた30年」だったのではないか。
臨教審以後、警鐘を引き継いで学力観や学習観の転換を図る手立ては、これに反する復古要素を含みつつ、あるいは執拗に首をもたげる学力信仰教に叩かれながらも、中教審を中心に学習指導要領改訂の節目節目で打たれてきた。しかし、冒頭で述べたように、教育現場は60年代高度成長の成功物語神話から抜け出せず、その頃の護送船団による学力信仰に未だにむしばまれ続けている様子である。
臨教審の最終答申が出た1987年当時は、日本丸はまだ沈み始めてはいなかった。だが30年後の今、護送船団日本丸は半分以上すでに沈みかけていると言えるだろう。それが、今日私たちが目にしている現実である。
教師に問われているのは、30年以上前と同じように、この沈みかけた船に子どもたちを乗り込ませようとするのか、そして乗り込んだ沈みかけの船の中で子どもたちに座席争いをするように励ましていくのか、それとも、乗りかけた沈みかけの日本丸船から降りて、各自にボートと櫂を与え、共にこの広い海へ漕ぎ出でるように勇気づけ支援しようとするのか、どちらを選ぶのかということである。
30年以上続く惰性の波に乗って生きるのもひとつの生き方である。未知の海原へてんでバラバラに漕ぎ出でるには勇気もいるし覚悟もいるだろう。
羅針盤は結局自分で作るしかない。さて、どうしたものか……
