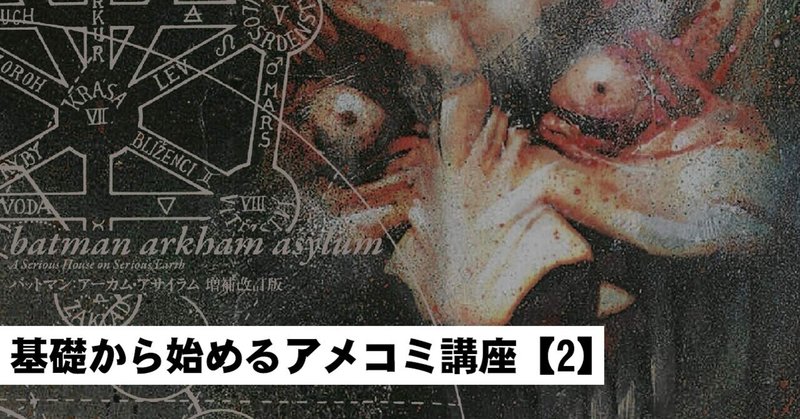
基礎から始めるアメコミ講座【2】
今回のテーマは、以前アップした「基礎から始めるアメコミ講座」シリーズ第2弾です!
【1】の記事はこちらからご覧ください。
「初めてアメコミを読んでみようと思う方」が対象なので、アメコミ読者にとっては“当たり前”のことが多いと思いますが、そこは温かい目で見ていただけると幸いです。
アメコミの制作体制
これは有名な話ですが、多くの場合、アメコミは分業制で作られています。細かい分担は下記のとおりです。
ライター(writer)
ストーリーを書く、原作者のこと。
日本のマンガでも原作と作画で分かれていることも多いため、イメージが掴みやすいかもしれませんね。もちろんケース・バイ・ケースだと思いますが、その“原作”となる文章を読むと、ストーリーラインや一つ一つのセリフはもちろん、作画担当者への細かい依頼や指示、コミック本編には描ききれないほどの盛りだくさんの情報が詰まっていることに驚かされます。
原作とコミックを読み比べたい方は、ぜひ下記の作品がおススメです! 今や名ライターとしての地位を確立したグラント・モリソンの出世作で、とにかくアーティスティックなコミックとともに、それに負けないほどの“濃い”原作を掲載してあります!!
この本は、ストーリーもアートもあまりに刺激が強すぎるので、疲れている時に読むと心を持っていかれる危険性があります。心身ともに元気な時にお読みくださいね(笑)。
ペンシラー(penciler)
作画家。 その名の通り、鉛筆で下書きを描く人のことです。
例えば「○○が描いたスパイダーマンが好き」という場合は、このペンシラーの名前が上がります。
コミックスによっては、特典ページで“ペンシル画(下書き)”を掲載しているものもありますので、ぜひ注目してください。
インカー(inker)
下書きにインクでペン入れをする人のことです。
線一本の違いで大きく絵の印象が変わってしまうことだってあるので、とっても重要な仕事ですね。
日本のマンガの場合、通常は下書きもペン入れも同じマンガ家さんが手掛けるため、実は一番大きな違いがあるパートかもしれません。
アーティスト(artist)
ペンシラーとインカーの両方を一人でこなすような人の場合、アーティストと表記されることがあります。
ぜひ、知っていただきたいアーティストといえば、アレックス・ロス。この方の描くコミックは、ページの1コマ1コマがまるで1枚の絵画のように美しいのです。それもそのはず、たった1コマを描くために、彼はとんでもない労力を費やしているのですが……。その素晴らしい作品と、作品作りの裏側はぜひ下記のコミックスでお読みください! 物語もアートも素晴らしい、大傑作です!
カラリスト(colorist)
これも言葉のとおり、絵に彩色をする人のことです。
ほとんどのアメコミは全ページフルカラーなので、とにかく大変な作業です。安定した作品作りのためにも専門家の存在が必須なんですね。近年ではデジタル彩色が主流になっていて、CGを使った迫力のあるビジュアルも楽しませてくれます。
レタラー(letterer)
このパートは日本のマンガ制作にはありません。文字や擬音語を書く方のことです。
現在はデジタルのフォントに移行していますが、以前はアメコミのセリフや擬音は手書きで書かれていたのです。そのため、担当者によって細かいニュアンスの違いがあり、玄人のアメコミファンにとってどのレタラーが担当しているのか? ということも重要な要素だったとか。
一方、日本のマンガは?
それでは、ちょっと視点を変えて、日本のマンガはどうやって作られているのでしょうか?
もちろんケース・バイ・ケースではあるのですが、比較のため、一人のマンガ家さんが作品すべてを描くパターンの一例をざっくり紹介します。
①プロット作り(やらない場合もあり)
物語の骨子となるプロットを、主に簡易な文章で作ります。(基本的にアメコミの原作よりもずっと簡易なものです)
同時にキャラクターのイラストと設定を書いた、「キャラ表」も作ります。主人公の目的と物語の進行、具体的なエピソードなどを編集者と打ち合わせ、問題なければネーム作りに移ります。
②ネーム作り
ネームとは、コマ割りや簡単なイラストを描き入れたマンガの設計図のことです。場合によっては、プロットを作らずに、いきなりネームから始めることもあります。
キャラクターが動いているか、プロットで意図していたマンガの狙いが表現できているか、それ以上に面白いかなどを編集者と打ち合わせ、問題なければ下書きに移ります。
具体的なセリフ回しや実際の作品の流れは、この時点で決まります。
③下書き
ネームで作ったコマ割りやイラストを、原稿用紙に書き入れます。実際に絵にしてみると、ネームとは違う表現や構図になることもあります。
④セリフの文字作り
日本のマンガも近年はデジタルフォントが主流になりました。下書きの時点で、編集者はセリフごとのフォントや大きさを指定して、写植を作ってしまいます。
⑤ペン入れ
下書きに、基本的にマンガ家さん本人がペン入れを行います。ただし、一部をアシスタントさんに任せる人から、すべて自分でペン入れを行う人まで様々です。
⑥仕上げ
基本的に本文はモノクロ印刷なので、いろいろな濃淡や模様を表現するスクリーントーンが大活躍。これもアシスタントさんに任せる人から、できる限り自分で行なう人まで様々です。
多少乱暴ですが、比べてみるとそれぞれの違いが分かって面白いですね。こうした制作体制以外にも様々な違いがあり、その(日本のマンガから見た)違いこそがアメコミならではの魅力を作っています。それらについても、おいおい書いていきたいと思います。
