
毎日コツコツ料理暮らし その72「料理を真似ることが上達の一歩」
こんにちは。ショクタクの久保です。
普段、色々な新しい料理を作ることが多々ありますが、真新しい料理というものは滅多にありません。何かを参考にしたり、言い方は悪いですがリスペクトを持ってパクる、真似るということをすることが多いです。
料理に限っては、参考にしたり真似して作るというのが多い分野だと思います。真似してもうまく真似できない・・・なんてこともあるかとは思います。
私は、仕事の案件で新しく何かを作る場合は、ネットで調べて作ることが多いのですが、このレシピだったらこうやったらもっと美味しくなるはず!など参考にしつつもアップデートを考えて作ってみます。
今回は、料理を美味しく真似る3つの方法をご紹介します。私の常にやっていることですので、参考になったらと思います。
1.料理の基本を学ぶ
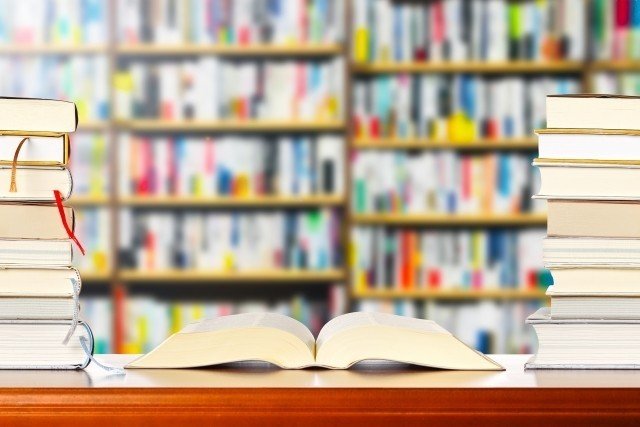
料理は、とても身近ですが専門的に詳しく学ぶということは料理人になりたい方で料理の専門学校に行く以外の人にはほぼないかと思います。私も料理の専門学校に行っていませんが、いろいろな飲食店で自分なりにいろいろな技術や味を学んで良い意味で真似て勉強してきました。一番、料理を教えてくださった店で店長さんがおっしゃっていたのが、「基本を学ばないと新しいことはできない。つねになんでこうなるのか?という疑問をもつべき」というようなことをアドバイスいただきました。基本を学ぶというのは先人の技術を真似ることですね。
料理をしていると、当たり前のようなことも疑問にしてみるとわからなくなることは多々あります。「煮物はなんで水から煮込むのか?」「料理のさしすせそはなんで順番があるのか?」などたくさんあると思います。料理は理科の実験に近いものがありますし、昔はこうしていたというのが今ではやり方が技術の革新によって変わってきたなどアップデートされることも多々あります。料理の基本系の本などもたくさん最近はありますが、なぜそうやってすると美味しくなるのか?など詳しく説明しているものを選ぶのがオススメです。
あと調理科学系の本もたくさんでています。論理的になぜそうなるのか?ということも書いており、知っておくことでいろんな料理に応用もできます。
『「こつ」の科学ー調理の疑問に答える』は、かなり古い本で内容が古い情報もあるのですが、私が最初にかなり参考にさせていただいた料理の科学本です。疑問に思うことから読めるのでさっと気になることも調べれます。昔ながらのやり方もあり、現代の最近のやり方と比べてみるというのも面白いと思います。
マツコの知らない世界の初期にも出演されていました、水島弘史さんはフレンチ料理の調理方法からのアプローチを家庭料理に落とし込んで料理を美味しくする方法をアップデートさせることを広めた一人だと思います。私もかなり参考にさせていただきました。水島さんの内容がかなり浸透して色々な人も同じように本で書いていたりしているので現代の料理の方法の基本になっているかもしれません。
レシピ本を大量に持っていても、料理の基本を知らないとなかなか料理のレベルアップができないものです。私もレシピ本ばかり集めていましたが、料理の基本の本などを参考にしてから、ステップアップできました。
その2:外食した時の料理を真似してみる
私は、外食した時に「真似して作ってみたい!これはパクれる。。。」なんてことを常に考えています。
真似をするというのはまねる=まなぶです。オリジナルを作らなければ!ってなるほど、美味しくないものができたりしますし、うまくいかないことが多いのは正直なところです。仕事柄アンテナを張っているのですが、仕事上でなんでも真似したらいいなんてことはありません。これはこういう案件に使えそう。これはあの人に作ったら喜ばれそう、これは改良の価値がある!、あの店のテーマに合う料理だ!なんて、状況を応じて真似るものを選んでいます。
真似るコツとしては、店の人に聞いてみると案外教えてくれることもあります。大手チェーン店では作っている側も知らないことが多いと思われますが、個人店でされているところなら教えてくれるかもしれません。私も店で作り方を聞かれたら教えています。私も知り合いの店でしたら聞いて参考にして作ることもあります。
もし、食べてこれはこれが入っているからこういう風にすれば作れるっていうことで作ることが私は多いです。絶妙な味わいを見分けるのは難しいかもしれませんが、失敗してもよいので自分で再現してみるというのは勉強になります。その1の基本を学んでいるとより再現力もつくかと思います。有名店の料理なら、某レシピサイトで再現してみましたレシピがあったりもします。真似ることを悪いと思わずに、どんどん真似して引き出しを増やすことが料理がうまくなるコツです。
その3:いろんな料理を食べる

私は普段の食生活はルーティーンなところはありますが、外食の時には出来るだけいろんな店にいくようにしていますし、トレンドもチェックします。今でしたらグルメバーガー巡りもしたりしています。コンビニの新作のチェックも好きです。味の流行もありますし、時代背景で求められるものも変動します。今は免疫力を上げるというのがキーワードの一つになっています。大地震や災害などの時には発酵食品が見直されて流行になるという統計もあります。新型コロナウイルス感染によって、発酵食品の売れ行きも増えています。様々な現代の食様式を味わいつつも、自分なりの食生活を確立するということの両方を行うことが重要だと思います。自分には合う合わないもありますし、料理以外でも言えますが、良い面、悪い面の両方があります。私はベジタリアンでもビーガンなどではないですし、宗教上で食べれないものもありません。いろんな食事方式はありますが、何かに特化するということはしていませんし、するのはもったいないと思う方です。
それぞれの食費方式を批判することはありませんが、それだけになってしまうと雑食な私はストレスになってしまうと思うからです。知り合いにはいろんな食事方式をされている方もいまして、その食事方式から生まれた料理方法などは参考になることもたくさんあります。特化した料理方法でもありますし、おもしろいと思うことは取り入れてみたいというのがあります。外食で料理をする時に、これは何を使っているのかな?こういう調理方法をしているのかな?など考えながら食べると、真似することに繋がると思います。
3つを紹介しましたが、基本を学んでいろいろなものを食べて真似てみるというのが私の真似るから学ぶという流れです。決して真似ることは悪いということにはなりません。真似ても自分の個性が出てしまうものなので、真似たら独特なものができるなんてことはよくあります。0から作り出すのではなく、既存のあるものとあるものを合わせて新しいものを生み出すというのがほとんどです。これはすべての分野のクリエイティブなことにも言えます。ぜひ、おいしい組み合わせを発見してみてくださいね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
