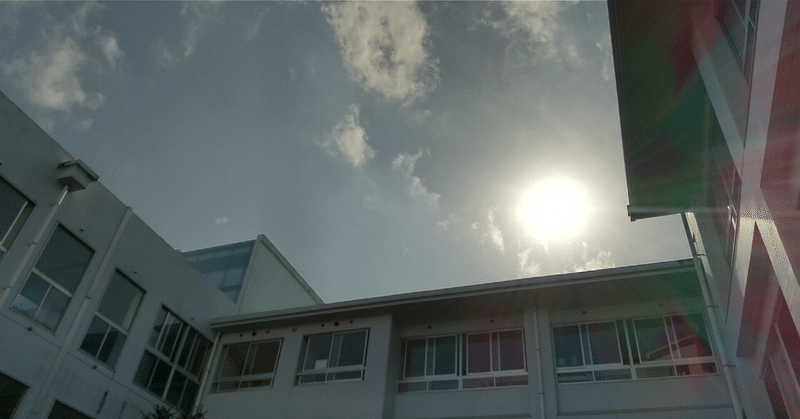
「硝子の鳥籠」 第2話 指針よ、揺らぐな(1)
「それじゃあね、早瀬川さん」
「はあい」
柊人が、去り際に爽やかな笑みを向けてくる。その隣を歩いていた千影は、こちらも見ずにさっさと職員室へと入っていった。
扉が閉まった途端、百香はヒラヒラと降っていた手を降ろしにこやかな表情を解いた。
(……戻ってきてから、もう一年か)
弓月柊人は、百香にとって単なる幼馴染ではない。
敵だと認識したのは、紅葉した落ち葉が舞い落ちる秋の日だ。早瀬川家の庭に立って談笑する彼と千影を、自室の窓からぼんやりと眺めていた。
仲がいいな、位に思っていたのに、クスリと笑みを漏らした千影を見た瞬間、どうしようもなく感情が燻ったのだった。
そして、柊人の背中に悪魔の羽が見えた。
わかったのだ。いつか千影をこの島から連れ出す相手になるだろうと。
それでいい……いや、それがいいと思っている。
ここに縛り付けておくより、千影はずっと幸せになれるはずだ。
(いつまで、教師なんて似合わねえことしてるつもりなんだか)
百香は硬い表情で教室へと歩き出した。
しかし、クラスメイトたちの顔は見たくない気分だったため、中庭に面する渡り廊下を通って遠回りすることに決める。
そのせいで、気分はさらに落ちた。
中庭には、寄り添い合う初代祓魔師夫婦の石像が建っているのだが、百香はそれが反吐が出るほど嫌いだからだ。
青々とした芝生の上で、まるで聖母マリア像のように清らかな雰囲気を纏っているのが気に入らない。
だって、自分と千影を石像にするのなら、きっと背中合わせだ。あんな風に手を握り身を寄せ合うなんて絶対にない。
(……あんな綺麗なモンに、なれるはずねえだろ)
ひとりでに足を止めていた百香は、剣呑な表情で再び歩き出した。
生徒たちは、歴史として彼らの存在は学んでも、担っていた役割は知らぬまま巣立っていく。
自分と千影もそうであったら良かったのにと思う反面、状況が違えば出会うことはなかっただろうと……それは嫌だと思ってしまうのだから、どうしようもない。
きっと、この矛盾した想いを死ぬまで持て余すのだろう。
「モカちゃん、おはよう。ギリギリだったね」
教室の扉を開けるとすぐに、気安い声が飛んできた。
モカというのは名前の後半からとった安直な愛称で、クラスの女子たちはみな百香のことをそう呼ぶのだ。可愛くてちょっと不思議な妹キャラにぴったりであるため、なかなか気に入っている。
ちなみに男子たちからは、早瀬川さん、早瀬川。中には、親しくもないのに平然と呼び捨てをしてくる強者もいる。
「おはよ~。みんな朝から頑張ってるのに、寝坊なんて恥ずかしい」
病弱という設定の百香は、朝から体力作りのための走り込みを行っているクラスメイトたちと違って、基本的に座学だけ参加している。
早瀬川家に生まれた以上、「祓魔師になることは難しくとも基本は学んでおくべきだ」という父の考えで在学させられているという体なのだ。卒業後は協会関連の事務仕事をするというのが、同級生たちが知る百香の進路だった。
「そ、そんなことないって!」
近くの席の男子が必死に声をかけてくれたため、ふわふわ~っと花が舞うような笑顔を向けてあげた。
「ありがとう。優しいね」
赤面する男子と、「モカちゃんってば、本当に可愛いんだから~っ! ホント天使だよねっ」と沸き立つ女子たち。百香は「そんなことないよ」とはにかみながらも、内心、したり顔をしていた。
(どうだ、今日も可愛いだろ? この顔を拝めることに感謝しろ)
こんなことを考えてるなんて、誰も思うまい。
百香はリュックの中身を机に入れつつ、こっそり視線を動かした。
誰が自分に好意を持っているのかある程度把握しているため、男子たちの行動を観察するのは面白い。「残念。俺、実は男なんだよな」と暴露したら、彼らはどんな反応をするだろう。
意味のない妄想をしながら壁掛け時計を見上げてみると、時刻は八時三十七分。時間を潰した甲斐があって、ホームルーム開始まではあと三分だ。
「よーっす。席に着けよー」
すぐにガラッと教室前方の扉が開き、担任の青山が入ってきた。体育教師であり、祓魔師というよりもボディビルダーと説明された方がしっくりくるような図体をしている。
二十六歳独身。背が高くて、見た目もまあそこそこ。情に厚いから、戦場に立ったら早死にしそうなタイプ。
(……で、望みなんてないくせに、千影に惚れてる)
望みがないというのは、百香の希望的観測ではなくほぼ事実だ。
千影を抱くことが許されているのは、世界で唯一百香だけ。
彼女の宿命を知る青山もそのことを理解しているはずだが、まさか実際に通じているとは思ってもみないだろう。
早瀬川家に引き取られてから、姉弟として育ったのだ。さらにはいつも険悪な雰囲気を醸し出しているため、教師たちはもちろん、両親や兄たちは、千影と百香の関係を予想もしていないはずである。
窓の向こうに、何気なく目を向ける。
自由に羽ばたく鳥たちを見ているうちに、遠い日の記憶がひとりでに蘇った。
* *
百香の母は、いわゆるシングルマザーだった。祓魔師だった父親が百香がまだ赤ん坊だった頃に殉死したらしく、彼女は女手ひとつで息子を育ててくれたのだ。紋様が出現したとき、祓魔師の血が流れているゆえの異変に違いないと察した彼女は、医者ではなく協会に急ぎ連絡を入れたのだという。
七歳の誕生日を迎えて間もない頃のことだった。
協会は、準備が整い次第、親子で早瀬川家に移住するよう指示を出した。
ようやく現れた要の君を、厳重な造りの屋敷で保護するためだ。初代要の君とうつしみの巫女の末裔だということで、早瀬川家は代々、両者を補佐する役割を担ってきた。
当代の巫女である千影の生家だということも手伝って、百香が身を寄せるのは避けようもない流れだったのである。
しかし、当初は早瀬川家の親類という設定だった。それが養子として迎え入れられることになったのは、引っ越しを目前に、母親が心筋梗塞で急死したからだった。
ちょうどアパートに訪れていた協会事務員が手早く救急車を呼んでくれたが、間に合わなかった。葬儀や身辺整理など、七歳の男児にはとても手に負えなかったであろう事柄を円滑に進めてくれた彼らには感謝している。
外では女として振る舞うよう義務づけられたのは、要の君の情報が漏れている危険性を加味してのことだ。
百香が覚醒するまでの七年間、祓魔師の人数は減る一方で、悪魔側にも戦力不足が悟られていたようだった。理由を探られ、真相に行き着いていたのなら、確実に狙われる。「要の君は、歴代男性」だということを逆手に取り、女として生きるというのが苦肉の策だったのだ。
ちなみに「百香」という名前は、長寿の願いを込めて付けられたものだと聞いている。
当時はまだ幼かったため、天涯孤独の身にならずに済んだ幸運に感謝することもできなかった。それどころか、母が死んだのはこのおかしな痣が出てきたせいだと自分を呪ったものだ。
やたら可愛い、新しい名前も大嫌いだった。
それがほんの少し変わったのは、千影から掛けられた言葉がきっかけだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
