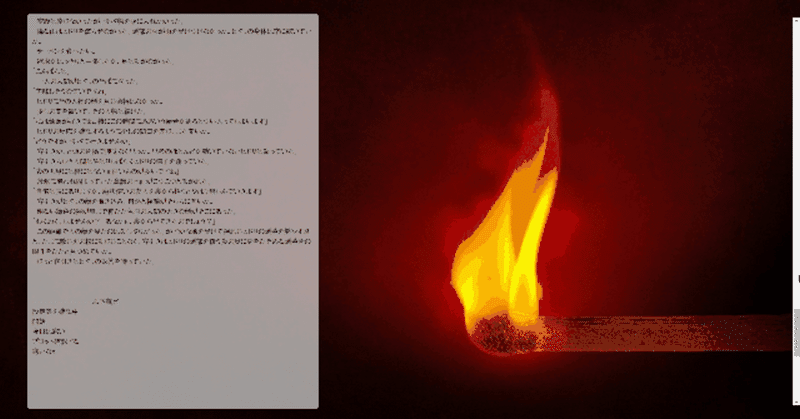
絶世の美人の頭部は火に包まれた頭蓋骨になった【2020/11/12進捗】
書き途中の進捗です。全ての文章は後に書き直す可能性があります。
下記の企画より設定を一部拝借しています。
-----------------------------------
「おめでとう!」
「ありがとう、君も契約し終わったの?」
「ああ、無事に魔法使いになったよ」
四つ角に設置された、水色の蛍光色を放つ四柱を光源とした広場は、小一時間前の静寂が嘘のように、新人魔法使いたちのざわめきで満ちていた。同色に発光する床に照らされ、目の下の影がなりを潜め、鼻や唇の上に影が伸びる新人魔法使いたちの顔からは、多かれ少なかれ喜びがこぼれていた。
「契約はどうだった?」
「こえぇやつだったよ。でも代償は軽めで済んだ」
「私も軽めだった」
「軽い代償で魔法使いになれたやつはラッキーだな」
契約を終え、魔法使いになった愛弟子たちが高揚し半ばはしゃいでいる様子を、教師陣は暖かい眼差しで見守っていた。
「こら、まだ戻ってきていないやつも居るんだ。静かにしなさい」
教師の一人が一声上げると、新人魔法使いたちの声量はわずかに小さくなった。
「まだ戻ってきていないやつって誰だ?」
「そういえばヒドリが居ないね」
「お前、ヒドリが魔法使いになって戻ってきたら恋人になって下さいって告白するんだろ?」
ゆらりと、原始的な火が闇の中で尾を引いた。
「ちょっとちょっと、あっちにも同じこと言ってる人居たよ」
弱々しい靴音を鳴らす黒塗りの革靴には、橙色の暖かい火の光が落ちていた。
「さすが絶世の美人、ヒドリ様は違うね」
一人の教師が契約から帰ってきた弟子に気づき、かけようとした声は出なかった。
だんだんとヒドリの登場を楽しみにする雰囲気が弟子たち全体に広がっていった。
「ヒドリって千年に一人の美人って呼ばれてるあの?」
「ああ、私見たことあるけど、本当に今まで見てきたどんな芸術作品よりもきれいだから、楽しみにしてな」
青ざめる教師にいぶかしげな視線を送りながら、隣の教師が契約から帰ってきた弟子を迎えようと一歩踏み出した。
「お帰り、ヒドリ」
そうかけた声は尻すぼみになった。
しかしその声に反応した弟子たちは一斉に振り返った。
誰も声を発さなかった。
新人魔法使いとしての契約のために着用したローブの上に乗っていたのは、空に向かって尾をたなびかせる一つの火の玉だった。一見すると頭部にだけ放火された人間だった。しかし首から下は正常に機能しているようだった。
火の奥で焼け焦げ燃え続ける頭蓋骨が薄らと見えた。眼孔にはまっていた眼球はとうていそこに存在し続けられないように思えたが、一対の眼は火よりも濃い色で光り、存在を主張しているのがわかった。
一人の生徒がその場で嘔吐したのを皮切りに、我に帰った教師の一人が慌ててヒドリ本人であることを確認するために駆け寄った。
魔法使いになるためには、魔法を使う力を授けてくれる存在と契約する必要がある。ある程度の訓練と勉強を積み、準備の整った弟子たちはそれぞれの適正に応じた存在と契約をする。これが完了して初めて新人魔法使いとなることができる。
しかしこの契約には代償が伴う。代償の内容は人それぞれで、重さも人それぞれだったが、今期の生徒たちの中でヒドリは最も重い代償を負った。
「ヒドリの代償見た?」
「見た。悪いけどもう顔見たくない」
人気のない廊下を歩きながら、教室内から漏れた声が耳に入り、ヒドリは寮の自室へと足を速めた。
「あの美人が」
「気の毒に」
「気持ち悪い」
「もう見れない」
契約の夜が終わってから散々陰で言われた言葉の数々だった。もう誰も目を合わせてくれなくなった。言葉を喋れなくなったヒドリに話しかけてくれる者はいなくなった。優しい者でも、優しさ故に心を痛めてくれているのか、痛ましさのにじむ笑顔を作って二言三言話しかけてくれたあと、居心地悪そうに去っていく。
そういった優しい心を持った同期に感謝できるほどの余裕は、ヒドリの心になかった。
逃げ帰るように電灯のない自室に入ると、ヒドリの火で室内が昼間のように明るくなった。教師陣が作ってくれた、ヒドリでも問題なく横になることができる闇のベッドにヒドリは飛び込んだ。
布団を被り、ベッドに顔を押し付けた。
契約が終わってからヒドリの生活は一変した。周囲の扱いだけではない。普通のベッドには火が引火するため寝れなくなった。今まで住んでいた部屋は引き払い、この身体になって要らなくなったり使えなくなったものは全て処分し、教師が作ってくれたこのベッドと燃えないものを傍に置いて暮らしていた。
呼吸や食事や水分摂取の必要がなくなり、排泄も必要なくなった。ヒドリは完全に魔法で生かされる存在になった。その代わり、頭部の火が消えたら死ぬということだった。
食堂に用がなくなり、容姿のせいで外に出かけづらくなり、魔法の指導以外で外に出る用事がなくなり、引きこもり、ますます他人と疎遠になっていた。
布団の中で自分の腕が目に入った。契約の夜から二週間が経ち、身体は病的に痩せ細った。骨と皮を残して全てを削げ落としていく自身の身体を目に入れるのは痛ましかった。
枕にあたる暗闇に顔を埋めた。何も見たくなかった。睡眠すら必要ない身体になったが、寝ようと思えば寝ることはできた。それが唯一の救いだった。人間でいられた。
「新たな魔法使いの船出を祝う『魔法使いの夜』が来週にある」
ヒドリはゆっくりと拳を握り込んだ。
「契約の成功と魔法使いの誕生を、契約相手を含む界隈全体が祝福する。私からの祝いの言葉はそこまで取っておく」
脳内で反響する今日の教師の言葉から目を背けた。契約で失ったものが多過ぎた。
「ヒドリ」
よく会話していた、友人と思っていた学友が微笑んでヒドリに話しかける。
ヒドリも応じる。学友の名前を呼び、たくさんの人々に褒められてきた笑みを見せて、たわいのない言葉を紡ぐ。
学友の背後に置かれた鏡には、何度も見た自分のきれいな顔が映っていた。
「美しい」
「絶世の美人だ」
「こんなにきれいな人間は見たことがない」
「性格も良いし」
「何人の人を恋情の沼に落としてきたんだろうな」
「そこにいるだけで光になる」
「美の神の化身なのかもしれない」
「良い人だ」
言葉が傍を通り抜ける。
しかしだんだんと、口が重くなってきた。おかしいな、喋り疲れたのかな。
声がかすれ、出なくなった。
ふと鏡に見たことのない光源が映った。
自分の顔が、燃えていた。痛くはない。しかし火の奥の自分の顔は、頭蓋骨を残しているだけだった。
目の前の学友は俯いていた。話しかけようとしても、声は出ない。学友は歪な笑みを見せながら顔を上げた。
「ごめん、このあと先生に呼ばれてるんだ」
そう告げた学友が走っていく。その先には、ヒドリとも仲が良かった数人の同級生が居た。ヒドリの学友を迎えた同級生たちは、楽しげに話しながら歩いていく。
そこに自分も居るはずだった。数週間前までは、自分も居た。
「ヒドリ?」
少し遠くで誰かが囁いた。
「残念だよね」
「もうあの宝みたいな美貌を拝めないのか」
「グロいから傍に来て欲しくない」
「喋れなくなったし表情もないから、何考えてるか全然わかんない」
いつの間にか囁く人数は増えていた。
「ヒドリを好きなやつなんてもういるのかしら」
「近寄りづらくなった」
「人間に見えない」
「本当にヒドリなの?」
「実は怪物なんじゃない?」
「ずっとそばにいると食われそう」
食堂のテーブルで同級生たちが食事をしている。彼らの顔には笑みが広がっていた。「美味しい」と口々に言い、おかわりを求めに行く。
大食いな同級生がスプーンに盛った肉や野菜を次々と頬張っていく。皿の山が出来つつあるその同級生を横目に、こんがりと焼き上げられたパンがいくつかヒドリの前には置かれていた。
ごつごつとした凹凸を感じるパンの表面を手でがっしりと掴むと、震える手を恐る恐る口元に持っていった。思い切り口を開く。食事時の口の開き加減などとうに忘れた。
パンの焦げる臭いがした。パンを噛み切るために口を閉じた。何も口内に入ってこなかった。手の中のパンに目を落とすと、口に向かって差し込んだ箇所が真っ黒に炭化していた。
「ヒドリ、食べれないの?」
横からすっと手が伸びてきた。
「じゃあちょうだい」
一人がヒドリの皿からパンを一つ取っていった。
「私も」
それを皮切りに次々と周囲から手が伸び、パンをさらっていく。
皿からパンが消え、ヒドリの手に半ば炭化したパンが残った。
食器の触れ合う音がそこかしこで響き、談笑する楽しそうな声が食堂に満ちていた。誰かがパンに噛みつき、引きちぎる。歯とスプーンの金属が触れ合う音が聞こえる。器に口をつけてスープをすする者もいる。肉にかぶりつき、肉汁で溢れる口の中を冷ますように息を吐きながら「うま、うま」と誰かがこぼす。
急かされるようにヒドリがパンを無理矢理口の中に押し込む。口の中に何かが入ってくる感触はなかった。ただ炭がぽろぽろとテーブルに落ちた。
「あーあ」
「もうお茶会にも呼べないね」
「気持ち悪いから食堂に来ないで」
顔を上げられなかった。何もなくなった皿を見つめた。
誰かが呟いた。
「ヒドリって、もう人じゃないよね」
ヒドリは覚醒した。電灯がないのにすっかり明るい天井が見えた。
動悸がした。心臓が追い立てられているかのように忙しなく動いていた。服が湿っていた。冷や汗だった。
慌てて上体を起こし、手首に埋め込まれたインプラントからスケジュール表を呼び起こす。手首の穴からぼんやりと青白い光が立ち上がり、その中に表の映像が浮かび上がると、今日が休日であることを思い出した。
青い光が消え、部屋は原始的な暖色の炎によって染め上げられるのみとなった。
外の廊下を駆ける同級生の足音が聞こえる。はしゃいだような声が玄関口へと向かっていく。皆、平日はまず行くことができない表世界へと遊びに出て行るようだった。
聞き覚えのある声も聞こえた気がした。いつも遊びに出るときに誘ってくれていた同期たちだ。
その声はヒドリの部屋の前で小さくなった。通り過ぎていく。
ヒドリの部屋に立ち寄るものはもういない。契約の夜が全てを変えてしまった。
動悸がだんだん激しくなっていることに、ヒドリは気付いていなかった。扉を隔てた向こう側の同期たちの声が脳内に反響した。扉の向こうは暖かかった。
生体情報を常に監視している手首のインプラントが異常を告げる歪な音を立て始めた。
すぐそばでかすれ声が聞こえた。
弾かれたように顔を上げると、鏡でよく見たきれいな顔をした自分が、炎に包まれた頭蓋を持つ自分に首を絞められていた。
わずかに空気のこぼれる口からかすれた音を漏らす自分の顔を見たかったのに、見えなかった。みしみしと骨が折れるのではないかと思えるような圧迫音が聞こえる。心臓が跳ね上がった。
やめてくれ、殺さないでくれ
叫び声は出なかった。声すらも奪われた。
インプラントがやかましい音を立てている。
靴音が人気と灯りの少ない裏路地に響く。今どき珍しい、原始的な橙色の火が辺りを明るく照らし、靴音とともに動いている。
路地の隅で、頭部のインプラントが顔前に投影した何かの画面を操作していた、みずぼらしい風態のヒゲ面の人間がギョッとした様子で光源に目をやった。
赤々と燃え上がる頭蓋をさらしたヒドリが、ふらつきながら路地を歩いていた。
怨霊や幽鬼が犠牲者を求めて徘徊しているような異様さを感じたヒゲ面は、すぐに目を逸らした。
この路地が魔法使いたちの住む裏世界に続く路地であることを思い出し、ヒゲ面が顔を上げたときには路地の薄暗さが戻ってきていた。
両手首のインプラントが埋まっている箇所に違和感を覚えたが、その正体が痛みであることをヒドリは自覚できていなかった。
寮を出て、多くの同期が遊びにやってきている、魔法を使わない一般人たちの住む表世界へとやってくるまでの記憶がなかった。
意識はどこか曖昧だった。全てが夢のようにふわふわとしている。かつて星が瞬いていたという夜空は魚眼レンズを通して見たかのように歪んでいた。ただ感情を抱いた本能がヒドリの足を突き動かしていた。
暗い路地から、躊躇なく光に満ちた表通りに踏み込んだ。青白いネオン色の光を数多の看板が放っている。通りに面したガラスの奥から冷たい光が溢れて路地にこぼれ、昼間のように通りは明るかった。小型の掃除用機械が通行人の邪魔にならないように控えめに動き回り、見た目の再現率の低いアンドロイドが歪な直立二足歩行を再現している。
店から漏れる音楽と通りにたむろす人々の声と、注意事項を喚起する機械音声や金属音、頭上を走り抜ける空中走行車の風切り音が混ざり乱れていた。
ヒドリの頭の中で色を伴ってぐちゃぐちゃと混ざり合う音は、車酔いのような気持ち悪さを呼び起こしたが、ヒドリの胃には吐き出せるものはなかった。
ちかちかと黒を帯びた花火が、身体が眩しいと感じていることを知らせるように視界に咲き乱れた。
大通りを堂々と歩く。以前の自分がしていたように歩く。ぐにゃぐにゃと脳裏が歪む。
通行人たちはヒドリに気づくと、ぎょっとしたような表情を浮かべてすぐに目を逸らし、ヒドリから距離をとりつつ足早に通り過ぎていく。
ああ、灯りがきれいだなぁ
不意に立ち止まった自分が胃液を地面に吐き散らしたことにも気づいていない。
あの店、今度みんなで行きたいなぁ
ヒドリが近づくと、人の波が二つに割れた。
きっとみんなで行ったら楽しい
ヒドリが近づくと人々は声を潜め、一瞬横目で見た後、何事もなかったかのように過ぎ去っていく。
試験管のような形の香水噴射器を人差し指と親指で持ったマークを、通りに面したガラスに映写している店がヒドリの目に入る。
香水、しばらく買ってないな
立ち止まり、胃液を路面に吐き出す。そばを歩く通行人が顔をしかめた。
胃酸の臭いを嗅覚は脳に届けなかった。脳裏には自分を囲む仲間たちと笑う自分の姿と匂いが満ちていた。君に似合う匂いだと褒められて、ヒドリは嬉しかった。あのときの嬉しさと香りに手を伸ばした。
香水を買おう。とびきり自分に似合うやつを買おう
ふらついた足取りで香水店へと向けた足を、別の匂いが止めた。
青白い電灯の下のカウンター席で、ずるずるとラーメンをすする客が居た。無人のラーメン屋台だった。カウンター席の奥で、ラーメンを作り販売することだけをプログラムされた機械腕がせっせと作業している。今の時代にしてはアナログにも、きちんと火を使って麺を茹でて料理しているらしかった。
良い匂いが鼻をくすぐる。客が美味しそうに音を立ててラーメンをすする。腹は空かなかった。もう何も食べなくなって二週間になる。全く腹は空かない。
でも食べたいと思った。そして今の自分の身体に物を食べる機能がないことを思い出させられた。
一瞬冷えた心臓を無視して、機械腕に注文しようと開いた口から声は出なかった。出せなかった。どんなに大声を出そうとしても出なかった。
それでもその場から離れられなかった。湯気を立てているラーメンが、人々の腹に収まっていく様子に釘付けになった。食べたいと思った。しかしどうすることもできなかった。
ぱらぱらと雨が都市を濡らし始め、人通りが多少減った。ヒドリはラーメン屋台のそばから離れられなかった。
そばで小型清掃ロボットがヒドリの吐瀉物を掃除している。通行人たちは不審げな視線をヒドリに向けていく。ラーメン屋台を任されたプログラムは淡々とラーメン作りを続け、路傍に立つ警備アンドロイドはじっと無機質な視線をヒドリに向けていた。
空腹は感じなかったが、食べ物を腹に入れたかった。
降る雨はヒドリを濡らせなかった。頭部の火が雨を受けつけなかった。ヒドリの身体は常に乾いていた。
ラーメンを食べたい。
欲求がはっきりと主張したが、足は動かなかった。
「こんばんは」
一人の人間がヒドリのそばに立った。
「美味しそうな匂いですね」
ヒドリにその人物の顔を見る余裕はなかった。
少しの間を置いて、その人物は続けた。
「私は麺類が好きでね。特にこの時間にああいう屋台があるとつい入ってしまいます」
ヒドリの反応を確認するように少しの間口を閉じ、また開いた。
「どうですか、食べて行きませんか」
客引きか、と頭の片隅で興味なく思った。思考のほとんどが動いていないヒドリは黙っていた。
客引きらしき人間はやはりしばらくヒドリの様子を窺っていた。
「表の世界には裏にはない面白いものが多いですね」
薄氷に覆われ固まっていた意識の水面がこつこつと叩かれた。
「自宅は表にありますが、魔法使いの友人を裏から招くとやはり楽しんでいきます」
客引きがヒドリの顔を覗き込み、自然と視線がそちらに向いた。
明るい緑色の髪が肩まで伸びた色白の人間の大きな顔がそこにあった。
「わくわく、しませんか? あなたも、裏から出てきたのでしょう?」
この距離で人の顔を見たのは久しぶりだった。かすかな風を受けて揺れるヒドリの頭蓋を燃やす炎と、たまに散る火の粉に動じることなく、客引きはヒドリの頭部を覆う炎の奥に身をひそめる頭蓋骨の眼孔をひたと見つめていた。
じっと客引きはヒドリの返答を待っていた。意識を覆う薄氷がぱきぱきと音を立てた。
開いた口からは何の音も出てこなかった。契約の夜とその代償の記憶が意識に押し寄せ、身体が震えだした。身体を濡らすことのない雨の存在が急に意識に迫り、その場の重い空気に宿る寒さが身に染みた。ラーメンの匂いよりも湿った雨の臭いが急速に強くなり、鼻を突いた。
防衛本能が懸命に記憶を意識外へと押しのけようと働き出すと同時に、ヒドリは震える身体を両腕で抱いてうつむいた。
その様子をじっと見ていた客引きは再び口を開いた。
「契約をしてまだ間もないように見受けられますが、裏世界のどこからいらっしゃったんですか」
びくりと身体が震えた。かつて話すための舌が収まっていた顎をかちかちと動かした。
ない。舌がない。声が出ない。あれだけ使っていた舌がどこにもない
身体の震えが激しくなった。
「……大丈夫ですか」
怪訝な声音で客引きが言うと、その声で弾かれたようにヒドリの片腕が上がった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
