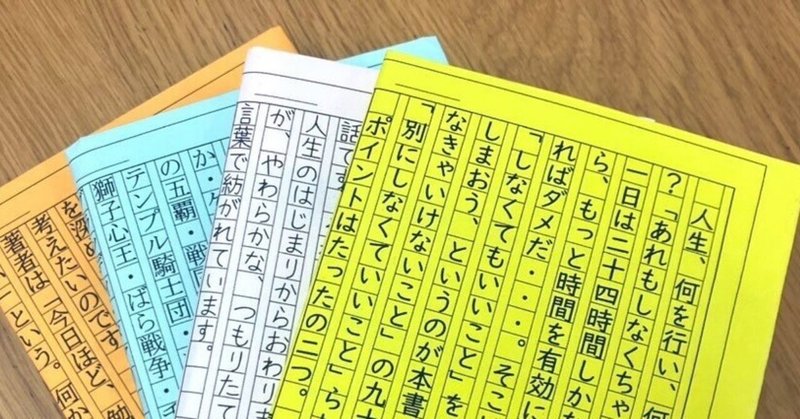
『イチオシ文庫企画』過去の推薦文集 第1回&第2回
書原では、昨年より「シークレット文庫企画」を行ってきました。
買う前に読めるのは、書原のおなじみのブックカバーに書かれた推薦文のみ。タイトルも著者も出版社も、あとは開けてみてからのお楽しみ。
ありがたくも御好評につき定番化したこの企画。
こちらでは、過去にスタッフが作成した推薦文の掲載&本のタイトルの種明かしをしていこうと思います。
第1回
ラジオのような1冊です。
ラジオのような一冊です。寝る前とか、電車に揺られている時とかに聞きたい。あるいはカフェでのんびりしながらってのも良いかもしれない。
そうやってぼんやりしている時の人間って、けっこう変なことを考えているものです。死んだあとのこととか、最近おいしかった料理のこととか、知り合いのこととか、ちょっと人には言えないようなこととか……。
そういうのを人が話すのを聞くのも楽しいもの。これはそんな一冊。
それとも今どき、隙間時間なんていうのは、ついスマホをさわってしまうものでしょうか? (私もそんな一人ですが。)
ですがほんの五分、この愉快な先生のお話につきあってみてください。いつもの夕飯にほんの少しだけ良いお味噌を使ってみたみたいな。そんな楽しさにきっと巡りあえますよ。
(遠藤周作『眠れぬ夜に読む本』光文社)
短歌です。えいえんに口ずさんでいたくなるような…
短歌です。えいえんに口ずさんでいたくなるような、胸をぎゅっと抱いていたくなるような、ひらりとそばをかすめた鳥の影におどろくような、砂糖のにおいのするような、いやオレンジかもしれないような、そっと目をとじたあともまだまぶしいものが見えているような、わけもなくスキップをしたくなるような、でもやっぱり歩くのもいいと思うような、綿毛のような、ヴァイオリンのピチカートのような、たとえ暗い日々がやってきたとしてもずっと憶えていたくなるような、雨上がりの雲の白さのような、今年はじめて菫が咲いているのを見つけたときのような、そんなどこまでもとりとめもなく運んでいきたい心が、五七五七七に収められていることのよろこび。
ぜひポケットに入れて、町を歩いてみてください。
(笹井宏之『えーえんとくちから』筑摩書房)
第2回 新書編
炎上、差別、ポリコレ、表現の自由、そして戦争――。
炎上、差別、ポリコレ、表現の自由、そして戦争――。誰もが自分の意見を手軽に発信できるようになった裏側で、色んな「正義」が溢れかえるようになり、けれどもその実像を顧みないまま時代は更に先へ――メタバースにまで進もうとしています。
そんな今だからこそ「正しさ」の正体を考えなおすことは、きっと大切です。
たいてい、ひとは最後には自分は正しいと信じている、でなきゃ社会生活なんてやってられない。けれども「正しさ」が悪意よりも恐ろしい凶器と化すことも世の常です。それでも、「正しい」方向を目指さなければ、世の中がもっと大変なことになる可能性だってあるのかもしれない。
地に足をとどめるための一冊。ぜひじっくりと読んでいただきたいです。
(品川哲彦『倫理学入門』 平凡社新書)
地球生命とは、いったいどういうものなのでしょうか?
地球生命とは、いったいどういうものなのでしょうか? 物質的に見た場合、その体の大部分は「水」でできています。私たち人間なら、水の大まかな割合は赤ん坊が80%、大人は70%、老人になると60%。歳をとることをよく「枯れる」といいますが、実際、人体の水分含有量は次第に減っていくわけです。
しかし、「生命とは何か」を考えるときに重要なのは、その水を除いた残りの部分です。人間の場合、水を除いたうちの半分は、炭素でできています。成人ならば70%が水ですから、残り30%の半分の15%が炭素です。ほかの生物も基本的には炭素でできています。つまり、地球生命とは「炭素化合物」なのです。
生命という「不安定な炭素化合物」が、なぜ40億年もの長きにわたって続いてきたのか? これは非常に不思議なことなのです。
(長沼毅『死なないやつら』 講談社ブルーバックス)
「思想家とは、時代を診る医者である」
「思想家とは、時代を診る医者である」
専門知識を駆使して”時代”という患者を「診察」し、適切な薬を「処方」できるプロフェッショナルのことなのです。残念ながら〈私〉たち、いわば素人は長期的な観点から時代状況を判断する余裕がありません。事件や自己について、ほとんど知識もないままに善意の判断を下し、場当たり的な思いつきを大層な「意見」だと勘違いしてしまう――特効薬だと思って毒薬劇薬の類を口にする危険は十分にあるわけです。では過ちを犯さないためにはどうすればよいのでしょうか? 「信頼できる先生のところで定期的に診てもらう」これが最善の予防策かと思います。
本書は丁寧な「時代診察」に定評ある先崎彰容先生が書かれた「処方箋」の数々です。全ての価値判断を自己決定しなければならない現代に。役立てて頂けますと幸いです。
(先崎彰容『違和感の正体』
NFT、DX、サステナブル、ダイバーシティ、ポピュリズム……。
NFT、DX、サステナブル、ダイバーシティ、ポピュリズム……。ニュースでもよく耳にすれば、ひょっとすると自分で口にもしているかもしれないこれらの言葉。ところで、その意味をきちんと説明してくれと言われたら、はたしてできるでしょうか?個人的にはポピュリズムあたりが怪しいです。あとダイバーシティも意外とふんわりしているかもしれない……。
よくよく考えずともこんなカタカナ言葉なんて勉強したのは受験だか、就活だかの時依頼で、けれどもここ数年でもNFTだとか、ニューノーマルだとか、新語なんてものはどんどん発生しているわけで。それがこれ一冊で総ざらいできるのは、ありがたい。枕元あたりにおいて、ちまちまとページをめくるのも良いかもしれません。
(造事務所『いまさら聞けない「ヨコ文字」事典』 イーストQ新書)
いかがでしたでしょうか? 少しでもお楽しみいただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
