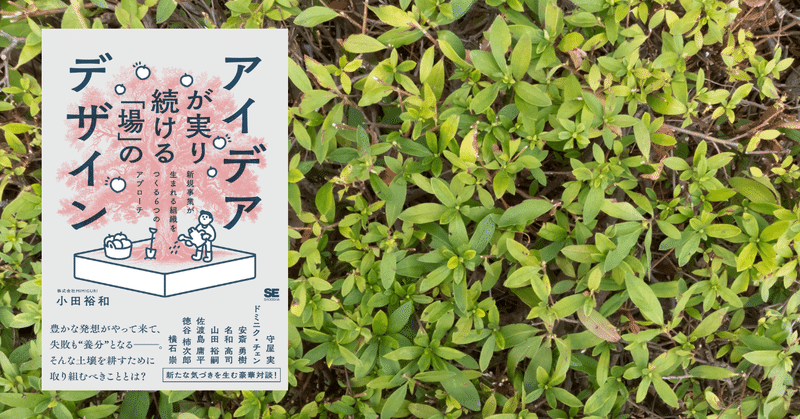
〔期間限定公開〕安斎勇樹氏に聞く――「アイデアを”評価する”側に必要なアップデートとは?」
新規事業を成功させるためには、「組織の土づくりから始めよう」
と提唱する『アイデアが実り続ける「場」のデザイン』。
2024年5月15日刊行の同書から、
6月30日までの期間限定で、抜粋をお届けします。
新規事業のアイデアがなかなか生まれないのは、
アイデアを生む側だけの問題でしょうか?
実は、アイデアを評価する側も、アップデートが求められているのでは?
評価する側の価値観が問い直されていくためには何が必要なのか、
株式会社MIMIGURI共同代表の安斎勇樹さんに聞きました。

株式会社MIMIGURI 代表取締役 Co-CEO、東京大学大学院 情報学環 特任助教。
ウェブメディア 「CULTIBASE」編集長。
著書に『問 いのデザイン』、『問いかけの作法』、
『リサーチ・ドリブン・イノベーショ ン』などがある。
小田裕和(以下、「小」) 新規事業施策の現場で、有望なアイデアが生まれることを促すために、「社員教育が必要なので研修をやってくれないか」「アイデア出しのフレームワークを社員に教えてほしい」というご要望をよくいただきます。
ただ、ジャッジを下す評価者側が特に変わろうともせず、「現場メンバーに変わってもらわなきゃ」と言っているだけでは、土壌が消費されて死んで
しまうという危惧があります。
安斎さんは「評価」という営みについて、僕も所属するMIMIGURIの共同代表として今までたくさん経験してきましたよね?
安斎勇樹(以下、「安」) そうですね、MIMIGURIは主に組織のコンサルティングを得意とするベンチャー企業で、70名ぐらいが在籍しているので、
評価という営みはどうしても必要になってきます。
MIMIGURIは同時に、文科省認定の研究機関でもあり、小田さんも僕も、大学で博士号を取って研究しながらそれを実践するという、研究と実践を行ったり来たりしながら組織やイノベーションの問題に取り組んでいるわけです。それで、ちょっと企業の文脈から離れて、アカデミアを例に考えてみたいなと。
研究という領域でも、「評価」が日々飛び交いますよね。学会に論文を10本出したとしたら、3本通るか通らないかですよね。その領域の専門家からジャッジされて、「この論文は全然ダメなので載せません」とか、「いいけど分析が微妙なのでやり直し」といったコメントがついて返ってくる。大学のゼミや研究室というコミュニティの中でも、指導教官や先輩の先生方がいる中で、日々評価されながら論文を磨いていく。
そういう場面を思い返して感じるのは、ダメなところや不備を見つけてNGを出すのは簡単だということです。
論文は、多面的に合格点に達していないと掲載されないですが、「いかにダメか」を指摘するのはわりと簡単です。一方で評価の力量が問われるのは、その中の良さやポテンシャルを見抜いて、「どうすれば良くなるかな」という期待を込めながら、良くなるための差分を「クリティーク」していくことですよね。そういう「評価技術」が必要なんです。
評価技術がないと、ダメな理由ばかり挙げていくようになり、「ポテンシャル」が日の目を見ることがない。
小 安斎さんはずっと、「自分はポテンシャルフェチ」だとおっしゃっていますよね。ポテンシャルを見抜くためには、どういうことを意識しているんでしょう? あるいは、どうやって見抜く力をつけようとしているんでしょうか?
安 人についてもアイデアについても、すでに顕在化している「良さ」の評価と、潜在的に良くなっていきそうかどうかという、未来の可能性に対する評価がありますよね。
新規事業やアイデアの評価については、「可能性を評価する」という目線を持たないといけないのは確実に言えることですよね。現状のプランがどうかというより、どう良くなっていきそうなのか。
僕自身の感覚で言うと、パッと見たときに、「あ、これ良くなっていきそうだな」とか、「ここがこの人のポテンシャルだよな」などと毎回分かっているわけではない。分かるのは、その内容が自分の専門領域や経験知に近い場合が多いんですよね。
自分はこういう経験をしてきた、こういう苦労をしたことがある、だから「これは結構おもしろいこと言ってるぞ」という嗅覚が働く。ただ、自分の専門領域以外は難しいですよね。
自分の基準で評価しようとすると、ポテンシャルでジャッジできなくなってしまう。だから、本人がどれぐらいこだわりを持っているのか、どう育てようとしているのか、という「執着」や「固執」を見ているのかもしれません。
小 自分の専門領域から離れていて内容がよく分からなくても、本人がそれを育てていけそうなのかを見るというわけですね。
安 そうです。例えば、小田さんに対する僕の最初の印象はその両方が入り混じっていて。小田さんは当時、デザインや心理学、学習に関する理論を参照しながら博士論文を書いていたわけですが、僕の専門領域から近かったのもあって、「この理論とこの理論を組み合わせて研究するっておもしろいし、ユニークな視点を持っているに違いない」という嗅覚が働く。その一方で、半分以上は僕の専門性では理解できない。
「何言ってるのかよく分からない」けれども、小田さんなりの強いこだわりと愛着、プライドを持っているのを見て、きっとおもしろい研究やパフォーマンスをするだろうなと。
小 自分のことを話されると、恥ずかしくなってきますけど(笑)。
研究内容やアイデアそのものについては、自分の領域から遠いとジャッジするのはなかなか難しいけれど、人そのものであれば、本人がどれくらいちゃんと向き合おうとしているかを見て、そのポテンシャルを見出してあげられる。その方が実は大事ではないかと。
「育成」を前提とした評価
安 内容に関しては、ジャッジが可能ですよね。例えば、僕が舌の肥えた一流の料理人で、小田さんがこれから料理人になりたい若者だったとして、小田さんが作ってくれた料理に対し、僕にその専門性があれば、「85点!」などと評価することはできますよね。
でも、「料理人としてこうなっていきたい」という、「人」に対する評価は、「うーん……75点!」などと点数をつけるというより、その人が実現し
ようとしているプロセスにどれぐらい関与したいか、応援したいか。ある意味、客観的なジャッジではないですよね。
小 ある程度の主観は入りますよね。
安 投資家の感覚に近いのかもしれないですね。惚れ込んで投資した相手なら、いろいろアドバイスしたり、人を紹介したり、そのプランがボツになっても違うプランを一緒に考えたり。共通のビジョンに向かって、協力関係を築きながらコミットしますよね。そういうことをやっていきたい相手なのかどうか。
小 その人のポテンシャルに投資したくなるかどうかが大事ということですよね。
安 投資する、応援すると決めたら、言い換えると小田さんと一緒に本を書く、小田さんと一緒に働いていく、と決めたら、小田さんに本当にポテンシャルがあるかどうかは正直どうでも良くなる。
ポテンシャルがあると思って一緒にやるんだけれど、その感覚が現実のものとなるように一緒に協力する、という関係性に変わりますよね。
小 一緒に探究していく関係性に変わるという。そう考えると、評価する側の人間性も問われるなという気もしますね。
安 やっぱり、メタファーとして教育は分かりやすいと思うんですよね。大学は入試によって入学者を選抜するけれども、いざ入学したら、その学生はちゃんと育てようとしますよね。本学の目指すべき人材像になってもらう、将来幸せになってもらうために育てていく責任が大学側に発生します。
アイデアにしても人にしても、育っていくものですよね。「評価」という営みのゴールは、撃ち落とすことではなく、成長させることにある。もちろん総合的に見たときに撃ち落とされるアイデアもあるけれど、より良いものをつくるために評価という技を使う。学校教育でも、何も心を折るために低い点数を与えるわけではないですよね。
小 自分の今の立ち位置に、ちゃんと気がついてもらうために評価するわけですよね。
安 そうです。評価ってかなり暴力的で、諸刃の剣ですよね。中間テストのフィードバックにしても、評価が緩くても中だるみするし、厳しすぎても心が折れてしまうし。その暴力性、権力性を自覚しながら、どうやったらみんながちゃんと勉強して成長するだろうか、と考えながら学校の先生は評価するわけですよね。そういう「育成」を前提とした、「手段としての評価」という感覚が必要なんだろうなと思いますね。
新規事業施策にも「カリキュラム」を
小 世の中には「結果を出したかどうかがすべて」という考え方もあって、それはそれで全然おかしいことではないと思うんです。でも僕と安斎さん
は、人が学んでいき、変わっていくことに惹かれてしまった側の人間だよなと。なぜそこに惹かれるんでしょう?
安 それは、ダメだと思われていた人、本人が自分でもダメだと思っている人が、あるきっかけによってポテンシャルが引き出されて輝き始め、ものすごい成果を出すというケースを目の当たりにしているからだと思うんですよね。
これは人間にとって根源的に魅力的なプロセスで、あらゆる少年マンガがそのフォーマットでできていますよね。最初から「最強の戦士」が出てきて、最強のまま終わるマンガなんてつまらない。
『DRAGONQUEST―ダイの大冒険―』(集英社)でも、ドラゴンの騎士の勇者ダイが最終的に魔王を倒すというストーリーの裏側で、当初はすべての戦闘から逃げまくっていた〝超ダメ〞なポップが、最終的に大魔道士になる。この裏側のストーリーの方が、読者を惹きつけていたりしますよね。
放っておいたら輝かなかったダイヤの原石や、ダメだと思われていたものが、ひょんなきっかけで成長し、覚醒するというフォーマットって、本質的にすごく魅力的なんだと思います。僕らは、そういうものが阻害される制度や仕組みが嫌なんだと思うんです。
『ダイの大冒険』の編集者はポップについて、「そんなに人気がないからどこかで殺してくれ」と、作者に何回も指示を出していたらしいんですよ。「ここらへんでポップが死ぬシナリオの方が盛り上がっていいんじゃない?」と。でも、作者が「絶対にポップは殺さない」と守り続け、輝かせたんです。だから、「こいつが成長した!」という物語を人は信じたいし、つくりたい。
小 ミドルマネージャーをやっていてしんどくなっている人って、その成長物語を信じずに、ただ結果を管理しなければいけない、となってしまっているかもしれないですね。
安 あるいは、もともとは信じていたけれど、3回ぐらい裏切りにあってガッカリしたのかもしれませんね。手塩にかけて育てようと思った矢先に、別の会社に転職されてしまうとか。打っても響かなすぎて、諦めてしまうとか。いろいろなガッカリ経験を経て、「そんな物語は少年マンガの中だけなんだな」と認識してしまう。合理性の問題や時間のなさに直面し、だんだん現実的になって、確実に評価しやすいものから評価するようになってしまう。
小 今は転職する人も多いし、会社の制度として育成の体制が整っていないとか、「それは人事がやることでしょ」と割り切られてしまうとか、いろいろあると思うんですよね。
安 育成計画やロードマップみたいなものを持たないと厳しいなとは思いますよね。大学の場合はまず入試で、どこまでできるかを見る。1、2年生のうちにこういうことができるようになってもらいたい、そして4年生でこういうことができたら学士、という育成ラインがある。
1年生が終わる段階で「3000字のレポートも書けません!」という状態はきついから、「これぐらいのことをやっておいてもらわないと困る」という段階があって、これがカリキュラムと呼ばれるものだと思うんです。
人を育てようとすると、その評価の背後にはカリキュラムが必要で、新規事業を育てる際に、そのカリキュラム的なものがないのかもしれないですね。それがないから、撃ち落とすしかない。この節目でこの段階に達していたら積極的に通すとか、達していないものは撃ち落とすけれど、もう一回チャレンジするためのアドバイスをするとか。
論文の査読もそうですよね。「現時点ではこの論文は載せられません。でも、こういうところを書き直してもう一回投稿することを期待します」というコメントがあったりする。
長期目線の育成計画と、短期的な厳しい評価が織り混ざっていないと、今、目の前で、この人をジャッジしないといけないとなったとき、易きに流れてネガティブ評価を与えて終わりになりかねない。
小 新規事業施策の担当者と人事部がコミュニケーションすることは、ほぼないですよね。
安 確かにそうかもしれませんね。社内でアイデアを評価して育てるという営みと、社内で人材を育て評価するという営みは、本来は連携しているべきですよね。
新規事業の評価者が、提案者の人事評価について人事と連携して、どういう成長課題があるかとか、どういうキャリアフェーズにあるのかということを踏まえて、アイデアにフィードバックする。そうすれば、プランだけを見てフィードバックするのと、だいぶ変わってくるかもしれません。
発案者を「好きになる」のが一番早い
小 マネジメントにおいて、どうすれば身の回りの「ポップ」を育てられるんでしょう?
安 ある人のアイデアがあって、それを会社でサポートしていくとなったとき、その人を好きになるのが一番早いと思うんですよね。みんな全力で育てようとして、うまくいかせてあげたいと思うじゃないですか。
例えば、僕が小田さんと出会ったとき、「一緒にやっていこう」「共に成長できるような機会をつくっていこう」となるためには、人間として好きでないと結構きついですよね。
もしポップが本当に嫌なヤツで、みんなに嫌われていたら、たぶん覚醒しない。逃げたり嘘をついたりするけれど、なんだか好かれているからうまくいく、というところがある。
だから、その人のケイパビリティやポテンシャルを評価する前に、本人を好きになった方が、結果的にポテンシャルが引き出されるよなと。
ただ、好きになるきっかけがあまりないんです。そういう感情は、会社に持ち込まないことになっている。「ここは学校じゃないんだ」とか言われてしまいますよね。一緒に働く人が好きになるような機会、アイデアを生み出そうとしている人を好きになる機会が組織の中にあったら、もっとうまくいくと思うんですよね。
田中聡さんと中原淳先生の『「事業を創る人」の大研究』(クロスメディア・パブリッシング)でも、アイデアが悪いのではなくて社内のサポートが得られていない、という話が出てきました。
よくこれは制度上の問題だと解釈されがちですが、「好き」だったらサポートすると思うんです。実はそっちが重要では?と思いました。
小 僕の博士課程の同期に、abaの宇井吉美さんというスタートアップ界隈の超有名人がいますが、彼女が博士論文で研究していたのが「巻き込み力」
だったんです。宇井さんは、本当にいろんな人を巻き込んで、事業を形にしている。いかに「推し」たくなる人を社内で育てていくかという話ですよね。
安 そう思いますよね。それは本人の人間性頼みのように受けとられるかもしれないですが、そんなことはない。
例えば新規事業のプランを聞くとき、プランだけではなくこういう情報も聞くとより推しやすくなる、というポイントがあると思うんですよね。一人ひとりの個人的な魅力に頼るのではなく、「推し」が起こりやすい組織にしていく。
あと、「推し上手」な人っているじゃないですか。そういう人が評価チームに一人いるといいですよね。評価者全員が推し上手だとちょっと不安
ですけど(笑)。
小 逆に、評価者側に対しても推しの感情があったら、提案する側のコミュニケーションが変わるかもしれない。社内で「推し合う関係」をつくるのは、評価という営みにおいて大事なポイントかもしれません。
安 推し上手な人は、意外と多いんですよ。「今から自慢話してください」と振られたら困る人って多いと思うんです。かなり準備して、気合いを入れて武装して、就活の面接みたいなモードで行かないとできない。
でも、「同僚や友だちのいいところをプレゼンしてください」と言われたら、堂々としゃべる人は多いんですよね。ワークショップで何回か実験したことがあるんですが、他己紹介で人を褒める方が生き生きとする。
他人推しができる人はたくさんいるのに、それはビジネス領域で評価されない能力ですよね。
小 新規事業を生み出すカルチャーをつくっていく中で、そういう存在が実はかなり鍵を握るんじゃないかと。
MIMIGURIでは「ミグシュラン」という評価制度があって、今期自分が何に取り組んだのかプレゼンしそれが評価されるのですが、評価の際に他者からの推しポイントを盛り込むことになっています。その人をもっと推せるようになることを重視した制度だなと改めて感じましたね。
評価という営みの中に、その人を推したくなるようなエコシステム、ポテンシャルを見出していく活動をどう組み込んでいくのかというのは、これまでにない視点ですね。
社内に「推し合う」文化をつくる
安 提案されたアイデアをすべて世に出すわけにはいかないという、出口のロジックは分かるんです。ただ、途中のプロセスにはいろいろ改善余地があるし、そのカルチャーとエコシステムをつくることが、組織づくりにおいて重要だと思いました。
「推しコミュニティ」をつくっていこう、推し合う文化をつくっていこうと言うと、「ぬるくする」とか「ゆるふわコミュニティにする」のかと思われるかもしれないですよね。「新規事業はそんなに生ぬるい世界じゃないんだよ」みたいな意見も出てきそうです。
でも、僕は逆だと思っていて。推し合っている方が厳しいクリティークをしやすくなる側面があると思うんです。僕は、小田さん推しだからこそ、小田さんのアウトプットには厳しくクリティークするじゃないですか。
小 たまに、すごいのが飛んできます(笑)。ぐうの音も出ないような。
安 それは、推していなかったら結構つらいですよね。お互いにつらい。僕はむしろ、「この人にはやらせない方が早いわ」という発想になってしまう。
「これを世に出してほしい」「うまくいってほしい」と思っている方が、そのクリティークに自分の責任も伴うし、お互いその前提のもとで厳しいことが言い合える。推し関係があった方が、アウトプットにこだわった関係性が築けるよ、と。
それがないまま、クオリティの高いアウトプットをつくるための評価関係をつくるのは、すごく難しいと思うんです。
小 ジャッジしなければならない、一方で成長してほしい、というある種のパラドックスをちゃんと利用して、成長機会につなげていく。そういうところも含めて、評価者が創造性を発揮し、楽しく評価できるようになったら、とてもいい場になっていきそうですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
