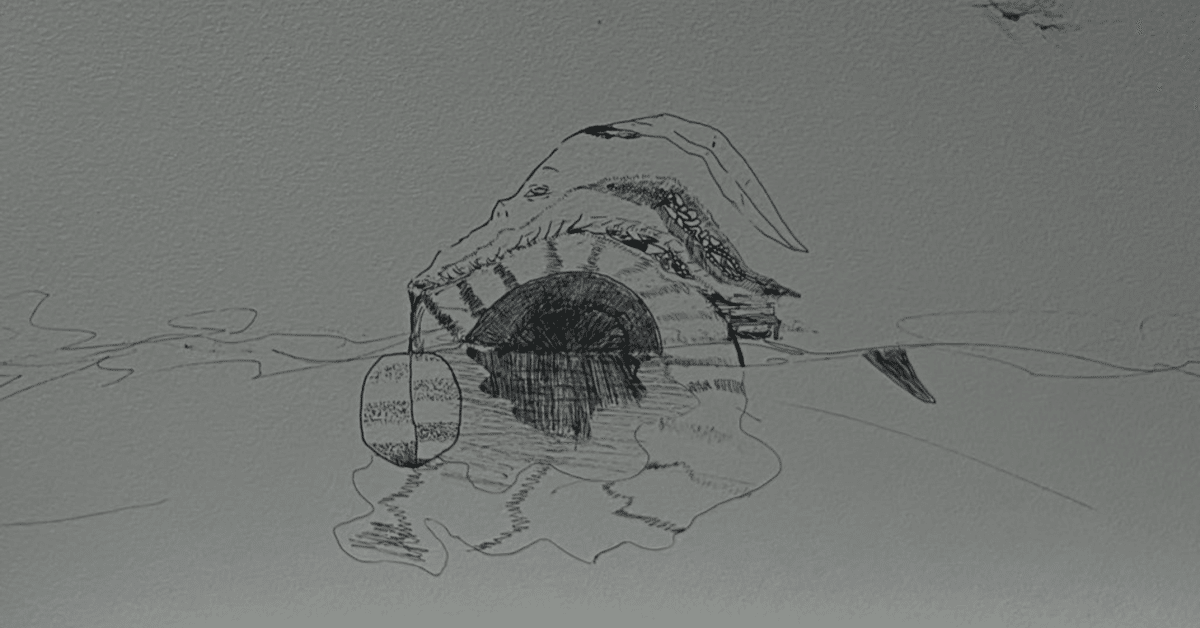
夢の中、外の現実。
カウンターテーブルで、横一列に、僕の姿形をした四人が座っている。
みんな、目を閉じて話している。
動く口から、泡に消える声。
みんな、夢を見ている。
夢は現実に持ち込めないらしい。
街の明滅する光が、のぼる泡に重なる。
初雪が上に昇っていくようだった。
顔を見合わせているというのに、誰もが独り言みたいに口を動かしている。
深夜、電子レンジの唸る音で目が覚めた時、それがなぜだか心地よかったことを思い出した。
排気口から漏れる褐色の灯りを眺めて、起きていれば、この時間がずっと続くような気がしてた不思議な感覚。
上の階の住人の物音ひとつで忘れ去られてしまうような、そんな程度に曖昧な記憶。
いつかの幼い白昼の記憶。
白塗りのアパート、砂利を敷き詰めた駐車場。
場所は、福岡県の甘木だったか。
状況に関わらず、ふと頭によぎる景色。
なにをしているわけでもなく、ぼーっと眺めてた。
断片的な記憶だから、というよりは、当時から僕はぼんやりとした人間だったように思える。
いつか、好奇心に突き動かされ、懐かしさに触れてしまえば、死んでもいいとすら思えるような気がしている。
今はまだ、懐かしさとは、夢の中だったのかもしれないと勘違いするくらいの距離がいい。
でも、できれば死ぬまで夢だと思いたい。
きっと、僕の姿形をした一人はこんなことを話してる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
