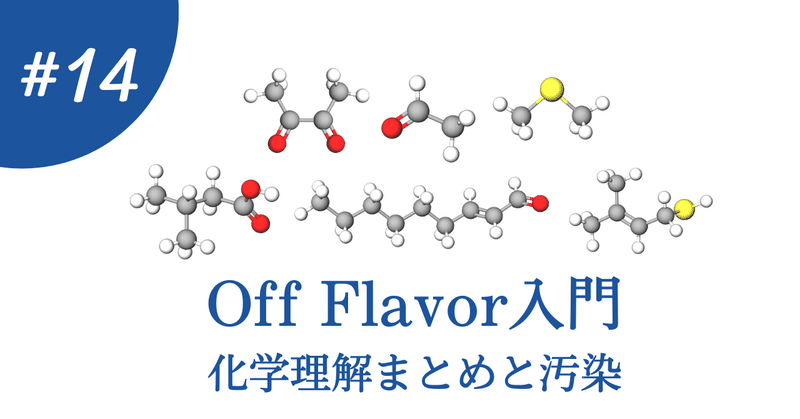
Off Flavor入門〜⑭化学的理解のまとめと汚染
前回からの続き
前回は酸化還元についての基礎理解を確認した内容でした。多くの化学反応はそもそも酸化還元であること、酸化還元も電子が関係してくることが確認できました。今回は第2回から13回までの内容をまとめてみたいと思います。
化学的理解のまとめ
このシリーズの第1回め「イントロダクション」で下記のような図を提示し、前回までにカバーしました。

匂いを感じる仕組み
オフフレーバーは嗅覚や味覚で感じるものですが、留保条件があります。嗅覚や味覚は案外あてにならなくて、視覚・聴覚などの他の感覚や環境、心理に大きく影響されるということです。その留保条件を確認するために、マルチセンソリー(多感覚)、クロスモーダル(五感の相互作用による統合感覚)、ガストロフィジクス(精神物理学的アプローチを取り入れた美味しさの科学)に触れました。
とはいえ、嗅覚や味覚がオフフレーバーを感知するのは間違いありません。したがって化学受容といわれる嗅覚・味覚が受容する対象である化合物を分子レベルで理解する必要があります。
分子レベルの理解
「分子レベル」と一言でいっても、ただ分子モデルを眺めているだけでは理解が追いつきません。分子の成り立ちを理解するためには、電子の性質の理解が欠かせません。そこで第3回では電子の性質と原子軌道についてざっくりとした解説をしました。この電子の性質というのは、一貫して化学反応に関わってきます。構成原理、パウリの排他律、フントの規則なども持ち出しましたが、要するに電子は原子核に縛られるものではなく本質的には自由に存在する(非局在性)ものです。その上で一番エネルギーの低い状態に落ち着こうとするので、様々な化学反応が起こります。化学反応は電子の性質を理解することで大枠は理解できると思います。それを突き詰めたのが分子軌道論やフロンティア軌道理論ということになるかもしれません。
エネルギーと生化学
電子の性質ともに化学反応の理解に欠かせないのがエネルギーです。エネルギーは化学反応に大きな影響を及ぼします。その理解のために熱力学の法則を持ち出してざっくりとした説明を試みました。熱力学の法則は本来はとても難解なので、ほんの入口しかお話できませんでしたが。そして、ギブスの自由エネルギーと発エルゴン反応・吸エルゴン反応は生化学を理解するうえで必須になるので押さえました。
電子の性質とエネルギーを確認したところで、今度は生物がどのように化学反応に関わっているのかを代謝(異化・同化)という仕組みを中心に説明しました。いわゆる生化学の分野です。ここでは酵素が代謝の中心になることを確認しました。
最後に確認した酸化還元は、基礎的な内容ですが誤解されやすい内容なので、定義をしっかり確認しました。ちなみに酸化還元にも電子の動きが関わってきます。化学反応は電子がすべてだと言っても過言ではありません。
オフフレーバーの全体像

オフフレーバー生成のイメージをラフに描いたのが上の図です。メインの産物であるエタノールや二酸化炭素と違って、オフフレーバーは微量でも感知されてビールのバランスを崩してしまう可能性があります。僅かな量のマイナーな産物や意図しない産物がそのままオフフレーバーになったり、他の化合物と反応してオフフレーバー化します。オフフレーバーであるかとうかはあくまでもバランスの問題なので単純に閾値を超えただけではオフフレーバーとならないこともあります。特定のフレーバーが突出してしまい、ビールの味わいバランスを著しく損なうと判断されるとオフフレーバーとされます。それがオフフレーバーであるかどうかは、最終的にはビアスタイルによってどう定義されているかどうかで判断されます。
汚染とは
ここで、これまでに触れなかった領域である汚染について。ビール醸造における汚染とは微生物汚染を指します。つまり醸造に使われるビール酵母以外の微生物が混入して活性することです。汚染の結果、混濁、香味異常やガス圧異常をもたらすと事故となります。
ビール変敗菌
ビール変敗菌として知られている細菌は、ラクトバチルス属(Lactobacillus)、ペディオコッカス属(Pediococcus)、ペクチネイタス属(Pectinatus)、メガスファエラ(Megasphaera)属の4属です。ラクトとべディオはいわゆる乳酸菌です。これらの細菌はビールを濁らせ、サワーミルクのような酸味を出し、バターのような不快なフレーバーを付与したりします。細菌以外では、ビール酵母と同じ真核生物のブレタノマイセス属(Brettanomyces)やサッカロマイセス属(Saccharomyces)の他の種が混入することもあり、これも汚染に含まれます。
汚染もバランスの問題?
ビールの汚染も究極はバランスの問題と言えます。そもそもステンレスの発酵容器が使われだしたのは長いビールの歴史の中でもつい最近のこと。日本では昭和40年代頃かららしいので、たかだか5-60年です。伝統的なビールは木製の発酵容器で多様な微生物(マイクロバイオーム)とともに造られてきました。現代のビールはCIPと殺菌による汚染の完全シャットアウトを目指していますが、伝統的なビールは狙いの酵母が優勢になるような管理をしつつもあくまでもバランスの中でフレーバーを構築していたと考えられます。農業でいうと自然栽培に似ているかもしれません。農薬をバンバン使って人間の都合の良いように育てるのではなく自然のバランスの中で育てるという発想は、伝統的なビール造りに近いと思います。
つまり汚染も他のオフフレーバーと同じく、ゼロイチではなく全体のバランスの問題であるという原則は心に留めておきたいものです。とはいえ、現代的なビール造りをする以上は汚染対策は徹底しないといけないですが。
次回へと続く
今回はこれまでのまとめと汚染について。汚染も含めてオフフレーバーはバランスの問題ということが確認できました。次回はビアスタイルについて。オフフレーバーがどのように定義されているかを見ていきたいと思います。
お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。
今年も造りましたアウトドア専用ビール「noon moon」、ホップ香る爽やかなペールエールです。

そして今回も同じ多摩川流域・檜原村で活動する皆さんと一緒に「Back to River」プロジェクトにも取り組んでいます。詳しくはこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
