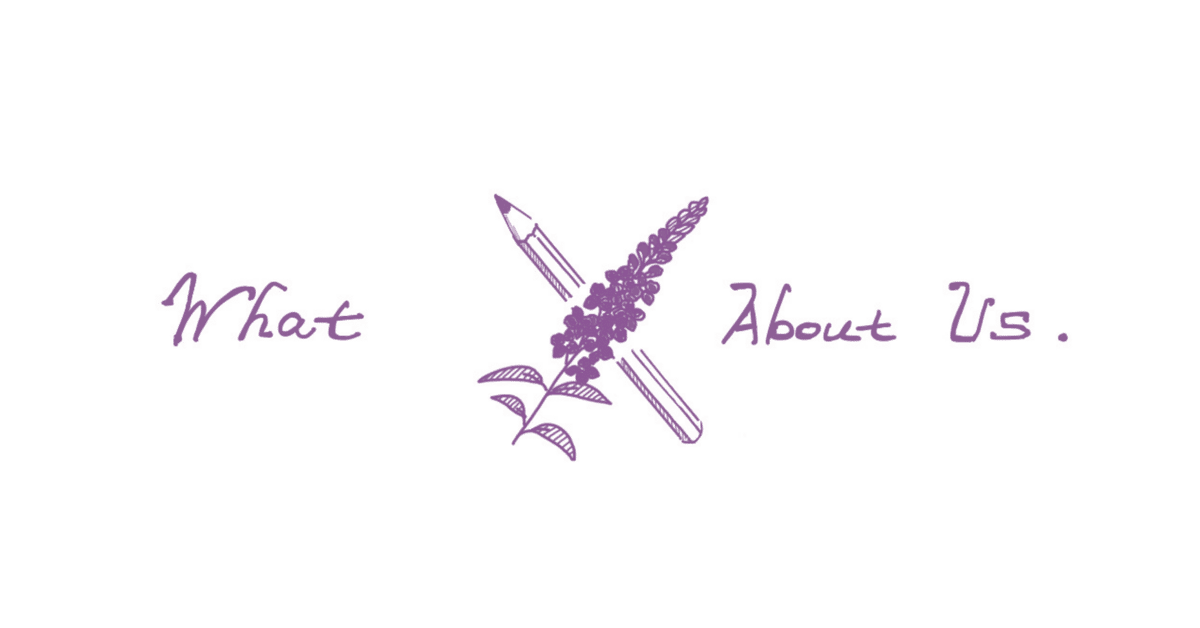
【掌編】ベロニカでは届かない
書く時間がもどかしい。思いながらも、僕はペンを走らせる。
初めて参加した即売会は、その界隈では有名なイベントだったらしい。ウェブで存在を知り、何の気なしに出店してみた僕は、当日になりようやくその規模の大きさを実感した。
端から端まで歩くだけで息切れしそうなほどに、広い会場。そこに所狭しと長机が並び、四桁に及ぶクリエイターがブースを構える。ただ薄い布を敷き、本を平積みしただけの自分とは異なり、棚を使ったディスプレイ、華やかなポップ類で集客を試みる周囲からは、この情報過多な空間の中、一人でも多くの目を我が作品に、という執念のようなものが感じられた。
一番違うのは、声だ。
通路を行き交う来場客に向け、魚市場のように呼び込みをかけているブース、目の前で足を止めた客に対し、すぐさま売り文句を唱えるブース。手法は様々だが、どのブースからも人の声が聞こえる。
対して僕はと言えば、開始から一時間半が経つ今になるまで、ただの一言も発していない。「いらっしゃいませ」も「ありがとうございました」も言っていないわけで、当然のことながら売上もゼロ。刷った部数はニ十冊。多くの本好きで賑わう中、いまだ誰にもページを捲られぬままのそれらを前に、肩身狭しと座り込み、焦りといたたまれなさに襲われている。
場の雰囲気に呑まれている、というわけではない。むしろこれが通常営業。昔からこの手の自己主張が、一際苦手なタイプであるだけだ。
よく言えば、謙虚。悪く言えば、臆病。
より端的に言うと、気が引けるのである。
見知らぬ誰かの時間を奪い、自分の作品をアピールする。そこで発生する相手への負荷と、ニーズが合致しなかった時のリスクを思うと、おいそれと容易くは踏み切れない。
せめて誰かしら、目の前で立ち止まる者が現れれば、勇気の出し様もある。しかし座ったまま縮こまる僕の姿は、さながらマッチ売りの少女のごとく見向きもされない。
右から左へ、左から右へ。こちらを見もせず、あるいは一瞥をくれるだけの来場者を、砂嵐になったテレビ画面でも眺めるように、無言で座る。
開始以降、そんな時間が続いている。
否。続いていた。
ふと、その嵐を切り裂いて、ひとつの影が僕の前で止まった。
慌てて焦点を合わせると、小柄な若い女性が、平置きされた僕の本のタイトルを食い入るように見つめていた。
「こ、こんにちは」
今しかない、と奮い立ち、どもりながらも声をかけた。しかし、女性は僕の言葉には反応せず、まだ本の表紙に目を向け続けている。
「よかったら、お手に取ってみてくださ…
い。
最後の一文字を言い切るかどうか、というタイミングで、女性は肩にかけた鞄に手を入れ、何かを取り出した。
黄色と黒の表紙の、スケッチブック。サイズは大学ノートぐらいか。そいつの表紙をめくり、あらかじめ書かれていた文言を僕に突き出す。
突然すみません。
私は耳が聞こえないため、筆談で失礼します。
これはどんな本ですか?
一瞬、反応ができなかった。
どうやって答えよう、という焦りと、どのように答えよう、という迷いが、二匹の龍のごとく脳内を暴れる。
とりあえず、メモ帳。売れた冊数を正の字で記録しようと用意し、しかし一本も線が引かれていない白紙の束を引っ掴み、ペンを取った。
取ったはいいが、どうする。何と答える。
短編集です。
WEBで公開したものから、いいと思うものを集めました。
メモ帳を見せる。女性は僕の書いた文字を数秒見つめた。そしてスケッチブックをめくり、カバンからペンを取り出す。また何か書きつけ、クイズ番組のフリップのように僕へ向けた。
ジャンルは何ですか?
ジャンル。ジャンルとは、純文学とかエンタメとか、そういうのか。
たまに目にするけど、よくわからない。僕のジャンルは何だろう。
わかりません。ただ、自分が良いと思ったものを書いています。
メモ帳を見せる。疑問符を浮かべたまま、目線を上げる女性。
またスケッチブックがこちらを向く。
どんなものを"良い"と思うのですか。
僕はペンを止めて、考える。
悩ましい。
これまで、こんな問答をしたことは無かった。作品を公開している創作サイトでは、こうした談義に花咲くコメント欄を見ることもある。しかし、僕に関しては、他の書き手との交流は皆無。そんな機会には恵まれたことがない。
そもそも、ネットに作品をアップしていること自体、僕としては思い切ったアクションだ。それまでは、ただ自分の中で湧き上がるものを、自分で消費するために書いていただけだった。しかし、出来上がったものは曲がりなりにも"作品"。自分以外の読者の存在を、どこかでひっそりと待ち続けていた。
長年の蓄積した孤独が臨界値を超えたのは、つい最近だ。読者を求め、僕は作品を世に解き放った。しかし、孤独は孤独のまま。広過ぎるネットの海で、作品に触れてくれる人はごく少数。新たなチャンネルを求めて参加したこの即売会でも、その孤独は継続している。
よく言えば、謙虚。悪く言えば、臆病。
そんな僕では届かぬ世界が、しかし、向こうからこうして問いかけてきている。
さぁ。僕は僕にけしかける。
何を答える。僕は世界に、何を伝える。
「基本的に、自分のことが嫌いなんですよね」
口にして、はっと気がつく。
急いでメモを取り、ペンを走らせた。
僕はあまり、自分のことが好きではありません。
驚くような取り柄も無いし、誰かの役に立てることも少ない。
ありきたりな言い方ですが、自分などこの世には必要がないのでは、と思うこともよくあります。
余白が埋まる。相手に見せて、次のページへ。
そんな僕なので、日々送る生活も味気なく、面白みのないものでした。
つまらない日常の中、「こうだったらいいのにな」と空想を広げることが、僕の唯一の楽しみでした。
そしていつしかそれを文章にして、形にするようになりました。
見せる。ページをめくる。次。
ずっと書いたものを、誰にも見せずに温めていました。
つまらない僕が書いたものだから、きっと他の人にとってもつまらないだろう。そう思っていました。
でも、もしかしたら、僕と同じように僕の書いたものを面白いと思ってくれる人がいるかもしれない、とも思っていました。
言葉が溢れてくる。顔が熱くなる。
書く時間がもどかしい。それでも、僕はペンを走らせる。
だって伝わらない。
こうして書かなきゃ、伝わらない。
僕が良いと思うものは、色々あります。
そのどれもが、僕が僕だからこそ見つけられたものであると信じています。
それを形にした作品が、誰かを喜ばせたり楽しませたりできたなら、こんなに嬉しいことはない。
つまらない僕が僕でいることを、そこで初めて肯定できる気がします。
ごめんなさい、言っている意味わかりますか?
メモの向こう、女性が頷く。
深くその表情を観察する余裕もなく、僕は続きを書く。
だからお願いします。一度読んでみてください。
あなたの時間を少しだけ、僕の作品に使ってください。
面白いかはわからない。はっきり言ってこれは賭けです。
でも、賭けて欲しい。
僕の言葉があなたに届くか。それを確かめるため。
チャンスをください。
「お願いします」
もはや手が追いつかず、声に出し、頭を下げた。
姿勢を戻すと、女性は虚を突かれたような顔をして、こちらを見ていた。ただジャンルを訊ねただけで、ここまでの熱量が返ってくるとは思っていなかったのだろう。僕自身、まるでその気はなかったのだから、当然だ。
手首の痛みを自覚し、メモをペンを置く。すると、またもや女性がスケッチブックに何かを書き始めた。
まだ質問が。満身創痍ながらも身構える。
女性のスケッチブックが裏返り、僕を向く。
おいくらですか?
テーブルの上を見る。値札を付け忘れているわけではない。『¥500』と油性マジックで書いたカードを指し示すが、しかし、女性は首を振る。
そのメモが欲しいの。おいくらですか?
スケッチブックを両手で持ち、可愛く揺らす。
何だそれ。
僕はこれまでに使用した分をまとめて千切り、女性の前に。
「……欲しければ、差し上げます」
女性はにっこり笑い、スケッチブックを鞄にしまう。そして今度は財布を取り出し、五百円玉をテーブルに置いて、積まれた本のうち一冊を手に取った。
メモと共に本を抱きしめ、お辞儀をして去っていく女性。
ふと見渡すと、周囲で何人かが立ち止まり、こちらの様子を眺めていたようだった。スケッチブックとメモ帳の応酬が物珍しかったのだろうか。しかし、その何人かも、また往来に紛れて消えていく。
僕は椅子に座り、息を吐いた。
そしてメモ帳に、正の字の一画目たる横棒を。
「ありがとうございました」を言い忘れていたことに気がついたので、その横に小さく書き加えておいた。
****************************************
この作品は、こちらの企画に自主練習として参加しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
