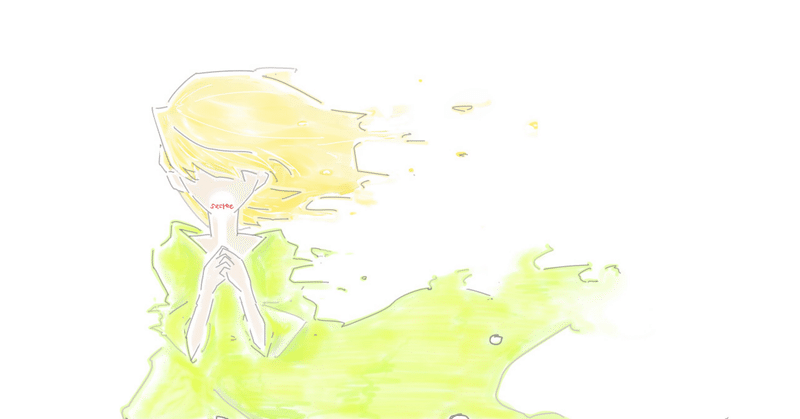
【掌編】チルアウト、三千世界。
十八歳。世界が散った。
誕生日には毎年、ケイちゃんのお母さんがプレゼントを送ってくれた。ケイちゃんは私が関西に住んでいた頃の友達で、と言ってもそれは三歳までの話であり、正直、私はその顔すら思い出せない。しかし母親同士が仲が良く、住む土地が離れてからも「ケイちゃんはブラスバンドを始めたらしい」だとか「ケイちゃんが中学受験に受かったらしい」だとか、数年おきにちょくちょく情報がアップデートされていた。その度私は脳内で顔が黒く塗りつぶされたマネキンに管楽器を持たせたり合格通知を受け取らせたりしながら、「はて。ケイちゃん」と首を捻る。親たち目線では私とケイちゃんは幼少の頃からの仲良しさんで今なおその友情は続いているのかもしれないが、いやその子私の中ではマネキンですけど、と温度差を感じずにはいられない。遠い地で暮らすケイちゃんもまた同じ思いでいるはずだろうが、その気持ちを分かち合う術も気力も動機もない。
そんな低温の私たちに対し、いまだ当時の熱冷めやらぬ親たちは、子の誕生日にプレゼントを送り合う。日付指定の宅配便で、伝票の品名欄に「衣類」と書かれたものが、私のところへ毎年届く。私へのプレゼントであるはずのところ、「お礼を言わなくてはいけないから」と必ずお母さんと開封の儀を行う。中身は伝票がネタバレした通り衣料品で、それはお母さんがいつも選んでくれるものより幾分ファッショナブルな代物であり、「わぁ、素敵。やっぱり中井さんはセンスがいいわぁ」と唸ったお母さんが「良かったわね」と私に確認してくる。うん、と私が頷くと「電話しなくちゃ」とそそくさとその場を離れ、別室でダイヤルをプッシュ。私はその声をドア越しに聞きながら、伝票を剥がして個人情報を消したり、服に巻かれていた白い薄紙を小さくまとめてゴミ箱に入れたり、襟元についたままのタグをハサミで切ったりする。ここまでが私と、そしておそらくケイちゃんのバースデーにおける定例行事となっていた。
中学の頃までは、私もこのプレゼントを楽しみにしていた。服のバリエーションが増えること、それが普段ない小洒落たテイストであることはありがたく、「ケイちゃんのお母さんの誕生日プレゼント」は私の重要な戦力となっていた。しかし高校に入ってからと言うもの、周囲の子たちのレベルが格段に上がり、やれどこぞのセレクトショップで買ったものだの、どこそこのブランドの新作だのを目にするようになってからは、ケイちゃんのお母さんの服すら世の女子高生にとっては二軍以下で、ちょっと近所に出かけるときに着用するあたりがギリセーフ、逆にうちのお母さんがたまに買ってくる無印良品のこざっぱりしたものの方がシンプル路線で勝負できる、との感性を身につけるようになった。
そんな調子であったため、毎年の開封の儀、「良かったわね」と私の反応を確かめるお母さんに対し「うん」と返す頷きが、ここ数年は重たいものとなっていた。かつての輝きを失ったケイちゃん母’sセレクトを前に、今や二軍なんだけれどなぁ、これはみんなの前では着ないなぁ、でも良かれと思って送ってくれているんだよなぁ、と感じながらも、わざわざこれを選んで送ってくれた労力、その背後にあるだろう「ケイの友達のためだから」という思いを想像し、申し訳ない気持ちで首を縦に振っていた。
そして十八歳。
私の誕生日は三月の後半で、既に私は高校を卒業し、来月からは大学生というタイミングだった。その日は平日だったが、学校も何もない私は家にいて、逆にお母さんは知り合いと出かけており、宅配便を受け取ったのは私だった。伝票にある住所と名前、品名欄の「衣類」の記載から、ケイちゃんのお母さんからだとわかった。
毎年お母さんと開封の儀を行うけれど、そもそも私へのプレゼントなのだから、私一人で開けてしまおうと思った。厚手の紙袋、貼られたテープをカッターで薄く切り、開いた口に手を入れて中身を引っ張り出す。包装紙のぱりぱりした手触りと、指先にかかる布の重み。包みを開くと、折り畳まれた薄手のカットソーが顔を出した。
あぁ、と落胆が生まれる。
基本無地のクリーム色のそれには、襟元にポイントとして草花を模した刺繍が施されていた。惜しい。むしろ完璧な無地なら着回しの効くインナーとして使えたものの、この刺繍があるせいで、そのようには使えない。むしろアウターをシンプルに、刺繍の意匠が映えるようにするしか選択肢がなく、それではダサさが増してしまう。上半身のメインに据えるポイントが草花って。森の精じゃないんだから。
ごめん、ケイちゃんのお母さん。今回の服も二軍行きだ。今いる我が家から半径一キロ圏内でしか、この服は着ない。
幼い頃の私、お母さんから寄せられる情報、そこから生まれるモンタージュを頼りに「これが似合うかな」「あっちの方が気に入るかな」とデパートをウロウロしてくれたのだろう。お手間を取らせて申し訳ない。しかもこんな凝った刺繍。さぞお高かったことでしょう。
でも着ない。着れない。どうか不義理をお許しください。
そう思い、服を広げた時だった。
折り畳まれて見えなかった布の内側、そこに貼り付いていた紙片が、はらりと舞って床に落ちた。
拾う。拾う前から予感がする。落ちる瞬間、視界にちらりと映ったそれが何であるかを、無意識がキャッチしている。
予感は当たった。
薄い赤、その上に打ち込まれた "SALE" の文字。
文字の下に並ぶ、生々しい値段表示。
十八年間、見つめ続けていた世界のメッキが剥がれる。
毎年のプレゼント。ケイちゃんとの友情が今なお続いているという母親たちの幻想。おめでたい大人たちに、辟易しながらの開封の儀。僅かながらの自責の念。
剥がれる。散る。散り落ちる。
裏切りなら経験してきた。騙し討ちなら食らってきた。その度怒り、悲しんできた。
今回は違う。感情が振れる前に、意識が変わる。転換する。
もちろんこのSALEの値札が、この服についていたものとは限らない。同じタイミングでレジで会計をしたものについていた、とか、何かの拍子で紛れ込んだ、とか。
だけど関係ない。そういう可能性がある。それ知った今の私は、もう今までのように世界を見られない。纏わりついた塗装の奥を想像し、最悪のケースを想定し。疑心暗鬼に歪んだレンズ越し、ピントを合わせるような物の見方しかできない。
そうしないと、生きていけない。
そういう身体になった。頭になった。
私になった。
紙袋のラベルを剥がし、住所氏名が判別できぬよう細切れに破る。包装紙の上にそれを載せ、ハサミで切ったタグも載せ、丸めてゴミ箱へ。紙袋はリサイクルに出せるよう、折り畳んで台所にあるストッカーに。例年通りの作業。
お母さんが帰ってきたら、ケイちゃんのお母さんからプレゼントが来たと報告し、この刺繍のカットソーを御披露目する。素敵ね、の声に頷く。これも例年通り。
だけど今年は、今回は。電話をかけようとするお母さんを引き留め、言う。
プレゼントは今年まででいい。
もう大学生になるのだから。
今までありがとうと伝えておいて。
なんなら私が直接伝える。
お母さんはきっと、安心した顔をする。今の私にはその未来が見える。
作業中、ポケットに入れていたSALEの値札を取り出す。家のゴミ箱には捨てられない。どこか外で。私は部屋着を脱いで、軽装に着替える。
もらったばかりの刺繍のカットソーは、もちろん選ばない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
