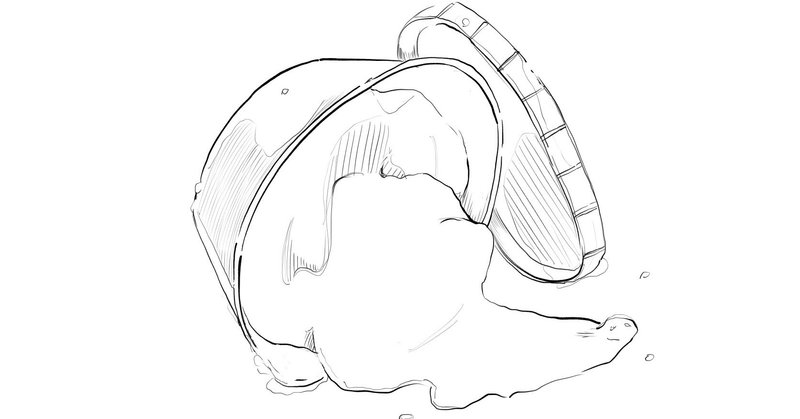
【掌編】形容動詞はまだ早い
中学一年の頃、急に学校へ行けなくなってしまった。
特にいじめに遭っていたわけでも、人間関係にトラブルを抱えていたわけでもない。何がきっかけかはわからないが、突然に、同級生のひそひそ話や、担任教師の叱り声、果てはチャイムの音までもが耳につき、終いには吐き気を催すようになった。制服に着替え、登校しようとすると、アラートが鳴るようにお腹が痛くなる。無理矢理外に出て、横断歩道の真ん中でふらつき倒れ、顎を三針縫う怪我をした。そこで初めて親も本気になり、その日から学校は「がんばっていく場所」から「無理して行ってはいけない場所」になった。
どうしてこうなったのか、方々から訊ねられたが、「わからない」としか答えようがなかった。いくつかの病院を点々としたが、納得のいく答えは得られず、何に効くのかよくわからない薬を出されて終わるだけだった。
共通して言われたことは、「とりあえず無理をせず、ゆっくりと休むこと」だった。その言いつけを愚直に守ることしかできず、一日の大半を自分の部屋で過ごし、ドアの外へ出るのはトイレとお風呂、あとは食事のときぐらいだった。調子が悪いときは、ご飯も自分の部屋で食べた。
何日も家の外に出ない日が続いた。ろくに話をしないので、時折母親に何か伝えるとき、声が掠れてうまく出せないことがあった。動かないので太ってしまうかと思ったが、逆に体重は日に日に減っていき、自分でもわかるほど腕や脚が細くなった。
カワサキさんが来たのは、私が学校へ行けなくなって四ヶ月かそこらが経った頃だった。当時はよくわからなかったが、民間の非営利団体に所属し、私のような不登校の生徒のサポートをする仕事をしている人だった。
親がその人を呼んだというので、最初は学校へ行けない私に、勉強を教えてくれる人なのかとも思った。だけど現れたカワサキさんは想像より若い女性で、黒髪を後ろでまとめ、服も白シャツにデニムというこざっぱりした出で立ちだった。近所のお姉さんがふらりと遊びにきたような雰囲気で、勉強道具はおろか、手ぶらで私の部屋にやって来た。
「小雪ちゃんは、漫画読む?」
自己紹介もそこそこに、カワサキさんは訊ねてきた。そこまでたくさん読むわけじゃないけれど、買い集めていたものはある。「どれ」と問われるので、本棚にあるいくつかのタイトルを紹介した。
ふうん、とカワサキさんは言って、翌週、今度はキャリーケースをごろごろと転がしてやってきた。
「小雪ちゃんが好きそうなやつ、いくつか持って来た」
キャリーケースには、コミックスがびっしりと詰まっていた。どれも昔の絵柄で、聞いたことのあるタイトルもいくつかあった。
「読んでみたいの、ある?」
正直どれにも食指が動かず黙りこくっていると、「じゃあ、これ」と十冊足らずを重ねて渡された。『赤ちゃんと僕』と背表紙に書かれていた。
「つまらなかったら、途中で辞めていい」
渡されたそれは、ネットで見てみると、名作と名高い少女漫画だった。
カワサキさんが帰ってから、一話、二話と読み進めたが、ほどなくして頭が痛くなってきてしまった。一ページ、一コマ、一セリフごとに、これはどういう意味だろう、なにを思ってこんなことを言うんだろう、と考えが生まれ、たちまち頭の中がいっぱいになってしまう。これ以上進めると、脳の回路がショートしてしまう気がした。
次にカワサキさんが来たとき、正直にそれを話した。ちょっとしか読めてない、と打ち明けたときはショックな顔をしたカワサキさんだったけど、理由を説明すると、ふむふむ、と真顔になって頷いた。
「小雪ちゃんは多分、考えすぎちゃう病だね」
曰く、色々なことがいちいち気になって仕方がない、頭のリモコンの感度がよすぎて、わずか爪先がボタンに触れただけなのにたちまち反応してしまう、そんな状態だと言う。
「大丈夫。絶対に『赤ちゃんと僕』が読めるようになるから」
まるでそこが最終到達点であるように、カワサキさんは言った。
そこから、カワサキさんとは色んな話をするようになった。ただ、その会話の中身が少し変わっていた。
「小雪ちゃん、これは何」とカワサキさんが部屋にあるものを指さす。文房具など、なんの変哲もない、ありふれたアイテムだ。「シャープペンシルです」、私が答えると、「ありがとう。芯は何ミリ?」と次の質問が来る。「0.5ミリです」、「ありがとう。濃さは?」、「HBです」。そんな具合に、英語の教科書で出てくる会話文みたいな一問一答が続いていく。
最初はからかわれているのかと思ったけれど、何故かそのやりとりは私にとって心地よく、安心できるものだった。「最近好きなものは」だの「何々についてどう思う」だのと訊ねられるより、答えが明瞭で答えやすい。意味のない会話ではあるものの、会話をしているという事実に、張り詰めていた気が解れていくように感じた。
「外へ出よう」
何日か経って、カワサキさんが言った。
「コンビニに、アイスを買いに行こう」
また気持ち悪くなるのではないか、と正直気が進まなかったけれど、日中だし、知った顔に会うこともないだろうこと、コンビニは学校とは反対方向にあることから、思い切って行ってみることにした。
「気をつけてね」
カワサキさんと玄関で靴を履くとき、母親が心配げな顔で見送ってきた。それはそうだ、それまでずっと部屋にいた私が、急に外へ出ようとしているのだから、不安になるのは当然だ。そう思うと、同じく私の胸にも不安が広がってきた。
玄関を出ると、昼間の明かりが瞳に刺さり、思わず目蓋を閉じてしまうほどの痛みを感じた。なんとか目を馴染ませ、歩みを進める。家の門までの短いスロープが、途方もない距離に感じられた。
「コンビニは、どっち?」
ようやく門を出ると、カワサキさんが訊いてきた。
「左です」
「ありがとう」
いつぶりだろうか。外の匂いを吸って、吐いて。カワサキさんと私はコンビニへ向かった。
勢いに任せて決行した外出は、予想はしていたがやはり苦しいものだった。家から離れていく度、足が重くなり、血の気が引いていくのがわかる。知らず、カワサキさんの服の裾をつかみながら歩いていた。
「コンビニまでは、どれくらい時間がかかる?」
「五分ほどです」
「ありがとう。あの横断歩道は、渡る?」
「渡ります」
「ありがとう」
いつも部屋でしていたような一問一答を、この時もカワサキさんは続けていた。側から見ればやや滑稽にも映るだろうが、答えている間は余計なことを考えずに済むので、ありがたかった。
コンビニには、本当に五分で着いたのだろうか。間違えて回り道をしたのではと思うほど、長い道程に感じられた。自動ドアを跨ぐと店内の冷房が肌を刺し、私を追い返そうとしているようにも思えた。
「小雪ちゃん、着いたね」
「はい」
「アイス売り場はどこかな」
「多分、あそこ」
指をさした方に二人で歩くと、アイスが陳列されたケースがそこにあった。カップアイス、袋詰めの棒アイス、モナカタイプの四角いアイス、よりどりみどりの選択肢が、冷気を纏いながら並んでいた。
「じゃあ、小雪ちゃん」カワサキさんが言った。「アイスを選ぼうか」
結論から言うと、私はアイスを自分で選べなかった。
棚の端から端まで、全種のアイスにひとつずつ目を向け、吟味した。どんな味だろうか、食べ切れるだろうか、帰るまでに溶けはしないだろうか。
どれぐらい時間がかかったかわからないけれど、結局どのアイスも食べる気がしなくなり、私はカワサキさんに「選べません」と言った。
「そっか」
カワサキさんは頷いて、「バニラは食べられる?」と私に訊いた。私が頷くと、バニラのカップアイスを二つ、ケースから取って、レジに行ってそれを買った。
アイスが入ったビニール袋をぶら下げながら、私たち二人は元来た道を戻った。帰り道の途中も、カワサキさんは私に話しかけるのを止めなかった。
「空が晴れているね」
「はい」
「電柱があるね」
「はい」
「前から犬を連れたおばさんが来るね」
「はい」
行きとは違い、カワサキさんの言う当たり前のことに、私はただ頷くだけだった。けれど、それすらも次第にできなくなり、私は途中で歩みを止めて、泣き出してしまった。
「いいよ、いいよ、小雪ちゃん」
カワサキさんが肩を抱いてさすってくれる。その暖かさが、一層涙を誘い、嗚咽が止まらなくなった。過ぎゆく人が怪訝な顔でこちらを見るのがわかったけれど、取り繕う余裕もなかった。
「がんばった。小雪ちゃんはがんばった」
カワサキさんは私を何度も励ましながら、少しずつ、少しずつ、家までの道のりを導いてくれた。時間がかかりすぎて、帰り着く頃にはアイスは溶けてしまっていた。
私が泣きはらした目で帰って来たからだろう、母親はカワサキさんを押し除ける勢いで駆け寄り、私の両肩を掴んで「大丈夫」「怪我はしていない」「気分はどう」としつこく確認をしてきた。そして私一人を部屋へと帰し、カワサキさんには残るように言った。カワサキさんを見る母親の目に、怒りが滲んでいるのがわかった。
案の定、カワサキさんは今後私の家に来ないことになった。その日の夕食の場で、それを母親から聞かされた。来週一度だけ、お別れの挨拶に来ると言う。それも、私が嫌と言うならば、断ってもよい、という話だった。
カワサキさんには申し訳ないが、来なくなるというのならそれはそれで構わない気がした。元の、自分の部屋に閉じこもる生活に戻るだけだと思った。
ただ、何故だかその日カワサキさんが買ったアイスのことが気になった。溶けてしまった二つのカップアイスを、カワサキさんはどうしただろうか。うちに捨てていくわけにもいかなかっただろう。コンビニのビニール袋に入れて、そのまま持って帰ったのかと思うと、申し訳ない気持ちになった。
翌週、カワサキさんが挨拶にやって来た。最初は母親とリビングで話し、その間、私は自分の部屋でそれを待った。思ったより時間がかかり、カワサキさんが私の部屋に来るまで、十分ぐらいかかった。
カワサキさんはいつもと同じ、ラフな服装だった。「小雪ちゃん」と呼びかけ、「この間は、無理をさせてごめんなさい」と謝ってきた。「大丈夫です」と私は答えた。逆にアイスのことを謝りたかったけれど、カワサキさんはすぐに言葉を続けた。
「小雪ちゃんは、前にお話したけれど、考えすぎちゃう病だと思うの」
そう言えば、以前そんなことを言われた、と思い出した。
「だからね、小雪ちゃんがもし、また考えすぎちゃった時のために、呪文を考えてきた」
「呪文?」
「うん。おまじないみたいなもの」
おまじない。少し子供扱いされているようで、気恥ずかしかったけれど、黙ってそれを聞くことにした。
「『私の名前は』。考えすぎちゃった時は、こう自分に問いかけてみて」
「……名前?」
「そう。で、心の中で答えるの、『篠原小雪です』って」
何を言っているんだろう、と思うと同時に、少し合点がいく部分もあった。
いつもカワサキさんが私に投げかけてくれていた、「当たり前な質問」シリーズのひとつだ。
「それでも落ち着かない時は、なんでもいい。『今日は、何曜日』でも、『ここはどこ』でも、『天気はどう』でも。自分が答えられる、簡単な質問を思い浮かべてみて。そして、それに心の中で答えていくの」
駄目な質問は。カワサキさんはじっと私を見て、続けた。
「駄目な質問は、答えを考えちゃう質問。『どれが好き』とか、『どんな気分』、とか『どう思う』とかは、まだ早い。小雪ちゃんの考え方、感じ方次第で答えが変わる質問は、避けておきましょう」
わかったかしら。カワサキさんの問いに、私は「はい」と答えた。
私の返答に頷いて、カワサキさんは「じゃあ、元気でね」と立ち去ろうとした。何かを焦っているようにも見えた。その背を私は慌てて呼び止めた。
「あの、これ」
私はカワサキさんに紙袋を差し出した。その日、忘れずに渡そうと思って用意していたものだった。
カワサキさんから借りた、『赤ちゃんと僕』だ。
「あぁ」顔を綻ばせ、カワサキさんは首を振った。「それは、小雪ちゃんにあげる」
「え、でも……」
「いつか、読んでみて。絶対に面白いから」
要らない、と突き返すことも、ありがとう、と礼を言うこともできず、ただあたふたとするしかできなかった。カワサキさんは微笑んで、「また会いましょう」と部屋を去った。
後で知った話だが、この時カワサキさんは、私との面会時間を制限されていたらしかった。当初、挨拶には母親も同席するつもりだったようだが、カワサキさんがそれを拒んだためだと言う。二人きりにする代わりに、数分だけ、という条件を母親から提示されていたようだった。
そうとは知らず、あっけない別れに茫然としながら、私はその場でカワサキさんを見送った。腕に持ったままの紙袋は、それなりに重みがあるはずなのに、ふわふわと浮いているように感じた。
私が『赤ちゃんと僕』を読めるようになったのは、高校生になった頃だった。
カワサキさんの言う「考えすぎちゃう病」は発症から一年足らずで治まりを見せ始め、中学三年の時には普通に学校へ通えるぐらいにまで、私の心は回復していた。
カワサキさんが教えてくれた呪文は、あまり使うことがなかった。なんとなくだけれど、軽々しく多用してはいけないもののように感じた。本当に辛いときに幾度か唱えてはみたものの、正直この呪文自体に、どれほどの効果があるのか、よくわからなかった。ただ、何かしら辛くなった時の拠り所があるというのはありがたく、そういう意味では、「おまじない」というより「お守り」として、それは大いに私の役に立ってくれた。
『赤ちゃんと僕』は全十八巻で、カワサキさんがくれたものは途中までだった。ちょうど豪華版だか愛蔵版だかが出揃った頃で、私はそちらで一からコミックスを揃えなおした。
カワサキさんにもらった分は不要になったが、捨てることも売ることもなんとなく憚られた。意を決した私は、カワサキさんにそれを返しに行くことにした。
リビングの、母親が通帳や保険証書などを収めている戸棚をこっそり漁ると、カワサキさんが所属していたと思われる非営利団体との契約書が出てきた。捨てられていたらどうしようか、と思ったけれど、母親の性格上、きっと保管しているものと踏んでいた。
電話番号をメモして、自室で携帯から電話をかけた。コール音が続く。その団体が存続しているかどうかは賭けだったが、ほどなくして電話が繋がった。
「はい、『ブランケット』です」
団体名を名乗ったその声は、初老を思わせる男性のものだった。
「あの……」
どう説明したものか。私はまず名を名乗り、数年前にカワサキさんにお世話になったことを伝えた。当時お借りしたものがあるので、遅くなったが返しに行きたい、と続ける。すると相手の男性は「あぁ」と間延びした声を発し、少し間を空けた後に、答えた。
「すみません。カワサキですけどね、随分前に退職しておりまして」
「え?」
タイショク、という言葉がうまく頭に入って来なかった。
「辞めてしまった、ということですか」
「ええ、まぁ」
「あの、いつでしょうか」
「えーっと、いつだあれは。少なくとも一年以上は経ってますかね」
「今は、どちらにいらっしゃるんですか」
「いやぁ、それは……」
「お借りしているものがあるんです。お住まいか、連絡先を教えてはいただけませんでしょうか」
「えっと、そういったことは、教えられないようになっているんです。すみません」
それはそうか。しかし、このまま引き下がる気にもなれない。
「じゃあ、そちらからカワサキさんに取り次いでいただくことは可能ですか。私のご連絡先をお伝えするので」
「なるほど。うーん」男性は言い淀み、「実はですね」と意を決したように切り出した。
「実は我々も、カワサキとは連絡がとれない状態にありまして。その……そういう退職の仕方をした、というか。ある日突然、いなくなりましてね」
「え……?」
「あぁ、いや、失踪とかじゃないんですが。急に来なくなったと思ったら、後日郵送で辞表が届きまして。こちらも手続や引継ぎなどありますから、連絡をとろうとしたんですが、電話も繋がらないし、家を訪ねても引越ししている。もう弱りましたよ、あれは」
半ば独り言に近いトーンで、男性は言葉を吐き出す。私はそれを黙って聞いた。
失踪ではないと言うが、ほぼそれに近い有り様だと思った。あのカワサキさんが、と思うと、どうにも現実感が湧かない。
思いも寄らぬ展開に、どう手を打ったものか、考えを巡らすが、こればかりはどうしようもなかった。
「あなた、篠原さんですよね」
「え、あ、はい」
覚えていますよ。男性は言う。
「確か、あなたを強引に外へ連れ出してパニックにさせてしまった。あなたのお母様にも、大変なお叱りを受けました。当時のこと、私からもあらためてお詫びします。大変な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした」
「いえ、そんな……」
「実は、あなただけではないんです。同じようなトラブルを、方々で起こしていましてね。それでも熱意はあるものだから、我々も、基本的には応援する気持ちで見守っていたんです。だけど彼女の中でも、忸怩たるものがあったんでしょう。それが積み重なり、結局、こういうことになってしまった」
いや、すみません。と男性は言葉を切る。
「こんなこと、お話をするべきではないんでしょうが、つい。初めてなんですよ、カワサキが担当した方から、また会いたいと連絡が来るのは」
申し訳ない、と男性にまた謝られ、諦めた私は電話を切った。
それから数年が経った今も、私はカワサキさんに『赤ちゃんと僕』を返せずにいる。元々もらったものであるため、不要ならば捨ててしまってもよいのだろうが、いつか返せる機会があるのでは、と思い、今も物置の片隅に眠らせている。
カワサキさんの呪文を使うことは、まるでなくなった。
大人になり、あれは余計なことを考えないためのメソッドなのだと気がついた。名前や日時、場所には答えがある。だが、「どんな」、「どう」との問に呼応するような、いわゆる形容詞や形容動詞に類する言葉には、主観が混じる。
主観は駄目だ。考えてしまう。当時の、カワサキさんの言う「考えすぎちゃう病」の私には、天敵とも言える問いかけだ。きっと、それらを私から遠ざけるために、カワサキさんは当たり前な問いを投げかけ続けてくれていたのだろう。
もしこの文章を読んだ方で、カワサキさんに心当たりのある方がいらっしゃったら、お願いしたい。
私が預かった漫画を返したがっていること。それを返すことを口実に、あなたに会いたがっていること。会って、御礼を言いたがっていること。
どうかそれを伝えて欲しい。
もしそれが叶わないほど、カワサキさんの心が凍てついているのならば。
彼女が私に教えてくれた、あの呪文を投げかけてみて欲しい。
あなたの名前は。今いる場所は。
あの日溶かしてしまったアイスを片手に、今度は私が駆けつけよう。
好きな味がわからないから、とりあえずバニラを二つ用意していく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
