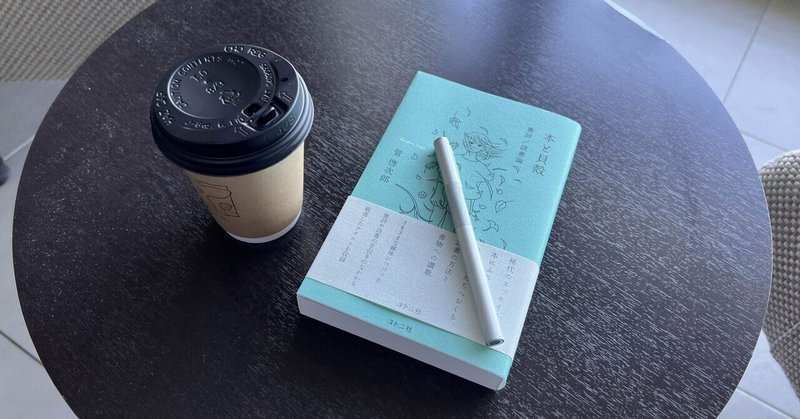
感想→菅圭次郎『本と貝殻』
那覇から東京に向かう飛行機で一気に読んでしまった。
すべて通読したというよりは、気になった部分をつまみ食いしたような形だが。
この本は彼の書評や読書論についてまとめられた本だ。故に書評の書き方も勉強になるし、読書の方法論みたいなものも雄弁である。
文字数にして1000文字ほど。だが、その1000文字は魅力的で、本を読んでみたいという気持ちにさせる。
最初の一言目が強いのだろうか。私だったら本のタイトル、著者について順接で語ってしまいそうだが、彼の言葉は違う場所から引っ張られてきたり、意外なところを頭に持ってきたりしている。ほとんど本そのものがただただ説明されることはない。
その本の中で語られたことが、自分の知的関心と混ぜられて表現されている。本書のあとがきで書評を書く行為を「いけばな」に例えている。以下引用。
> 本という素材の一部を切り取り、それを新しいアレンジメントに投げ込む。組み合わされた配置された花たち(=引用文)は、もともと持っていた生命の連関の名残により、新たにつむがれた文の中でも新しく輝く。 p312
彼は書評の中で直接の引用をしない。これは情報カード的な、いやむしろZettelkastenの思想にも合致する気がする。
本の冒頭、この本を読む時の指針が明示された。
それは開いたページを気まぐれに読むこと。
彼は適当に開いた新しい本の1ページを毎日の占い的に取り入れて、その中の言葉について反芻する。
読書論の中で強調されるのが、本を手に取った時点でそこには何かがあり、なんとなく開いた1ページはあまりにも豊かだということ。
本をただ情報を受け取るものとしてではなく、自分の内側の何かを触発するものとして描いている。
具体的に言えば本を読んで、直接の引用を羅列することは論文的な意味はあっても、読書という行為においては少し意味が異なるのだ。
本は1冊の本から50文字くらい面白い箇所が見つかればよい。
私が考えるに、その本の中から興味をそそられる本を派生させることができる。その派生された本の中から、新たな本が出てきて、また派生する。
これがある種のセマンティックツリーであり、構造的で誤りのない解説を毎回求められているわけではないのである。
もちろん、原著を蔑ろにしたものであってはいけないが、自分の中から感応したものを合わせて言葉にしていく。
なので、もう少し自由に文章を書いても良いのでないだろうかと思い、今回のnoteを書いた。
コーヒーを一杯プレゼントする☕️
