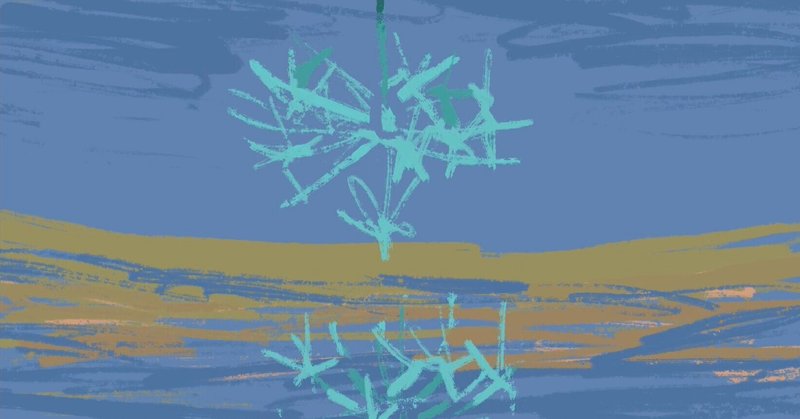
Turquoise Blue
たった今、会社を辞めてきた。
新卒から働いた職場ではあったが、未練はさほど感じなかった。
「結婚おめでとう。ねー、どのマッチングアプリ使ったの?」
餞別にこんなことを言われるくらいなのだから、寂しさなど湧くはずもない。しょせん貯金のためだけに勤めた会社だった。内定した企業のうち、一番平凡な空気感が漂うこの職場に落ち着いたのが三年前の話だ。
花束を片手に帰路を急ぐ。すれ違うバイクがスモークを運ぶ。この道を歩くのも最後になることはわかっていたが、感傷に浸る余裕などなかった。住所変更。退去時の手続き。すべきことは山ほどあるのに、昨日押入れで見つけた一枚の絵が頭から離れない。アパートの踊り場に燻る、夏の残り香。錆びついた階段を一足跳びで上り、鍵を開ける。広さと虚しさを取り戻した部屋の、一番奥に積まれた段ボール箱。その上にはらりと、八つ切りの画用紙が乗っている。
吸い寄せられるようにそれを手にとった。高二で描いた水彩画。夜空をバックに線香花火が鋭く煌めく。両サイドに描かれているのは、淡いターコイズブルーのシャツの二人。私と、当時付き合っていた彼だ。美術部の文化祭展示用に描いたものだったから、展示を見に来たクラスメイトに随分と冷やかされたものだ。花火のオレンジに溶け合う水色は、青春の代名詞と言わんばかりに私に微笑みかける。私イタいことしてんじゃん、と馬鹿にするのが精一杯だ。
構図、骨格、取り合わせ。わざと声に出しながら、絵にダメ出しを重ねる。高校時代の自惚れを咎めるように、美大で学んだことは無駄じゃなかったんだと確かめるように。高校推薦で合格したはずの大学の授業に、私は全くついて行けなかった。壊れたイーゼルの下に置かれていた私の作品には、個性も輝きも見てとれなかった。何を模写しても形にならなかった。今見ているこの絵だって、どんなに欠点を直しても、個性を勝ち取ることができないどころか、元々持っている初々しさや迫力まで奪ってしまうような気がした。
何が足りなかったのかはわからない。それを考えることを諦めてからすでに三年が過ぎていた。さっきまで灰色に霞むだけだった都心の空は日が落ちて暗くなり、往来する車のテールライトが、すりガラス越しに明々と光っていた。我に返ってスマホを開くと、雄介からのLINEが大量に届いている。ほとんどは明日の引っ越しについての用件だったが、最後に「好きだよ」と添えるのを忘れないところが彼らしい。一通り目を通した後、夕食の買い出しに外へ出た。繁華街のネオン。流行りのJ―POP。ノースリーブのカップル。水溜りに映るファミマの看板も、ビビッドな色合いで気持ちがいい。買い物を済ませても家に帰る気にはなれず、ほろ酔いの空気感に同化しようと試みた。
レジ袋を持ったままコンビニの前をうろついていると、三角巾姿でこちらに近寄ってくる若い男性が目に留まった。
「あの、烏屋という居酒屋の者なのですが、今ハイボール一杯百円クーポンを配布しておりまして、よければいかがですか?」
少し考えて、私は答えた。
「お店まで案内して頂けますか?」
一人で居酒屋のカウンター席に座るのは初めてだった。この時間にも関わらず客足が悪いせいか、あるいは注文に手間取る私を気遣ってか、先程の男性が時々私の元に来て、世間話をしては去っていった。
「僕、美大生なんですよ実は」
ハイボールと焼き鳥を差し出しながら彼は言った。誇らしげなその口調が少し可笑しかった。
「学科はどこなんですか?」
「デザインです。ロゴとかレタリングの方に興味があって」
「なるほど」
会話が途切れる。じゃあまたお客さん呼んできますね、とクーボンの束を探し始めた彼を、思わず「あの、」と呼び止めた。
「実は私も美大卒なんです」
「マジっすか?! いいっすね! 学科とかお聞きしちゃってもいいですか?」
突然のハイテンションに困惑しつつ「油画です」と答えると、「あーいいっすね! 超エリートじゃないですか」ときた。何を言ってもいいっすねとしか答えないのだろうとは思ったが、「まあ油彩が好きなわけじゃなかったんですけどね」と独り言のように続けた。
「まー、あそこは油画って言ってますけど、いわゆるなんでも学科ですからね。お客様は何にご興味があったんですか?」
「水彩です。あとデジタルイラストも少し」
「いいっすねぇ……今でも絵に関するお仕事とかされてるんですか?」
「いえ全然。もう卒業してから一枚も描いてないレベルです」
吐き捨てるように言ってしまってから胸がきしりと痛む。あの絵の中の線香花火が、きりりと脳みそを突き刺す。後悔していないはずの三年間の平凡な日常を、人生からむしり取りたい衝動に駆られる。きっと酔いが回ったのだろう。痛みを誤魔化すように「あ、でも、今描きたいなって思うものはあって」と付け足した。
「おっいいっすねー。社会人一発目、何を描きましょう?」
暇なのか、さっきからこの店員はずっと私の話に付き合ってくれている。
「線香花火です」
「うおおおアガりますねー、何色のやつですか?」
(……何色?)
流れで返事をしようとして返答に窮した。何色って……オレンジと黄色の混ざった色。あの独特な奥行きのある、不思議な色。それ以外に、何色があるというのだろう。ブロンド、アプリコット。どれもしっくりこない。そもそも線香花火に対して、「何色ですか」という質問が成り立つ場面なんて思いつかなかった。打ち上げ花火と間違えているのだろうと推測して、苦し紛れに口を開く。
「うーん、私は赤い花火が好きなんで、真っ赤な大きいやつとかどうでしょう。打ち上げられてるのを下から見る感じで」
「え? さっき線香花火って言ってましたよね?」
あてが外れたようだ。思わず黙り込む私をフォローするように、
「いや僕、個人的に線香花火の方が好きなんですよね。なんか自分の手に負える感じがして。すみません」
と彼が頭をかく。照れたように笑う顔。シャープな顎のラインが、笑うと少し膨らむ感じ。心なしか、絵の中の元彼に似ている、ような気もする。
「水色とか、どうでしょう」
思いがけない言葉が口をついて出た。まるで私の声ではないかのようだった。戸惑う頭の中に、闇に浮かぶ水色の線香花火の姿が現れる。記憶から甦ったかのように鮮やかな、ターコイズブルーの蛍光色。曖昧なニュアンスを足した色使い。普通の線香花火よりももっと、もっと柔らかな、線の細いタッチ。
「うおおおおおいいっすね!!!! マジで見てみたいっす水色の線香花火。っていうかそれ先例ないんじゃないですか、めっちゃ興奮しますね」
これまでで最大の「いいっすね」に思わず顔が綻ぶ。未知のものを生み出そうとする胸の高鳴り。大学時代にも経験したことのない心のざわめき。早く形にしたい。今なら、形にできる気がする。
鳴り出したLINEの通知音を無視して席を立った。会計をお願いします、という言葉の代わりに彼に目配せをする。レジを打つ度に収縮する筋肉、しなやかな手首の動き。この腕で、昼間はデザインを描いている。そのありふれた事実が、今日はやけに興味深い。
帰宅してすぐにiPadを起動した。学生の頃に使っていたイラスト用ソフトを再インストールする。仕様変更を知らなかったことに軽い落胆を覚えながら、徐々に勘を取り戻していく。線香花火は、どの角度から描くのが一番映えるのだろう。ネットで参考写真を探す。何度も描き直す。背景は藍色がいい。下絵を飛ばして色を直接乗せてみたり、線を引き込んだ後から、ブラシで強弱と奥行きを出したり。ターコイズの炎にブロンドの光を乗せるとき、思い出にチョクで触れている気がして脈が速くなる。高校二年の夏。美大に行けば、線香花火のようにきらきらした世界が見えると信じ込んでいた、愛おしいまでの全能感。半袖の制服で、一番細い筆で、震えながら画用紙に色をのせた、あの感覚をなぞっていく。引越し前のがらんとしたワンルームをアトリエに、私はひたすら描き続けた。
絵が完成した頃には夜の十一時をまわっていた。部屋の電気を全て消すと、ブルーライトの中に、まるで宝石のように輝く水色の線香花火が浮かんでいる。満ち足りた気分だった。長い間探し求めていたものが見つかったような安心感につつまれていると、静けさを破るようにスマホの着信音が鳴った。
「涼香? 大丈夫?」
雄介からだった。居酒屋で何度か響いたLINEの通知音を思い出す。
「ごめん大丈夫よ、さっきまで寝てて」
嘘をついた。
「引っ越し業者の方が、結局十五時回んないと来れないって言ってて。僕その間住民票移しに行ってると思うから、涼香対応お願いしてもらっていいかな?」
そうか、明日は引っ越しか。都心のアパートから、郊外の一軒家へ。雄介との同棲にも実感は沸かず、ふわふわした頭で「分かったー」と返すのが精一杯だった。
「なんか、僕楽しみすぎて最近あんま眠れてなくてさ」
「そうなの?」
「そうだよ。だって涼香とやっと一緒に暮らせるわけじゃん? それだけで一生の幸せ」
私はなんて幸せ者なのだろう。心から愛してくれる人。何不自由のない人生。
「私も」
「へへ、なんか照れるなぁ。……とりあえずお仕事三年間、お疲れさま」
「そんな頑張ってないけどね」
「続けただけ偉いよー。じゃあ明日待ってるね。今日は疲れてるだろうししっかり寝て」
「ありがとう」
私には勿体ないくらいの夫だ。そういえば彼には、絵の話をしたことがない。もしかしたら今後も、することはないのかもしれない。
電気をつけて、iPadの画面をじっと見つめた。脇に高校時代の絵を置いて見比べてみる。大学で得た知識や技術は取り入れられているが、結局大きなところは何も変わっていない、そんな気もする。けれどもう、そんなことはどうでもよくなっていた。穏やかな雄介の声が私をそうさせたのかも分からなかった。ターコイズブルーの線香花火。大学のアトリエの片隅ではどうしても届かなかった表現が、今、目の前にある。でも、それだけだ。線香花火の煌めきとはほど遠い感情を、私は静かに受け入れた。胸のすくような静寂。それは大学卒業時の絶望に似た諦めとはとても似つかない、夜空のように果てしない諦観だった。不思議と悪い気はしなかった。
iPadのゴミ箱ボタンをタップした。「このデータを削除してもよろしいですか?」に躊躇なく「はい」を選ぶ。八つ切りの画用紙は無造作にまるめ、ゴミ袋に入れた。改めて部屋を見渡す。何もないなぁ、と自然に笑みが溢れる。少し埃っぽい部屋の空気さえも愛おしかった。
もう絵は描かないだろうな、と呟いて再度電気を消す。夜闇の中、私は眠りについた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
