
第171回芥川賞予想してみた。
え~、ご無沙汰しています。(古畑任三郎オープニング風)
お昼に再放送、Tverでも配信している「古畑任三郎」、やっぱ面白いっすね。こういうドラマに今世で出会えるのかしら、と心配になるね。
前回、noteを更新したのが22年の10月。この2年弱の間に、地方に移住して、なぜか稲刈りや果樹園で仕事をしてみたり、人生初の救急車搬送されたと思ったらまた関東でサラリーマンを再開したりしていました。こうやって列挙しただけでもいろいろあるな、私。ということで、久々に第171回芥川賞の候補作を全作読めたので、予想をしてみたいと思います。
毎回そうなのですが、どの作品も読みごたえがありました。候補作発表から楽しく過ごせた1ヶ月間でした。
サンショウウオの四十九日(朝比奈秋)
主人公は濱岸杏と瞬という、結合双生児。
私たちは、全てがくっついていた。顔面も、違う半顔が真っ二つになって少しずれてくっついている。結合双生児といっても、頭も胸も腹もすべてがくっついて生まれたから、はたから見れば一人に見える。今でも初対面の人は、私たちの顔を見た時、面長の左顔と丸い右顔がくっついたものとは思わない。結合双生児ではなく、得意な顔貌をした「障がい者」だとみられる。
正直、これだけの説明ではあまりピンと来ない。体がひとつで、意識は別?身体をコントロールするのはどちらなのか?正直そこが気になってしまったのですが、読み進めているうちに、そんなことはだんだんと気にならなくなります。
高校1年生のときに校外学習で博物館を訪れた際、二人は「陰陽図」に出会います。タイトルの「サンショウウオ」はこの図が2匹のサンショウウオに見えるところからきているようです。
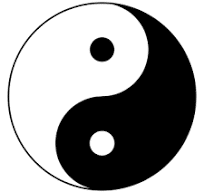
「白の頭部の中心には黒い点が、黒の頭部の中心には白の点があるでしょう。陽中陰、陰中陽とそれぞれ呼ばれていて、陽極まれば陰となり、陰極まれば陽となる、を表していて、対極はその果てで反転して循環するという意味であります。また白と黒がこのようにお互いの陣地に攻めいりつつ一つの円を成しているのは相補相克を表現しております。相補相克とは、補いあい、かつ、競いあう、という意味ですね。」
1つの体を共有する姉妹をこの陰陽図にみたてており、なるほどよく読んでいると、物語の中での視点は交互になっているのですが、最後の方になるとどちらの視点なのかがはっきりしなくなってくるのです。まさに、陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる。
そして、この物語にはもうひとつ仕掛けがあって、姉妹の父親と伯父の出生にまつわる話です。この父親と伯父、杏と瞬の構造を陰陽図に絡めて人間の存在、実存とは、といったことを惹起させる作品になっていると強く思いました。
作者の朝比奈さんの前作「受け手のいない祈り」(文學界 2023年12月号)は、読みながらこちらがその辛さを共感せざるを得ないくらいの「強い」作品だったので、前回の芥川賞の候補に入ると思っていたのですが、今回は異なるアプローチをしてきたな、と思いました。
転の声(尾崎世界観)
物語の舞台は【Rolling→ticket】が台頭、「転売」とは「展売」である、という掛け声とともにそこに乗るプレミアムこそが、アーティストの価値であるという世界。主人公の「以内」メジャーデビューして間もないバンドのボーカルで、自分たちのチケットにどれだけ「プレミアム」が乗せられているか、すなわち転売市場で需要(【求】と表現、供給は【譲】)があるかをチェックする日々。ここでチェックされるのが、【Rolling→ticket】の公式SNSである、「転の声」なのだが・・・。というお話です。
転売によって、つけられたプレミアム=アーティストの価値であるということが先鋭化を続け、無観客ライブ果ては、ステージに立たない無観客ライブが開催されるというトンデモ展開なっていきます。うーん、ディストピア。
なんでしょう。この「ライブとは何か?」という問いになる哲学的に感じる存在。「われ思う、故に我在り」というデカルトの思想を彷彿とさせます。
読んでいて、主人公の以内の焦燥感がひしひしと伝わり、転売を大否定していたのに、最終的には転売=展売の世界に籠絡されていく様子は、トンデモ設定なのに妙にリアルに迫ってくるのです。
海岸通り(坂崎かおる)
5作品中、最も短くてスッキリ読めるかと思いきや、読後感がなんとも言えない。主人公の久住さん、何だかとても気持ち悪いのです。周りからは言いたいことをすべて言っているように思われてるのかもしれないが、本人的には全然そんなつもりはないし、むしろ言いたいことを抑えながら生きている、みたいな。
なんやかんや言ってるけど、自分の会社で面倒事を起こしたくないってことでしょ、と私は思った。でも、そんなことは言葉にできない。どうでもいいことは口にできるくせに、大事なことは、なんにも相手に伝えられない、わたしは、と、わたしは思ってしまう。
この作品は老人ホームが舞台で、そこで掃除係として働く久住さん。ホームの中には、痴呆症の入居者のためにダミーのバス停が庭にあります。バス停でよく話をする、サトウさん、スタッフとして新しく入って来たウガンダ人のマリアさん。私はこの入りを見て、いわゆる介護、ケアをテーマにした小説だと思ったのですが、全然違うでやんの。
私が不思議でならなかったのは、久住さんの主張のなさなのです。仕事についてはルーチンワーク以外のことはやりたくないし、不正を追及されてもなんの弁明もしない。家賃の支払いを求められる内容証明が来ても何も対応せずに、マリアさんに言われるがまま、ウガンダ人のコミュニティが集団で住む家に転がり込む。と思いきや、最後になって、マリアさんに不正の嫌疑がかけられるとなると、マリアさんを守るためにいままでにない激高を見せるのです。
でも、わたしの腕はいまきっと、火山みたいな熱をもっていて、あつくてあつくて、誰も触れることができない。わたしは知っている。私はなおも叫び続ける。だってわたしは正しくない。あなたも正しくない。この世界に正しい人なんていない。たぶん、絶対。
上記2つの引用部分、この変化というのがウガンダ人のコミュニティで迎えられ、そのなかで氏族制度の「クラン」の名称を決めましょうということになり、そこで「海」を意味するクランにしたことによる、と読むのが妥当なのでしょうか。久住さん、そんなヒューマニズムにほだされるようには見えず、何がここまで久住さんを変えたのでしょうか、というところだけがモヤモヤするので、そこが私にとっての気持ち悪さにつながるのかもしれません。
いなくなくならなくならないで(向坂くじら)
今回の5作品の中で一番感情移入してしまう作品でした。移入しすぎてハイカロリーすぎた。しかしながら、一番好きな作品はと問われればこの作品を推します。
主人公の時子の前に、死んだはずの高校時代の親友である朝日が現れる。
時子が一人で住むアパートに同居することになり、時子の就職に伴い2人は時子の両親が住む実家に住むことになる、というストーリーです。
私は最初の部分を読んで「お、これはシスターフッドものか?」と思ったのだが、全然違った。むしろ人間関係はだんだんと壊れていく。そして、タイトルの意味「いなくなくならなくならないで」の意味に改めて気づくのであった。(「な」の文字がゲシュタルト崩壊を起こしてしまい、意味をよく考えずに最後まで読み進めてしまった・・・)このタイトル、一見して「いなくなるなら亡くならないで」という意味にとってしまったのだが、そうではない。「いなくなくなら」は「存在するなら」、タイトルを意訳するのであれば、「(そこに)存在するんなら、最初から死ぬんじゃねぇよ」という意味であると分かってしまった瞬間、ラストの展開と相まって絶望の淵に落とされるのであった。辛い。
ただ、こういう経験は私にもあって、以前勤務していた会社でリクルーターをやっており、割と気に入った大学生が(自分が関与しない)最終面接も通ってしまい、たまたま自分の部署に配属され、自分が教育係を拝命したものの、一緒に働くうちに「あれ、こいつこんな奴だったけ?」という違和感から、だんだんと距離が離れてしまい、最終的に険悪になってしまうという、ネガティブな思い出のかさぶたを久々にいじられてしまったのだ。
んで、この人間関係が壊れていくにも、いろんな装置が働いているのだが、私にとってさらにイヤ~な気持ちになったのが時子のお父さんなのだ。
時子は知っている。父が敬語になるのは、自分の存在を主張したいときだ。対等な関係のために、と本人は言うけれど実際のところ、だから自分の発言は正当で、耳を傾けられるべきだ、というニュアンスを含んでいる。
はい、これ私です。私の場合、実際には怒っているけれども、「別に怒っていません」というエクスキューズのために敬語を使っているだけで、「怒っているけど冷静です」という自分を演出するためだけに敬語を使っているのです。
ここまで書いて思ったのだが、これイヤミスの「イヤ」と同じ感情が残るので、純文学こんな気持ちにさせるって冷静に考えたら、それはそれで稀有な経験ができたと思うのであります。イヤな思いを残してみたい方にはぜひとも読んでいただきたい、と強く思いますし、私はこういうの大好きな人間です。
バリ山行(松永K三蔵)
山小説です。ただ、舞台は山と建物の外装の修繕を専門とする会社。主人公はこの会社に勤める波多。そして、物語の中心となるのは、同じ会社に勤める妻鹿(めが)さん。山アプリのSNSのアカウント名は”MEGADEATH”。主人公が勤める会社にのサークルで登山に出掛けた波多。そんなサークルとは参加せずに、週末には一人でバリエーションルート(山地図で実線ではなく、破線で表されるような万人向けではないルート)で山に登り、会社では孤立してはいるが、防水に関しては誰よりも職人的な手腕を発揮するも、なぜか激高することもあり、周りからは距離もおかれている妻鹿さん。
防水修繕で、妻鹿さんに助けてもらった波多は、それをきっかけとして二人バリエーション山行に行くことになるのだが・・・。というお話です。
私、これを読んで思い出したのが往年のギャンブル漫画「カイジ」なのであります。文字通り生きるか死ぬかのギャンブル、何かにベットするときのひりつき、生への渇望・・・。妻鹿さんにとってはバリエーションルートに単独行することがそれにあたるのでしょう。
「な、本物だろ?波多くん」
本物?私がその意味を掴みきれずにいると、「この怖さは本物だろ?本物の危機だよ」と続けて言った。その声に異様な響きを感じて見上げると、逆光の中で黒い影になった妻鹿さんが薄く笑みを浮かべているように見えた。
ああ、この時の妻鹿さんの中ではアドレナリンがドバドバ出ているのだろうな、瞳孔、開いてるんだろうな、と思う。この時会社の中では、その方針をめぐってざわついている時期ではあったのだが、妻鹿さんにとってはそんなものは危機でもなんでもない。本物の危機はバリ山行にこそある。
あと、登山とは別に会社の描写がやけにリアルなのである。会社の後輩と実際に登山をしたことあるが、山頂ですこし落ち着くと、会社の話になっていたり、有休で休んでいるときにふと「今、会社は普通に稼働しているんだよな」と思ったりするところは、サラリーマンに復帰したての自分としては「あるある」だったりするわけである。
受賞予想
おまけコーナーです。
◎(本命)サンショウウオの四十九日
〇(対抗)バリ山行
△(大穴)いなくなくならなくならないで
最近の芥川賞、直木賞と比べて渋い。過去5回(第166~170回)でダブル受賞の回数が直木賞4回(第167回以外)に対して、芥川賞は1回(第168回)だけなのである。で、今回はすべて読みどころがあり、かなり迷うところではありますがダブル受賞があるのではと思っている次第です。というかたまには2作出しても良いのでは・・・?
それにしても、年に2回、きっちりと純文学を読むという機会があるのは幸せなことですな。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
