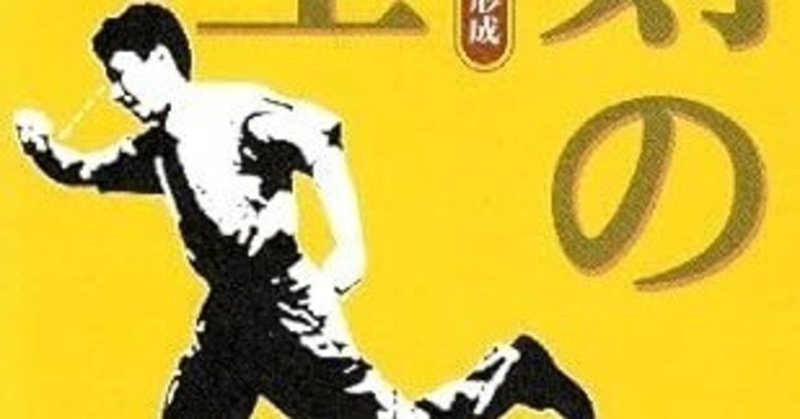
遅刻の誕生 近代日本における時間意識の形成
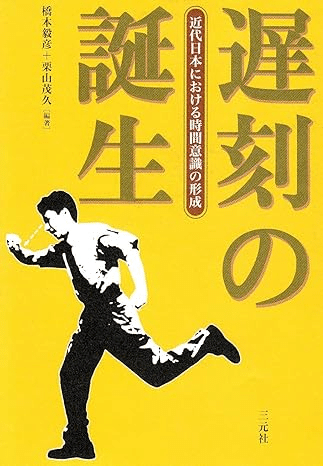
橋本毅彦+栗山茂久 編著 三元社 2001/8/1発売
目次
序文 3
第1部 定刻志向──鉄道がもたらしたもの 15
第1章 近代日本における鉄道と時間意識(中村尚史) 17
第2章 一九二〇年代における鉄道の時間革命──自動連結器取替に関連して(竹村民郎) 47
第2部 時間厳守と効率性──新労働管理の発展 77
第3章 近世の地域社会における時間(森下徹) 79
第4章 二つの時刻、三つの労働時間(鈴木淳) 99
第5章 蒲鉾から羊羹へ──科学的管理法導入と日本人の時間規律(橋本毅彦) 123
第3部 時間の無駄のない生活──子供の教育と主婦の修養 155
第6章 子供に時間厳守を教える──小学校の内と外(西本郁子) 157
第7章 家庭領域への規律時間思想の浸透 羽仁もと子を事例として(伊藤美登里) 189
第4部 新暦と時計の普及──近代的タイム・フレームの形成 211
第8章 明治改暦と時間の近代化(川和田晶子) 213
第9章 歳時記の時間(長谷川櫂) 241
第10章 明治時代における時計の普及(内田星美) 267
第5部 時間のゆくえ 289
第11章 農村の時間と空間──時間地理学的考察(荒井良雄) 291
第12章 「時は金なり」のなぞ(栗山茂久) 321
文献解題 時間を考えるための五〇の文献(橋本毅彦) 345
以下は引用。強調は断りがない場合は引用者。また適宜改行した。
幕末の一八五七年から二年間、長崎海軍伝習所に滞在し、西洋式の操船技術と科学技術の知識を日本人に伝えたウィレム・カッテンディーケは、その『滞在日記抄』において「日本人の性癖」という一節を書き残している。そこにはまず、「日本人の悠長さといったら呆れるくらいだ」という文句が一言述べられると、その悠長さを示す事例が次々に紹介されていく。修理のために満潮時に届くよう注文したのに一向に届かない材木、工場に一度顔を出したきり二度と戻ってこない職人、正月の挨拶まわりだけで二日を費やす馬丁など。そして当時の日記には、「日本人は無茶に丁寧で、謙譲ではあるが、色々の点で失望させられ、この分では自分の望みの半分も成し遂げないで、此処を去ってしまうのじゃないかとさえ思う」と暗澹たる思いで認めていたことが、感慨深げに記されている。
彼の心配は杞憂であった。維新後の日本は近代社会の建設に成功し、それから一世紀ばかりの内に、日本は世界の先進国の仲間入りを遂げた。そして今、日本の鉄道は世界一正確に運行し、工場では資材と時間が極限的に節約され、市場では正しい時刻を永久に指し続ける「電波時計」が発売されている。腕時計を身につけ、数分おき数十分おきに正確な時刻を確認しながら、スケジュール通りに日々の行動が進むよう、現代人は時間を律して生きている。
この律儀なオランダ人の悩みは、実は、幕末から明治維新以降に近代日本を建設するために到来したお雇い外国人技術者にとって、ほぼ共通の悩みであった。彼らは、工場や建設現場で日本人労働者の勤務ぶりにしばしば業を煮やしたが、その主たる原因は、彼らが時間を守らないこと、まるで時計の時間とは無関係に物事が進行する日本人の仕事ぶりだったというのである。
時間との戦いを日々迫られている現代社会において、その目まぐるしく動く活動の大前提となっているのは、人々が時間を守ること、すなわち時間規律を有していることである。我々が当然のこととして受けとめている時間厳守の行動様式が、明治初期には当たり前ではないどころか、それとはほど遠い状態にあったとするならば、それではいったい、明治以来このかた百数十年の間、日本人はいつ頃どのような経緯を経てそのような時間規律を身につけるようになったのか。時間規律の近代日本における起源、遅刻が遅刻として見なされるようになる由来、この問いが、本書の出発点となる課題である。
この問題を本書を通じて考えていくに先立って、次の二つのことを予め説明しておきたい。すなわち、第一に江戸時代から明治時代への変わり目の時代に生きた日本人の時間感覚、生活のペースやリズムとはどのようなものであったのか、そして第二に、その一方で当時の西洋人はどのような時間感覚で生活を進めていたのだろうか、という二点である。
明治初年度の日本人の生活のペースを理解するためには、まず、日本人は明治五年まで「不定時法」で時間を計り、日々の生活を営んでいたという事を知っておく必要がある。不定時法とは、昼間の時間と夜間の時間をそれぞれ等分して時間を計測する方法であり、時計の進み方に合わせて一日の時間を一様に等分した「定時法」に対比される。
しかし労働における時間規律が励行されるようになるのは、一八世紀になってからのことである。歴史家E・P・トムソンは、西洋社会における近代的な時間規律の成立を論じた先駆的論文において、産業革命以前と以後の労働のあり方を比較対照させながら、そのことを論じている。それまでの職人や労働者にとっては、週末にしたたか酒を飲む、月曜日は仕事をさぼる、といったことも日常茶飯のことであったが、工場に高価な大型機械が導入されることによって、事情は一変する。機械の始動時間に合わせて、その運転に直接間接に関わる作業者も工場に来て仕事を開始することが強制されるようになる。それまでのように「今日は天気がいいから」と、月曜日に仕事を放り出すことは許されないようになる。時間規律の励行により、サボることはもちろん、遅刻も厳しく罰せられるようになっていく。
一九世紀における鉄道の普及も、人々のもつ時間の意識と制度に対して革命を引き起こした。それは定時運行のために時間規律を励行させただけでなく、各地の時間を正確に同期させた標準時の制度を誕生させた。それまでは独立に定められていた各地の時間を、電信の助けを借りて標準時に合わせることで、鉄道の運行を円滑に進ませることができるようになった。
西洋でそのような時刻制度が誕生している時代に、日本は開国し、西洋文明の社会の仕組みを一挙に導入しようとした訳である。とりわけ、鉄道、工場、学校、軍隊といった近代的な制度の導入において、時間規律の励行が要求され、日本においても早い時期に時間規律が定着するようになったとされている。だがそこには、さまざまな戸惑い、努力、葛藤、強制があったことであろう。
第一部 定刻志向 鉄道がもたらしたもの
第一章 近代日本における鉄道と時間意識 中村尚史
鉄道の発達が、定時法の定着や全国標準時の設定といった社会的な時間意識の変化に重大な影響をおよぼした点については、すでにイギリスやアメリカの事例を用いた先行研究が存在する。たとえばM・オマリーは、鉄道が「機械の時間」の普及を促した点や、アメリカの標準時設定における「鉄道時間」の重要性を指摘し角山栄や小松芳喬は、イギリスにおける標準時の普及過程で鉄道が大きな役割を果たした点を強調した。しかし、日本人の時間意識の変化と鉄道との関係を、以上のような視点から本格的に検討した研究は、残念ながらまだ登場していない。
2 鉄道運行システムの形成と時間管理
1 運行システムの移転
日本への鉄道運行システムの移転を考える場合、まず検討しなければならないのは発足時における官営鉄道の状況である。そこで最初に、その人的資源の配置をみてみたい。
創業期の官営鉄道では、駅長から駅夫に至るまで運輸・運転関係の多くの職種に、日本人職員・労働者がついていた。ところが同時に、運輸長(traffic manager)以下、鉄道運行にかかわるほとんどの職種でイギリス人を中心とする外国人が雇用されていた。そして日本人は、彼らお雇い外国人の指示に従って、業務を遂行していたのである。このような状況下において、日本人側の運輸部門責任者である運輸課長の役割は、自ずと限定されたものになった。実際に一八七〇年代には運輸課長として、語学に堪能な洋行経験者や翻訳方出身者が任用されており、彼らの主な任務が外国人と鉄道当局との連絡にあったことがうかがえる。
創業期における運行システムの運営マニュアルである「鉄道寮汽車運輸規定」(一八七三年) … は全二一〇条からなるが、駅長をはじめとする駅務従事者の服務規程の中には、時間と時計の管理に関する具体的な手順を定めた規定が繰り返し登場しており、彼らに定時運行確保への絶えざる努力を要求している。なおその時間管理の中心となったのは、以下のように駅長と線上巡視役(お雇い外国人)であった。
一方、ちょうどこの頃、全国標準時というもう一つの「標準時」の設定も進みつつあった。日本で最初に標準時が定められたのは一八七九年のことであり、東京地方平均太陽時を標準時とした。しかしこの「標準時」は、実際にはあまり普及せず、地方各地では、それぞれの地方真時(local time)が用いられていた。ところが一八八四年一〇月に開かれた国際子午線会議に日本も参加し、国際的な標準時設定の動きに賛同する。そして一八八六年七月、勅令により一八八八年一月一日以降、東経一三五度の子午線時刻を全国標準時にすると宣言した。以後、日本の時間は基本的にグリニッジ標準時を基準とすることになる。
このように鉄道の発達が全国標準時の必要性を提起した欧米と違い、日本の場合には国際子午線会議という外的要因によって、全国標準時の設定がうながされた。そのためグリニッジ標準時への切換のわずか二ヶ月前に布告された「営業線路従業諸員服務規程」は、当然、これを意識してあえて「東京時刻」という言葉を用いたと思われる。この点は裏を返すと、時間の厳守から時間の統一へと時間管理の強調点を移したこの制度改正は、グリニッジ標準時採用問題からも影響を受けていたことになる。
以上のように官営鉄道では、運行システム移転と従業員の時間意識の進展をふまえ、制度の再編を行った上で、その民営鉄道への普及を目指していく。それに際して鉄道局は、新設会社はもちろんのこと、日本鉄道のような既設会社に対しても強くその採用を求めていった。そのことにより鉄道局は、時間の面からも全国的な鉄道運行システムの統一的な管理を試みたのである。
一八九四年から日清戦争による中断をはさんで一八九九年までの間、日本では第二次鉄道熱と呼ばれる鉄道ブームが生じた。その過程で、五九社の新設鉄道会社が営業免許を取得し、そのうち一九〇〇年までに三三社が開業した。一八九四年から九九年の六年間に建設された営業線路は、既設会社の拡張とあわせると二三〇八kmにのぼり、鉄道車輌も機関車で六六〇台、客車は一九二七台、貨車は九三五七台増加するこの数値を、一八九三年末現在における民営鉄道の営業距離(二二〇一km)、車両数(機関車二一一台、客車八〇六台、貨車三四六五台)と比較すると、その増加幅の大きさが歴然となる。このような鉄道業の急拡張は、当然、従業員需要の増加を導いた。一九〇〇年度末における鉄道従業員総数(官営鉄道・北海道鉄道部を含む)は五万八六七五人であるが、これは一八九七年度末の段階(四万二〇七一人)からみても一万五九七四人の増加であった。この間、平均すると年間約五三〇〇人が、他業種(新卒も含む)から鉄道業に流入したことになる。前掲史料中の「十日前に採用したる駅夫をして貴重なるポイントを扱はしめ、一年前に掃除夫たりしものをして重大なる汽罐車を運転せしむる」という比喩も、あながち過言ではないといえよう。
4 鉄道輸送の本格化と時間意識
2 鉄道への批判と時間意識
このような鉄道運行の混乱に対して、一九〇〇年頃になると利用者である荷主や乗客は、極めて厳しい眼を向けはじめる。貨物停滞に対する各地の荷主を代表する商業会議所からの批判だけでなく、列車遅延や早発につながる鉄道従業員の時間意識低下への批判が、乗客や鉄道関係者の間で次のように表明された。
近来私設鉄道の列車が其発着時間を誤まることは毎度のことで、時間通りに発着するは稀れで、遅着が殆んど通常になつて居り、時間の整斉を以て第一の務めとすべき駅員自からさへも遅着を普通のことと見做して敢て怪まぬ位ひである〔※強調は原文傍点〕。或る鉄道にては一年中殆んど定時に発着したことなしと云ひ、或る鉄道の発着時間は遅刻を意味した一種の謎言となり居ると云ひ、且つ其遅着も五分十分の差にあらずして、三十分より一時間位ひも遅ること敢て珍らしからずと云ふ。(中略)連絡線に乗換ゆる乗客の如きは遅着の為め旅行の予算を狂はすことがある。此等は尚以て気の毒の至りと謂はなければならぬ。(中略)之を要するに、遅延の原因は日本人の常弊なる時間を厳守するの念が、当務者にも乗客にも欠け居ること、一方には営利に重きを置く結果、知らず知らず時間を等閑に付するからである。
論者は傍点部分からわかるように、列車遅延が日常化していることに加え、鉄道従業員自身に「時間を厳守するの念」が欠如している点を痛烈に批判している。そしてさらに遅延の結果、乗客が連絡線に乗り遅れるなど、深刻な被害が生じていることを指摘した。この点は、官民双方で鉄道建設が急速に進んだ結果、二社以上の線路を経由する連絡輸送が本格化し、時間斉正と定時運行の必要性が日清戦争以前に比べ、飛躍的に増大したことを示している。そのため以前は許容されていた三〇分程度の遅延も、当該期になると社会的な批判の対象となったのである。
しかし運行間隔に余裕があり、また従業員の中における時計所持階層も限られていた明治前期において、実際には「定時」の考え方そのものが大らかであった可能性が高い。日本鉄道の例では、一八九〇年代に入ってからも、「整理」すべき遅延は三〇分以上の場合に限られ、それ以下は基本的に修正されなかった。また一九〇〇年前後になっても、鉄道従業員の間で一〇分から二〇分の遅延は、「一向平気」という認識が存在した。
このような大らかな時間認識に変更を迫ったのが、産業革命の進展にともなう輸送量および列車運行密度の上昇と、各鉄道間における連絡輸送の本格化であった。とくに後者の場合、列車の遅延が連絡線との接続を困難にすることから、鉄道自身のみならず、鉄道利用者の側からも定時運行への圧力が強まることになった。
このような事態の変化をうけて、一九〇〇年以降、官営鉄道や各鉄道会社は本格的な「定時」運行への取り組みを開始した。日本鉄道の場合、運行システム自体の見直しに加え、時計所持階層の大幅な引き下げや遅刻規定の厳格化を含む従業員の規律引き締め、さらには熟練労働者確保のための年金制度創設といった対策を次々に打ち出し、システム運営の円滑化をはかっていく。これらの対応策により、同社は業務上過失や事故といった列車遅延の原因を一定程度低減することに成功する。しかし依然として規律の弛緩は残存しており、そのシステム運営は未だ不安定な要素を含んでいた。そのため分単位の定時運行確保という課題は、国有化後まで持ち越されることになったのである。
第二章 1920年代における鉄道の時間革命 自動連結器取替に関連して 竹村民郎
再びくりかえすと定時法による分単位の時間管理を、鉄道当局は目標とした。しかしかんじんの実際の鉄道運行については、どうも我国では創業時以来かなり規律がルーズであったらしい。もとより甲武線鉄道現業部門の実例を直に一般化できないとしても。このようにみてくるならば、あらためて定時運行は、先進国、後進国を問わずきわめて難しい問題であったことが理解されるだろう。
鉄道にゆかりのある文学作品は、列車運行の定時性の問題をどのように描いていたのだろうか。衆知のように夏目漱石は、近代日本の作家のなかでもかなり鉄道に関心をしめした文学者である。
「汽車程二十世紀の文明を代表するものはあるまい。何百と云ふ人間を同じ箱へ詰めて轟と通る。情け容赦はない」。「汽車程個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によって此個性を踏み付け様とする」。「余は汽車の猛烈に、見界なく、凡ての人を貨物同様に心得て走る様を見る度に、客車のうちに閉ぢ籠められたる個人と、個人の個性に寸毫の注意をだに払はざる此鉄車とを比較して、―あぶない、あぶないと思ふ。現代の文明は此あぶないで鼻を衝かれる位充満している。おさき真闇に盲動する汽車はあぶない標本の一つである」。
とは、「草枕」の一節であるが、文明の利器汽車を見事に読みこんで、近代の情報空間における個性の喪失を鮮かに描いている。漱石は一九〇八年九月一日から一二月二九日まで『朝日新聞』に「三四郎」を連載した。「三四郎」は冒頭から汽車の車中の描写から始まっている。三四郎が上京のために下関駅から乗車した汽車は、山陽・東海道を上り名古屋駅が終着であった。最近佐藤喜一氏はこの汽車に関して述べられて、当時の『旅行案内』には掲載されていな仮空の汽車であるといわれている。しかし実在しない汽車であるにせよ、漱石は当時かなり一般的であった汽車の遅延に注意を払い、文中で同列車が終着駅名古屋駅に四〇分程遅着したと記しているのは興味深い。
名古屋に一泊した三四郎は翌朝名古屋駅から新橋行の汽車に再び乗車している。佐藤喜一氏の考証によれば、この汽車は各駅停車の大垣駅発六時三〇分の二四列車と推定できる。この二四列車は時刻表によれば一一時〇八分浜松駅着、同一四分発車となっている。「浜松で二人(三四郎と広田先生一筆者注)とも申し合せた様に弁当を食った。食って仕舞っても汽車は容易に出ない」。
おそらく小説の読者のなかで、汽車の遅延に関心をもっていた人など殆どいなかったはずである。にもかかわらず漱石は小説にリアリティを与える効果を狙ったのであろうか。右の文中でも浜松駅を容易に出発しない汽車について書いている。漱石の鉄道と時間のかかわりにたいする鋭い感性は、三四郎に名古屋駅構内の「大きな時計ばかりが眼に着いた。」と語らせているところにもみられる。こうした漱石の時間感覚は、その秀れた感性の働きによるものだけではなかった。彼はイギリス留学中しばしば鉄道駅舎を訪れたとき、駅舎を飾る大時計を眺めたことだろうから、そうした経験も、「三四郎」にとり入れられた名古屋駅大時計についての描写を可能にしたのであろう。
国鉄は国有化を達成し一九一〇年代を迎えた。この時期は第一次世界大戦を契機とした日本経済の目覚ましい発展にともなって、輸送量が飛躍的に増大した。国鉄の輸送能力は限界に達し旅客輸送は逼迫し滞貨は急速に増加の一途をたどった。例えば一九一三年全複線化が完成し輸送力を一段と増強させた東海道線も、大戦による輸送需要の画期的な増大によって麻痺寸前の状況となった。一九一八年四月一三日の『東京日日新聞』は「鮨詰列車、鉄道の大混雑驚くべし」の記事のなかで「鉄道全線に亘る旅客の輻輳は四月に入りて最頂上に達し定員超過乗遅れ等枚挙に遑あらず殊に東海道線は混雑更に激甚なると共に乗客の迷惑一層なり......鉄道院は之に対して如何なる策を取らんとする乎」と鉄道当局を攻撃した。こうした批判にたいして当局は「機関車の牽引力の許す限りは列車を増結して居るのだから此上の能力はない」と居直る以外に打つ手はなかった。当時の国有鉄道は鮨詰列車の解決もさることながら、「経済界多端の秋に際し滞貨を速に処分」することのほうが緊急の課題となっていた。
鉄道の輸送能力には限界があり、その設備を増強させることは一朝一夕に望めない。だから滞貨の増加は一九一六年末より一段と激しくなり、一九一七年秋に及んでますますその度を加え、さらに翌一八年初頭には輸送力の極限に達した。そしてこの危機はわたしがこれから述べるように、列車時刻の正確性をとにかく実現せしめた。当時を熟知する石田太郎(運転課長、仙鉄局長、神鉄局長を歴任)はいう。
世運の進展につれ列車は増加し、新線は建設され、単線は複線化された。従って新規採用者も多くなりこれが指導訓練の必要を痛感された。機関幹部の養成の外、機関車乗務員教範を造り、これを部内一般に配分し各自の啓発に資し、後進者の技術並に実務の習得に便ならしめた。程経て、機関手及び火夫養成所が設けられた。かくして、大正四、五年の頃より管内全体に亘って列車は時刻通りに動くようになった。その後これが習慣付けられて汽車は遅れるものだとの世間の不評は一掃された。
かくて生れでたのが日本の国有鉄道が世界に誇る列車の定時運行の確保である。大島藤太郎教授は列車の定時運行の実現について、「第一次世界大戦前後における異常に増大した輸送の要請にたいして、資本の追加投資が少く、旅客・貨物の増加に対比し、当然なさるべき車輌・施設の増加が、不十分にしか行われなかったという条件の下で生れたものである」。「こうした『優秀な』成果は新しい機械や、設備の採用によって達成されたものではなく、国鉄労働者の個々の熟練した技能が、集積されたものであり、異常な労働強化の産物である」と指摘している。わたしも大島藤太郎教授の指摘には、大いに賛意を表する。しかし、「個々の熟練した」労働者の技能の集積が持続性を持たないことはいうまでもない。端的にいうならば「異常な労働強化の産物」としての列車運行の定時性の確保が、前述した一九三〇年代国有鉄道の分秒単位の時間管理を、直接支えた唯一の基礎であったのではない。
ヨーロッパの鉄道技術を追い抜く画期的な自動連結器取付け計画を提案し実行したのは、工作局長島安次郎を先頭とした国有鉄道の技術者集団であった。彼等は国有化を契機として集まった各鉄道の優秀な技術者である。彼等が鉄道技術の全国的統一とその発展をはかったという点で、技術の流れを敏感に読みとることができた先駆的な人々といえる。即ち彼等は全国の鉄道工場をシステム化し、総合プロデューサーとして、自動連結器取付けを見事に成功させた。彼等がきわめて先進的であったのは、準備作業にあたって、タイム・スタディ、モーション・スタディを重視する技術感覚を持っていたということである。
国有鉄道におけるタイムスタディ、モーション・スタディ研究が、アメリカ合衆国におけるインダストリアル・マネージメントの影響を受けて始まったことは充分注意されなければならない。それは端的にいうならば、当時の技術者たちは、世界で最も進んだアメリカ合衆国のタイムスタディ、モーション・スタディについては、文献の上では知っていたとしても、一九世紀末葉以降、工場経営と結合して目覚ましく進展していた経営管理運動の実態については、現地に赴いて学ぶまでほとんど知ることはなかったのである。ついでに書き加えておくと、たとえばフレデリック・W・テイラー(Taylar, Frederick Winslow, 1856-1915)は一八八二年にフィラデルフィアのミドベイル鉄鋼会社の職長となったが、これが科学的工場管理法の基礎を定めるはじまりであった。即ち彼は同社における仕事にもとづいて、「経営者の義務」というものを考えだしたが、それを要約すればつぎのごとくであった。
1、人間の作業の各エレメントに関する科学を発展させ、それによって昔からの当推量のやり方をやめること。
2,労働者が自分自身で仕事量をきめたり、技能を磨いたりするこれまでのやり方の代わりに、個々の特定作業につき最優秀の作業者を選びだし、教育訓練を行ない、その進歩をはかること。
3、進歩した科学の諸原則にそって諸活動を遂行するにあたっては、経営者と労働者の心からの協調をはかること。
4、労働者に大部分の仕事とより大きな責任が課せられていたこれまでのやり方の代わりに、おのおのがより適した方面を受けもつように、経営者と労働者との双方に仕事を平等にわけること。
科学的管理というテイラーのシステムの主たる目的の一つは、右にも明らかなように「経営者と労働者の心からの協調をはかること」にあった。テイラーは「労働者に大部分の仕事とより大きな責任が課せられていた、これまでのやり方」から科学的管理へ移すことを「経営者の義務」であるとしたのである。このため労働組合の批判がテイラーのシステムに向けられたのは当然であった。しかし第一次世界大戦中に労資双方にとって、生産性における人間的な要素についての認識が深まっていった。大戦後アメリカ労働総同盟(一八八六年創設、AFL)は、戦時中の経験から科学的管理にたいしてより友好的となった。いわば産業上の能率向上を伝統的なやり方で実行しようとする多くの企業家を批判するものが、労働組合に生まれつつあったことを知るのである。
以上みたような状況は、とにかく国有鉄道が自らを革新するとするならば、あたらしい経営管理の方向と結びつかなければならないことをしめしていた。一九一二年頃国有鉄道の技術者山下興家(大宮工場長、機械課長、工作局長等を歴任)はアメリカ合衆国に出張し、そこでモーション・スタディ、タイム・スタディと結合した車輌修繕技術がいちじるしく進歩していることをはじめて認識した。山下興家はそのことを「作業研究というのは、いわゆるモーション・スタディで、書物では見ておったが、それは多量生産とか、精密工業に対して、実行出来るものと思っていたが、アメリカに行ってみたら、アメリカの修繕工場でさかんにやっておった」。「機関車の修繕は、一週間から九日くらいでやっておった。又貨車は、僅か、一日で修繕するのに、当時、日本では機関車は四、五十日、貨車は十五日という有様であった」と述べている。山下の事例は前述のごとく二〇世紀の経営管理の合理化の発展とも関連し、国有鉄道の技術集団がタイム・スタディ問題に正面から挑戦する時期にきたことを明瞭にしめすものであった。単に機関車、貨車の修繕のみではなく、国際的な経営管理の潮流に対応した国有鉄道の技術システム構築への構想が要請されることとなったのである。
たしかにアメリカ合衆国のタイムスタディ、モーション・スタディを学んだ山下興家の体験は、彼自身の知識の啓蒙をはるかに超え、国有鉄道全体に影響を及ぼした。全国の技術者や労働者の支持と関心がタイム・スタディ、モーション・スタディの定着を決める時代を迎えたのである。例えば山下興家はそのことをつぎの如くいっていた。
野田君や加藤君(三菱の野田信夫、加藤威夫のこと―筆者注)を頼んで、しきりに講演をやってもらい、引続いて、全国の鉄道工場から人を選抜して、たくさんの人を専門家に養成したのです。それで日本ではモーション・スタデイを、大規模に始めるのに、鉄道が先鞭をつけたことになったのです。今いったモーション・スタデイを、後に、我々は、作業研究と称することにしました。
山下興家の中央の技術者が全国の工場から選抜した人々を系統的に教育して、「作業研究」のエリートとし、工場の技術環境のボトムアップに努めるというのが、国有鉄道の「作業研究」の基本構想となったのである。技術者が個々に研究するよりも、研究システムをつくり国有鉄道全体で「作業研究」を行ったのである。したがってタイム・スタディ、モーション・スタディの実行では、国有鉄道が我国産業界の先頭を走る役割をになうこととなったのは当然であった。
第三章 近世の地域社会における時間 森下徹
1 近世の時間のとらえ方
前近代を対象にして時間という問題を考えようとする場合、朝尾直弘の次の指摘がまずは手がかりとなる。
一粒の種子が地に落ちて死し、新芽となって現れ成長し、多くの花をさかせ実を成らせて、ふたたび地に落ちて死ぬ。永遠に続くかと思われる円環的な自然のリズムのなかで、人々は農耕をいとなむ。その時間は直線的に、前へと進む近代の時間とは性質をことにしている。同様に、狩猟民には狩猟民の時間があり、漁民には多様な魚種とその生殖・回避の周期にあわせた時間があった。地域ごとに、自然条件のちがいごとに、労働と生活のかたちごとに、それぞれの時間があり、世界があった。これらを一括して、近代の(資本制にもとづく産業経済の)時間で一方的に区分することは許されるであろうか。
直線に前へと進む近代の時間とは全く別の時間が前近代にはあり、しかもそれは産業や地域ごとに多元的な様相を呈していたというのである。近代の時間と前近代の時間を区別するこうした二元的な把握の仕方は、大方に広く受け入れられているところといえる。
ところで朝尾のこの発言を評した塚田孝は、近代の時間とは対比される循環する時間についても、「それ自体が持続的ではあるが歴史的時間と考えるべきだ」と批判する。近代の時間の特質を浮かび上がらせるだけの、いってみればネガの位置を与えるだけで事足れりとするのではなく、前近代の時間についてもその固有な歴史性を明らかにすべきだという主張には傾聴すべきものがあろう。
また塚田は「朝尾氏は、二つの時間を対立するものとして、あれかこれか式に捉えているかに思われますが、両者を統一して把握することが必要」とも述べている。たしかに角山栄によっても、「十七世紀中ごろ以降、全国的規模で時鐘による時間システムがぱっと拡大してゆく」ことが指摘されていた。ここでいう「時間システム」とは時鐘が全国各地に設置されるようになった事態を指すが、だとすればこの時期、全国各地に暮らした人たちに新たな時間意識が浸透したのではないか。これも近代と前近代を単純に区別するだけでは解けない問題であって、両者の重層という事態に注目すべき所以となろう。
第4章 二つの時刻、三つの労働時間 鈴木淳
さて、大久保利通が薩摩藩で役所に出ていた時期の日記を見ると、一八六二(文久二)年九月には「二六日、四つ時出勤、八より退出」とあり、前後連日ほぼ同じである。朝四つ、すなわち九時から一〇時ころに出勤して、昼八つ、午後二時前後に退出している。これからすると、一〇時から二時という太政官の勤務時間は、幕末薩摩藩庁のそれと大差なかったことがわかる。他藩の武士の勤務時間が大幅に異なったとは考えにくく、多分これは「武士の勤務時間」とでも呼ぶべき労働時間の観念だったのであろう。大久保日記によれば、一八七〇(明治三)年の夏に夏季のため八時に繰上げられた出勤時刻は、秋になっても一〇時にはもどらず九時になっている。そして翌七一年の春には二時退出だが、同年の秋には三時退出と六時間体制になっている。ちょうど廃藩置県を終えたあたりで六時間体制が確立したのである。六時間でも、不定時法時代の日の長い季節とは大差ないから、長くなったとは言え「武士の勤務時間」を継承していたといえよう。一八七三(明治六)年九月の置賜県庁務条例は九時から三時、同一二月改定の滋賀県事務条例は九時から四時としているから、府県庁はかならずしも一致しないものの、ほぼ類似の勤務時間であったと考えられる。
これが九時から五時までの八時間になるのは太政官制から内閣制へと変わり各省で「改革」が進められる時期、すなわち一八八六(明治一九)年の一月から二月にかけてである。同じ時期に東京府や大阪府も九時から五時、あるいは六時の執務時間へと延長されており、府県庁まで含めた官庁の勤務時間がおおむね八時間体制になったものと思われる。
四民平等と唱えられ、江戸時代の身分制度は崩されたものの、階層や都市・農村の別によって、全く異なる時刻体系や時間感覚、そして労働時間の習慣が併存していた。それが工場という場を中心に定時法の時刻体系やその時間感覚の下で、都市部と農村部の労働時間の違いを明瞭にしつつも統合される傾向が明らかになったのは、産業革命が始まり、近代的な国家体制の整備が緒につく一八八六(明治一九)年ころであった。これらの平準化は人々の身分意識や生活の平準化とともにその後数十年かけて進む。それは時刻においては定時法と時計が示す時間感覚の更なる浸透であり、労働時間にあっては、武士の勤務時間に由来する部分では延長、他の部分では産業革命期の延長を経て短縮に向かうものであった。現代の我々は一つの時刻体系と労働時間観念を当然の前提としているが、それはそれほど当然のことではない。
第五章 蒲鉾から羊羹へ 科学的管理法導入と日本人の時間規律 橋本毅彦
2 遅刻もいけない、早出もいけない - 宇野利右衛門の欠勤解消法
明治から大正にかけて職工の労働と生活の問題を詳細に調査し分析した人物に、宇野利右衛門という人物がいる。出版社に勤める傍ら職工の状態を調査し、雑誌『職工問題の研究』を発刊するとともに『職工問題資料』を発行したその中で、彼は職工たちの欠勤率の高さを指摘し、その解決策を提示している。
紡織工場の調査に基づき、彼がまず指摘するのは、欠勤率の一年と一月を通じてのバラツキである。一年を通じては三、四月には多くの職工が出勤し、八月に最低となる。その差は二〇~三〇パーセントにも及ぶ。八月の暑い盛りに欠勤が多くなることを企業の方も見越して、余分の労働者を雇用しておくという。一方、一月を通じては労賃が支払われる五日、帳締めが行われる二〇日をピークとして、その翌日から三、四日はストンと一〇〇パーセントから八〇パーセント程度に出勤率が落ちてしまう。このような生産効率に悪影響を及ぼす出勤率のバラツキを平均化するとともに、それを全体的に高めることを目的として「出勤率中和法論」なる解決法が執筆された。
宇野は出勤率を高め均一化する方法のさまざまを以下のように整理している。 まず全体としては、
(1)強励法、
(2)皆勤賞与法、
(3)短期賞与法、
(4)工銀循環毎日払法
(5)矯癖法、
(6)休養法
の六種類に分け、その内たとえば強励法は、
(i) 欠勤者の制裁、
(ii) 出勤者の奨励、
(iii) 追い出し、
(vi) 工銀支払日の延期、
という四つに分けている。そしてさらに(i) の欠勤者の制裁については、
(a) 欠勤室に収容して、自室に入ることを許さない、
(b) 食事を遅らせて、出勤者とその交代者の食事が終わった後に食事をさせる、
(c)外出を許さない、
という三つの具体的方法が実際になされている処置法として紹介されている。これらのうち特に食事を遅らせるという処置はかなり職工に不満を抱かせ、工場への反感を募らせてしまうことになるとして、これらの制裁処置は「手加減の宜しき」が必要であると注意している。また(iii)の「追い出し」とは、寄宿舎であれば「世話係」や「舎監」が一人一人の部屋に行き出勤するように促す方法である。 宇野によれば、通勤者に対しても、「外勤方」「督促」と呼ばれる専門の係員がいて、一人一人にあたって出勤を強励させたという。またこれらの係員が出勤を促す方法としても、
(a)皆が出勤するまで部屋や家に居座って動かない「居出し法」、
(b) 出渋っている者がいる所で喧しく督励する「追い出し法」、
(c) 欠勤を願い出るような場合でも必ず出勤の服装をさせて許可を得させる「仕度法」
という方法があったと いう。また(5)の矯癖法というのは、仮病を欠勤の理由にする者に対する対処の方法で、病気を理由に欠勤を願い出る者はすべて医師の診断を受けさせるという帝国製麻会社の一工場の例が紹介されている。寄宿舎の女工にはこの癖が多く、同室から一時に五、六人も仮病を理由にすることも少なくなかったというが、医師の診断を受けさせるようにしてから一年程のうちに欠勤者が激減したとしている。
宇野はこれらの種々の欠勤解消法の紹介の後、「出勤時刻の励行法」として時間規律を身につけさせることの重要性を説いている。それはまず欠勤理由の分析から始まる。春眠暁を覚えずのように、暖かい季節になると若い職工はぐっすりと眠り込み汽笛の音も聞こえずに出勤時刻を寝過ごしてしまう。目を覚ますと出勤時間にはとうに遅れてしまっていることに気づき、「エゝマゝヨ」と一日骨休みをすることを決め込んでしまう。しかも、誰にもありがちなこの悪習は、数を重ねると遊興や不良の悪の道に踏み込みかねないことになる。では、朝寝坊をなくすにはどうすればよいか。
寝坊しないためにはとにかく早く起きればいいのだ、という意見を宇野は採らない。「星を踏んで出で、月を戴いて帰る」という農民らの早起き習慣を、農村出身者の多い職工たちに励行させることは比較的容易であるかも知れない。だが、農民の仕事と工場労働者の仕事とは質的に大変な差がある。「規律に縛ばられ、運転せる機械に追立てられて、二六時中、過失を仕出かさない様、不正品を造らない様、気を張り通しで、少しの油断もなく単調な仕事に、長時間従事して居る工場労働者」と「美しい、天然の中に、呑気に高談放歌しながら、自由の労働に従事して居る農業労働者」との間には、精神的緊張と身体疲労の上で大きな差がある。従って、余りに早い起床は十分な休養を妨げて好ましくないと言うのである。現に鐘紡の経営者は、一番号の汽笛を聞いてすぐに出勤してくる職工に対し、休養を十分に取らせるため、早出をせず二番号の汽笛を聞いてから出勤するように促したという。遅刻もいけない、早出もいけない、正確な時刻を守ることこそが肝要だと宇野は結論するわけである。
出勤時間の正確さを奨励することは、必然的に就眠時刻の正確さを奨励することにつながる。就眠時刻については、寄宿舎では励行されているが、通勤者の社宅が集まる地域でも、当番が拍子木などで就眠時刻に近いことを知らせ、社営の浴場・理髪所・販売所などは就眠時刻の三〇分前に終了、就眠時刻の三〇分後には消灯すべきであると上野は述べる。また通勤者の定刻通り起床を促す習慣に関して、イギリスの「戸叩き」という例を引用している。マンチェスターの職工の住む地域では毎朝職工の家を叩いて回る人物がいたという。
3 遅刻という病気の治癒 ―科学的管理法の導入のはじまり
宇野の著作出版と同じ頃、米国生まれの科学的管理法が日本に紹介され始めた。テイラーの『科学的管理法の原理』が出版された一九一一年前後から、テイラーの名前が日本に伝わってくる。同年、「無益の手数を省く秘訣」というテイラーの管理法を紹介する記事がとある新聞に連載された。著者の池田藤四郎は、米国から科学的管理法関係の著作や講義録を取り寄せ、それらを基にこの解説をした。形式は読みやすい連載小説のようになっており、翌々年に同名の単行本として出版されると実に一五〇万部が売れたという。
著作の内容は、主人公の少年太郎が徒弟から能率技術者として大成するまでのさまざまな工夫と苦労を描いたものである。家庭の事情で工場の職工になった太郎は、そこで古参の職工たちから仕事のこつを盗みとるが、さらに材料の配置や積載方法などに工夫の余地が残されていることに気づく。また金槌の持ち方、振り下ろし方にしても、効率的な方法を編み出して実践する。そんな太郎の姿を見た工場長が感心し、夜学に通う太郎を励ます。卒業した太郎は「能率調査所」に就職し、能率技術者として腕を振るうことになる。
最初に彼が派遣されたのは、機関車の修理工場。そこで彼は工員たちの無駄に満ちた作業法を目撃する。使われぬ最新式機械、延々と工場内を動き回される工具類、そして機関車の下に潜ると監督の足音がするまで出てこない作業員。このような観察を重ねることで、太郎は職工たちの作業における時間の無駄の多いこと、時間的規律の重要性を痛感していく。とりわけ職工たちが終業の二〇分前に機械を離れて帰宅の準備を始めることに彼は驚き、その損失はすぐに数万円に上ると試算する。職工たちは物品こそ盗み出さないが、時間を盗み出しており、道徳上の矛盾を犯しているのだと彼は主張する。また遅刻と欠勤も重大な損失をもたらしており、両者による時間的損失は総就業時間の一五パーセントに及ぶと計算する。そこで彼がとった対策は、皆勤を奨励するような支給法を編み出すことであった。出勤日数について標準を定め、皆勤には賃金の五パーセントをボーナスとして与え、半月間の遅刻の合計が二時間をオーバーしないときには賃金の二・五パーセントをボーナスとして与える。女工に対しては皆勤賞を倍額にする。
かくして科学的管理法を紹介する著者にとって、時間規律を励行していくことは根本前提であり、遅刻の常習者は病人として扱われることになる。「元来、遅刻なるものは、慥に或種の職工にとり、一の病気である。此病は激烈なる荒療治を施して初めて駆逐することが出来る。若しそれ相応の手当をせぬと遂には立派な持病となる虞がある」。遅刻を頻繁にしてしまうことを病気とまで呼び、その病気を治療すること、すなわち時間規律を守ることで健康体を保つことができると論じるわけである。
4 時の記念日 ―生活改善運動と時間厳守
時間規律を庶民のレベルでも浸透させていくことは、大正期に力を入れてなされたが、その最も象徴的なできごととして「時の記念日」の制定を挙げることができよう。その制定にあたっては、大正九年に東京教育博物館(現国立科学博物館)で開催された「時」展覧会がきっかけになっている。
東京教育博物館は、明治末年から通俗教育館が併設され一般大衆のための教育がなされるようになり、それとともに大正五年からさまざまなトピックで展覧会が開かれるようになった。大正八年には、日本人の日常生活における能率向上を目指した生活改善展覧会が開催された。開催主旨には、日本人の生活様式が欧米に比べ「繁雑不合理を極め」ていること、そして欧風の生活法と日本固有の生活法との調和が日本社会で達成されていないことが指摘され、生活方法を根本的に改善することで無駄を省いた能率的生活法が必要であるとされている。この生活改善展覧会は反響を呼び、「生活改善同盟会」が設立され、それとともに各地で生活改善展覧会が開催されることになる。
この生活改善同盟会の協力で、教育博物館は時間厳守の風潮を普及させる目的で「時」展覧会を翌年企画した。展示されたポスターには次のような標語が記された。「婦人一生の御化粧時間」「集会と時(今日も亦流会か)」「退出時間も励行したい」「内外病院の診察時間比較」「内外芝居見物の比較(お支度、お出掛け、幕間、芝居の二日酔い、西洋の芝居見物)」「時を知らぬ人達(井戸端会議他)」「迷惑な訪問」「訪問の仕方」「接待よりも用弁」「返書はその日のうちに」「名士の接客日一覧」。これらの標語から読みとれる主催者のメッセージは、日本の日常生活においては伝統的な慣習による繁雑な手続きのために多くの時間が浪費されている。それらを簡素化し、時間厳守を励行することで、時間を効率的に使用することが可能であり、またそのことが強く望まれるということである。
第六章 子供に時間厳守を教える 小学校の内と外 西本郁子
明治維新前後の日本社会を見聞したイギリスの外交官随員アーネスト・サトウ(Ernest Satow, 1843-1929)は、当時の日本では「一般の人々は時計(clocks)を持たなかったし、また時間の厳守(punctuality)ということはなかった」と記している。それから四半世紀後、特権的な教育環境にあった子弟はともかく、一般の子供は果たしてどのように時間の概念を身につけていったのであろうか。
そもそも時間厳守とは、何だろうか。英語で言えば、punctuality, to be punctualである。punctualの語源はラテン語のpunctualis、すなわちpunctum「点」を意味する語幹にālisという語尾がついた形に遡る。punctuate(「句読点を付ける」)やpuncture(「...に穴をあける」そしていわゆる「パンクさせる」)などの動詞と同源の単語である。punctualとは「点の」がその根本的な意味である。つまり時間厳守とは、ある一定の時間の範囲、言い換えれば時間帯、にではなく、時間上のある一点を捉えることができるか否か、その能力に係わっているといえよう。逆に言えば、punctualityを求めることのない社会では、人は時間のゆるやかな「帯」の中で活動すれば事足りた。その「帯」の幅がどれほどであるかは、それぞれの社会や時代、また事柄の性質に依るだろう。共同体ごとに、活動の種類によって暗黙のうちに了解された時間の幅があった。時間厳守を求める社会、時間の規律が厳しい社会とは、その「帯」の幅が次第に狭くなり終には「点」へと移っていく社会である。日本においてそれはいつ頃からのことだろうか。
明治政府は一八七二(明治五)年末に改暦を決定、翌一八七三(明治六)年から西洋の時刻制度を導入する。「分」「秒」という新しい語彙を通じて、これまでにはない極めて短い時間の単位を一般の人は知ることになる。以降、様々な新制度のもと、新しい時刻の表記とともに、新しい時間の考え方に接し、また新しい態度を人々は求められるようになる。しかし、新しい概念を理解することはそうたやすいことではない。増してやそれを行動に移すのはなおさらのことである。
藩校、漢学塾、寺子屋など、身分によって異なる種類の学校があったが、町人の子供の教育の場で、読み、書き、そろばんを教えた寺子屋は、通例は辰刻(午前八時)に始まり未刻(午後二時)に終わった。夏期は、卯刻(午前六時)始まりで、午刻(正午)にはきりあげた。教授の時間帯はおおよそ決められてはいるものの、「何時ヨリ等ノ定メナシ」の状態であった。あったところで、時計がないので、時刻を知る方法はといえば陽射し(雨天曇天には役立たず)や、鶏鳴を聞くという大雑把なものだった。教育方法は、進度の異なる子供の個別指導で、一人または二人ずつ替わるがわる教師のもとに出て、本を音読してはその読み方を学び(素読)、手習いでは、師匠はひとりひとりに手本を書いて渡し、子供はそれを参考に練習した。そして師匠は子供が書いた文字を添削したが、その間そのほかの者は自習をした。従って、子供たちは来た順に教授を受け、その日のうちにすべきことを終えた者から帰宅した。やや極端に言えば、子供たちは三々五々やって来て、三々五々帰っていったのである。休みは五節句、盆や正月などのほか、毎月一日と一五日であった。師匠の都合により、様々な変更もあった。明治時代にはこれから詳しく見てゆくように、教育制度は大きく変わる。とはいえ、寺子屋のような学習の仕方が完全に消滅したわけではない。例えば現在でも書道教室では、かつての手習いと基本的に同じスタイルをとっている。
明治政府が導入した教育制度は欧米のもの、ことにアメリカの制度に倣っている。一八七一(明治四)年から一八七三(明治六)年にかけて文部大丞田中不二麿らは欧米諸国の教育制度を視察し、師範学校にはアメリカ人教師を招聘する一方、初めて製作した教科書は主としてアメリカで使用されていたものを翻案したものである。新しい教育制度の実施により、教育方法のうえで従来とは大きく変わった点がある。個人教授に代えて一斉教授法を取り入れたことである。複数の子供たちが、同じ内容を同時に学ぶようになったのである。ここで初めて、教育において時間の規律が問題となる。
江戸時代のゆるやかな学習時間の区切り方から、一体どの様にして「十分前」という細かな時間の単位を用いることになったのだろうか。欧米諸国の教育制度が参考になっているようである。欧米の教育機関の視察の報告書『理事功程』はコペンハーゲンの学校の規則を紹介している。そのなかに「登校規則」の項があり、次のような記述がある。「学校開業ニ先ツコト十分時乃至十五分時間ニ於テ生徒儘ク学校圍内遊園ニ来會スヘシ...…妄ニ教場ノ内ニ入ルを許サス」。「小学生徒心得」との類似を想起させる規定である。
一般の家庭はさることながら、学校ではどのようにして時刻を知ったのだろうか。機械時計がないところでは、自然や有機的な方法に頼らざるを得なかった。相変わらず日の長さによって時間を決めたり、中には「腹時計」を用いた教師もいたようである。一方、秋田県大湯学校の場合、早くも一八七七(明治10)年の備品一覧にはテーブルや椅子、教科書に混じって「時計、但シ破損ノ儘」という文字も見える。たとえ壊れていたにせよ、この時期に時計そのものがあったということ自体、稀なことであろう。文部省は一八七五(明治八)年に実物に代わる教材として「木製假時規」(時計)を製作している。一八九一(明治二四)年には教育上必要な備品として規則の上で時計が明記されている。「小学校設備準則」は、校具を甲乙の二種に分け、乙種で「国旗、門札、生徒用及教員用ノ机及腰掛」に続いて「時計」を挙げている。実際、時計の有無は江戸期と明治時代の教育の仕組みの違いを特徴付けるもののひとつである。一八九二(明治二五)年のある比較によれば、江戸期には見られなかったが「今時ノ必用具」には、墨板、白墨、博物標品、体操用具、楽器などがあるが、その筆頭に挙がっているのが時計である(ちなみに、旧帝国大学の象徴とも言える時計塔とは異なり、公立小学校の校舎の外壁に時計が取り付けられるようになったのは比較的最近、一九六六年頃からのことのようである)。
「時間」という新しい語彙が小学生の教科書に登場するのは一八七三(明治六)年である。文部省が初めて編集した教科書の第一課に早速あらわれる。学校生活を述べた文章である。
学校にありて、稽古するものには必ず、遊歩の、時間あり、○此時間には遊歩場に出でヽ、思ひのまヽに遊歩して、身を動かし、心を慰むべし、○勉強することあれば遊歩するも、楽しみなり、遊歩を、楽みと思はヾ、稽古の時間は怠らず、勉強すべし。(『小学読本 巻一』)
当時、教科書は無償で配布されたわけではない。学校に通う子供をもつ親は教科書の購入を強いられた。高価な和紙に印刷された本は、決して手軽に買える値段ではなかった。経済的困難を理由に通学しなかった子供の数は実際少なくない。このような事態を少しでも改善すべく、考えられた手段の一つが、掛図の作製である。これもアメリカで使われていた掛図(chart)に習ったものである。これで一度に何人もの子供が同時に同じ教材を見ることができる。文部省は一八七三(明治六)年にいくつか掛図を作る。「時計」の文字が、翌一八七四(明治七)年の改訂版の「第五単語図」に見える。第一学年で使用するものでありながら物の名前がすべて漢字で書かれているのには、正直のところ驚く(後の改訂版ではすべて平仮名にかわる)。一方、教師用のハンドブックとでもいうべきものが存在し、それにはすべてふりがなが振ってある。手引書にはまた、それぞれのものについての簡単な説明が添えられている。「時計」の項には次のように書いてある。「時計金銀等ニテ造り時計ルニ用ヰル物ナリ」。先程校則を見たときにも触れたが、小学校制度が始まったばかりのこの時期、時計を実際目にしたことのある子供はまずいなかったはずである。
教科書に収録された時間をめぐる教材に、ある特徴を見いだすことができよう。低学年の児童に対しては時間厳守を教え、学年が進むにつれて強調されるのが、規則正しい生活そして浪費の戒めである。これに「時は金なり」が加わる。興味深いのはその格言の取り上げ方である。それが極めてはっきり現れているのが先に見たダゲッソーの逸話である。この物語は『西国立志編』が基になっていることは先に述べた。ところが実際には、スマイルズの原文はおろか中村正直の翻訳にすら、このフランス人にまつわる教訓中に「時は金なり」の言葉はない。ダゲッソーとこのことわざとは直接の関係はないのである。確かに、『西国立志編』全編に張る精神から見てそう書き加えたとしてもさほどの違和感はない。むしろある意味ではスマイルズの考え方を確実に読み取ったとも言える。それにしてもなぜ教科書執筆者はあえてそのような加筆をしたのだろうか。ここに、「時は金なり」という格言に対する教科書の考え方が反映されているのではないだろうか。
修身の授業で時間の浪費を戒めその大切さを説くのは、もちろん、ベンジャミン・フランクリン本来の蓄財の思想ではない。資本主義的価値観の初歩的教育を施すわけでもなければ、効率の概念を教えるためでもない。校則や教科書を通して「時刻を守れ」と言い聞かせてはきたものの、必ずしも時間厳守を徹底させるものでもないようだ。もしそうであれば、一分でも遅れることによって全てが無に帰す恐怖を教える、シンデレラの物語を取り上げてもよさそうなものだ。が、そういうこともない。では教科書が教える「時は金なり」の考え方とは何か。教科書は子供に向かって言う。毎日規則正しい生活を送り、寸刻惜しんで絶えず学び、その長年の蓄積によって優れた人物になり、学問なり芸術(あるいは軍事)において立派な業績を築きなさい……。勤勉こそまさに明治の小学校教育が採用した思想である。教科書上で「時は金なり」という諺を何度となく紹介してきたとはいえ、その言い方は比喩的である。僅かずつではあっても、金銭は貯めればやがて積もり積もってかなりの金額に達するように、毎日少しずつでも努力を積み重ねていけば、やがては立派な仕事をなすに至る偉大な人物になるでしょう……というのがその教えだ。
時間の概念を子供に教えるのは教科書だけではない。子ども向けの雑誌にも時間の大切さを説くものがある。そのひとつに『少年園』という雑誌がある。小学校高学年から中学生を対象とするこの定期刊行物の一八九四(明治二七)年二月号は、「処世の秘密時間を守れ」と題する文章を掲載している。三ページほどにわたって書かれた内容は、例えば、「時間の貴重なる所以を深く考ふるときは、従て時間を守るの習慣を養ふ得べし。……人の信用を得ることの速なる、時間を守ることを実行することより速なるはなく、人に信用を欠くことの速なる、又これを怠るより速なるはなし」といっている。スマイルズの名前もその書名にも触れられてはいないが、これも『西国立志編』から所々抜粋してまとめられた文章である。その浸透力の広範であることを改めて知る。
石井研堂の『時計の巻』(一九〇三[明治三六]年)は時計の仕組みの説明で始まり、日本製とスイス製やアメリカ製の時計の質の比較に話が移ってゆく。結果はつねに西洋のものの方が上だ。問題は時計の精度のみならず、それを使う人の側にもある。幾分誇張気味の逸話で筆者が不満気に紹介するのは、時計の使い方をよく知らない日本人だ。鎖付きの金時計を身に付けていながら、おしゃべりばかりしていて時間を浪費したり、集まりの予定を一、二時間も過ぎてからやってきて平然としている者、汽車の出発時刻の二時間も前に駅にやって来て、幾度となく欠伸を繰り返し何もせずただ汽車の到着を待っている人の姿に、筆者は苛立ちを隠せない。挿絵にも、いかにも田舎者風情の、大きな荷物を背負って駅の待合室にいる二人が描かれているが、それはこれを見るものにどことなく、「ああいう人にはなりたくない」と思わせる筆致である。そして教訓とはこうだ、「時間だと思ふから、二時間をたゞ費してるですが、これを、一時間幾らといふ金銭だと思ふたならば、まさかかうでもないでせう」。これに対し、研堂は時間の使い方において従うべき模範をあげる。渋沢栄一(一八四〇~一九三一)である。〔引用者中略〕渋沢が時間の利用の仕方の輝かしいモデルであるというのも、まず彼は仕事上の約束を二週間も前に決めているからである。そしてまた彼が称賛に値するのは、面会に際しては話の最後の一割を客を送り出しながら聴き、次の来客を迎える準備をするからであった。
西洋における勤勉や時間厳守の態度は明治期の日本人には未だ欠けていた習慣であり、できるだけ早急に身に付ける必要のあるものだと考えられた。予定を立てることと時間厳守の必要は、殊に重要だ。研堂は、商用でアメリカに旅立った日本人の逸話を紹介する。その日本人はアメリカのビジネスマンと約束をしたが、二〇分遅れて行ったところ面会を断られてしまう。「こんなことは、あちらでは、当り前なのですが、こちらでは、珍しがっておるです。彼と我と、国風の違ッてる程度が知れませう」。
明治政府は様々な西欧の制度を導入した。小学校であり、時刻制度であり、それは日本が欧米を模倣し見習う対象であった。時計そして時間厳守の態度は、いわば文明そのものであった。ここでその構図に変化が起きている。これまで欧米から学ぶばかりの日本人であったが、今や植民地下の人々に教える立場にある。欧米―日本―植民地という重層的な構造へと変わったことになる。因みに漫画では、ダン吉が現地で最初に導入した近代的な制度は軍隊であった。次いで上述の小学校、鉄道、診療所と続く。それはまさに、明治政府のもと日本が体験した「近代化」の過程そのものであり、漫画はその体験を植民地において再現したことになる。
角山栄は、日本において腕時計が使われ始めたひとつの大きな契機が、日露戦争(一九〇四~一九〇五[明治三七~三八]年)にあったことを指摘している。もし腕時計が戦争と密接にかかわりを持つ道具であったとするならば、子供たちを魅了し続けた奇想天外な冒険譚の背後にも、また軍事力が控えていた。
第十一章 農村の時間と空間 時間地理学的考察 荒井良雄
「近代」の人々の「時間」のあり方が、産業革命以降の大工場制生産様式に端を発していることは、よく知られている。たとえば、アメリカの地理学者プレッド(Pred, A. )は、一九世紀中葉のアメリカ都市を例として、それまで卓越していた家庭内での職人的な生産様式が、大規模な工場に多数の労働者を集めて大量生産を行う生産様式に取って代わられるにつれて、それまで個人や家族の意志に委ねられていた時間の流れが、工場の時間タクトに従った「時間規律」の下に再編成されていく過程を描いている。産業革命以前には、太陽の動きと家族間の緩やかな調整のみによって決められていた人々の時間の使い方は、大工場制生産様式の浸透と共に、組織が定めた生産のタイムスケジュールに厳密に従うことを求められるようになる。多数の労働者が関わる生産過程を混乱なく成り立たせるためには、個々人や個々の家庭の事情は斟酌されず、規則的かつ画一的な時間割を正確に守ることこそが価値と見なされるようにな る。 一度そうした価値観が定着すれば、「時間規律」は単に生産の場に止まらず、学校や家庭を含めた社会全般に広が ることになる。そのような「時間の近代化」の過程で、もっとも重要な役割を果たしたツールが、時計の普及であり、 定時法の浸透であることは、本書第四、十章でも述べられているとおりである。
ところで、産業革命にともなう生産様式の変化が近代的都市の発達を促したこともよく知られている。 多数の労働者が一カ所に集まることを前提とする大工場制生産様式の社会では、職住近接を旨とする都市職人の居住形態を維持することは困難である。労働者は労働の場から一定の距離を置いて住居を構え、そこに住宅地が形成される。そのための基礎的インフラストラクチャーとして鉄道網の整備が進み、住居と職場とを往復する「通勤」という活動形態が生まれる。それまで、徒歩圏のなかに生産と消費の場が雑然と混在していた都市空間に、職住分離と用途純化という 「空間規律」が持ち込まれるようになる。かくして、産業革命は時間と空間との両面において社会に規律をもたらした。
であるがゆえに、「時間の近代化」は「都市化」の文脈の中で語られる。ハンガリーの社会学者ザライ(Szalai, A. ) の主導の下で一九六〇年代半ばに実施された国際プロジェクトは、生活時間に関する実証研究の金字塔とされるが、 その報告書のタイトルに「都市および郊外住民の日常活動」なる副題が付されているのは、そうした事情を象徴している。
「時間」を「都市化」と重ね合わせる見方は広く認知されている。近代の日本にとっても都市化は一〇〇年来のたゆまざる流れであったから、日本人の時間意識を都市化の文脈で捉えてみようとするのはごく自然な立場といえよう。しかし、ここまで論じてきたように、「日本人の時間」は決して一元的な都市化の過程を経てきたのではない。いま、近代日本の時間意識の変化を「職業の都市化」と「空間の都市化」という二元論に沿って整理してみよう。
「職業の都市化」は、いうまでもなく、農民や職人が中心であった社会が、「都市的」な工場労働やオフィス労働に従事する人々で占められるようになっていく過程である。大工場に象徴される都市的労働は、人々の時間を同期化させるタクトを必要とし、そこに、定時法に立脚した都市的時間規律が生まれる。いったん成立した時間規律は、それ自体が倫理的価値観を付与されるから、「まっとうな大人」を育てるべき場である学校でも、工場の擬制としての時間規律が重要視される。
そうして社会全般に浸透していく時間規律にもっとも忠実な僕が、電波メディアである。電波メディアは時報と番組という共通化されたキューを津々浦々まで瞬時に送り届け、人々の生活リズムを定時法に沿って標準化し、同期化する。そのように同期化された生活リズムは、それ自体が準拠規範として機能するから、専業農家のように、職業的には定時法に合理性を見いだしえない人々ですらも、そのタクトに従うようになる。かくして、「職業の都市化」がも たらした定時法の時間規律は社会全体に貫徹する。
一方、産業革命によって出現した大工場制生産様式は、同時に、職住分離の空間規律を必要とした。土地や建物の物的空間と、人々の活動と意識の空間との両面にわたる「空間の都市化」の端緒である。しかし、「空間の都市化」は、 工場とその周りの労働者住宅地といった当初の素朴な姿を大きく超えて進展した。今日の大都市は、交通機関の長足の発達を前提として、巨大に膨れ上がり、農村やコンパクトな地方都市とは異質な都市空間を作りだしている。
少なくとも日本の大都市に限ってみれば、その都市空間の広がりは鉄道に支えられている。都市交通の手段としての鉄道は、その大量性、定時性において他に比肩するものがない。日本の大都市で、これだけ多くの人々が、これだけの距離を毎日通勤するといったことが可能なのも、郊外電車と地下鉄を統合した鉄道網が早期に整備された結果である。しかし、鉄道はその効率性の反面として、フレキシビリティに限界がある。鉄道の通勤輸送力を前提として広がった郊外住宅地は、通勤以外の諸々の移動にははなはだしい不便を感じる。 長距離通勤にくたびれきった亭主族はもとより、主婦や子供達も夜には外に出かけようとしないという事実は、大都市における活動空間の矛盾を表象して いる。なまじっか、大都市のあちこちに広がった社会ネットワークの広がりの中で、活動の空間的時間的調整が困難であることが、大都市住民の活動の多様性をむしろ低いものとする。いわば「電車の路線図と時刻表」とで作り上げられた生活のリズムが、大都市住民の時間意識の根底にある。まさに、「電車社会の時間意識」に他ならない。
むろん、大都市化だけが、「空間の都市化」ではない。 地方都市がそれなりの拡大を遂げる一方で、農村において 「職業の都市化」たる兼業化が劇的に進んだ背後には、モータリゼーションによる空間の制約の克服がある。 高度成長期に急速な普及を遂げた自家用車は、地方の生活を一変させた。バスを中心とした貧弱な公共交通と徒歩のみに立脚した活動空間の中で、大都市に比べて著しく限られた活動機会しか持ちえなかった人々は、モータリゼーションの進展によって、路線図にも時刻表にも縛られることのないフリーハンドを手に入れることになった。一〇〇%を超える自動車普及率と整備された道路網、渋滞の心配のいらない交通密度。それらを前提とすれば、人々の活動の空間的時間的自由度はきわめて高い。地方では、地域コミュニティが今もなお実質的に機能し、さまざまな活動の基盤をなしている。そのために、活動機会が比較的コンパクトな空間的範囲に収まっていることと相俟って、地方の人々は、一面では、大都市より多様な活動を実現しうる。地方都市や農村の充実した夜の活動が、それを物語っている。自家用車の自由さを前提として地方の地域社会に繰り広げられている生活のバラエティこそが、今日の地方住民が感じるリアリズムであろう。すなわち、「車社会の時間意識」である。
さて、「職業の都市化」と「空間の都市化」の双方を同時に体現する例を挙げよ、ということになれば、それは間違いなく、電車の「ラッシュアワー」ということになろう。画一的な始業時間、都心への一極集中、その他諸々が「痛勤ラッシュ」とも揶揄される現象を生んでいる。しかし、最近では通勤ラッシュも一頃ほどではなくなったように思える。もとより、膨大な建設投資を費やした輸送力整備を背景としたことではあるが、一方では、フレックスタイム制の導入やオフピーク通勤の啓蒙など、「時間の柔軟さ」ということが、社会的に価値を持つという意識の芽生えであるようにも思える。
産業における「脱工業化」が唱えられて久しい。しかし、産業革命を機に進行した時間の近代化は、未だ、「工業化」の段階を通り過ぎていない。工業化社会の硬直的な時間規律を再考し、「柔軟さ」をキーワードとした時間意識が浸透したとき、はじめて真の「脱工業化社会」が到来するのかもしれない。
文献解題 時間を考えるための五◯の文献 より
▼ゲルハルト・ドールン・ファン・ロッスム『時間の歴史―近代の時間秩序の誕生』大月書店、一九九九年。
中世から近代に至る機械時計の登場に伴う時間観念の推移を詳細に論じた著作である。ル・ゴフの論文以降の多くの歴史研究を踏まえ、近代的時間制度の誕生の経緯を丹念に説明した好著である。機械時計の誕生に伴う新たな時刻制度の創出、公共時計の普及と時計師の実体、またこの時刻制度の転換期における市場、教会、役所、学校などでの時間の使われ方が詳しく論じられている。時間賃金の観念の早い時期における登場についても記されている。
▼スティーヴン・カーン「時間の文化史(時間と空間の文化:1880-1918年上巻)』法政大学出版局、一九九三年。
一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて西洋社会に登場した新しい科学技術によって変容された空間と時間の観念をさまざまな側面から論じたものの時間編である。「時間の性質」「過去」「現在」「未来」「連度」という五つのからなり、それぞれのテーマにおいて、新しい科学的知見と技術的発明の成果が、哲学・芸術・文学にどのような影響を及ぼしたか、豊富な事例を引用して生き生きと語られている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
