
ビジョンを描くこと。ビジョンに囚われないこと。|起業研究室の研究2
すっかり年末になってしまったけれど、ONthe UMEDAで開催中の起業研究室。これもスタートしたのは遠い昔のことのようで12月に入ってからだった。写真は「人に指さしたらあかんねんで」と怒られそうですが、楽しく個別相談していた時のヤラセ写真です。
3か月の設計は3つのステップを踏んでいきます。
1.ビジョンを描く
2.ビジネスモデルを練る
3.マネタイズを設計する
もちろんこの3つのステップは直線的に上がっていくものではなく、実際にビジネスを始めてからも行ったり来たりをグルグルと繰り返しながら考え続ける要素。
第1回の「ビジョンを描く」演習は、特任研究員として臨床心理士(公認心理師)、キャリアコンサルタントの佐藤浩さんにお願いしました。ONtheで知り合ったのですがキャリア相談をするならこの方がNo.1お勧めです。ご自身は元新聞記者でありながら心理系領域の学び直しをするため大学院に行き資格を取得、現在は大手企業のカウンセラーをしながらフリーランスとして大活躍。
佐藤さんにプロフィール写真を依頼したら、普段のイメージとは違う強そうな写真が返ってきて「めちゃくちゃ強そうな写真ですね」とお伝えしたら「そうでしょ、フィリピンの闇ブローカーみたいやねん」と返してくれるお茶目な方です。返事が具体的すぎて、きっとフィリピンの闇ブローカーに知り合いがおるんだと思います。知らんけど。
自分自身に気づくこと
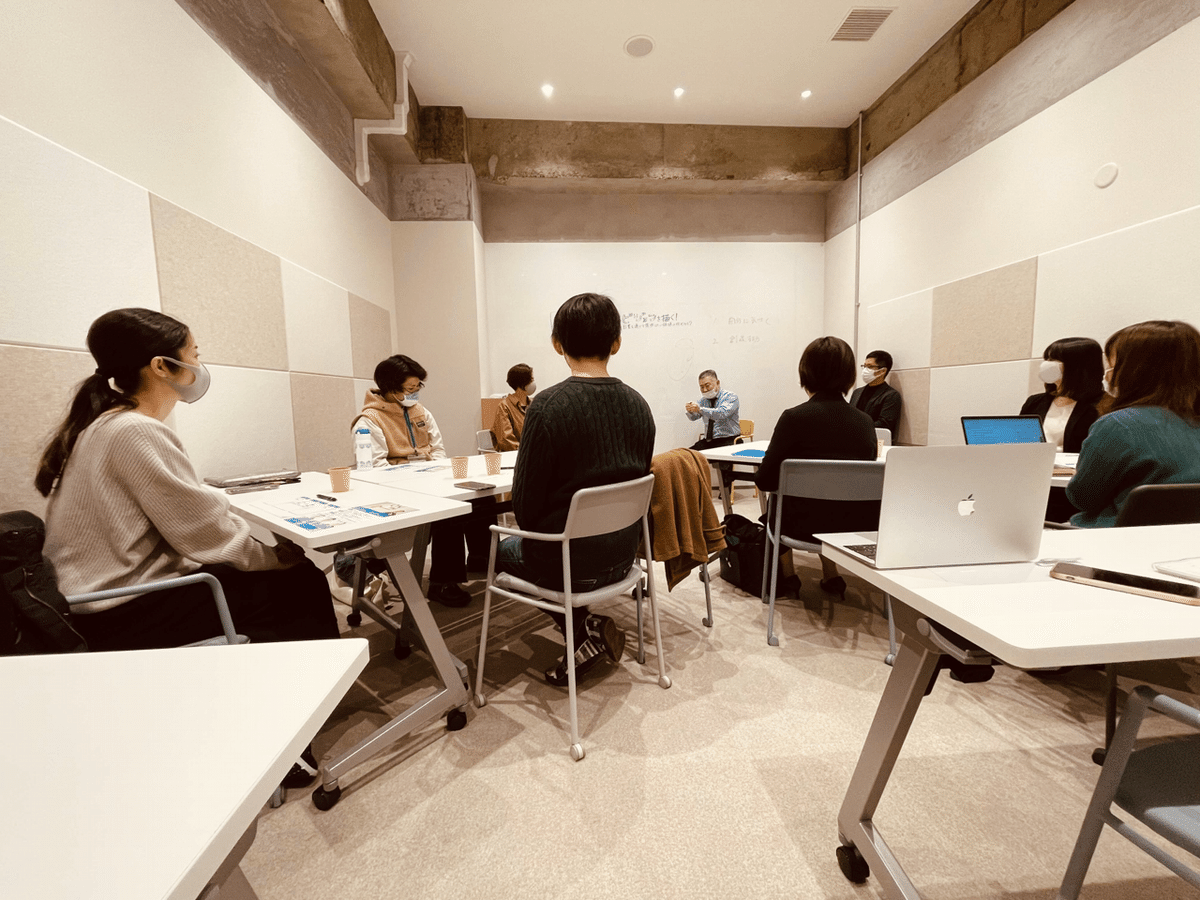
起業研究室では各演習の間に個別相談の機会を設けていて、佐藤さんに個別相談をした方に話を聴くと「グッとなっていたところが、ファーッっとなりました!!」という、まぁ身体感覚的な表現が返ってきました。もはや「よ、よかったね!」としか返しようがない。
佐藤さんがよく話していることは、まず一番最初の段階として「自分に気づく」ということ。佐藤さんからいろんな問いを投げかけてもらいながら対話をし、言語化する中で自分の言葉にしっくりいっていない感覚の部分がある。それが話しながら感じる違和感。その違和感に気づき、大切にするということ。
私もマインドフルネスであったり、コーチングであったり、気づきに関して様々な方からお話を聞きますが、やはりビジネスの入り口ではない心理を専門にしている方から聞く話は興味深い。
自分の話をすると、佐藤さんとの会話の中で「自分の仕事は何かということをまだきちんと言語化できていないし、あまり言語化しすぎたくない」ということを話していて。
ビジネスライクすぎる「コンサルティング」という言葉に違和感を感じて、今はよく「支援」という言葉を使っている。でも佐藤さんとの会話の中で佐藤さんがもつ「支援」と「コンサルティング」のイメージに触れながら、もしかするとやはり一般的には「コンサルティング」に近いのかもしれないと感じた。でもしっくりとくるのは「その人がポテンシャルを発揮できる環境を整えること。変化の担い手であること」という言葉なのだと。それを一言で表す言葉に出会っていないしあまり出会いたいとも思っていない。一言で表すことでその言葉にイメージが収斂されてしまうからだ。それは周りの人の見る目以上に、自分がその言葉に囚われてしまうから。だから相手が認識しやすいように資格名を出すことはあるけれど、自分=資格ではない。
というような自分しか興味がないようなことを普段から考えていて、それが自分の軸を形成するためにとても重要な時間だと思っている。大体において起業家や経営者は同じように「自分、自社はどういう存在か」を考えて続けている。それは答えを出すことが目的なのではなく、歩みを続けるために必要なのだろう。一番恐れているのは止まってしまうこと。思考停止しないためにビジョンについて考え続けることが大事なのだと思う。
それは何か大きな環境変化があったときにも、「自分は何を提供すべきか」ということに立ち返る軸になる。なかなか一人ではそうした自分自身の考えに気づくことはできないので、他者との対話を通じてそうした自分に気づく過程をこの起業研究室では提供していきたい。
創造力を発揮すること

こうした「自分に気づく」ことと合わせて「創造力を発揮する」ということが「ビジョンを描く」演習で佐藤さんが伝えたかったこと。
たとえば「多様性のある社会をつくる」などきれいな言葉をつくることが「ビジョンを描く」ことでは決してない。その言葉に至るまでの過程が一番大事であり、周りの人が関わることができる余白になる。
多様性とは何か、なぜそれが必要だと思うのか、どうして自分がそれをしようと思うのか。そうした話をきれいに整理せずに他者にすることでまた新たな気づきが得られ、ビジネスアイデアにフィードバックできる。
「自分に気づく」ということは誰しもに大切なこと。起業を考えている人にはそれに加えて「創造力を発揮する」ことが求められている。そうした創造力をかき立てるようなワークも交えながらの演習でした。なにより楽しかった。
ビジョンに囚われないこと
「まだ自分がどうなりたいとかないんです」
そう話をする人も多い。当たり前だと思うし、早くから「自分がどうありたいか」が固まりすぎている方が、それはそれで視野が狭いと思う。僕の周りには「この人は何をしているかよくわからない」という人が結構いて。でもみんなとても楽しそうにどこまでが仕事なのか遊びなのか境界線が分からないような動きをしていて謎の魅力がある。彼らは何かしらの軸を持ちつつ走りながら自分のやりたいことを見出しているのだろうと思う。
かたや「自分の故郷の過疎地域を活性化したい」という明確な想いをもってアクティブに動き出す若者も多く知っているけれど、小さく収まりすぎているケースも見受けられる。自分はどうありたいか、考えてみることはとても大事だけれど、ビジョンに囚われすぎずいろんな方向に走り続けることも大事だろう。もっといろんな人と話してみるのがいいと思う。
「自分がどうありたいか。どんな価値を提供したいか。」それを考えるのは目的ではなく手段でしかない。今の自分が思いつく限り考えてみる。それはくさびを打つことに似ている。そこまで背伸びして考えてみて、それをまた誰かに話したり、その想いをもって仕事に向き合う。そうすると、次第にまた新しい言葉が頭に浮かんでくる。そこでまたくさびを打つ。その繰り返しで進んでいけると思っている。
だからこそ、「今こう思っている」ということを大事にしながら、そのビジョンに囚われすぎないことも大事。
起業研究室に参加してくれている山下さんが今考えていることをnoteにしてくれました。
透明感のある文章に触れて刺激された。せっかくの年末年始の機会なので、ゆっくりと自分の気持ちに気づく時間をとろうと思います。
そして起業研究室演習2は2021年1月14日(木)19時~20時半予定。「ビジネスモデルを練る」です。今のところ新規に申し込み受付はしていないのですが、またリクエストをいただければ開講したいと思います。
どうぞよい年末年始をお過ごしくださいませ。
みなさまのサポートがとても嬉しいです!いつも読んでいただいてありがとうございます!
