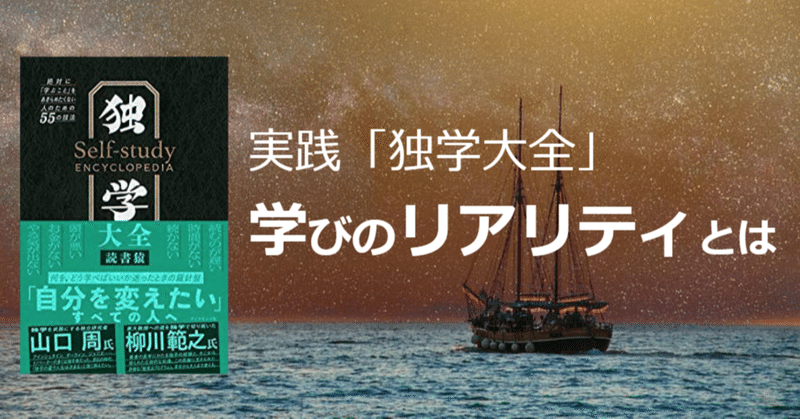
実践 #独学大全 学びのリアリティとは
ども、しのジャッキーです。2022年にじっくり取り組もうと思っている課題図書がいくつかあります。その一つが「独学大全」です。788ページというかなり分厚い一冊です。2021年は「世界標準の経営理論」に5ヶ月ほどかけてじっくり読んで非常に有益だったので、その2022年版の一つです。
本書は、タイトルにある通り、独学のための55の技法が紹介されています。前回の記事では技法1-5からの学びをまとめるといいつつ、技法1からの学びをじっくり書くことになりました。そして、今回も技法1の深堀記事となります。
技法1-5
1.やる気の資源を掘り起こす「学びの動機付けマップ」
2.学びの出発点を見極める「可能の階梯」
3.学びの地図を自分で描く「学習ルートマップ」
4.未来のミニチュアを組み立てる「1/100プランニング」
5.重い腰を蹴っ飛ばす「2ミニッツ・スターター」
前回記事
1.やる気の資源を掘り起こす「学びの動機付けマップ」

一つ目は重たいテーマです。そもそも自分が「学ぼうと思ったのはなぜか?」を振り返り、その出来事がどんな影響を自分に与えたのかを見える化し、それぞれの影響の評価とその理由づけをする、という技法です。
この技法を活用するにあたって「自分が学ぶ動機となったことは何か?」という問いに対して書き散らかしたメモが以下です。

過去二回の振り返り
前々回の記事では、上記の一番あたまの中学受験について書きました。ということで、私の学びの原点は中学受験にあり、その経験から、
自分の周囲の環境が変化したとき、道を定め、学ぶことで望ましい環境は勝ち取ることができる
という考え方を私の心の奥の方に埋め込んだのだと確信した、という話を書かせていただきました。
そして、前回の記事では、中学受験で入った中学でいきなり数学と英語で赤点を出したときに、担任&英語教師の先生から言われた以下の言葉が、へこんでいるときの元気の素になっていることをご紹介しました。
篠崎君、大丈夫。これからは上に上がっていく以外ないから。
大学時代を振り返る
さて、今回は大学時代を振り返りたいと思います。

読書家&旅人xxxへの憧れとあります。これは別に、ベタぬりの必要もなかったかもしれません。過去に何度か本noteでも紹介しているPodcast「ホンタナ」のパーソナリティの一人タナカ君のことです。
読書家&旅人なタナカ君
彼は大学時代からの親友なのですが、いつも何かしらの書籍を読み、そして、長期休暇というと山へ旅に行く。時に、海外にも登りに行く。そして、渡航先の山で高校の友人にばったり出くわす。

そんな彼の冒険の話を聞くのが大学時代の一つの楽しみでした。時に、こんな断崖絶壁なところにテントを張るんかい!という写真を見せられたりしたものだ。山道具屋でバイトもしていた。いろいろな登山にまつわるの道具の話をしてくれた。私は、山にこそいかなかったが、登山の雑誌を眺めながら、CGじゃなくて、本当にこういうところにいくやついるんだよなぁ、と思っていた。
また、彼はただの登山好きでもなかった。森林整備のサークルに入っていて、よく上高地などにいってゴミ拾いやら登山整備やらもしていたようだ。当時、趣味はギター。サークルにも入らず、バイトしたお金でCDを買うか、ライブに行くか、ギターマガジンやヤングギターを買うか、そんな生活をしている私には、彼がまぶしく見えたものだ。
文武両道という言葉がある。学道も武道もできること。タナカ君は、本を読み、知った世界に飛び出していく。本の中の世界と現実の世界の行き来によって、世界がリアリティを持つ。
Podcast「ホンタナ」の中でも、パーソナリティのナリタ君とのやり取りで、「よくいろいろな引き出しからコメントができるものだ」と感心するのだが、それは、そうした2つの世界の行き来から彼の中に形成されたリアリティがあるからこそできることなのだと思います。そして、それが人物としての魅力につながっているのです。
今回の学び
学びとは、実践を通して初めてリアリティへと変容する。
そして、リアリティこそが人の魅力の源泉である。
おわりに
以下の実践「独学大全」というマガジンにこういった記事をまとめているので、もしよかったらのぞいてみてください。本記事への「スキ」やアカウントのフォローをしてもらえると励みになります!
「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標にnoteを更新してますしのジャッキーでした。
Twitter: shinojackie
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
