
明解「日本だんじり文化論」①
令和3年7月17日(土)のYouTubeライブ+オフライン企画「明解・日本だんじり文化論」(https://note.com/shinobue/n/ne04a8f39ca17)に先だって、当日の簡単な予習も兼ねて、『日本だんじり文化論』(創元社)の読み解きを行なって参りたいと思います。何回かに分けて、章ごと、あるいは、項目ごとに、伝えたいことを記しておきます。〔 〕は本書のページです。

表紙
表紙の地車の絵は、松川半山の下絵を昭和初期に模写したものを、加筆修正して着色したものです。メインの絵は、やはり地車が大きくあった方が良いとだろうと、l私と編集部とで意見が一致しましたが、選択肢は二つしかなく、一つは、有名は『摂津名所図会』の坐摩(いかすり)社の夏祭の図〔57P〕。ただ、この絵は、少し地車の歴史に興味のある人にとっては、お馴染み過ぎる図ですので、他のものを、ということで、松川半山の絵となりました。
前著『日本の祭と神賑』では、地車の舞台で、天岩戸のアメノウズメ(お多福)と思しき舞が、笛と胴拍子という雅楽や浪速神楽を彷彿とさせる音曲とともに描かれているので、かつては、神楽に準じる芸能が地車の上でもなされていた可能性がある、と示唆しましたが、これは、間違いでした。この絵は、忠実な往時の地車の姿というよりも、地車の特徴やルーツを暗示する「絵解き」になっていたのです。〔78P〕に詳述しております。この部分は少し話が込み入ってきますので、以下の要点を押さえていただければと思います。
・大屋根の扁額に「ニワカ(二+○×2)」の文字が見える(地車は滑稽寸劇・ニワカを演じるための舞台であったことを示唆)。
・本来なら扁額には「天満宮」とあって然るべき(飾幕に「堂」の文字が見えるので、天神祭の天満宮氏子の堂島米市場の地車であることがわかる。
・ところが、舞台で披露されているのは真面目な神楽である。
・ニワカの指南書ともいえる『古今俄選』には、ニワカの始まりは、日本神話の天岩戸の庭神楽(ニワカグラとニワカを掛ける)と大真面目にボケる。
・地車の舞台で天岩戸の神楽が舞われたわけではなく、この絵は地車の縁起を巧みに語っている。
地車は、ニワカを演じるための移動式芸能舞台であることは、この他の文献や絵画などからも明らかですが、それが事実であったことが、この「絵解き」で確実となりました。
帯
本書には、膨大な情報が詰め込まれておりますが、最も伝えたいこと、あるいは、それが興味を惹いて本書を手に取ってもらうきっかけになることは何か、と考えて作成したのが、帯の裏面です。
こちらの絵に記されているように、地車は「川御座船」と「俄(ニワカ)」が偶然に近い科学反応を起こして誕生しました。偶然、とはいいながら、それが生まれる素地は、享保(1716~36)という時代にありました。第一章の主題は地車の誕生です。
前著『日本の祭と神賑』でも、地車のモデルが川御座船であることは、論証しましたが、それではなぜ、船が船であるための「船体」が地車には存在しないのか、という、かなり重要な問題を解決できずにいました。今回の本では、それに答えを出しております。詳しくは、第一章をお読みいただければと思いますが、
・地車は、あえて、船体を持たなかった。
というのが、本書の結論です。その結論に達するに至ったきっかけは、絵画史料に出てくる流し俄に必須の「俄行灯(にわかあんどん)」と手持ちの「吹き流し」です。
まえがき・あとがき
「まえがき」では、第一章、第二章、第三章、終章、それぞれの概要を述べていますので、まずは、こちらをお読みください。また、以下の二点を押さえて上で、本書を書き進めたことを述べています。
・全国の都市祭礼の起源を祇園祭に求める向きがあるが、地車は、祇園祭の山鉾とは、まったく系譜の異なる大坂独自の文化である。
・これまで発刊されてきた地車関連の書籍は各論に留まり、市町村史に喩えるなら、資料編は多く刊行されているが、本文編は企画すらされていない状態であった。本書は、このような地車研究の現状を憂い、地車研究を次の次元に推し進めようとするものである。
「あとがき」では、なぜ、私がここまで、こだわって地車研究に執着してきたかということを語っています。私、個人としては、この「あとがき」をもって、アイデンティティ・クライシスからの回復がなされたといっても過言ではありません。
巻頭カラー(前半・後半)
出版社の努力もあって、この価格帯の書籍にしては多い40頁近くのカラー頁がございます。前半は、ほぼ絵画史料です。江戸期の色付きの絵画史料は、ほぼ網羅しているはずです。本文に入る前に、こちらをご覧いただくと、地車の誕生(第一章)と隆盛(第二章)で述べたい世界観を直感的に把握いただけます。
後半は、各地の現在の祭の写真を可能な限り掲載しました。本書の構成上といいますが、私の能力の限界もあって、祭の熱狂という、祭が祭である重要な側面を文字で表すことに苦労しています。中途半端に文中に心象描写を入れるよりは、写真で表現した方が良いとの結論に至りました。それでも、本文の論を進めていく上で、雰囲気だけでの写真ではいけないので、やや説明的な構図のものが多くなっておりますが、ここから、本文からは感じられなかった祭の熱量を感じていただければ嬉しいです。
参照指示
今回の「だんじり文化論」は、一直線に筆を進めて論じられるようなものではなく、三次元、四次元的に、網の目のように各要素が関連しています。それを文字通り「紐解き」ながら話を進めていかねばなりません。そのため、随所に「○章〇節を参照」「巻頭口絵○頁参照」といった指示を添えています。中々骨の折れる作業でしたが、これは読み手にとって便利なガイドとなるかと思います。
年表
年表の有無で書籍の完成度が変わってきます。頁数も限られており、また、本文に登場する事項すべての掲載しても混乱を招くだけなので、取捨選択に苦労しましたが、何とか地車年表を完成させることができました。年表を追っていただければ、地車の誕生・隆盛・展開の大筋をイメージいただけるかと思います。
さくいん
索引の作成は、本文執筆後、さらに校正の後になります(ページ数が変わる可能性があるため)。肉体的にも精神的にも限界に達しているタイミングでの作業となるので、おもわず妥協しがちなのですが、粘りに粘って項目を拾い上げました。特に、本文中に出てくる文献史料と絵画史料を索引で拾えたことは良かったです。異なる頁で同じ史料を参照することが度々ございますが、特に絵画史料の場合は、一ヶ所にしか掲載できません。その他、神社名をはじめ、重要な語句を索引で拾っております。是非ご活用ください。
以上、『日本だんじり文化論』を読破するための手引きとなれば幸いです。

〔8P〕の「だんじり相関図」は、本書の内容を凝縮したものです。本文を通読の上、あるいは要所要所で確認いただければと、迷子にならずに読み進めることができるはずです。
『日本だんじり文化論』(創元社)お求めはこちら
→ https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4261
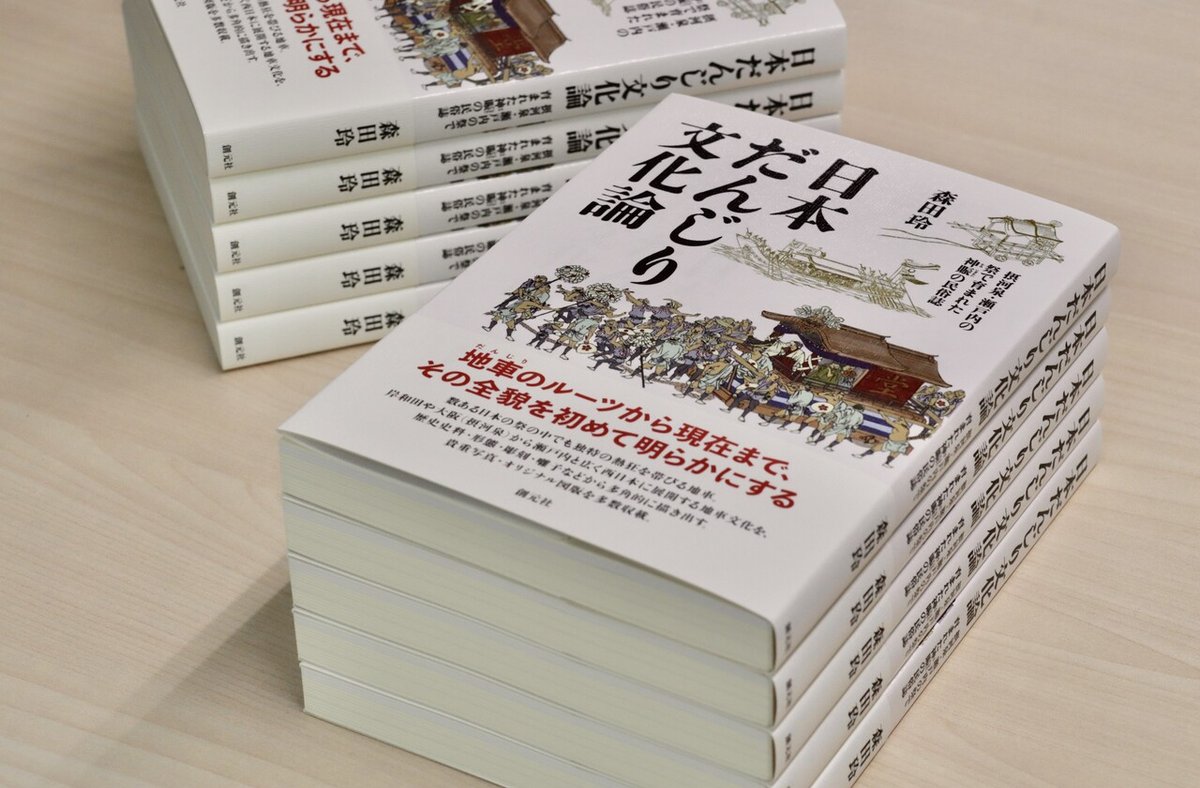
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
