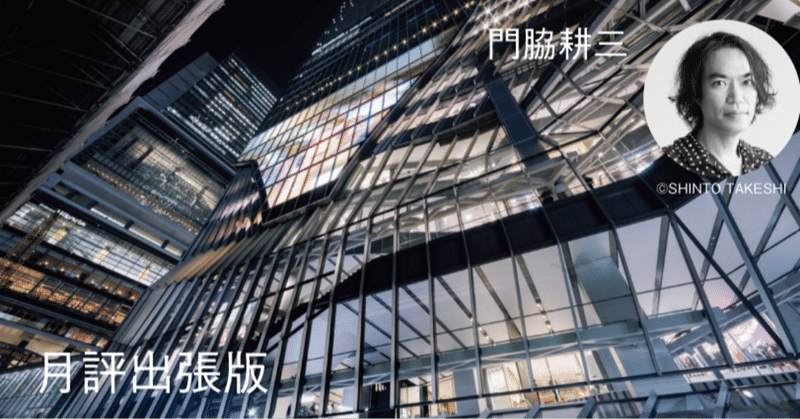
異質な要素の集合体─『新建築』2019年12月号月評
「月評」は『新建築』の掲載プロジェクト・論文(時には編集のあり方)をさまざまな評者がさまざまな視点から批評する名物企画です.「月評出張版」では,本誌記事をnoteをご覧の皆様にお届けします!
(本記事の写真は特記なき場合は「新建築社写真部」によるものです)

2020年の東京
2020年である.焦土から再出発した日本の都市と国土の復活を,東京から世界に向かって宣言する機会となった1964年の東京オリンピック.その記念すべき祭典が,成熟した東京で再び演じられようとしている.進歩主義的な近代化路線の絶頂を,国を挙げて祝った1970年の大阪万博からは半世紀が経つ.万博後の進歩主義の行き詰まりに伴う混乱と,それまでの路線からの転換の決意をうやむやにしたバブル景気の狂騒を経て,不況と災害にあえいだ平成は終わり,ついにわれわれは,昭和の幻影も手が及ばない新しい時代を迎えた.2020年は後世の歴史家から,日本が次の歴史的段階に至った年だと位置付けられるに違いない.しかし明るい材料はまったく見えない.ネットには「世界に先駆けて人口減を経験する日本こそチャンス」だとか「製造業に固執し情報化に乗り遅れた日本こそスマートシティ化の波を捉えられる」などといった「ピンチはチャンス」論法の日本再興論が踊っていて,状況が暗いことをかえって露呈させている.こういう時こそ,それぞれが目の前の課題に地道に取り組むことが重要なのだろう.
その意味で渋谷の再開発にはいくぶん救われる思いになる.ひとりのユーザーとしては,2013年の東急東横線の地下化以降,渋谷はもっとも立ち寄りたくない街だった.京王井の頭線から東横線に乗り換える時など,延々と歩かされた挙句,造形以外の意味を持たなさそうなGRCの卵型に遠回りさせられれば,悪態のひとつもつきたくなるのが正直なところである.しかし渋谷スクランブルスクエア第I期(東棟)の開業によって,この状況は劇的に改善された.そのために膨大な検討が行われて大量の図面が描かれ,それを物理化すべく自らの身体を駆使してコツコツとモノを移動させ,構築へと至らしめた人たちがいることを思うとほんとうに頭が下がる.世界を変えているのは,地道な作業の積み重ねにほかならない.
そういうわけで新しくなった渋谷をさっそく訪れた.平日の日中だったせいか喧噪も落ち着いていて,アーバン・コアを介した移動はとてもスムースで感動さえ覚える.それは以前のストレスフルな渋谷からすると霞が晴れたかのような体験なのだが,そこにはどこか猥雑な印象も忍び込んでいる.新品の街にふさわしくないこの印象は,アーバン・コアを貫く独立柱と揺らめくカーテンウォールに由来するのだろう.垂直方向の人工の谷間にいきり立つファリックな柱と,そこにまとわりつく柔らかなヒダ状のカーテンウォール――よく見るとなんとも卑猥なこの形象は,ある意味において渋谷的と言ってよい.渋谷の谷間がつくる影には,今も猥雑な欲望がしぶとく渦巻いている.一方でこの形態は,法的な規制やインフラの取り付きなどから工学的にも根拠付けられている.しかしその最大の根拠は,言うまでもなく渋谷の地形なのだろう.このアーバン・コアは,地形によって揺らぐインフラの線形や街区の形態と,そこに生じる高低差に翻弄されつつも,それらを調停する存在である.

異質な要素の集合体
渋谷スクランブルスクエアに見られるように,都市が抱える背景を前景化させ,空間に固有性を与える方法にはとても共感できるし,今後の都市開発においては必須となるに違いない.では,都市の固有性をつくるものとは何か.地形や歴史に裏付けられたコンテクストなど,一定の時間に耐えた都市の要素はすぐに思い浮かぶ.加えて,建築論壇:都市をつくるで内藤廣が指摘するように,建築家という個性を備えたデザインの主体も,都市の固有性を高める要素になるのだろう.渋谷の再開発においては,建築家の参加を実現させるために,デザインアーキテクトと呼ばれる方式が採られたというが,一方で,このようにさまざまな主体が複雑に協働するプロジェクトは,建築作品とは何かという問いも投げかけているように思われる.どういうことだろうか.
建築の作品性は,ひとつには,それを構成する物理的な諸要素の,強い統合によって生じると考えられる.建築作品の主流が長い間,新築であったことは,ある瞬間にひと続きの空間的領域をつくり上げる新築という方法が,この統合性と親和的だからだろう.また,こうした統合は,単一の人格的主体を通じて果たされることが一般的であるとされてきた.その人格的主体こそ建築家にほかならないのであるが,しかし12月号にさまざまな協働が見られるように,現在ではひとつの建物をひとりの建築家が専制的にデザインするという図式は自明ではない.さらに言えば,ひとつの建物は統合的にデザインされるべきだとする暗黙の前提が,そもそも揺らいできているようにも思える.特に渋谷スクランブルスクエアのように,延床面積が20万㎡近い巨大プロジェクトではなおさら,ひとつの完結的なデザインとしてパッケージされる根拠は不明確になる.都市を飲み込むかのような巨大な建物は,ジェイン・ジェイコブスを参照するまでもなく,都市と同様に,むしろ多様で雑多な要素で構成されるべきなのだ.
ここで改めて渋谷スクランブルスクエアを眺めてみると,キュービックなガラスのタワーに対して,揺らぐアーバン・コアが亀裂を入れるように取り付き,この異質な文法の衝突によって,建物としての完結性も大きく揺らいでいることが分かる.このアーバン・コアの存在は,低層部ではどのフロアにいても感じることができて,均質になりがちな超高層ビルの中間階に都市的なノイズを体験的なレベルでもたらすことに寄与している.またアーバン・コアのデザインは上階に向かうに連れて変奏されて,屋上では透明な展望台へと姿を変える.展望台の様子は,その眺望性の高いデザインのおかげで地上からもよく眺めることができるのだが,それは結果として,スクランブル交差点のずっと上空に人混みが見えるという異様な光景を都市に産み出している.ここには異質な要素を都市にばらまくさまざまな仕掛けが組み込まれていて,したがって渋谷スクランブルスクエアは,統合性ではなく,異質な要素の集合体であることが志向された建築であると言ってよいだろう.しかし,だとするならば,異質な主体による異質な要素の集合体を,ひとつのプロジェクトに繋ぎ止めている枠組みは何か.形態的な統合を半ば積極的に放棄したかのような建築が,それでもひとつの建築作品たり得るのであれば,おそらくどこかに非-形態論的な統合のロジックと方法が隠されているはずだ.ひとりの属人的主体を通過することによる統合の道は既に絶たれている.統合の主体は不可視のシステムへと移行してしまったなどとニヒルぶるのも生産的ではない.その意味で,時には衝突も伴っただろう,そのメタレベルでの統合の過程には非常に興味をそそられるのだが,誌面からは詳細が分からないことが惜しまれる.12月号では,他のプロジェクトについても,多かれ少なかれ同様の感想を抱いた.
最後に,この原稿自体も協働の枠組みの産物であることを付記しておく.本稿は,筆者が主宰する研究室に所属する長谷川敦大,大栁友飛,磯野信,伊藤公人,小松素宏,佐塚有希,十文字萌,鈴木遼太との対話に基づいており,とりあえず今年度いっぱいは,彼らと一緒に議論を組み立てていくつもりでいる.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
