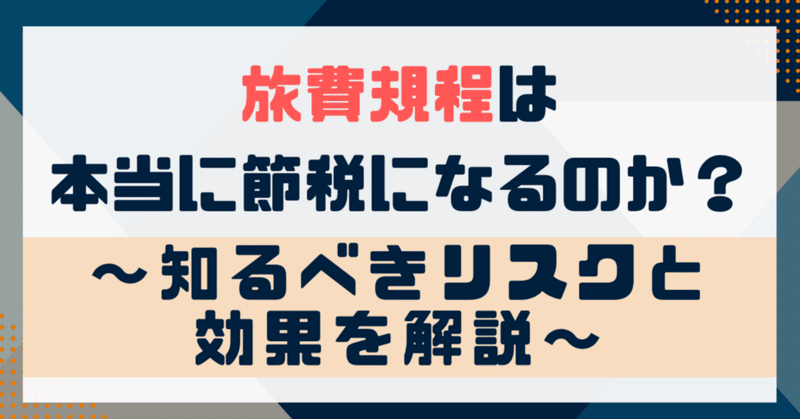
旅費規程は本当に節税になるのか?~知るべきリスクと効果を解説~
はじめに
こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。
法人化して旅費規程で節税、というテクニックを聞いたことがある方は多いのではないかと。
昔から節税策として有名ですが、本当に事業者が望んだ結果をもたらしてくれるテクニックなのでしょうか。
この記事では、旅費規程の税務上のルールはもちろん、旅費規程節税を導入する場合の注意点を網羅的に解説していきます。
旅費規程節税の内容
巷に出回っている旅費規程節税をまとめると、
法人側で旅費が損金(経費)になる
役員や従業員に所得税非課税で資金移動ができる
法人側で旅費を消費税の仕入税額控除の対象にできる
役員や従業員の社会保険料の削減になる
つまり、所得税、法人税、消費税、社会保険料の4つを削減できるという、一見ウルトラCのようなテクニックです。
図にするとこんなイメージかと。

そこで、なるべく多額の旅費日当を出す旅費規程を作って、最大限節税効果を狙おうというのが旅費規程節税です。
税務上のルール
旅費規程節税で特にキモとなるのは、上の図のうち②の所得税非課税で会社から役員に資金移動ができる点です。
これに関しては所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3が根拠になっています。
参考程度に下記に記載しますが、法律は読みにくいので無理に読まなくても大丈夫です。
第9条 非課税所得
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
・・・
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
要するに、
役員や従業員が業務で旅行をするにあたって
現地でご飯を食べたり日常品を買ったり、バスやタクシーに乗ったりするための費用を
合理的に見積もって定額で支給しても
結局業務のために使うから課税すべきじゃないよね
という考え方です。
なので、会社から旅費規程に沿って支給される金品は、役員や従業員を通じて、旅行で利用したサービスを提供する事業者の懐に入る、というのが前提です。
つまり、役員や従業員は旅行で払ったお金を支給してもらうだけなので、トクをすることは想定されていません。
これを実費弁償ともいいます。
もう一度図にするとこのようなイメージです。

そして、実費弁償であっても、特定の役員や従業員のみに支給している場合は、特定のその人物に対する給与と同じなので、全員にバランスよく支給すること、それから、同業他社と比較して通常の旅費だと認められる(豪華すぎない)範囲であることが要件とされています(所得税基本通達9-3(1)(2))。
国税不服審判所の裁決例
この旅費規程節税が認められなかった裁決があります。
その裁決をかいつまんで紹介すると、所得税法は
旅費の支給を受けてもそれは本来、旅行により消費されるものであること
支給金額と旅行実費との間に若干の差額があっても、それは僅少の差に止まること
が認められれば課税しない、としていて、逆をいえば、
実際は旅行していないのに支給していること
結果として役員や従業員に多額の利得が生じていること
同業他社と比較して支給する金額がかけ離れていること
のような事実があれば非課税とはならない、という判断を示しています(平15.9.12大裁(諸)平15-13)。
これが国税の見解です。
なので、旅費規程節税をしているのに、上の太字のような事実や処理が見つかると税務署の指摘を受けることになります。
たとえば、旅費規程による支給が2万円なのに、実際に使った旅費は1万円だったら、役員や従業員は出張をするごとに1万円トクをしていしまいます。
これは先ほど説明した所得税法の趣旨から逸脱していますよね。

もし旅費規程節税が否認されたら
では、先ほどの裁決例のように、旅費規程節税が認められなかったらどうなるか。
税務上は、①所得税、②法人税、③消費税の3つの税金を追加で払わなければいけません。
①所得税は、会社から役員や従業員に支払われたのは旅費の精算ではなく給与という扱いになるので、源泉所得税を追加で納付することになります。
②法人税は、役員への支給の場合は役員給与の扱いになり、法人の経費の範囲外になるので、経費が減り法人税を追加で納付することになります。
③消費税は、旅費日当であれば仕入税額控除が認められますが、給与になれば仕入税額控除が認められないので消費税を追加で納付することになります。
②と③に関しては、法人側で法人税と消費税の修正申告書を提出しなければいけません。
ついでに、過少申告加算税や不納付加算税という制裁金を払う必要が出てきます。
その税率は増えた税額の10%前後です(タイミングや種類等により差あり)。
あとは、延滞税という納付が遅れた分の利息も支払わなければいけません。
このように、追加で払うことになる税金が多くなれば、本来払わなくてもよかったお金を多額に払うことになります。
旅費や日当が否認されない相場感
そんな無駄な制裁金を払わずに済むようにするためには、一般常識の範囲内で旅費や日当の金額を決める必要があります。
ただ、残念ながら税法に「この金額なら絶対大丈夫」という金額がバシッと規定されているわけではありません。
そこでひとつ参考になるのが、産労総合研究所が実施して公表している「国内・海外出張旅費に関する調査」です。
これの2019年度版によると、
日帰り出張の日当を支給する企業は84.2%。平均支給額(距離・時間・地域区分がない場合)は,部長クラス2,666円,一般社員2,094円
宿泊出張の日当を支給する企業は91.2%。平均支給額(全地域一律の場合)は,部長クラス2,900円,一般社員2,355円
宿泊出張の宿泊料(全地域一律の場合)の平均支給額は,部長クラス9,835円,一般社員8,605円
となっています。
もうひとつ、参考になるのは国家公務員の日当です。
国家公務員に支給する日当や旅費は法律(国家公務員等の旅費に関する法律)で決められています。
それによると、最高位である内閣総理大臣の日当は3,800円、宿泊料は19,100円、食事代は3,800円になっています。
内閣総理大臣と民間の役員や従業員とを単純比較することはできませんが、税務調査ではこれらの指標を武器に出してくる可能性があることを念頭に置いておいてもよいかと思います。
旅費規程節税の効果
先ほど解説したとおり、税務署に否認されないためには、実際に旅行を伴う出張の事実があり、旅費の精算をしても個人に多額の利得が生じないように支給金額を決める必要があります。
つまり、無税で個人に資金を移転することが目的だと、旅行を何度も繰り返して少ない金額をコツコツ積み重ねるしかないんですね。
内閣総理大臣と同じ日当3,800円を支給するとしても、これを毎回ちまちま貯めるために無駄な旅行をするなんてことはありえませんよね。
宿泊料や食事代から生じる差額も同じです。
そんなことをしている暇があったらさっさと本業で稼いでしまったら早いはずです。
ましてやコロナ後はリモートワークが台頭してきたこともあって、出張が不要なビジネスが増えたのではないかと。
本当に旅行が多い業種なら旅費規程を導入する意義はありますが、自分のビジネスモデルをよく考えたうえで導入の有用性を考えていただければと思います。
まとめ
旅費規程節税に限らず、節税をするときには、それが法律や制度の趣旨に逸脱していないか考えみることをおススメします。
逸脱している場合は、リスク満載の節税テクニックである可能性が高いからです。
ご自身のビジネスとお金を守るためにも、今回お伝えした内容を踏まえながら節税情報とうまく付き合っていただければ幸いです。
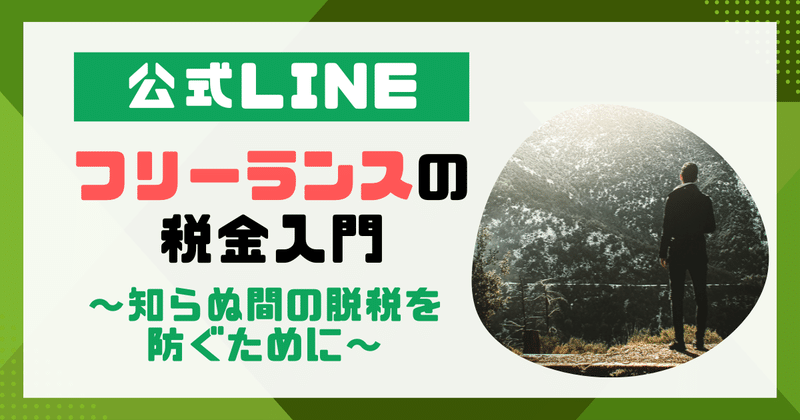
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
