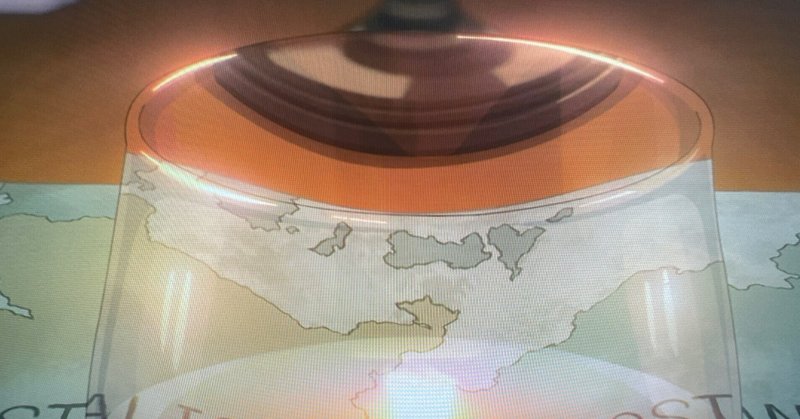
アニメのワイングラスに見る“世界の裏側”
ビジネスに役立つデザインの話
ビジネスに役に立つデザインの話は、こちらのマガジンにまとめています。
今回の話は、意外なほどにビジネスに直結した話です。
アニメに登場するワイングラス
アニメに限った話ではないのですが、わかりやすくするためにアニメに限定しています。まずはこちらのシーンをみてください。

このグラスのリム(縁)には、ぼてっとした膨らみが描写されています。この膨らみは、機械を使って作っている、マシンメイドのグラスの特徴です。しかしこの場面は、なんだか偉いひとたちの集まりの場でした。そこで使うグラスなら、マシンメイドでももう少し精度の高いものを使うかもしれないし、ハンドメイドのグラスを使うかもしれません。しかしグラスの向こうの風景の歪ませ方や光の反射などはものすごく凝っています。
同じアニメ『スパイ×ファミリー』の別のシーンがこちらです。

ちょっと興味深いのですが、皿や水を入れたグラスに対して、ワイングラスの描写がちょっと甘いんです。登場している女性は、マフィア的な組織のボスの娘で、場所は高級レストランのはずです。であれば、ワイングラスもそれなりに(手吹きじゃなくても)良いものを使うし、注がれるワインの量はもう少し少なく、そして肘をテーブルにつくのは、レストランに慣れているはずの女性ならまずしないはずの行為です。
(まあまあ難癖みたいに聞こえるかもですが、もっと良い例を引っ張り出してくる余裕がなかったので、すみません。)
つぎにこちらを御覧ください。


2枚めはワイングラスではありませんが、グラスの薄さがうまく描写されています。1枚目は、ちょっとマニアックな描写なんですが、このグラスが使われているのは、無重力空間なんです。そのため、特殊なつくりなっていて、グラスが二重構造になっていて、一部だけ縁まで流れれる空間があり、そこを伝って液体が飲めるよになっています。仕組みがよくわからないかもなので、こちらの動画で、無重力で使う新しいグラスのあり方が示されており、これを反映したグラスになっています。
ワイングラスの向こうに見える“世界の裏側”
実は、今回例につかったグラスが好例ではなかったこともあり、腹落ちがいくぶん弱いかもです。それでも、アニメに限らず、映画やドラマの描写にこれから語るものに当てはまるシーンを多々見つけることができると思うので、話を続けていきます。
デーブ・スペクターさんだっと記憶しているのですが、テレビ番組か映画かについて、「良いものを知らない人は良いものを描写できない」という主旨のことを発言していた気がします。じつは、これ、映画などにおいて、美術監督という人が担う仕事です。
さきほど例がそれほど良くないと断りましたが、『スパイ×ファミリー』においけるグラスの描写が「良いものを知らない人は良いものを描写できない」という例とはちょっと言い難いところがあるからです。しかし、それでも、そのグラス、姿勢は、高級レストランと合致しないぞ!というというところはあるんです。それほど細かい描写をする予算(お金だけじゃなくて時間も)がないからじゃないか?といえば、そうじゃないはずなんです。なぜなら描写全体には、けっこうコスト(手間暇)がかけられているからです。
描写にはコストをかけているのに、描写されるものにコストがかけれられていない
というのが今回のテーマの切り口です。そこから見える“世界の裏側”とは、描写をする監督、美術監督が、ワインや高級レストラン、ラグジュアリーホテルのスタンダードを「知らない」ということです。誤解されたくないのですが、高級レストランやラグジュアリーホテルは、「金持ちの世界」というフレームでくくられたものではありません。うまくタイミングを見計らえば、東京のラグジュアリーホテルに5万円以下で宿泊できます。食事ならもっと少ない予算で体験できます。それは、自分たちが描写する世界の精度をあげるためのコスト、と考えるならば、少なくとも、美術監督だけでも、そのコストはかけておいたほうが描写の精度が高くなるはずです。
先のアニメはさほど悪い描写ではないのですが、テレビドラマなどで、リッチな登場人物が、高級なワインを飲んでいるシーンになっても、そのワイングラスではリッチな人はワインを飲まないじゃないかなーという描写が多々あります。ここには、2つの世界の裏側がある、と考えます。
1つ目は、描写する側が、その世界を知らない
2つ目は、描写する側が、これを観ると人だってそんなことに気づかない、と考えている
これが、じゃあ大きな問題か、といえば、さほど大きな問題ではありません。文字通り、アニメに触れる人々のほとんどが出てくるワイングラスの形をみて、「それは違うだろ!」なんて思うことはありません。ということで無問題(モーマンタイ)なんです。しかし、作品の規模が大きくなったり、種類が変わってきたりすると、これが大きな問題になる、ということは知っておいたほうが良いんです。なぜなら、描こうとしている世界と描いている世界に見落としているギャップがあると作品のグレードが下がってしまうからです。
そして、これは、ビジネスの世界で言えば、見せようとしているものと見られて感じられることのギャップにも同じ影響があります。高級ラインでアピールしたいのに、高級ラインとしてはズレがあるとき、大きな問題(そのほとんどが売上やプロジェクトの失敗)に至ります。これについては、以前『バルミューダフォンがなぜダサいのか?』という記事でも触れました。
ダサい=大きなズレ
面白い例:ジョジョ第5部
最後にちょっとおもしろい例を紹介します。荒木 飛呂彦氏の漫画『ジョジョ』シリーズの第5部『黄金の風』のアニメの描写についてです。アニメは漫画と描写がまま異なりますが、それは少しわきにおいて以下のシーンを御覧ください。

ご覧の通り、ワイングラスの形状はひどいものです。こんな形のグラスはなかなか見つけれれないほど。しかしこちらも御覧ください。

ここに描かれているティーカップセット。こちらは、ウェッジウッドのフロレンティーン・ターコイズです。

画像引用:https://www.le-noble.com/event/200831ww/
漫画では、セリフにまで、ウェッジウッドと明確に謳ったシーンも出てきます。
おもしろいのは、ワイングラスとティーカップの描写の熱量の差です。漫画ではブランドは明確に触れることができても、アニメではそうは行かないとい事情があるのかもしれませんが、それでも、ワイングラスは手抜かりがあり、ティーカップのセットには、細かい描写がされれています。これは、原作者かアニメの監督か美術担当者かが、ワインはともかくウェッジウッドは好き、という志向を持っているkとを示唆しています。それがおもしろい。そこは大事なんだ!ということが見えるのがおもしろい。
まとめ
こういうギャップを埋めることが、どれほど大事かは、明言できないんです。定量化がうまくできないので。それでも、予算が許す範囲か熱量かなにかで、詳細にコストを注ぐのは、構築しようとする世界やブランド、商品のレベルを確実にあげるんです。ある段階から、詳細がとても重要になってくるんです。でも、まだ「ある段階」がどこにあるのか、わからないでいます。
関連しておすすめする本
養老孟司(著)『神は詳細に宿る』
詳細って大事だなーと予想外の方向から納得させられます。
荒木飛呂彦(著)『荒木飛呂彦の漫画術』
ジョジョの作者が語る漫画術。漫画の裏側をすみずみまで覗き見できます。
よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。
