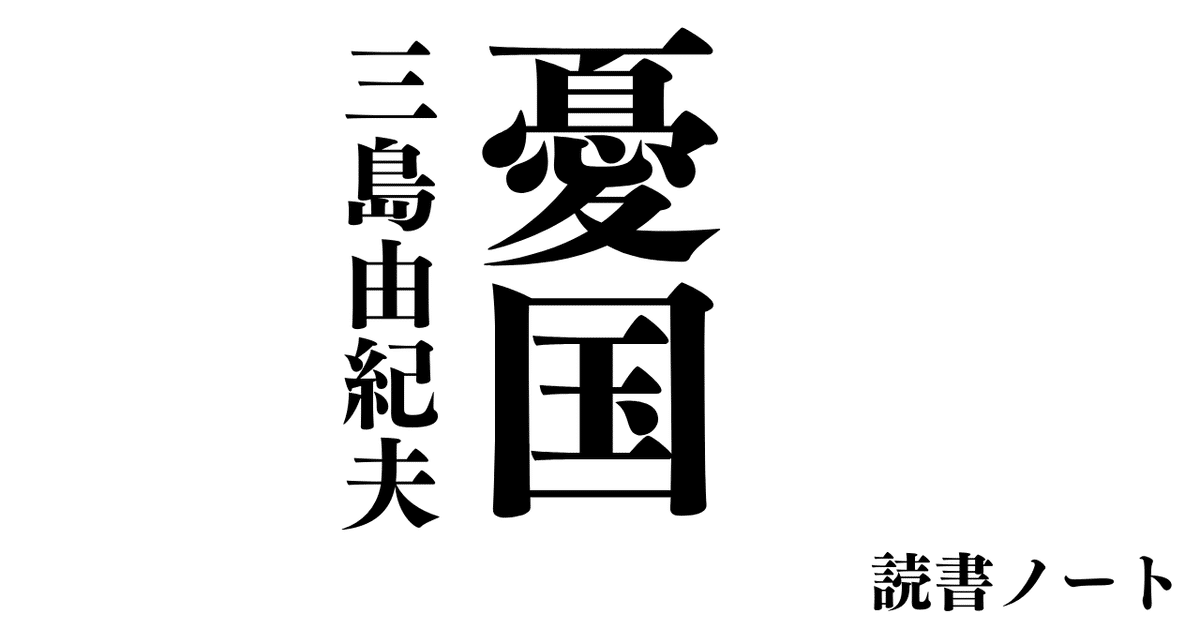
「憂国」(三島由紀夫)【読書ノート】
「切腹のシーン」を文章で書こうとしても、たぶんこれ以上のものは誰も書けないだろうという気がした。
読んでいるだけで卒倒してしまいそうなほどに迫ってくる描写だった。
目の前で切腹を見ているかのような、あるいは自分が切腹をしているかのような感覚になるほどの描写だった。
(という訳で、読むのは結構覚悟してから読んだほうがいいと思う。。。)
文章でここまでの表現ができるのかと驚いた。
* * *
死ぬ前の二人の行動と心理描写にも目を見張った。
武山信二中尉は、死ぬ前に風呂に入ったり、「見苦しい剃り残しをしてはならない」というほどに丹念に髭を剃って死顔を作ったりした。
死んだあとのことを気にするというのはいかにも軍人的な精神というか、武士道精神というか、そんな気がした。
妻の麗子も死ぬ前に「家の鍵を開けておくべきかどうか」を迷った。
鍵をかけておいたら、死体の発見が遅れてしまうことを懸念して、鍵は開けておいた。いかにも人間的な発想が描かれていると思った。
死を前にして流れる時間は、意外にも静かだ。
窓の外に自動車の音がする。道の片側に残る雪を蹴立てるタイヤのきしみがきこえる。近くの塀にクラクションが反響する。‥‥‥そういう音をきいていると、あいかわらず忙しく往来している社会の海の中に、ここだけは孤島のように屹立して感じられる。自分が憂えるこの国は、この家のまわりに大きく雑然とひろがっている。自分はそのために身を捧げるのである。
「窓の外からクラクションの反響する音が聞こえてくる」というのがすごくリアルだ。
まるで、昭和十一年二月二十八日(二二六事件の三日後)の四谷の中尉の家の中にいる気分になる。そこに流れていた時間が見事に再現されている。
また、死を前にして甘美な瞬間が訪れている。
二人は内側に燃えている火照りを感じながら、今味わったばかりの無情の快楽を思い浮かべている。その一瞬一瞬、尽きせぬ接吻の味わい、肌の感触、目くるめくような快さの一齣一齣を思っている。暗い天井板には、しかしすでに死の顔が覗いている。あの喜びは最終のものであり、二度とこの身に返っては来ない。が、思うのに、これからいかに長生きしても、あれほどの歓喜に到達することが二度とないことはほぼ確実で、その思いは二人とも同じである。
「死を前にした刹那的な美」が描かれている気がした。
また、「暗い天井板には、しかしすでに死の顔が覗いている」と表現がとても文学的だなと思った。
* * *
「仲間を討伐することなど出来ないから、自刃する」という切腹の動機も、当時の軍人の精神性を象徴している気がした。
* * *
おわりに。
当然、現代日本とは大きく違う時代背景と価値観である。
しかし、当時の時代の空気感や切腹という日本特有の精神性と文化、そして死を前にした心理描写が三島由紀夫の筆で描かれた短編ながらもズシリと質量のある小説だった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
