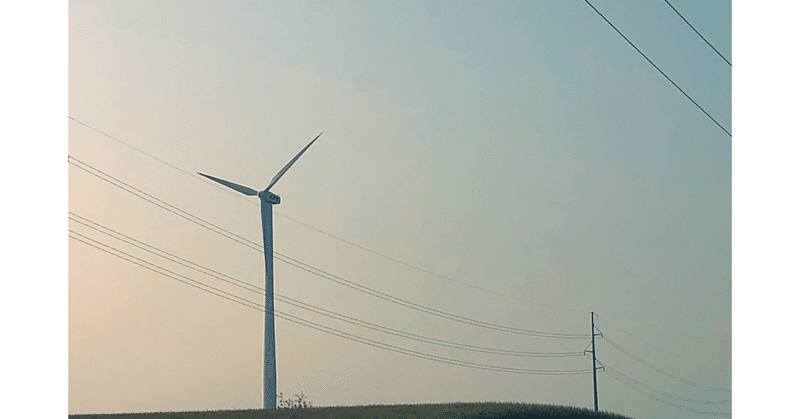
子のいない夫婦が相次いで死去したが、各々生前に清算型遺贈の趣旨を含む遺言をしていた場合
遺言・相続実務問題研究会 (編集), 野口 大 (編集), 藤井 伸介 (編集)『実務家も迷う 遺言相続の難事件 事例式 解決への戦略的道しるべ』2021、新日本法規出版のCase24 子のいない夫婦が相次いで死去したが、各々生前に清算型遺贈の趣旨を含む遺言をしていた場合、からです。
・仮の日付
平成18年1月1日夫が、遺言書を作成
内容・甥姪5名に各自100万円を遺贈し、残額全部と不動産を妻に相続させる(予備的に、清算の上宗教法人に包括遺贈)
平成19年1月1日妻が、遺言書を作成
内容・全財産を換価し、清算後、宗教法人に遺贈する。
平成29年2月18日 夫死亡
平成29年4月18日 亡夫の遺言執行者として弁護士就任
平成29年5月3日 妻死亡
平成29年7月5日 亡妻の遺言執行者として夫と同じ弁護士就任
手続選択の視点
1、夫の遺言の解釈
㋐ 夫の相続財産には、甥姪5名各自に100万円を遺贈するだけの現金がない場合、預金等を解約できるか。
㋑ 夫の相続財産には、甥姪5名各自に100万円を遺贈するだけの現金も預金もない場合、不動産を売却できるか。
㋒ 『予備的に、清算の上宗教法人に包括遺贈』という部分はどう解釈するか。
2、妻の遺言に従って財産を換価する際の留意点
㋐ 不動産の登記手続はどうしたらよいか。妻の名義から、換価により不動産を取得した者の名義に登記を移転することはできるか。
㋑ 登記識別情報は誰に通知されるか。
㋒ 不動産譲渡で譲渡取得が発生する場合は、誰にどのような税金が発生するか。
3 相続税
㋐ 夫の相続について、誰が申告・納税義務を負うか。何か留意点はあるか。
㋑ 妻の相続について、相続税の負担はどうなるか。遺言執行者の対応で留意するべきことは何か。
4 不動産譲渡税
㋐ 不動産取得について、いつ、誰に課税されるか。
㋑ 遺言執行者の対応で留意するべきことは何か。
㋒ 妻が不動産をそのまま宗教法人に遺贈する場合の課税はどうなるか。
5 本Caseのような事案で遺言を作成する場合の留意点
㋐ 第三者への遺贈の遺言を書く場合の留意点は何か。
㋑ 法人に遺贈するような遺言を書く場合の留意点は何か。
㋒ 妻の相続人に迷惑をかけないよう工夫する点はあるか(税金や諸費用はすべて売却代金から控除することを明記した方がよいのか)。
手続選択の視点
1、夫の遺言の解釈
(1) 『甥姪5名各自に100万円を遺贈する』との文言
・・・遺産である現金や預金等のうちから、甥姪5名、各自100万円を取得させる意思、と書籍では解釈。
ア 遺贈する現金がない場合、預金等の解約の可否
遺言者の意思の解釈・・・現存する現金残高が「各自100万円」取得させるに足りない場合に、他の財産を換価し取得させることも含まれる。
イ 不動産換価の可否・要否
遺言執行者は、不動産などの遺産の換価も求められる。
妻に不動産を「相続させる」旨の条項よりも、受遺者「各自100万円」を取得させる条項が優先し、不動産を換価する必要があると解釈。・妻が既に亡くなっているから(P293)妻に相続させる旨の条項よりも、甥姪への遺贈が優先。民法985条、同法998条が根拠?
・参考
遠藤俊英ほか『金融機関の法務対策5000講 1巻』金融財政事情研究会、2018、P1534~ 最判昭和49年4月26日民集第28巻3号503頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52045
<概要>
・法定相続人以外の者に承継させる遺贈の場合、遺贈義務者である相続人の署名を求めるこのが無難。
・遺言執行者が選任されている場合、トラブル防止の観点からは、その署名を得ておくことが望ましい。
・遺言書の規定振りから、自行の預金が承継の対象が明確になっているとはいえない場合、相続人全員の署名を取得すべき。
ウ 不動産売却を要する場合の遺言執行者の実務上の対応・配慮
不動産売却の結果、妻が居住場所を失い、かつ、困窮する場合
(1)遺言執行者から各受遺者に、不足分について遺贈の放棄をしてもらうように説得、依頼。
・遺贈の放棄について説得・依頼するのは、遺言執行者の権限・義務でしょうか?
→民法987条、催告の程度。
(2)遺言執行者が妻に対し、妻固有の金融資産から、甥姪への遺贈義務を履行するように説得。遺贈義務履行と妻への所有権移転登記の申請が、同時に行われるように計らう。
(3)甥姪に対する遺贈義務を履行するための、妻の遺留分(2分の1)が侵害される結果となる場合
妻から甥姪に対して、遺留分(減殺)侵害請求権を行使して、遺留分を確保するために必要となる範囲で、遺贈義務の履行を拒絶。
(4)「残額全部」を妻に「相続させる」旨の文言 遺産の中から、甥姪に各自100万円を取得させた後、残りを妻に対し相続させる意思と解釈 前提として、遺産の現金や預貯金残高の合計額が、「500万円」を超えること。
(5)『清算の上宗教法人に包括遺贈』する旨の予備的遺言 妻が夫よりも先に亡くなった場合の意思表示と解釈。
2 妻の遺言に従って財産を換価する際の留意点
(1)妻の遺言の法的性質
・清算型遺贈
(2)清算型遺贈における不動産の権利義務移転過程の登記名義の反映
・遺言執行者は、一旦、妻の相続人への相続登記申請を行い、その後、売買による買主への所有権移転登記の申請。
1、遺言執行者の単独申請により、被相続人名義から相続人名義への相続人名義への相続による所有権移転登記の申請(現行不動産登記法63条3項)。
2、遺言執行者と買主との共同申請により、売買を原因とする所有権移転登記の申請
・登記研究 277号 74頁 昭和45年10月5日 民事甲第4160号 民事局長回答 〔本誌第二七六号六一頁掲載の回答の解説〕◎四一〇九遺言による所有権移転登記について
・登研究 277号 74頁 昭和45年10月5日 民事甲第4160号 民事局長回答 〔本誌第二七六号六一頁掲載の回答の解説〕◎四一〇九遺言による所有権移転登記について
・登記研究 417号 63頁 昭和52年2月4日 法務省民三第773号 民事局第三課長回答 《四六七四》弁護士法第二十三条の二に基づく照会について(ドイツ連邦共和国(西独)人である被相続人の日本にある相続不動産を、遺言執行人が売却処分し、その売却金を受贈者に分配しようとする場合、右不動産についての登記手続について)
・登記研究 619号 219頁 1999年8月30日 【質疑応答】 〔七六九五〕相続人不存在の場合における清算型遺言による登記手続について
(3)登記識別情報を受ける権限
遺言執行者に、登記識別情報が通知される(民法1015条。)
3 相続税(1)夫の相続
ア 納税義務者
妻、甥、姪ら。
イ 留意点
特例の利用
(2)妻の相続
ア 妻の相続人には、納税義務が生じない(所得税法12条、法人税法11条等)。税務署に相談の上、対応。
イ 遺言執行者が留意すべき事項
妻の相続について、所轄税務署に事前に説明。妻の相続人について、所轄税務署からお尋ね文書が届くことを知らせる。
ウ 宗教法人に対する非課税
相続税法1条の3(相続税の納税義務者)、租税特別措置法40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)、法人税法別表第二の公益法人等の表。
(3)登記識別情報を受ける権限
遺言執行者に、登記識別情報が通知される(民法1015条。)
3 相続税(2)妻の相続
ア 妻の相続人には、納税義務が生じない(所得税法12条、法人税法11条等)。税務署に相談の上、対応。
イ 遺言執行者が留意すべき事項
妻の相続について、所轄税務署に事前に説明。妻の相続人について、所轄税務署からお尋ね文書が届くことを知らせる。
ウ 宗教法人に対する非課税
相続税法1条の3(相続税の納税義務者)、租税特別措置法40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)、法人税法別表第二の公益法人等の表。
4、不動産譲渡税
(1)課税に関する検討の重要性
ア 一般的な留意事項
不動産を売却して代金を受け取った場合、その代金が帰属する者には譲渡取得税と住民税が課され、納付義務を負う。
イ 清算型遺贈における留意点ー実質取得者課税の原則の適用
本Caseでは、妻の相続人は実質的に利益を得ていないので、課税要件を欠く。個別案件ごとに所轄税務署へ確認。
ウ みなし譲渡取得課税が生じる場合
・妻が宗教法人に対して、不動産を遺贈する場合
妻の相続人・・・譲渡取得が認められれば、譲渡取得税課税。所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
受贈者の宗教法人が、租税特別措置法上の公益法人等に該当し、他の要件も満たせば、妻の相続人は非課税。
5 本Caseのような事案で遺言を作成する場合の留意点
(1)第三者に遺贈をする場合
予備的な遺言条項として、「遺言執行時に、甥姪5名、各自に100万円を遺贈するだけの現金も預貯金もない場合、現存する現金及び預貯金の範囲で甥姪に按分弁済する。」条項を設ける。妻に相続させる不動産を換価しないため。
(2)法人に遺贈をする場合
受遺者となる法人の寄付金受取取扱規定、運用基準、遺贈による寄附受け入れの可否の事前確認。遺言の効力発生時にもう一度確認。
(3)妻の相続人に迷惑をかけないよう配慮すべき事項
みなし譲渡課税の可能性がある場合、納税資金の確保について遺言に明記。不動産の売却代金から、税金を控除するなど。
あ
