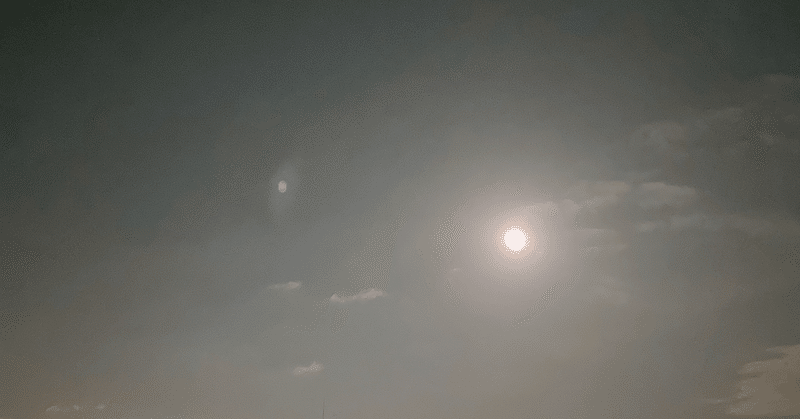
【短編小説】その男の物語(1)
先日の当て書きの、「劇中劇を書いたら面白いかも」というご提案を受け、素直に書きましたw(素直が取り柄です)
こちらのお話の続きになります。
---------------------------------------------
朝からパソコンの前に向かうこと数時間。
目の前の新緑が眩しい。
わたしの麗しいアシスタントは、昼前に美味しいパンを探してきますと言って、出て行ったっきりだ。
主役不在のまま、わたしは物語の骨組みを作る。
☆
浅草の観音裏にある小さな一杯飲み屋。
磨りガラスのはめられた引き戸。
外から中の様子を窺い知ることはできないが、酔客の笑い声が漏れていることから繁盛店だと分かる。
青いブルゾンにグレーのスウェットを着た男は、慣れた様子で引き戸を開け、中に入る。
被っていた黒いキャップを脱いで、髪を無造作に直しながら
「ママ、こんちはー」
とカウンターの中にいる女将に挨拶する。
女将は「いらっしゃい、来てるよ!」と下町らしい口調で言い、視線を奥のテーブル席に向ける。
カウンターの常連たちの背中を小突いたり、ひょこっと頭を下げて挨拶しながらテーブル席へ向かう男。
「雄太、遅かったな」
白い髭を蓄えた年配の男が日本酒の入ったコップを持ち上げる。
「すいません。遅くなりました」
丸い椅子に、長い脚を持て余し気味に開きながら座ると、出された瓶ビールをコップに手酌で注ぎ、「乾杯」と言って一気に飲み干した。
「乾杯」
年配の男もコップを持ち上げる。
「で、雄太、乾杯ということはうまいこといったんだな」
「多分、明日には連絡が来るはずです」
そう言って、雄太は唇についた泡をぺろっと舐めた。
ー2時間前 神楽坂ー
店の暗さが取り柄のオーセンティックバー。
黒いクラシカルなワンピースを着た女がカウンターに座っている。
肩が時折小刻みに揺れるのは、泣いているのだろうか。
黒いタキシードにボウタイ姿の雄太は、そっと彼女の隣の席に座った。
スツールの足掛けに、片足だけ乗せ片足は床についたまま、バーテンダーにオンザロックを注文する。
真後ろから見ると、まるで洋画の葬式の帰りのような二人だ。
バーテンダーが飲み物を雄太の前に置く。
「ありがとう」
少し雑味があるがどこか愛嬌のある声で微笑みながら返事をしてから、今度は真剣な表情でバーテンダーに目配せをする。
隣の女はやっと落ち着いたのか、今は背筋を伸ばしてグラスを口に運んでいる。
氷の乾いた音が聞こえ、グラスが空になったのが分かる。
「すみません、ご迷惑じゃなければ一杯おごらせてくれませんか?」
優しげな微笑みを浮かべ、雄太は女に話しかける。
彼女が返事を渋る隙も無く、バーテンダーに、同じものをもう一杯と注文をする。
女は40代半ばくらいだろうか、マスカラはすっかり落ちてしまい、憔悴した顔は本当に葬式の帰りのようだった。
「ごめんなさい、わたしもう帰りますので」
小さい声でそう言うと、椅子から降りようとする。
少し足元がおぼつかないようだ。
雄太がそっと体を支えると、彼女は警戒した小動物のようにピタッと動きを止めた。
「大丈夫ですか?」
彼女の顔を覗き込むように声をかける。
「本当に、大丈夫です」
先ほどよりは少し大きな声で返事をして、歩こうとするがやはり足元が心許ない。
バーテンダーが近寄り、少しあちらのソファーで休まれてください、と声をかける。
茶色の皮張りのソファー席は、カーテンが引けるようになっている。
雄太は彼女の体をいつでも支えられる位置で付き添い、ソファーまで案内した。
彼女は水を一気に飲み干すと、目を瞑ってソファーに寄り掛かった。
雄太も向かいのソファー席に座り、ボウタイの左側だけ外して、シャツのボタンを緩めた。
腕時計に目をやる。
あと1時間。それまでに浅草に戻れるだろうか。
(まぁ、なるようになれか)
同じように目を瞑って腕を組んだ。
先に目を開けたのは彼女の方だった。
目の前で、無防備にボウタイを外して眠っている男の、暗闇に白く光る喉元と、美しい半円に形取られた睫毛を見つめる。
雄太は彼女の起きた気配を感じ、目を開けるタイミングを10秒見計らう。
時計の針がきっかり10秒刻んだところで、ゆっくりと目を開け、自分を見つめている彼女の目をしっかりと捉える。
少し虚な瞳で。でも、優しさはたたえたまま。
「ああ、良かった。少し休めましたか?」
彼は軽く咳払いしながら言うと、身を起こしてポケットから一枚の名刺を取り出した。
「もし何か困ったことがあれば、いつでもご連絡ください」
そう言って名刺を彼女の手に握らせると、雄太はさっと立ち上がり、店員を呼んだ。
そして、テーブルに現金を置くと、足早に店から出て行った。
名刺には
「佐伯探偵事務所 佐伯良介」
という文字と、携帯電話の番号だけ印刷されていた。
☆
ここまで書いて、いつの間にか机にうつ伏せになって居眠りをしていたようだ。
アシスタントが戻ってきたことにも、彼がそっとブランケットをかけてくれていたことも気づかなかった。
夕闇の近づいた部屋を見回すが、彼の姿はない。
テーブルには軽井沢で人気のパンとチーズと果物の皿があった。
隣のメモには
「ちゃんと筆が進んでいるようで安心しました。僕は取材に出かけるので、夜もがんばって書いてくださいね K」
と書かれていた。
どっちが上司か、さっぱりわからない。
わたしはため息をつくと、パンをひとかじりした。
「やだ、美味しいじゃん」

(つづく)
サポート頂けるととても嬉しいです🐶 サポート代は次の本を作るための制作費等に充てさせていただきます
