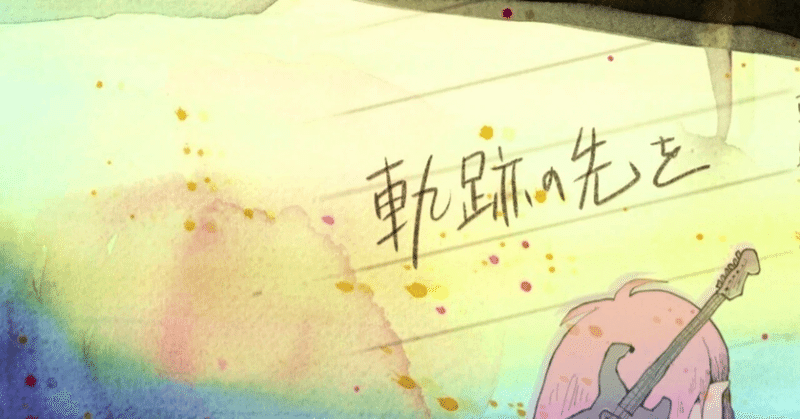
軌跡の先を #5
●3年ほど前に初めて書き、翌年にヒイヒイ言いながら改稿し、そのまた次の年(昨年)に印刷所に頼んで紙の本として作った長編小説の前半くらいまでをnoteに投稿する試みです。筆力の未熟さを承知の上で、投稿にあたっての手直しをせず、印刷所に納品した本文データそのままをお届けします。
●ほぼ「心意気を買う」形にはなりますが、紙の本を売っているページはこちら→https://sheep16-baa.booth.pm/items/5074168
5
〈サムシングが再結成するんだって〉
由香里と玲奈に「須賀先輩と会って話せないか」と頼んで、渋い顔で保留の返事をもらい、そのまま休日に入った。そんな朝早く、私は寝ぼけ眼で穂乃果からのメッセージを読んだ。まだ覚醒しきっていない頭では、穂乃果のメッセージの意味が理解できない。
〈何の話?〉
神経が鈍ったような指で返信する。すると、驚くべき速さでメッセージが再び届いた。
〈サムシングだよ、サムシング、私の好きなバンド!〉
文面をしばしじっと見て、ようやく理解が追いついた。
〈今理解した。よかったじゃん〉
穂乃果が喜ぶ顔を想像してそう返した。
サムシングとは、穂乃果が小学六年生の頃から大ファンのロックバンドだ。メンバーはギターボーカル、ベース、ドラム、キーボードの四人で、いずれも現在は五十代後半くらいの男性。穂乃果によると熱心なファンが多いバンドらしいのだが、彼女がファンになった頃にはすでに解散してしまっていたのだった。そのサムシングが再結成するという情報を穂乃果がどこからか得てきて、私はメッセージの通知音で叩き起こされることになったようだ。自分が生まれる前にリリースされたデビューシングルをはじめ、音源も映像作品もすべて手元に揃えるほどのファンで、解散ライブの映像を見て「ライブに行けないなんて」と号泣していた穂乃果だ。きっと私の想像の何倍も嬉しいことだろう。
〈妹尾さん、少し前にSNS始めてたんだよね。もちろんフォローしたんだけど、まさか再結成するとは思わなかった〉
興奮してメッセージを打ち込んでいる穂乃果の様子が目に浮かぶ。妹尾さんというのは、サムシングのギターボーカルだ。事あるごとに穂乃果から聞かされたいくつもの話が脳裏に蘇る。穂乃果がSNSをチェックしていたという妹尾さんも、他のメンバーも、解散後はソロ活動や他のアーティストのサポートなど、それぞれに活躍している。
〈やっとライブに行けるじゃん。本当によかったね〉
あの時は中学生だった穂乃果の号泣を思い出して、メッセージを打ちながら口角が上がった。と、穂乃果からは思いもよらない返信が来た。
〈まりあが羨ましいよ。サムシングの後輩だなんて〉
頭に疑問符が浮かんだ。私がサムシングの後輩で、羨ましい。どういう意味だろう。穂乃果に尋ねる代わりに、メッセージの画面を閉じて検索エンジンを開き、「サムシング 皆川大学」と打ち込んでみた。
検索エンジンから得られた情報によると、ドラムを除いたサムシングのメンバーは全員、私が通う皆川大学の出身なのだそうだ。旧学科の体制だった頃の音楽学科を卒業していて、在学中は軽音楽部で活動していたということもわかった。その当時のバンドがサムシングの前身だ。そこまで穂乃果から聞いたことがあったかどうか、よく覚えていない。ついでに、穂乃果が目にしたのであろうサムシングの再結成を宣言する妹尾さんのSNSの投稿も発見したし、それに沸くファンの投稿も数えきれないほど目にした。本当に、多くの人に支持されていたバンドだったのだ。
穂乃果と数往復のメッセージをやり取りして、それからやっと私の身体にエンジンがかかった。簡単な朝食を作って胃に収め、食器を洗って片付ける。洗濯機を回しているうちに乾いた前日の洗濯物を畳む。実家からそれほど物を持ち込まなかったから散らかりようがない部屋に軽く掃除機をかける。そうしているうちに洗い上がった洗濯物を干す。いつもの休日だ。こうした家の中での細々としたタスクは、アスリートのルーティンのように私の心を整えてくれる。
座椅子に腰を下ろして、狭い部屋に漂う柔軟剤の匂いを静かに吸っては吐きながら、ふと考える。今頃、大学の軽音楽部では、サムシングの再結成が話題になっているのではないか。大先輩のはずだから、サークル内にもファンが多いだろう。折に触れ軽音楽部の話をしてくれる由香里と玲奈の顔が浮かんだところで、スマートフォンが短く鳴った。確認すると、タイミングのいいことに由香里からのメッセージだった。
〈マリー、須賀先輩から、話してもいいって連絡来たよ〉
背もたれに体重を預けていたのをぐっと起こす。話に聞いていた印象では、おそらく話すことは叶わないだろうと思っていた。
〈本当? ありがとう〉
メッセージを送信して少しも経たないうちに、音声通話の着信があった。慌てて応答すると、由香里のややまくし立てるような声がすぐに耳へ届いた。定型文のような挨拶もそこそこに、いきなり本題に入る由香里。
「マリー、オペラってわかる?」
「オペラ? 音楽の?」
由香里の言葉で連想したイメージは、すぐさま「違う違う」と打ち消された。
「喫茶店だよ。大学から駅の方にちょっと行ったとこにあって、国道の手前かな。電車通学の人はわりと行くんだけど、マリーは行ったことないか」
「うん、ない。ごめん」
「いや、それはいいんだ。明日の昼の一時、オペラで待ってる、って。須賀先輩から」
今日はまだ声を聞いていないマリーの気配が少し変わった。
「明日の一時ね。場所、調べとくよ」
「たぶん行ったらわかると思う。駅の方に真っ直ぐ、右手の方。緑色の建物だよ」
「わかった。ありがとう、いろいろ」
電話の向こうで、由香里が一瞬沈黙した。
「由香里?」
「ごめん、なんでもない。そうだ、サムシングが再結成するね」
由香里は無理に話題を変えたように思えた。訝しむ気持ちをぶつけようとしたが、直感が「触れない方がいい」と言っていた。
「幼馴染が大ファンで、朝早くに連絡来たよ」
「そうなんだ。ファンにしてみればビッグニュースだもんね」
由香里の笑い声にはもはや翳りも何もない。ほっと息をつきたくなるのは、私かマリーか。
「わざわざ電話してごめんね。私、気が短くて」
「ううん、大丈夫」
「じゃあ、月曜日にね」
「うん」
何事もなかったように通話は切れた。スマートフォンを操作して、検索エンジンに今度は「皆川市 オペラ」と打ち込んだ。由香里の言葉の通り、大学から駅まで真っ直ぐに通った道のちょうど真ん中あたりに位置する喫茶店がヒットした。お洒落な三角屋根と深緑色の外壁を持つ、店の外観の写真も見つかる。小さな店に見えるが、長く愛される店のようで口コミでは評価が高い。
検索エンジンのアプリを閉じて、手帳代わりにしているカレンダーのアプリを開いた。明日は日曜日。四年生ともなると、やはり時間を作れる日は限られているのだろう。
「マリー、須賀先輩と話してどうするの?」
座椅子に再び背中を預けて、マリーに問うてみた。マリーは少し考えてから、答えになっていないような返事をよこした。
(須賀くんは、すごく怒るかもしれないね)
「マリーと須賀先輩は、面識がある、ってことだよね」
(そうだね)
やはり、マリーの様子が今までと違う。突然現れて、私に取り憑いて、それなのに事情を一ヶ月も黙秘し続けたマリー。身体を共有しているからかある程度伝わってくるマリーの心の動きようは、須賀先輩の話が出た途端に明らかな変化を見せた。軽音楽部が気になっていたらしいことも、須賀先輩の存在と関係しているのではないか。マリーは旧学科の学生だったのかもしれない。そして、須賀先輩とも何らかの形で関わりがあった。私が想像できることは、残念ながらここまでだ。
「須賀先輩に、マリーのこと、話すの?」
マリーのこと、というのは、もちろん「幽霊になったマリーが藍川まりあに取り憑いている」という事実のことだ。
(須賀くんには、悪いけど話さないつもり。でも、状況次第かな)
「そっか」
マリーの望みで須賀先輩と会うのだから、マリーの考えるようにすればいい。そう思ったのも一瞬のこと、それが「一年生の藍川まりあとして、面識のない四年生に話を聞きに行く」という恐ろしい状況を意味していることにすぐに気が付いた。
「ちょっと。私、本当に大丈夫なんだよね?」
(先に謝る。ごめんね)
「待ってよ。こういう時こそうまくやってよね」
慌てる私にマリーの返事はなかったが、マリーが何かを思案しているのだと理解して、いつも通りの休日を過ごすこと、それしか私にはできなかった。
いただいたサポートて甘い物を買ってきてモリモリ書きます。脳には糖分がいいらしいので。
