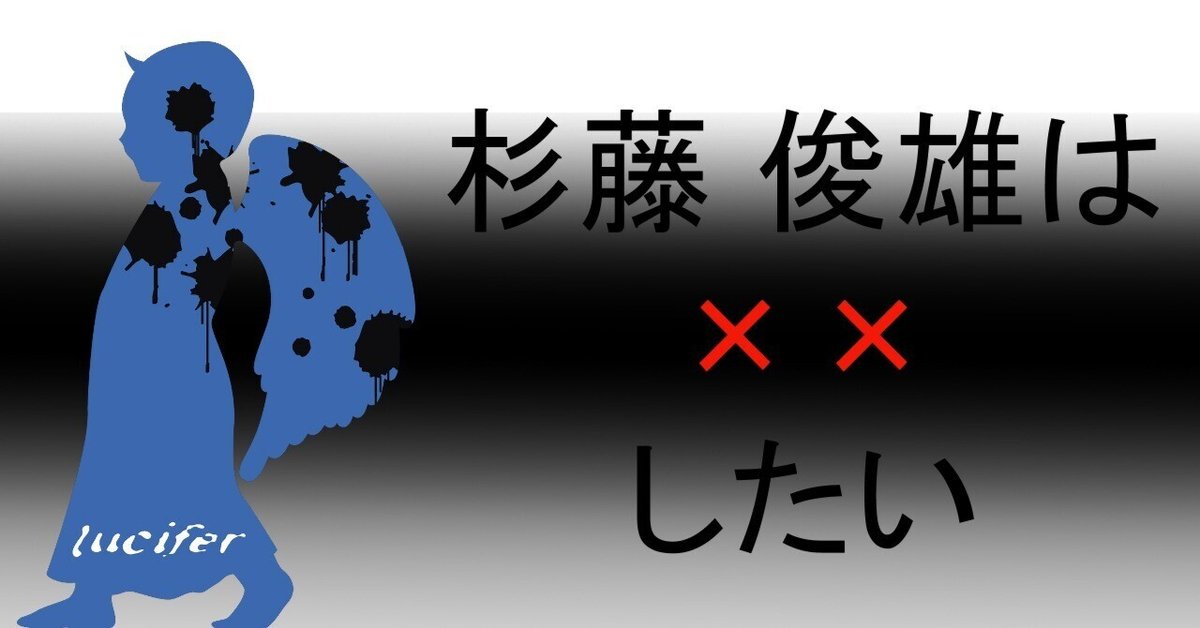
【加筆・修正ver】杉藤 俊雄 は××したい_93_閑話 07
1970年の11月か12月ぐらいだったかもしれない。
女子寮の自室で、ルームメイトのエリコが声をあげて泣いていたのは。
まるで我が子が死んだかのように分厚い本を何冊もきつく抱きかかえて、眼鏡を涙で曇らせるほど悲しみの湯気を立ちのぼらせていた。無防備に空いた唇が涎まみれで、鼻水も垂れ流しで、しゃくりあげる度に首筋がこわばって、セーラー服の襟から除く鎖骨が艶めかしく浮き上がっている。
いつもの澄ました表情とは程遠い、年齢相応どころかそれ以上に幼いエリコに、私はまるで奇跡に立ち会えたような感動を覚えた。
まるでエリコの存在そのものを見つけて、独り占めに出来たような悦びを、彼女の存在の奥底に秘められた魂の一端に触れられた光栄を、予知で知っていたはずなのに、まるで生まれて初めて見たような鮮明で新鮮を。
「エリコ」
「どうしよう、貴子。私、もう、生きていけないかもっ……」
私は自分が次になにをするのか知っている。
どんな行動を執り、どんな言葉をかけるのかも。
「彼のように典雅を感じさせる文章を誰がマネできるかしら。こんな文化レベルの衰退を招くような損失を、周囲が気づいてあげられなかったことを」
はらはらと大粒の涙を零し、三島 由紀夫の死を悼む彼女を、どうすれば自分の方に向けることができるだろう。
どうすれば彼女から私以外の何もかも奪い取って、私の為に悲しみにふけり、涙を流すことができるだろうか。
答えは未来が知っている。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ガキの頃。海辺で迷子になった。親父やお袋は三歳児のわりに体がでかいから、オレのことをすぐに見つけられたと言っていたけど。当のオレは、果てが見えない海とかたくさんの人とか、打ち上げられた海藻とか、ゴミとか、カニとか、アサリとか、とにかくいつもと違ういろんな物に取り囲まれて、びびってその場で泣きだした。
もうダメだ。ずっとオレは誰にもみつかることなく、ひとりぼっちで海をさまようんだと想像しちまったんだ。
公民館で俊雄に抱きしめられた時、そのことを思い出しちまった。そんで肩越しに見えたのは、アイツのいない世界だった。まぁ、ガキだから許してくれよ。その時に、オレはアイツの視界にはアイツがいないんだってわかったんだ。オレらの視界には、嫌でもアイツの顔が目について、気色悪くてしかたがなかったんだけど、アイツの眼にはアイツの醜い顔が、鏡でしか確認できないんだ。まわりのヤツラの態度でしか分からないんだ。
それが分かっちまったから、なにもかも許しちまった。
腐れ縁の始まりで、お前に付き合わされるオレは、お前に感謝すると同時に恨んでもいる。
だってそうだろ。おまえのおかげで、おまえのせいで、オレは死体しか愛せなくなっちまったんだから。
けど、なぁ、結局、オレ等って友達だったよな?
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
オトンの故郷は北海道で、じいちゃんは広大なラベンダー畑をもっちょった。ものすごぅ、暑い日じゃっかな。オカンはこなくて、おとんとワテだけで里帰り。ラベンダーの匂いが泊っている部屋までただよってきよった。
下の階からは、おとんとじいちゃんの言い争う声がきこうて辛かった。
しだいに声が聞こえのうなって安心して寝てたら、いきなりオトンに叩き起こされて、無理やりパジャマのまま外に連れ出された。
手伝えとシャベルを渡されて、ラベンダー畑の一角に穴を掘れとオトンが言った。青い月の光に照らされて、頭から血をながしているじいちゃんが地面に転がって、ワテは怖くなった。
オトンはじいちゃんを、これからラベンダー畑に埋めるのだと言う。
死んだから埋めるのだと、オトンが言う。
ワテもいつか、死んだら誰かに埋められるんやろうか。
ラベンダーの匂い、血の匂い、夜の匂い。土の匂い。死の匂い。シャベルに絡まる根っこ、うねうねと顔を出す細長い虫たち、ワテを見下ろすオトンは腕を組んで口笛を吹いている。
だからワテはこういう時、なにも考えないようにしちょった。
なるようにならんからや。なにもかもがムダやから。
だから堪忍してぇや、先生。
ワテはもう疲れた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
あの人が大切にしていた化粧箱を叩き壊してしまった。
ほぼ衝動的だった。
だって耐えられなかった。あの人だと思い込んでいる、貴方が、あの人が大切していたものを、あの人のようにいじくりまわすのが。
貴方は言った。
あの人の代りになって、あの人がやりたかったことを代りに果たしたいのだと。オレは頭が悪いし、その人とも長い付き合いだったから、額縁通りに受け取って快諾してしまった。
オレはいつもそうだった。人の言葉が頭に入ると、思考がそれだけに一点に集中して、オレの脳内を支配するんだ。
ただ、あの人は命令するだけじゃなく、オレに居場所をくれた。オレのしていることが、大切な恩人を裏切っているような気がして辛かった。
ある日、園生さんが思いつめた顔でうちに来て、いろいろ話して手紙を託された。その数日後に、園生さんが死んだことで、生まれて初めてちょっと怖くなった。
オレは生まれて初めて、自分の意志で行動しているのだと思う。
思ったよりも簡単に、思うように体が動いてびっくりした。
走って走って追い詰められたけど、なんかすっきりした気分だった。
体が宙に浮く。遠くから、雪の香りと赤ん坊の声が聞こえてくる。
あぁ、なるほど、これが罰なんだ。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
小さい頃、母さんに連れられてフィリピンに来たことがある。母さんはこのまま山中崎から逃げたかったんだと思うけど、幼いぼくは断固として異国での生活を拒否した。
言葉の通じない親戚を拒絶し、自分の生まれ育った屋敷を恋しがり、血反吐を吐いて脱腸するレベルで泣き喚いた。
帰りの空港で出迎えに来たのは、父ではなく胃袋の顔をした魔女だ。魔女は勝ち誇った顔でぼくを見降ろし、ぼくも幼いながらも、この魔女に従うしか道がないことを否応なく理解させられた。
ぼくは望んでいなかった。骨壺を盗んだ時点で、山で遭難した時点で、杉藤の首を締めた時点で、学生寮を放火した時点で、警察の死体を便所に隠した時点で、ぼくはなにもかも諦めて、杉藤家からも園生家からも山中崎からも逃げて自由になればよかった。
人間なんて、死んだら汚物だ。
山で遭難して、動物に食い荒らされた腐乱死体を見て知っていた筈じゃないか。こんな大切なことを、どうしていままで忘れていたんだろう。
ぼくはぼく自身で、ぼくだけの人生をムダにしてしまった。
今、ぼくは手紙を書いている。
この手紙には父ががぼくに教えてくれた暗号が盛り込まれて、読み解けるのは多分、園生家に縁のある人間だと思うけど、多分、利喜おじさんしか解読できないだろう。あのおじさんが今更なにができるのだろうかわからないけど。
形勢を逆転させる切り札を、ぼくはすべてムダにしてしまった。
葛西 真由の死体を処理したことにして、彼女の死体を屋敷に隠して、なにかがあった時の交渉材料にしようとしたんだけど、結局、杉藤にいろいろバレた。もう、いい加減にして欲しいから殺した。葛西 真由の死体と同じ部屋にいれてあげるから許してほしい。
――はぁ、エリコさんに会いたいな。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
物心ついたときから、なんとなく、自分の人生は祝福されたものじゃないことは理解できた。母に殴られ、兄に殴られ、父に無視されて、いつも貴子さんがぼくを守ってやさしくしてくれた。
言葉を教えてくれた。文字を教えてくれた。計算の仕方を教えてくれた。貴子さんがぼくの親代わりだった。
貴子さんだけは、ぼくだけの味方でぼくだけの家族でぼくだけの友達。
いつもぼくが泣いていると、必ず現れて、ぼくを慰めてくれた人。
あまりにもぼくの扱いに、貴子さんが父へ抗議したことで、だいぶぼくの待遇は良くなったと思う。
醜い魔女? 呪い?
冗談じゃない。貴子さんを悪く言う、緑もキライ。
「死ね」
ある日、前置きもなくそう言われた。貴子さんがなにかを視たかもしれない。
「どうして? ぼく、死にたくない」
「そう、だったら」
ねぇ、貴子さん。言うことを聞いてくれたら、ずっとぼくと一緒にいてくれるよね?
いなくなったりしないよね?
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ぼくは自分を「私」と呼ぶようにする。出来る限り、貴子さんの真似をしてどんな時でも、堂々とした大人になりたいから。
貴子さん死んじゃったのはショックだったけど、そのころには、なんとなく彼女が遠くに行きそうなことが分かっていたから、尾をひくような痛みはなかった。
貴子さんの弟のあの男は、みっともないくらい取り乱して狼狽して、悪趣味な骨壺に貴子さんの骨を入れて、貴子さんが嫌がっていたことをしようとしている。
許せない。本当に貴子さんのことが大好きなら、そんなことしちゃいけないのに。
ぼくの話を聞いてくれた、あの男の子供――ぼくと同い年の杉藤 俊雄くんが骨壺を盗もうと言ってくれて嬉しかった。
盗むことはこわくてびっくりしたけど、こんなにもぼくのために考えてくれる人間は、貴子さん以外に杉藤くんが初めてだった。協力してくれた大川くんがビビる緑を脅した時はざまーみろとすっきりした。
ぼくは、いや。私は、この時から私になろうと思った。
兄ではなく、僕が五代家の正式な跡取りになれば、ずっと杉藤くんと一緒にいられるかな。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ひどいな、すごい腫れているぞ」
「そうなの」
「あぁ、見事な蚯蚓腫れだ」
「ミミズ……? なにそれ、気持ち悪い」
葉山の拷問じみたトレーニングは徐々にエスカレートしていた。
杉藤から背中の手当てを頼まれた私は、背中に刻まれた痛々しい傷跡に軟膏を塗り込んで、湿布を貼り付けて、早く治るように願いを込める。それしかできない、歯がゆさと無力さ。私がもっとしっかりしていれば、山での遭難も防げたかもしれないのに。
「ねぇ、五代くん。僕ね、大きくなったらみんな殺そうと思うんだ。僕たちをこんな目に遭わせたヤツラ全員、殺したい」
背を向けて、私に胸の内を語る杉藤の声。普段の雑談の延長線のように語られた内容は、あまりにも自然すぎて、杉藤はずっとずっと私たちが知らない間、周囲への怒りを募らせて、何度も何度も心の中で殺意を反芻させたいたのだろう。
私は杉藤の語る殺戮と復讐劇を聞き続けた。聞き続けているうちに、全身が痺れるような熱気に包まれて、そして、なにもない荒野を見た気がした。
彼にしか視えない肉が織りなすグロテスクな世界。胃袋の形をした不幸を食む神様。罪人を断罪して異形の翼を持つ天使。他者を支配する肉で出来た触手。
「五代くんは協力してくれるよね?」
貴子さんが、予言していた私の罪は、もしかしたら杉藤の復讐に加担することなのだろうか。
だとするなら――。
「うん」
私は魂を彼に売り渡そうと思った。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
私が中学にあがったあたりから、家の雰囲気がおかしくなった。正妻のプレッシャーに耐えきれなくなった兄が、ついに壊れてしまったらしい。兄は私に強く当たった。私は大げさに痛がるふりをして、最小限のダメージにとどめたけど、もうダメだと思った時、警察が私を保護してくれた。
それが、貴子さんのもう一人の子供であり、私の兄であるAとの出会いだった。Aは私に自分の身の上を語り、親身に私の相談に乗ってくれた。うれしかったけど、Aは私と違って山中崎と貴子さんはおろか杉藤家に対して強い復讐心を募らせているようだった。
――なぁ、公博。どさくさに紛れて、逃げちまおうぜ。そして、俺たちは俺たちの人生を取り戻すんだ! お前はなにも心配しなくていい。全部俺に任せてくれよ。
私は兄を止めることが出来なかった。
心のどこかで、私も山中崎や杉藤から逃げたかった。自由になれた自分を想像して、心動かされてしまったんだ。卑怯者の私に罰が当たるのは当然なんだ。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「公博、もっと折ろう。これじゃ、つっかえて下に落ちない」
「…………」
緑が何かを言っている。
私はなにも考えずに、一緒に逃げようと言ってくれた人を、私を気にかけてくれた肉親の足の骨をさらに折る。手ごろな支柱になりそうな物に死体の足をのせて、てこの原理を応用しながら成人男性の骨を折っていく。
血抜きは済ませていたけど、折るたびに肉が膨れて血が噴き出して、細くて黄色いチューブみたいな筋が、透明な液を滴らせて嫌な匂いを放っている。
「…………」
ぶーんと、蠅が飛んでいる。粘ついた暑苦しさに、汗が次から次へ噴き出て止まらない。涙のかわりに流す体液は冷たくて、私の体温を氷点下まで下げていく。
本当は兄と逃げるつもりだった。
そんな兄が私を助けようとしてくれた大川に殺されて、杉藤の鶴の一声で、私は私を助けようとしてくれた兄の骨を折り、ぼっとん便所に血を流し、友人たちを巻き込んで死体の処理をすすんで行っている。
「…………」
どうしてこうなってしまったのだろう。
もうなにが正しいのかわからない。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
僕の、最初の記憶は、母の声から始まった。
「俊雄《としお》が男の子に生まれて、本当によかった。本当に……」
実感のこもった母の声は震えていた。赤ん坊の僕の顔をそっと撫でる手は冷たく、頬をなぞる長い指は僕の首あたりを移動し、踊るようになぞっている。
このまま指に力をこめれば、無力な赤ん坊はひとたまりもないだろう。
どん。と、遠慮なく押される。
園生くんがいる照明の当たるスペースから、暗闇が広がるスペースに押し出されて、体勢を立て直せないまま斜面に背中を打ち付ける。
「あああああああああああ……」
園生くんが叫び声をあげて、僕に向かって走る。手が僕の首にのびて、思いっきり締め上げる。
「ぐっ、あ」
園生、くん。
「あああ、ひひっ、あああぁ、ひ」
笑っている、嘆きながら顔を引きつらせて笑い、体中からとんでもない悪臭を爆発させる。硫黄と唐辛子と生ごみを混ぜたような、温泉の匂いよりも刺激のある臭いだ。視界が黄色くちらつき、蠅の羽音が耳にまとわりつく。
「強くて弱い真由。そんな彼女を追い詰めてしまったのは――」
真由は裏切られたと思ったのだろうか。
真由は僕の愛を信じていたけど、彼女は自分自身が耐えられなかった。
妊娠という肉体の変化が理性にヒビを入れて、自分が人間を生むという現実がおぞましさを伴って神経を摩耗させる。
だから僕は油断してしまった。我慢することになれてしまった人は、痛みを感じないわけではない。
痛みに耐えて絶えて、ついに壊れてしまった真由は、僕が目を離したすきにバスタブで手首を切っていた。睡眠薬を飲んで苦痛とまどろみに顔を蕩けさせた真由。駆けつけた僕に気づいて薄目を開けた彼女は、もごもごと唇を蠢かせて、僕に何かしらを訴えていた。
――助けて。
そんな声が聞こえた瞬間に、僕の手が彼女の首にかかる。
手の甲に青い血管が浮いて、彼女の首が鈍い音を立てて締まる。
苦し気な声を上げて、それでも真由の瞳が訴え続ける。
助けて。助けて。助けて。
おかしい、おかしいと連呼する大川くんの声には、苦い後悔が滲んでいる。幼い子供のように頼りなく嘆く彼は、僕の首に首輪をかけるように、両手で首を絞めつけてきた。
「…………っ!」
一気にぞうきんを絞るように、容赦のない強さに背中がびくんと跳ねる。ぎゅううと音を手て、僕の首を締めてこのまま骨を砕く勢いに、痛みと恐怖が内側からせり上がってきた。
「大川くん、やめて。苦しいよ」
僕は大川くんの腕をタップするが、力が緩まることはない。それどころか、さらに力を込めてくる。
あ、死ぬかな。
それでもいいかな、って思ってしまった。
酸欠で朦朧とした頭が、ぐらぐらガンガンと脳内を揺さぶって僕の意識に囁きかけるのだ。
杉藤顔に生まれた人間は、短命。自殺か狂うかの時間の問題。
僕が死ぬのは時間の問題だった。
僕の首にかかる指。僕自身も手を伸ばして、首に指をかけたけど……。
『ああああああああああっ、もう、どうしてくれるんだよ。みんなみんなお前のせいじゃないかああああああああ』
すぐ近くで園生くんが叫んでいる。
動かない体で、ろくに動かない頭で、僕は自分で自分に何が起こったのか、ぼんやりと理解した。
思い出したのは葛西 真由をくびり殺したとき。
彼女に手をかけたのは僕自身なのに、見開かれた大きな瞳が鏡となって、僕を僕を見つめている。
葛西 真由を通じて僕と僕が見つめ合い、肝心の首を締めている場所は真由の瞳に映っていない。だから、過去が想像を補完する。酸欠で疲弊した脳みそが僕が僕自身の首を締めている絵を完成させる。
僕を殺したのは、母でも、園生くんでも、ましてや真由でも大川くんでもない僕自身。
あぁ、なんてわかりやすい末路だ。
そんな結末だったら
それが分かっていたら
最初から
生まれなければよかった。
【つづく】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
