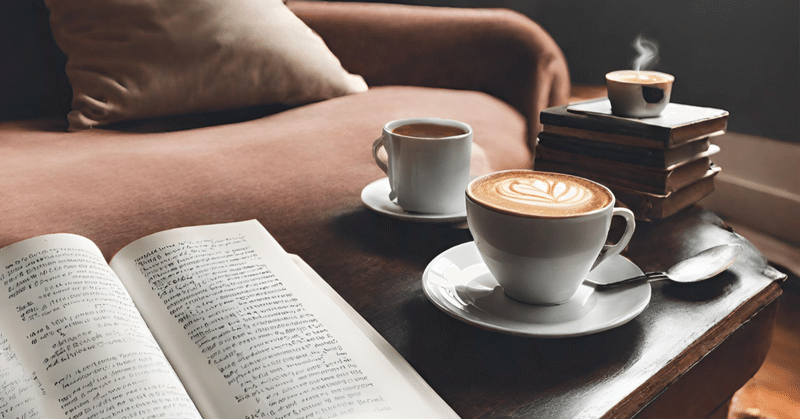
【自戒のエッセイ】本は読んでも読まれるな。毎日読書を三年間続けて見つけた、ライフログ読書
一冊読み終わった後の多幸感は計り知れない。
でも、それだけに留まるのが、元々の私の読書だった。
昔から好きな読書だけど、読みたくなくなってしまう瞬間だってあった。
それは、別に自分にとって必要ではない情報と知りながら、「読み切る事」だけに注力していた時。
もはやそれは執着みたいなもので、
この本を読む目的は何?などという
「読む準備」すらしていなかった為、
読むこと自体が目的に変わって、
読書がちっとも面白くなくなってしまったのだ。本は何も悪くないのにね。
さらに言うなら、
本を読みながらその内容を
ノートにまとめている時期もあり、
これはこれで一見、
記憶に残りそうな方法に思った。
実際に
「これこそ、血肉になる読書の仕方じゃなかろうか」なんて私はたかを括っていたのだ。
けれども無限ループだった。
ただ、まとめているだけに終わったのだ。
要は主体的な読み方をしていなかったゆえ、本質的に内容を理解しないまま
人に話すだけの二番煎じに
なってしまっていた。
「知識オタク」にはなりたくない
と思っていたのに、まさに自分がそれだった。
これはいかん。なんとかせねば。
でも読書は大好きだ。
だってそこには心震えるような
未知との遭遇があったりするから。
もっと「活きる読書」はなかろうか。。。
そんな事を思いながら、
また読書を再開した時、
「あ、あの体験はそういう事だったのか」
と自分の過去の経験と
紐づけられた瞬間を得た。
この時の快感といったら堪らない。
更にそんな時の読書の内容というのは
記憶に残りやすい。
なぜなら、自分の体験と繋げているから
エピソード記憶として長期記憶に残りやすくなっている。つまりなかなか忘れない。
そんな気づきから、
私の場合、読書というのは
自分の経験に紐づけたり、
日常に転用するまでが読書で、
読み切る事が読書ではない
という結論に至った。
さらに私は「時間」を大切にしたい人だ。
それは自分の時間だけでなく、相手の時間も然り。
一日24時間という限られた時間を有効に使って未来の過ごし方にレバレッジをかけるのは「今」の使い方次第だと本気で思っている。
そんな思いが念頭にあるから、
読書の時間だって無駄にはしたくない。
本は思考の集まり、体験の集まり、概念の集まり。それをコトバというコミュニケーションツールを使って形に表してくれているのがが著者だ。
だから、ただ読むだけになると著者の言う事だけに目を向けてしまい、「その通り」と疑いもなく思ってしまう節がある。
そんな自分の感想も意見もないような
読み方では記憶に残りにくい。
だから本を読む目的を改めて考え直した。
そこで分かった事。
それは私の読書の目的は
「知り得た知識を日常に転用すること」
「QOLを高めること」
これだった。
更に、本の読み方をもう一度見直しもした。
・私にとって読書って本を読み切る事?
・私の読書の目的って要約する事だっけ?
・読んだ本の冊数と知識量がイコールにならないのは何故?
という疑問を呈して
読書をしながら読書法を漁ってみた。
そしてとうとう、
・本は好きだけど、まとまった時間がとれない
・必要な個所を効率的に読んで仕事や日常に活かしたい
・答えを探すように楽しく読みたい
・脳が疲れない読書がいい
・主体的な読書スタイルがいい
という私のニーズを満たす読書法ができた。
その名も「ライフログ読書」👍
『ライフログ読書』とは……
「私」の知りたいことを探索しながら読むピックアップ読書のこと。過去の経験での学びや気づきを本で確認したり、本で得た知識を自分用に転用して日常で試すといった仮説と検証を繰り返し。
そうすることで、物事の本質を見抜くチカラと
自分のQOLを高めていくことが目的。
本は読んでも読まれるな!
※ ここでのQOLとは、
頭のエコになること、
考え方のヒントになること、
カラダが喜ぶことなどを指します。
これが私が独断と経験で作り上げた読書法の定義。
この読書法には
読む前の準備、
読んでいる最中の姿勢、
読んだ後の提案、
と三つのフェーズがある。
三つのパート、とでも言えるけど、
うん、「フェーズ」がいい。
順番が大事だから。
読んだらそれで終わりではない。
アナロジーを使って日常生活で活かすレベルに変換して転用する。ざっくりいうとこんな流れになる。
そして、このライフログ読書で
私が感じたベネフィットとは
時間の効率化:自分にとって知りたい所だけをピックアップして読むことで、一日の限られた時間を守る→知りたい事の答えを探しながら読むから記憶に残りやすい
目的の顕在化:自分が知りたいトピックや問題を再認識→今の自分を客観視できる
情報過多への対処:自分にとって重要度の低い情報を避ける→脳の活動をエコできる
具体的な読書法はここでは割愛するとして、
きっとまた進化して
変わり続けるものであろうと思う。
とにかく
読書に慣れている方も
慣れていない方もまず、
「その本を読む目的」
「知りたい事の答え探し」
この二つだけでも意識してみてはどうだろうか。
一瞬にして読む姿勢が変わり
私の場合読書がかなりラクになった。
ライフログ読書を始めてからは、今までは本という船長がいて、自分は船に乗ってただ流れる景色を追い、気がつけば目的に到着(本の最後のページ)していた感覚だったのが
今度は自分が舵を取って、
自分が決めた航路で本という景色を進み、
目的地に到着(最後のページとは限らない)する感覚になった。
本の中に自分があるのではなく、
自分の中に本がある。
心と頭が忙しいと、つい本に読まれてしまう自分に自戒の念を込めて。「ライフログ読書」を提唱する秋の昼下がり。。。
追記:小説の場合はストーリーが繋がっているので、ライフログ読書は通用しないかなぁ。小説はゆったり読書をオススメします😌
参考図書
📕望月安迪「目的ドリブンの思考法」Discover
📘メンタリストDaiGo「知識を操る超読書術」かんき出版
📗西岡壱誠『「読む力」と「地頭力」が一気に身につく 東大読書』東洋経済新報社
※ここで紹介されるエッセイは全て、
私の個人的解釈により自由に書かせていただいております。ゆえに情報の正確性 有効性 最新性 安全性を保証するものではないということをご理解くださいませ。
皆さまの中にある気づきこそ
読書のエッセンスそのものです。
しゃろん;
※画像 Canvaで生成
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
