
人間の絆~読書記録226~
イギリスの作家・モームの長編小説。半分は自伝で、そこにフィクションも取り入れている。
この作品は、キリスト教を少しでも知っている者と、全く知らない者とでは感想も違ってくるかもしれないと思う。
私が田舎娘で、聖書やらクリスチャンやら全く知らないで過ごしていた若い頃に、中野好夫先生の訳で読んだのが最初であった。
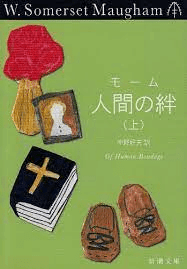
幼くして両親を失い、牧師である叔父に育てられたフィリップは、不自由な足のために、常に劣等感にさいなまれて育つ。いつか信仰心も失い、聖職者への道を棄てた彼は、芸術に魅了され、絵を学びにパリに渡る。しかし、若き芸術家仲間との交流の中で、己の才能の限界を知った時、彼の自信は再び崩れ去り、やむなくイギリスに戻り、医学を志すことに。
イギリスに戻ったフィリップの前に、傲慢な美女ミルドレッドが現れる。冷たい仕打ちにあいながらも青年は虜になるが、美女は別の男に気を移してフィリップを翻弄する。追い打ちをかけられるように戦争と投機の失敗で全財産を失い、食べるものにも事欠くことになった時、フィリップの心に去来したのは絶望か、希望か。モームが結末で用意した答えに感動が止まらない20世紀最大の傑作長編。
人生の意味など、そんなものは、なにもない。
そして人間の一生もまた、なんの役にも立たないのだ――。
文豪モームが描く、自伝的小説。青年は官能の世界を彷徨う。
こちらは、中野好夫先生が訳された本の紹介をコピーさせていただいた。
中野好夫先生は素晴らしい翻訳者で、高校生だった私は感動したように覚えている。
その頃、私は父親が事故死し、人の生き死になどについて生意気に考え、不安定な時期でもあった。
中野好夫先生は明治生まれである。今となっては言い回しが難しく感じる所も多く、又言葉も難しい。
例えば、主人公のフィリップの足を「エビ足」と表している。
「人間の絆」については、ひろさちや先生が深い考慮を与えてくださった。
元々、絆とは、犬や馬などの家畜を縛り付けておく意味。
最初に日本で訳された時に題名を付けた翻訳家は、そんな意味で訳された。 絆を辞書やネット検索すると、そちらの意味になる。 東日本大震災以後、絆の使い方が変わってきたのだ。
で、私は、今回は、戦後生まれの金原瑞人先生訳で読んだ。
文章が読みやすい。
主人公の足の事は「内反足」と訳している。
ただ、これはメディアも普及したことであるし、ニュースの報道、ネットの普及などで一般人でも、正しい医学用語が理解できるようになったからかもしれない。
昭和の半ばに「内反足」と言われてもわからなかっただろう。
「エビ足」と表現されていると、イメージしやすい。

さてさて、主人公のフィリップのコンプレックスである足の症状。これは大きな意味をこの作品では持っていると思う。
主人公は両親を亡くし、牧師の家に引き取られるわけだが、聖書の言葉を聞かされ、
「信仰があれば山も動かせる」という事を聴き、足が治るように必死に祈るわけだ。
マタイ17:17:19-21 そのとき、弟子たちはそっとイエスのもとに来て、言った。「なぜ、私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。」イエスは言われた。「あなたがたの信仰が薄いからです。まことに、あなたがたに告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、『ここからあそこに移れ』と言えば移るのです。どんなことでも、あなたがたにできないことはありません。〔ただし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出て行きません。〕
そして、フィリップは信仰を捨てる。
フィリップが信仰を捨てたのは、それなりの理由があったからではなく、そもそお宗教的な気質ではなかったからだ。それまでは、外から宗教を押し付けられてきたというだけで、信仰心は環境と体験のせいだったのだ。
フィリップは暗唱させられた祈りの文句や使徒書簡を想い出し、聖堂での長い礼拝の間、じっと座っているうちに動きたくて全身がもぞもぞしてきたことを思い出した。
フィリップは自分の知性と大胆さが誇らしく、そんな自分に酔って、新しい人生を歩みだした。だが、信仰を捨てたわりに、行動は思ったほど変わらなかった。キリスト教の教義は捨てたものの、キリスト教的な倫理を批判する気にはなれなかった。(本書より)
モームは、キリスト教が嫌いと公言していた。ここに書かれている事は、実際にモームの実体験に近いのだと思う。
下巻に入り、主人公のフィリップの様々な体験が描かれる。涙にくれるような日々だ。
そして、「生きることに何の意味があるのだろう」と考え始めるのだった。
生は無意味で、死は何も残さない。フィリップは歓喜した。
十代の頃、神への信仰という重荷が肩から消えたときの歓喜を味わった。責任という最後の重荷から解放されたような気がした。そして生まれて初めて、完全に自由になった。自分が無価値だという自覚は力につながった。そして突然、いままで自分を迫害してきた残酷な運命と対等になったように感じた……(本書より)
モームが悟ったのは、まさにこれだったのだろう。
そしてわかったのは、世界には普通の人間など殆どいないということだ。誰もが心や体に何らかの不具合を持っている。
自分にできるのは、人の良い所を受け入れ、人の過ちに耐えるしかない。詩を目前にしたイエスの言葉が記憶によみがえった。(本書より)
ここで、ルカの福音書が出て来る。
そのとき、イエスは言われた、「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」。人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。ルカ23:34
若い頃とは又違った感慨がある。これが世界的に後世まで残る名作というものだろう。
主人公フィリップは案外、多くの人の心が持っているものかもしれない。
キリスト教ではなくても、創価学会でも天理教でも統一教会でも、何となく環境で信仰を持ったように思えてしまった。。。。
やはり、「人は何のために生きるのか?」は、多くの宗教のテーマであるのだから。
モームは、キリスト教ではなく、信者が嫌いだった。それは、私と同じだ。
とても身近に感じてしまうのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
