
樹木葬という選択~読書記録339~
2016年、フリージャーナリストの田中敦夫氏によ著書。
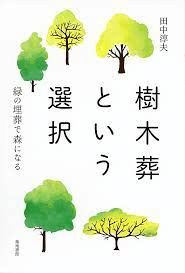
自然の中で眠りたい。遺骨を土に埋葬し、石ではなく樹木を墓標とする、樹木葬。里山を守りたい、自然の一部になりたい、継承の手間をかけたくない、無縁墓とも無縁でいたい、そんな人たちの注目を集める新しい「お墓」のかたちを徹底ガイド。樹木葬を行えるお寺も掲載。
【「樹木葬」チェックリスト】
□終活やお墓について考えたことがある
□石の団地のような大規模な墓地が苦手だ
□墓の継承について、子供たちに苦労させたくない
□寺の檀家になりたくない、宗教・宗派にこだわりたくない
□墓にあまりお金をかけたくない
□環境保全に興味がある
□動物・植物を育てるのが好きだ
□ハイキングや登山、森林浴が好きだ
□身の回りのものは、プラスチックや金属より木質系が多い
1つでもあてはまった人におすすめです!
近年雑誌や新聞で「終活」に関する記事を目にする機会が増えた。自分が亡くなった後の事を、自ら決めておく活動である。まず相続や遺品の処理方法を示し、次は葬儀が課題となる。自分なりに望む形式を記すわけだ。そして最後に墓の問題が外せない。
そうした「終活」から浮かび上がるのは、従来の葬儀や墓に満足していない、違和感を持っている人が多いという事実だろう。(本書より)
左系か?日本人じゃないのか?と、寺の関係者は言うのだが、かなり多くの人は仕方なしに寺や葬儀会社に逆らえず、又、国の法律、自治体の条例に従うしかなく、何も言うこともなく大人しくしているのではないだろうか。とも思っている。
例えば、お墓は、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と法律で定められている。
あれ?私の育った集落では、個人の所有する裏山に墓を作っていたのだが・・・菩提寺の僧侶もそこで式を行ってくれたし。
多分、この法律が施行される前に作ったものだったからだろうか。
都市部では衛生面からやはりこの法律は必要だと思う。が、現在、次男、三男など田舎から出てきて、元々の菩提寺を持たない人が金銭面の関係でお墓を持てない、などがあるのだ。
戦後、菩提寺を持てない悩みを持つ人をターゲットにしたのが創価学会であるが、これはカルト宗教がーー!ではなく、仏教界全体として考えるべきではないかと思う。田舎を出て都市部に移るなどの人に対して、親の菩提寺側が同じ宗派のお寺さんを紹介するなどあれば解決できるのだ。カトリックや日本基督教団などは、就職して故郷を離れるなどの人に自分の宗派の教会を紹介するなど上手く連繫が取れている。
葬儀会社、石材店が要求する金額が払えないよ、という人も冗談抜きに増えてくるのではないかと思う。簡単でいいよという人もいるだろう。戒名は要らないという人もいるだろう。
実際、日本は経済的な冷え込みから生きていくのに本当に必要な物まで節約しないとならない人だらけになってしまった。死んだ人間、ましてや、会った事のない祖父母やその上の世代の管理料まで支払う余裕がない人が多い。
だが、その現実を寺側は全くわかっていないのではないか?とさえ思ったりもする。
ま。この経済的な問題は、お寺ではなく増税眼鏡の岸田総理が悪いのだ。お寺だって被害者だと思う。
これは、よーく読むと、人口減少の為に住職がいなくなり兼務寺を持つことになった。で、兼務寺の運営にもお金がかかる。けれども、家がお寺で小さい頃からお経しか唱えた事がなく、世間知らずの僧侶は税金関係なんか疎くて当然。全く教えず、いきなり税金隠しだ、なんだ、とやって来るほうが悪い。今まで何ともなかった。はい。増税眼鏡・岸田さんの前まではね。
国会議員以外からは税金を搾り取る気満々の眼鏡さん。
だから!葬儀やお墓にかけるお金が一般人にはなくなるのだ。
と、自分の勝手な言い分で申しわけない。
墓じまいをしたい人も増えてきている。時代が変わり、子供を持たない人、結婚しない人だって増えている。そういう人の墓は誰が守るのか?
1つの記事に、2つの本を同時にで申しわけないのだが、田中敦夫氏が紹介していたのが、千坂住職の話だった。
元々は、岩手県一関市にある臨済宗妙心寺派祥雲寺の住職だったそうだ。
岩手県一関市にて、日本で始めて樹木葬を始めた僧侶である。
現在は、祥雲寺から独立して、知勝院という宗教法人となったのだ。
一緒に読んだ。

首都圏で問題となっている里山開発において、特に墓地造成のために貴重な自然が失われる例が目立つ。一方で地方では、里山は放置され荒廃が進む。この事態に一人の和尚が立ち上がった。
荒れた里山に墓地としての許可を取り、手を入れ、整備する。墓標として植えるのは、その地域・環境にふさわしい花木だ。この「樹木葬」は、単に墓石代わりに木を植え、その周りに納骨するだけの記念樹型集合墓ではなく、地域の自然を後世に残していくためのものなのだ。
今、注目の「樹木葬」発案者であり、民間発意としては初の自然再生事業を立ち上げ、地域づくりに取り組む著者が、里山の生物多様性保全・再生という樹木葬の真の狙いと、その活動を述べる。
イーハトーヴで想い出すのは宮沢賢治の世界観だ。岩手県と言ったら、奥州藤原氏、宮沢賢治。若い人は大谷翔平しか知らないだろうが。
こちらの知勝院。平泉中尊寺にも近い。
樹木葬は自然を愛し、守りたい。そんな願いを持った場所なのではないだろうか。そんな想いがしている。
お墓が必要と言うが、墓石そのものも高い。日本産では追い付かず、輸入するのだ。そこまでして狭い日本に一般人の墓が必要なのだろうか。
人は死んだら塵になる。土に還る。私は自分はそうありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
