
日本人の宗教心~読書記録286~
元学習院大学院長である磯部忠正先生による書

従来、宗教の枠で正当にとらえられなかった日本人の「集団的無意識」を一遍、宣長、賢治、遠藤周作などの思想の跡をたどりながら初めて解明する、独自の日本文化論。1983年刊「日本人の信仰心」の復刊。
従来、宗教の枠で正当にとらえられなかった日本人の「集団的無意識」を、一遍、宣長、賢治、遠藤周作などの思想の跡をたどりながら初めて解明する、独自の日本文化論!自我意職に焦点をあてた、哲学者による東西比較の試み。著者が求めつづけたのは、明確さを欠いた日本人の宗教意識の深層に潜在しているものを探求し発見して、それに自覚をもたらすという仕事であった。
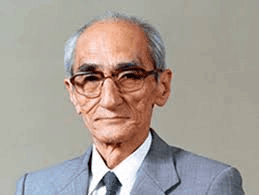
著者が何度も主張されているのは、顕と幽である。
目に見えるものと(顕)、見えないもの(幽)だ。
この本では、長いページを割いて、時宗開祖である一遍上人の事が書かれている。
一遍上人のされた踊り念佛。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と言いながら踊るのであるが、仏教の観点からだけではない。まず、熊野という古代神道の聖地で一遍上人が啓示を受けた事が大きいのだとする。つまり、本当に神仏習合だ。
熊野での啓示については、時宗総本山である藤沢市・遊行寺が詳しい。
西洋の一神教であるキリスト教と日本人の持つ宗教性についても論じられている。キリスト教の場合、神との個人的な結びつきの宗教と言えるが、日本の場合、集団性が大きい。神社での祭り、行事などがある。
最も違うのは、世界の初め、人間の生まれだろう。
それは、古事記と聖書の創世記を比較するとわかることである。
現に日本人の一般的な宗教意識には、キリスト教にいわれるような人格的な唯一絶対神はないのである。その代わり、日常身近のあらゆる事象や自然現象の中に、神秘の世界を感じる。いわゆる「もののあはれ」の意識である。これは一切の価値判断の究極を唯一神に託すキリスト教との際立った相違点である。
自然との一体感は、日本人の心性の特色である。
人間以外の生き物は、ことごとく人間の生きる為に存在を許されているという思想である。これによって、キリスト教徒はいわば心おきなく動物を殺す事が出来る。(本書より)
日本人の祖先は「ハレ」と「ケ」のけじめを厳しく守ってきた。それは生活が豊かになっても守り続けなければならない。と、磯部先生は言われる。
飛鳥時代より、日本人は他の国の文化を受け入れ、取り入れてきた。明治期以降、キリスト教の布教も解禁されたが、西洋の文明の良い面は取り入れても、日本にはキリスト教は定着していない。
私が知っている限りでは、1%というのは、統一教会やエホバの証人なども入れての数字であるし、磯部先生がお元気であられた昭和時代よりも現代は、もっと信者は減っている。
何故に定着しないのか。その理由を教えてくれた本であった。
常日頃の生き方、考え方。それらが違うからだ。



このような供養塔は、キリスト教圏では考えにくいだろう。
数年前の話になるが、横浜市伊勢佐木町にあるカトリック教会の勉強会に参加したことがある。そこでは、頭だけは良い、心のない、30歳くらいの若い日本人神父が司祭をしていた。
マタイ伝にある「平和を求める者は幸い」の個所から、
「これは、ヨルダン、シリアなど常に紛争の多い地域だからこそ語られた言葉であり、日本人には理解出来ないかもしれない」
と言われていた。
実に的を得ていると思う。

アラビア圏、大自然の小さな家に出て来る場所。日本のような四季がないのだ。だから、彼らには「もののあはれ」「季語を味わう俳句」はわからないだろう。
私自身は、無宗教と断言してしまおう。それでも、昔からの日本人が感じ
てきたように、四季を味わい、「もののあはれ」を想う者である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
