
【巨人の肩の上から #8】 -壁も戸もない部屋
「お前がそんなことをしたら日本人になれるとでも思っているのか」
ベンは口をつぐんだまま、しっかりした手つきで縦の文字を綴りつづけた。その背中には、小さな震えが走った。
「お前は東京であれだけ勉強をしているくせに、まだ日本の常識が分っていない」
いつもは無口な父がなおも言いつづけようとするのに、ベンは本当に驚いた。
「お前がやつらのことばをいくら喋れるようになったとしても、結局やつらの目には、ろくに喋れないし、しゃべろうと思ったこともない私とまったく同じだ。たとえお前が皇居前広場へ行って、完璧な日本語で『天皇陛下万歳』と叫んでセップクをしたとしても、お前はやつらのひとりにはなれない」
そう言い捨てて、父はドアを静かにしめた。
日本語では、日本人と外国人の親から生まれた混血の人物のことを「ハーフ」と呼ぶ。half、すなわち「半分」という呼称に込められている意味は、どのようなものだろうか?
私には時折、“純粋な”日本人が、あたかも同質性によって結束した「自分たち」から「彼ら」を切り離すために、半分しか日本人ではない人物、という要素を全面に出す言葉として「ハーフ」を用いているかのように聞こえることがある。
英語では、たとえば自分やほかの誰かがアメリカ人と日本人の混血であると伝えたい時には‘I am / He is half American, half Japanese’と紹介するそうだ。Americanとしての半分と、Japaneseとしての半分。きちんと、足し合わせて一つの自己を形成することができる。アメリカ人の親と、日本人の親の両方から授かった、一つの命。そこに誇りを抱くことができる。
しかし、周囲から暴力的に貼り付けられる日本語の「ハーフ」というラベルには、「半分が日本人」という情報しか書かれていない。私はその立場になったことがないから想像することしかできないが、私が「ハーフ」だったら、そういう呼ばれ方をされたとき、きっと自分のアイデンティティ——halfは日本人で、もう一方のhalfは他の、日本人であることと同じように大事であるはずの、属性であるという誇り——を半分に切り裂かれたような気持ちになるのだろう。
‘国家’にせよ‘民族’にせよ’人種’にせよ、私たちの世界には多くの「境界線」が存在する。人々はよく、山や川、国境線といった物質的なものだけではなく、精神的にも、「私たち」と「彼ら」の間に一本の線を引こうとする。肌の色、髪の色、年齢、性別、性的指向…。目に見えるものだけでも、線を引く根拠は様々である。言うまでもなく、目に見えない抽象的な根拠(たとえば’文化’、’政治思想’、言語使用の’滑らかさ’… )も無数に存在する。
やや悪意のある言い方をすれば、境界線の完全な内側に安住している人々が誰かを「ハーフ」と呼ぶとき、彼らはその相手が境界線の内にいるのか、外にいるのか値踏みをしているともとれる。「半分」だけ内側にいる彼らは、自分たちの共同体に片足だけを踏み込んでいる準アウトサイダーだ、とでもいうように。
しかし、そのような境界線を設けることで自分たちの同質性を守り、いちいち他者を値踏みすることの必要性——その人は境界の内の人間なのか、外の人間なのか、「半分」の人間なのかのラベルをいちいち貼り付けていく必要性——はいったいどれほどあるのだろうか?ひとつのヒントは、とある作家の作品と生き方に見出すことができるだろう。
処女作『星条旗の聞こえない部屋』で野間文芸新人賞を受賞したリービ英雄は、「日本人の血を一滴も持たない」アメリカ生まれの日本文学者だ。『星条旗の聞こえない部屋』の主人公、17歳の少年ベン・アイザックのモデルは、間違いなく少年時代のリービ英雄本人だろう。
横浜のアメリカ領事館で働く父の家で暮らしていたベンは、日本人を見下す父との対立や、自分を奇異の目で見つめてきたり、「外人」として扱ったりしてくる周囲の日本人との交流のなかで、自分の「アイデンティティ」の在処を見つけられず葛藤する。この短編小説の最後には、ベンは父を捨て、アメリカ領事館内にある父の家から「脱出」し、新宿の街に降り立つ。そこで、道端にしゃがんでいた二人の労働者風の男たちに「外人」「カエレカエレ」と言われたとき、ベンは自分は「外人」でありながら、家にも、アメリカという母国にも「帰る」ことができないと自覚し、新宿という街へ駆けだすのであった。

小説を執筆するまでの自らの人生を「それまでは人生を真二つに割るように、ぼくはアメリカと日本の間に、ちょうど半分ずつ生きていた」と語るリービ英雄は、自伝的作品であるこの『星条旗の聞こえない部屋』を日本語で執筆した理由について次のように回想している。
なぜ、わざわざ、日本語で書いたのか。「星条旗の聞こえない部屋」を発表してからよく聞かれた。母国語の英語で書いたほうが楽だろうし、その母国語が近代の歴史にもポスト近代の現在でも支配的言語なのに、という意味合いがあの質問の中にはあった。
日本語は美しいから、ぼくも日本語で書きたくなった。十代の終り頃、言語学者が言うバイリンガルになるのに遅すぎたが、母国語がその感性を独占支配しきった「社会人」以前の状態で、はじめて耳に入った日本語の声と、目に触れた仮名混じりの文字群は、特に美しかった。しかし、実際の作品を書く時、西洋から日本に渡り、文化の「内部」への潜戸としてのことばに入りこむ、いわゆる「越境」の内容を、もし英語で書いたならば、それは日本語の小説の英訳にすぎない。だから最初から原作を書いた方がいい、という理由が大きかった。壁でもあり、潜戸にもなる、日本語そのものについて、小説を書きたかったのである。
ぼくにとっての日本語の美しさは、青年時代におおよその日本人が口にしていた「美しい日本語」とは似ても似つかなかった。日本人として生まれたから自らの民族の特性として日本語を共有している、というような思いこみは、ぼくの場合、許されなかった。純然たる「内部」に、自分が当然のことのようにいるという「アイデンティティ」は、最初から与えられていなかった。そしてぼくがはじめて日本に渡った昭和四十年代には、生まれた時からこのことばを共有しない者は、いくら努力しても一生「外」から眺めて、永久の「読み手」でありつづけることが運命づけられていた。…
リービ英雄は日本語で小説を書くことによって、言語、人種、文化、そして国籍を全て共有する、純粋にして単一な「内部」が存在するという神話を破壊すること——「外」にいるはずの者が「越境」するということ——に成功したのだった。
2001年に刊行された彼のエッセイ集『日本語を書く部屋』の解説を務めた多和田葉子が「『コトバ=民族』という概念に反し、外国人が『日本語を書く』ということは、せつなくも本物の越境行為だ」と述べているように、これは間違いなく大きく、そして孤独な挑戦であっただろうし、誰にでもできることではないはずだ。そして同時に、これは「日本人」「外人」「ハーフ」というラベルの有効性を疑う上で極めて重要なエピソードと言えるだろう。
彼が語っているように、ことばは「潜戸」であり、言葉を入り口として彼は文化の「内部」に入りこんでみせた。日本語という私たちにとって最も身近な同質性の根城に、正面玄関から’侵入’することが可能なのだと、示してみせた。
これは、1992年(『星条旗の聞こえない部屋』の刊行年)の話である。2022年、もはや私たちは、このような営みを「侵入」と呼ぶことの妥当さ、孤独と闘いながら「越境」しなければならないような境界線が、そもそも存在することの妥当さを疑わなければならない時を生きている。
「多様性」と一口で言っても、目に見ることのできない「境界線」を相手取って疑うことは難しい。私たちは誰だって(少なくとも内心では)「自分たち」と「それ以外」をいろいろな方法で区別しているし、それをしなくては社会は滅茶苦茶になってしまう。境界線を引くという行為に排除性を見出し、多様性の名の下に'No Border'といくら主張しても、それは無限後退に陥るだけなのかもしれない。それでも、疑い、悩み、社会とはどうあるべきかという問いと向き合うことは重要だ。
くどくなるが、最後に、リービ英雄のエッセイから2つ、日本語を母語としないアメリカ人として日本語で文章を書き、日本を見続ける彼の、鋭く見識に満ちた記述を引用して終わりにしたい。どちらも1996年に発表された文章だが、現在読んでもずしりと私たちの胸に刺さる内容であると感じたものである。
これはぼくのまったくの憶測にすぎないけれど、これから先の運命は日本人にとっていちばん辛いものになるのではないか。世界一になることもなければ、小国に戻ることもない。その間、中間国家を生きるという体験は、近代百年の日本人にかつてなかったことだ。
その意味で、阪神大震災、地下鉄サリン事件などの九〇年代の大事件に染まりきったマスコミの報道ぶりは興味深く、不安にもなった。バブル時代の過剰な自信が完全に裏返って過剰に悲観的になり、ひたすら国内の被害に目を向け、鎖国的なものさえ見え隠れしていたように思う。だが、震災にせよ、サリン事件にせよ、日本人が被害に遭うところでは、在日外国人も一緒に被害に遭う時代になったことを、図らずも証明している。日本人がこれから体験することは、ことごとく在日外国人によって共有されるだろう。
もしかすると、在日外国人も参加する、新しいナショナリズムが生まれる可能性もあるかもしれない。ぼく自信、今や日本の一員として、そんなナショナリズムの可能性について考えることがある。「民族」とか「人種」という一九世紀の発想ではなくて、「言語」と「文化」という二十一世紀の発想に基づいた愛国心。少なくとも、アイデンティティをもう少し柔軟に幅広く考えることが、これからの日本人に求められることは確かである。
ぼくは、「異文化の共存」という言葉が好きではない。ことに日本人がこの言葉を用いる場合、「おまえはおまえでオレはオレ」「おまえとオレの間の一線を越えるな」というニュアンスを強く感じる。もちろんそうでない場合もあるが、「外人は日本語をしゃべれない」「外人は日本文化を理解できない」という思い込みと、それはどこかで一脈通じている。
最近、自身の日本での体験を英語で著したフィリピン人労働者の本を読んだが、そこには日本で蓄財に成功するための二つの秘訣が記されていた。
一、日本人に近寄らないこと。
二、日本語でしゃべらないこと。
どこかで聞いたことがあると思ったら、十代のころ、横浜は山下町の領事館に住んでいたときに聞かされた、当時の「外人コミュニティ」の白人の言い方とそっくりだった。一九六〇年代の特権的な白人社会と一九九〇年台のアジア系労働者では、いろいろな意味で事情が異なるに決まっている。しかしこの国では、いずれにせよ「外人」であるほうが有利なのだ。四半世紀以上が経過してなお、「一線」を越えてはいけないらしい。
…(中略)
「外人」を日本人とほぼ絶対的に分けようとする日本社会の構造は変わっていない。ほとんどの外国人は共同体の一員とは認められず、孤立した小さな共同体を作ることを余儀なくされている。だが、そんな「異文化の共存・共生」に意味があるのだろうか。外国に生まれながら、日本に来て、実質的には新しい日本人として生きてる、少なくともボーダーを越えてくる前の自分とは違った、日本文化共有者となった者は少なからずいる。その事実は「異文化論」の大きな盲点であるように思えてならない。
2022/05/09
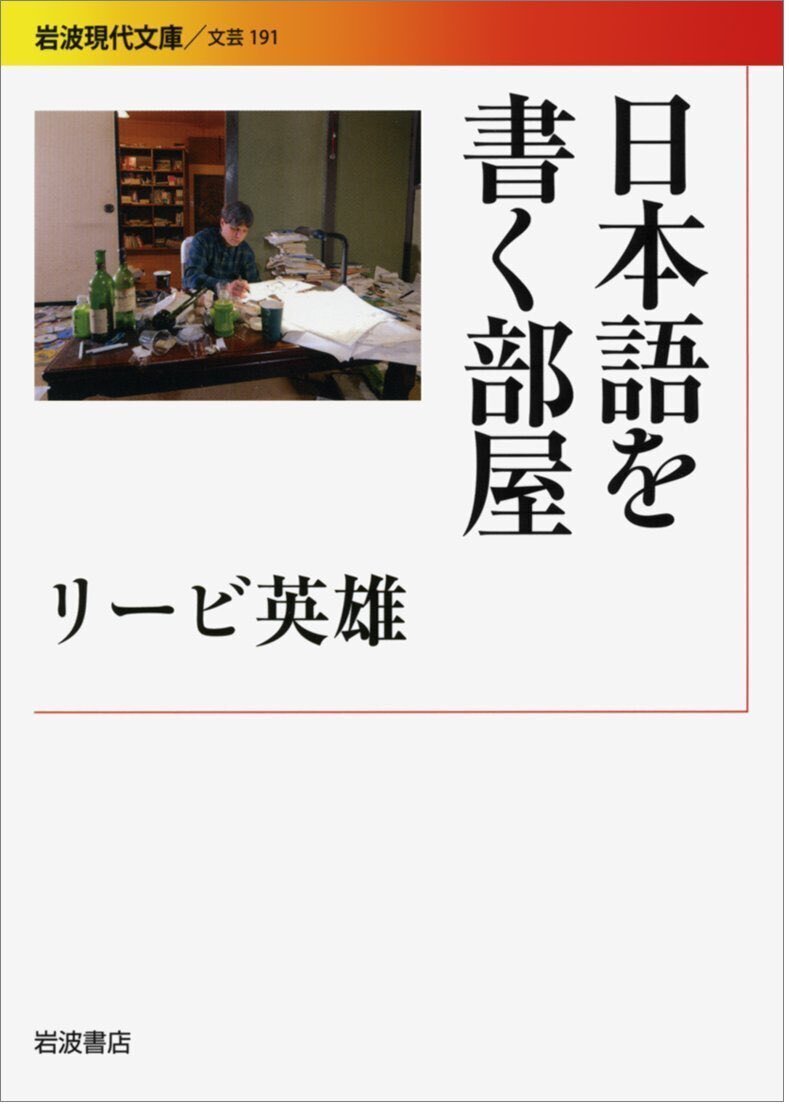
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
